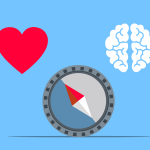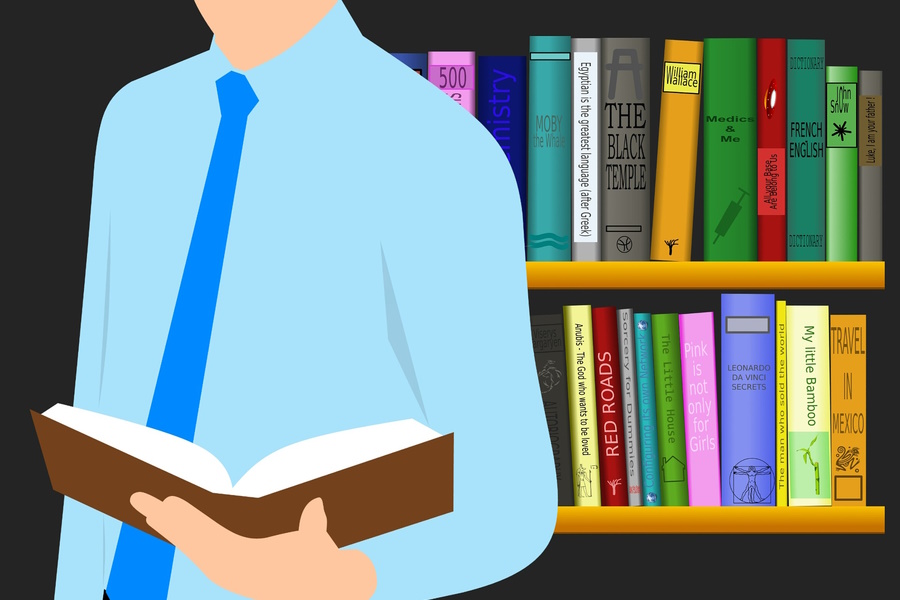
※本ページはプロモーションが含まれています。
ビジネスをしていると、ちょこちょこ知らないキーワードが出てきますよね。
- 「チームメンバーはアサインした?」
- 「エビデンスは取ったの?」
- 「グロスでいくらだった?」
このようなフレーズを知らなければ、スムーズな仕事はできないので、全てのビジネスパーソンが知っておくべき言葉だと思います。
そこで今回は、今更人には聞けないビジネス用語を一覧にまとめてみました。
就職活動をしている大学生や新卒社員はもちろん、転職活動している人まで幅広くご覧ください。
目次
- 1 ビジネス用語の基本一覧(例文付き)
- 1.1 1:ブランディング
- 1.2 2:プロモーション
- 1.3 3:AIDMA(アイドマ)の法則
- 1.4 4:AISAS(アイサス)の法則
- 1.5 5:AMTUL(アムツール)の法則
- 1.6 6:BtoC(B2C)・BtoB(B2B)
- 1.7 7:フラグシップ
- 1.8 8:インバウンド
- 1.9 9:ホスピタリティ
- 1.10 10:IR(総合型リゾート)
- 1.11 11:アイスブレイク
- 1.12 12:ハンガートーク
- 1.13 13:ラポール
- 1.14 14:アドホクラシー
- 1.15 15:エクスキューズ
- 1.16 16:オープン&クローズドクエスチョン
- 1.17 17:インセンティブ
- 1.18 18:コミッション
- 1.19 19:ネゴシエーション
- 1.20 20:フットインザドア&ドアインザフェイス
- 1.21 21:リテール&ホールセール
- 1.22 22:コストパフォーマンス
- 1.23 23:CS(顧客満足度)
- 1.24 24:オポチュニティ
- 1.25 25:チャネル
- 1.26 26:リレーション
- 1.27 27:ワンストップサービス
- 1.28 28:アサイン
- 1.29 29:カウンターパート
- 1.30 30:スーパーフレックス
- 1.31 31:リファラル採用&リファラル営業
- 1.32 32:フリーアドレス
- 1.33 33:ロールモデル
- 1.34 34:PDSサイクル
- 1.35 35:PDCAサイクル
- 1.36 36:コーポレートガバナンス
- 1.37 37:アジェンダ
- 1.38 38:アントレプレナー
- 1.39 39:ステークホルダー
- 1.40 40:コアコンピタンス
- 1.41 41:コンペティター
- 1.42 42:エンドユーザー
- 1.43 43:スタートアップ
- 1.44 44:ペルソナ
- 1.45 45:バリュープロポジション
- 1.46 46:ゾーニング
- 1.47 47:ブルーオーシャン&レッドオーシャン
- 1.48 48:コモディティ
- 1.49 49:バリューチェーン
- 1.50 50:サブスクリプション
- 1.51 51:マネタイズ
- 1.52 52:フリーミアム
- 1.53 53:ビッグデータ
- 1.54 54:クレド
- 1.55 55:SWOT(スウォット)分析
- 1.56 56:VRIO(ブリオ)分析
- 1.57 57:クラウド・コンピューティング
- 1.58 58:AI
- 1.59 59:シンギュラリティ
- 1.60 60:ディープラーニング
- 1.61 61:エバンジェリスト
- 1.62 62:アフィリエイト
- 1.63 63:UX・UI
- 1.64 64:バズマーケティング
- 1.65 65:ローンチ
- 1.66 66:CGM
- 1.67 67:デフォルト
- 1.68 68:コンバージョン
- 1.69 69:IoT(アイオーティ)
- 1.70 70:サプライチェーン
- 1.71 71:ファブレス
- 1.72 72:トレーサビリティ
- 1.73 73:OEM
- 1.74 74:PB(プライベートブランド)
- 1.75 75:エビデンス
- 1.76 76:クリティカル
- 1.77 77:アジャイル
- 1.78 78:パラダイムシフト
- 1.79 79:エンパワーメント
- 1.80 80:ファシリテーター
- 1.81 81:キャズム
- 1.82 82:インタラクティブ
- 1.83 83:プロパー
- 1.84 84:LTV(ライフタイムバリュー)
- 1.85 85:ストックとフロー
- 1.86 86:レベニューシェア
- 1.87 87:スケール
- 1.88 88:ゲームチェンジャー
- 1.89 89:ケータリング
- 1.90 90:ワーケーション
- 1.91 91:IPO(株式公開)
- 1.92 92:ベンダー
- 1.93 93:報連相(ホウレンソウ)
- 1.94 94:OKR
- 1.95 95:オンボーディング
- 1.96 96:オーソライズ
- 1.97 97:SEO
- 1.98 98:オフレコ
- 1.99 99:グロースハック
- 1.100 100:ピッチ
- 2 ビジネス用語は”重要フレーズ”だけ覚えよう!
ビジネス用語の基本一覧(例文付き)
ビジネス用語には、絶対に押さえておくべき基本フレーズというのがあります。
しかし新入社員には馴染みがなかったり、業界が違うと全く分からないというケースも散見されます。
ここではビジネスパーソンが知っておくべきカタカナ用語や英語言葉など、一般的なビジネスフレーズを例文付きで一覧にまとめています。
ぜひ最後までご覧ください。
1:ブランディング
ビジネスにおいての「ブランディング」とは、特定の商品・サービスのブランド構築や管理を行うことです。
具体的には、ブランド価値を高めて、ターゲットに認知してもらうための活動を「ブランディング」と呼んでいます。
例えば、数ある商品・サービスの中でも「牛丼屋といえば○○」「高級時計といえば▲▲」など、ある程度イメージする企業がありますよね。
これはブランディングが成功している事例なので、そのような企業のマーケティングをチェックしてみましょう。
主力商品であるAのブランディングを行う。
2:プロモーション
プロモーションは製品サービスに対する関心を高めて消費者の購買意欲を促進する活動のことです。
広告、広報、販売促進、口コミ、パブリシティなどがこれに当たりますが、FacebookやTwitter、LINEなどのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)が急速に発達したため、双方向のコミュニケーションが要求される時代になっています。
つまり、単純なプロモーションでは効果が出ないので、マーケティング担当者はしっかり戦略を練る必要があるということです。
潜在顧客にアプローチするプロモーションを実施する。
3:AIDMA(アイドマ)の法則
AIDMAの法則は、1920年代にアメリカで提唱された消費行動の仮説です。
- Attention(注意)
- Interest(興味)
- Desire(欲求)
- Memory(記憶)
- Action(行動)
この5つの頭文字をとったのが「AIDMAの法則」と呼ばれており、消費者が商品を知ってから実際に購入するまでの心理的プロセスをモデル化しています。
この法則はビジネスパーソンの常識なので、必ず押さえておきましょう。
AIDMAの法則を取り入れながら販売戦略を企画する。
4:AISAS(アイサス)の法則
AISASもAIDMAの法則と似ていますが、消費者が実際に商品を認知してから購入するまでの行動をモデル化したものです。
しかしこれはインターネット時代の消費行動にフォーカスしているところが特徴的です。
- Attention(認知・注意)
- Interest(興味・関心)
- Search(検索)
- Action(行動)
- Share(共有)
この5つの頭文字をとったのがAISASなのですが、全ての行動が説明できるわけではなく、インターネット上で「自ら能動的に検索する」ということが前提になっています。
AISASの法則を取り入れながらウェブマーケティングを企画する。
5:AMTUL(アムツール)の法則
AMTUL(アムツール)の法則は、下の5つの頭文字をとった言葉です。
- Awareness(認知)
- Memory(記憶)
- Trial(試用)
- Usage(日常利用)
- Loyalty(固定利用)
こちらも消費者の意思決定プロセスを説明するモデルの一つなのですが、顧客が商品を見つけて購入し、その後も継続的に購入してくれる長期的な購買決定メカニズムを指します。
AIDMAの法則が”短期的”な購買決定メカニズムなのに対して、AMTULの法則は”長期的”な購買決定メカニズムということになります。
AMTULの法則を取り入れながら長期的な販売戦略を考える。
6:BtoC(B2C)・BtoB(B2B)
この言葉は一般的に使われているフレーズなので、ほとんどのビジネスパーソンが知ってるはずです。
BtoC(B2C)は「Business to Consumer」の略称で、BtoB(B2B)は「Business to Business」の略称です。
つまりBtoCは個人向け営業という意味で、BtoBは法人向け営業ということになります。
慣れた人では「それはtoC向けの商材ですか?」や「それはC向けの商材ですか?」という使い方もするので、さらに省略しても十分伝わります。
その商材はBtoCですか?それともBtoBですか?
7:フラグシップ
フラグシップとは、もともと海軍の軍用語で、司令官が乗船して艦隊の指揮をとる旗艦のことです。
しかし英語では「グループの中で最も優れたもの、又は重要なもの」という意味があるので、それが転じて、企業が最も力を入れている商品やサービスを指すようになりました。
なので、象徴的な店舗のことを「フラッグシップショップ」と言ったり、高品質な商品のことを「フラグシップモデル」と言ったりしています。
フラッグシップショップは、流行の発信源である原宿の表参道にあります。
8:インバウンド
この言葉は度々テレビでも耳にしますが、外国人旅行客が日本を訪れて観光することを指します。
英語のInbound(インバウンド)が語源になっているので、「外から中に入る」という意味があります。
それ以外にも、見込み顧客からの問い合わせや資料請求なども「インバウンド」と表現するので、ビジネスでは様々な使われ方をしています。
弊社はインバウンドマーケティングに力を入れています。
9:ホスピタリティ
「お・も・て・な・し」という言葉が流行語になって久しいですが、まさにそれがホスピタリティのことです。
意味的には「思いやり」という意味もありますが、主に飲食店やホテルなどのサービス業や医療・福祉現場においてよく使われている言葉です。
見返りを求めず相手に尽くす言葉なので、営業現場でも使えるフレーズだと思います。
このホテルはホスピタリティマインドが素晴らしい!
10:IR(総合型リゾート)
企業が株主や投資家に対して、業績や財務状況などを情報提供するのをIR(Investor Relations)と呼びますが、それとは違います。
このIRは「Integrated Resort」の略称なので、カジノや会議場、劇場や映画館、ホテルなどが一体となった複合施設のことを指します。
各国がIRによって観光客の誘致に成功しているので、日本もIRに注力していく方向になると思います。
各国でIRの誘致が行われている。
11:アイスブレイク
アイスブレイクを直訳すると「氷を壊す」ということですよね。
つまり、初対面の緊張している状態を打ち砕くという意味のあるビジネスフレーズです。
アイスブレイクは商談や営業時に活用されているので、様々な場面で使えるノウハウだと思います。
営業では一番最初のアイスブレイクが重要。
12:ハンガートーク
Hanger(ハンガー)とは飛行機の格納庫を意味した言葉です。
これは格納庫の中でパイロット同士が雑談していたことから生まれた言葉ですが、ビジネス界隈では何気ない雑談で情報共有したり意見交換することを「ハンガートーク」と呼んでいます。
同じく短い時間で話すフレーズには「エレベータートーク(エレベーターに乗っている間に話すこと)」という言葉もあるので両方とも押さえておきましょう。
円滑にビジネスを回すためにはハンガートークが必要。
13:ラポール
ラポール(Rapport)の語源はフランス語で「橋をかける」という意味です。
ラポールは相手との信頼関係を構築する時に使うのですが、主に医療や介護の現場で使われることが多い言葉だと思います。
しかし、営業現場でも使われている言葉なので、かなり汎用性の高いフレーズですよね。
お客様だけでなく、ビジネスにおける全ての人との関係性構築に使える言葉なので、ビジネスパーソンは覚えておきましょう。
顧客との間にラポールが成立する。
14:アドホクラシー
アドホクラシーは「Ad Hoc(その場限りの)」と「Cracy(制度)」を組み合わせた造語です。
その時々の状況に応じて柔軟に対応する姿勢のことを指しているので、クライアントからの要求に迅速に対応することを指します。
このようなシチュエーションはあるある話なので、アドホクラシーは日常的に存在しているはずです。
クライアントの要求にはアドホクラシーで対応します。
15:エクスキューズ
エクスキューズは「言い訳」や「弁明」する時に使われています。
基本的には言い訳をする人に対して使うので、クライアントや上司のような”目上の人が使うフレーズ”だと思います。
あなたはエクスキューズが多すぎる。
16:オープン&クローズドクエスチョン
オープンクエスチョン(拡大質問)は話を広げる時に使う質問話法ですが、自由に会話できるので、話題が広がりやすいメリットがあります。
その一方で「オープンクエスチョンは初対面の相手に不向き」という側面があるので、そのようなケースではクローズドクエスチョンが向いていると思います。
クローズドクエスチョンは「限定質問」と言われていて、「Yes or No」で答えられる簡単な質問のことを言います。
クローズドクエスチョンは二者択一の質問話法なので、初めての商談や交流会など、初対面の相手と距離を縮めたい時に有効的です。
クローズドクエスチョンで会話のきっかけをつかみましょう。
17:インセンティブ
インセンティブは営業職にとって馴染みがありますが、従業員のやる気を引き出すための”動機付け”を指す言葉です。
ビジネスにおいては「臨時ボーナス」みたいなイメージですが、相手のモチベーションをアップさせるために使われています。
なので、従業員に対する金銭だけでなく、お客様に対するプレゼントやノベルティもインセンティブの一種になります。
インセンティブを与えて売上を伸ばそう!
18:コミッション
コミッションは「歩合制の報酬」を意味する言葉です。
インセンティブやマージンと同じ意味で使われていますが、インセンティブと比べて外向き(業務委託契約など)の言葉として用いられています。
例えば「販売代理店のコミッションは…」という時に使われるので、どちらかといえばマージンと同じ類になります。
今月のコミッションは30万円だった。
19:ネゴシエーション
ネゴシエーションは「交渉」「折衝」などを意味する言葉ですが、「ネゴる」と略されることもあります。
売り込みを意味するセールスよりは、「お互い歩み寄る」というニュアンスが強いので、協業(アライアンス)や買収、企業合併の時などに使われるフレーズです。
ネゴシエーションは出世する上で必要不可欠だと言われているので、ビジネスパーソンはこのスキルを学んでおきましょう。
ネゴシエーションスキルがなければ、偉業を成し遂げることができない。
20:フットインザドア&ドアインザフェイス
元々はセールスマンが「ドアの隙間に足のつま先を入れる」ことで商機を得るのが由来となっていますが、フットインザドアとは「徐々に要求を上げていく交渉術」のことを言います。
つまり最初は「ご挨拶だけ…」と言って、実際に話せたら「ご説明だけ…」と言って、提案ができたら「初回のお試しだけ…」という風に要求段階を上げていくのです。
その逆が「ドアインザフェイス」です。
先に大きな要求(例:今日のランチを奢って)をして、それが断られたら小さい要求(例:じゃあデザートだけ奢って)を提示すると、人間は罪悪感からOKしやすくなるのです。
これは人間心理を巧みに利用した話法なので、営業マンは理解しておくべきだと思います。
フットインザドアで懐に入れば成功です。
21:リテール&ホールセール
リテールは「小売り」を意味する言葉で、ホールセールは「卸売」を意味する言葉です。
この言葉は証券や銀行などの金融業、アパレル、不動産業など、様々な業界で使われています。
なので、これらの業界に携わる場合は理解しておくべきフレーズだと思います。
私はリテールに従事しています。
22:コストパフォーマンス
コストパフォーマンスは日常的に使う言葉なので、馴染みがありますよね。
略して「コスパ」と言われることもありますが、作業に必要な費用(コスト)と、そこから得られる効果(パフォーマンス)を比較した言葉です。
この商品はコストパフォーマンスが高い。
23:CS(顧客満足度)
CSは(Customer Satisfaction)の略称なので、「消費者満足度」や「お客様満足度」と言われることもあります。
つまり、顧客が商品を購入したり、サービス提供を受けた時の満足度についての指標となります。
現代はインターネット社会なので、一人のお客様の影響力(拡散力)が強くなっています。
なのでCSを強化することが非常に重要だと言われています。
今月はCS強化を目標にします。
24:オポチュニティ
オポチュニティは「opportunity」という英語から来ています。
これは「好機」や「機会」という意味の言葉なので、ビジネス界隈では「セールスチャンス」を指すことが多いです。
ニュアンスとしては、「自ら動いて掴み取ったチャンス」という感じなので、積極的なイメージがあります。
本日はオポチュニティを頂きましてありがとうございます。
25:チャネル
チャネルというのは「販売チャネル」「コミュニケーションチャネル」「流通チャネル」「オムニチャネル」といった使われ方をしています。
その語源は「Channel」なので、水路を意味するのですが、つまりは商品が製造されて消費者に届けられるまでの流れを意味しているのです。
その選択肢は様々なので、自社製品にあったチャネルを組み合わせる必要があります。
販売チャネルを構築するのが急務だ!
26:リレーション
リレーションは「関係」を意味する言葉です。
営業職であればCRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)という言葉に馴染みがありますよね。
これはつまり「顧客との関係性を構築する」という話なのですが、ビジネスにおいての基本とも言えるので、ここで押さえておきましょう。
企業は顧客とのリレーションを構築するべきです。
27:ワンストップサービス
分散していた手続きを一箇所で提供するサービス形態のことですが、そのような店舗のことを「ワンストップショップ」と言います。
麻雀をする人は「一気通貫で…」と表現しますが、それと同じだと思ってください。
省略して「ワンストップで提供…」という表現もしますが、これも同じ意味です。
弊社はお客様に対してワンストップサービスを提供しております。
28:アサイン
アサイン(Assign)は、「任命する」「割り当てる」「付与する」などを意味する言葉です。
ビジネスシーンでは、担当者を任命したり、役職に就けるなど、様々な使われ方をしています。
しかし一般的には、目上の人が下の人に対して命令するニュアンスが含まれているので、使うシチュエーションには注意しましょう。
早急にメンバーをアサインしましょう。
29:カウンターパート
カウンターパートとは、対等な立場で共同作業する相手のことを指します。
例えば、企業に対して”コスト削減サービス”を提供した場合、その窓口となるのが総務部の人だったりします。
その人は仕事の一環として対応してくれるのですが、一緒にコスト削減する「カウンターパート」でもあるのです。
このように対等な立場で一つのプロジェクトに携わる相手のことを指すのが「カウンターパート」という言葉です。
最適な人材をカウンターパートとして任命しましょう。
30:スーパーフレックス
従来のフレックス制度(コアタイムのある働き方)からコアタイムをなくした制度が「スーパーフレックス」です。
リモートワークが推奨されている現代では、スーパーフレックスという働き方が一般化してきました。
これは働く時間と場所を自由に決められるので、まさに現代風の働き方だと言えます。
私はスーパーフレックス制なので比較的自由です。
31:リファラル採用&リファラル営業
リファラル(Referral)は「推薦する」や「紹介する」という意味の言葉です。
なので、知人・友人・社員から、候補者を紹介してもらうやり方のことを指します。
リファラルは採用活動や営業活動に使われており、数多くの企業で実施されています。
AさんはBさんからの紹介されたリファラル採用みたいだよ。

32:フリーアドレス
フリーアドレスは「フリー(自由な)+アドレス(場所)」という意味の和製英語です。
従来型の会社では固定の席がありましたが、フリーアドレスの会社では「空いている席であればどこでも座ってOK」ということになります。
この制度は自由で良いのですが、「毎回席が変わると落ち着かない」という人もいるので、メリット&デメリットがある仕組みだと思います。
当社はフリーアドレスを導入しています。
33:ロールモデル
ロールモデルとは、自分にとって模範となる行動や考え方、人物のことを指します。
新しいことにチャレンジする場合、どういう仕組みにすればいいか迷ってしまいますが、ロールモデルがあれば解決します。
例えば「海外留学制度」を新設する場合、まず誰か一人を海外へ留学させて、それをロールモデルとするのです。
そうすれば、その後に海外留学する人達は「一人目を模倣すればいいだけ」なので、制度が仕組み化していくのです。
まず最初にロールモデルを作りましょう。
34:PDSサイクル
PDSサイクルは「Plan(計画)⇒Do(実行)⇒See(評価)」の頭文字をとったものです。
この3つのフローをぐるぐると回すのが「PDSサイクル」と呼ばれています。
これは目標達成に向けて業務を継続的に改善していく手法なので、ビジネスにおける様々な場面で使われています。
PDSサイクルを回して、業務改善を目指しましょう。
35:PDCAサイクル
PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(測定・評価)、Action(対策・改善)の頭文字をとったものです。
先ほどのPDSサイクルと似ていますが、仮説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念なので、使われるシチュエーションが少し違っています。
PDSサイクルはビジネス全般で使える考え方ですが、PDCAサイクルは、主に製造業に向いていると言われています。
PDCAサイクルを回して、業務改善を目指しましょう。
36:コーポレートガバナンス
ガバナンス(Governance)は「統治」という意味の言葉です。
なので企業経営を統制して、監視する仕組みのことを「コーポレートガバナンス」と呼んでいます。
難しくすると伝わりにくいので、簡単に言えば「悪いことをしないようにする」のがコーポレートガバナンスなのだと理解しておきましょう。
企業価値を最大化するためにコーポレートガバナンスを強化する。
37:アジェンダ
アジェンダは「なされるべきこと」という意味のラテン語なので、今後なされるべき検討課題について指しています。
その一方で、英語では「予定表」という意味あいがあるので、「本日のアジェンダはこちらです」とスケジュールを提示されるケースもあります。
どちらにしても、ビジネスシーンではよく聞く言葉なので、ここで理解しておきましょう。
これが今日の会議のアジェンダです。
38:アントレプレナー
アントレプレナーは、いわゆる”起業家”のことです。
一つの事業に限らず、いくつも事業を立ち上げている人のことを「シリアルアントレプレナー」と呼んでいます。
その一方で、会社員として働きつつ、その企業内で新規事業を立ち上げる社内起業家のことを「イントレプレナー」と呼ぶこともあります。
社長は素晴らしいアントレプレナーだと思います。
39:ステークホルダー
ステークホルダーは、企業経営における利害関係者全般のことをいいます。
なので、お客様だけでなく、株主や従業員、取引先、金融機関、地域社会まで全て含めた言葉なので、かなり適用範囲の広いことが特徴的です。
すべてのステークホルダーの利害が一致することは難しいですが、「企業が正当な利益を上げる」という行動を取ることで、ほぼ全てのステークホルダーの利害は一致することになります。
当社にはたくさんのステークホルダーがいます。
40:コアコンピタンス
コアコンピタンスは「核となる能力」という意味なのですが、ビジネスシーンでは「他社が真似できない自社独自の強み」という意味で使われています。
- たくさんの特許を取得した技術
- 圧倒的な営業力
- 他社では真似できないような仕組み
企業ごとに様々な強みがあると思います。
それをコアコンピタンスと呼んでいるのです。
ライバルに勝つためには、コアコンピタンスの強化が重要です。
41:コンペティター
コンペティター(competitor)は「競争相手」という意味の英語です。
ビジネスの現場では略して「コンペ」と呼ばれているので、かなり身近なフレーズだと思います。
一般的にはクライアントに対して提案する場合、コンペになるケースが多いので、そのようなシーンで多く使われています。
今回のプレゼンはコンペティターが多い。
42:エンドユーザー
エンドユーザーは商品サービスを購入してくれる「最終消費者」という意味の言葉です。
一般消費財であれば分かりやすいのですが、法人向けのBtoB商材であってもエンドユーザーは存在します。
その場合の定義は「法人顧客」ということになるので、シチュエーションに応じてエンドユーザーは変化することになります。
御社のエンドユーザーは法人ですか?
43:スタートアップ
スタートアップとは、投資家からエクイティファイナンスで資金を集めて、急激な成長を目指す企業やビジネスモデルのことを言います。
稀にベンチャー企業と混同されているケースもありますが、基本的には「新しいビジネスモデル+急成長」という定義にハマるのであれば、その企業は「スタートアップ」だと言えます。
逆に、既にあるビジネスモデルを少しずつ拡大させて、収益の安定化を目指しているのであれば「ベンチャー企業」に該当するはずです。
あの企業は投資家から注目されているスタートアップです。
44:ペルソナ
この言葉は、営業やマーケティングに携わるのであれば、必ず覚えておく必要のあるキーワードです。
元々はラテン語で「仮面」という意味の言葉なのですが、ビジネスシーンでは「ユーザーイメージ」のことを指します。
「自分たちの製品サービスを購入してくれるお客様はどのような人なのか?」を言語化したのがペルソナなので、このイメージが正確であればあるほどマーケティングも効率的になってきます。
当社のペルソナをもう一度考え直す必要があります。
45:バリュープロポジション
バリュープロポジションを直訳すると「提供価値」となりますが、自社の独自性や強みのことを指します。
例えばクリーニング店はお客様が来店するのを待っていますが、「自分から洗い物を取りに行く」という付加価値をつければ、他のクリーニング店と差別化できます。
他にも、品揃えを豊富にしたり、トッピング無料を打ち出すことで、バリュープロポジションを発揮できるのです。
当社独自のバリュープロポジションを見つけましょう!
46:ゾーニング
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、店舗ビジネスでは当たり前のキーワードです。
ゾーニング(Zoning)はZoneを語源にしているので、空間や領域のことを指すキーワードです。
つまり、空間ごとにテーマを決めて、購買意欲を最大化させることを指します。
この辺りについては下の記事をご覧ください。
普段使うコンビニエンスストアやスーパーでも、ゾーニングは行われているので、今度行った時に注意深く観察してみてください。
ゾーニングを実施しなければ、効率的に売ることができない。
47:ブルーオーシャン&レッドオーシャン
ビジネスシーンにおける「ブルーオーシャン」とは、競合他社がほとんどいない市場(マーケット)のことを言います。
逆に「レッドオーシャン」とは、競合他社ばかりの市場(マーケット)のことを言います。
例えば「一般的なドア」を製造する場合にはレッドオーシャンですが、「どこでもドア」を製造する場合にはブルーオーシャンという具合です。
もちろん全ての企業がブルーオーシャンで戦うべきなのですが、それを見つけるのは至難の技なので、誰もがつけられる市場(マーケット)ではないと理解しておきましょう。
弊社の商品はレッドオーシャンなので、ライバルとの戦いが熾烈です。
48:コモディティ
コモディティ(Commodity)は「商品」という意味の言葉です。
いわゆる一般化した商品のことを指すので、石油、食料品、冷蔵庫などがコモディティに当たります。
コモディティは需要が安定しているのですが、そのぶん競合も多いのでレッドオーシャンで戦わなければいけません。
そう考えた場合、どうしても低価格競争の”体力勝負”になりがちなので注意しましょう。
弊社の商品は既にコモディティ化しました。
49:バリューチェーン
これは「マーケティングの第一人者」と呼ばれている、マイケル・ポーターが提唱した考え方です。

バリューチェーンとは、顧客に価値を届けるための「一連の活動」を言います。
バリュー(価値)が鎖のように繋がっていく様子を表した言葉なのですが、働く上では自社のバリューチェーンを理解することが必要不可欠だと言われています。
当社のバリューチェーンには問題があります。
50:サブスクリプション
「サブスクサービス」でお馴染みのサブスクリプションです。
いわゆる定額制サービスなので、企業収益の安定化に寄与します。
なんとなく最近出てきたような言葉に感じますが、実は以前から「食べ放題」「定額制」という形で浸透していました。
それをただ横文字にしただけなので、基本的には同じだと考えましょう。
サブスクリプションのビジネスは安定する。
51:マネタイズ
マネタイズは「無料で利用できるサービスを提供し、それを収益化させること」を指す言葉です。
例えば、アフィリエイト収入などが代表的ですが、現在では「ビジネスにおける収益化全般」を指す言葉として使われているケースが多いです。
このサービスはマネタイズが課題です。
52:フリーミアム
フリーミアムは「フリー(Free)」と「プレミアム(Premium)」を合わせた造語です。
一般的には「無料サービスを提供することで集客を最大化し、そこから一部を有料化する施策」のことを指します。
ITサービスで良く見られる「30日間無料」などがフリーミアムに該当しますが、それ以外にも様々な業界で使われています。
本サービスのマーケティングにはフリーミアム戦略を採用します。
53:ビッグデータ
インターネットが普及したことによって、とてつもない量のデータが日々収集されています。
これらを「ビッグデータ」と呼んでいますが、それを整理整頓して、情報活用する動きが出ています。
個人情報を含むデジタルデータは、GoogleやAmazon、FacebookなどのITプラットフォーマーが大量に持っていると言われています。
ビッグデータを使いこなした会社がビジネスを制する!
54:クレド
クレドは「信条」「約束」「志」などを意味するラテン語で、企業独自の価値観や行動規範を明文化したものです。
経営理念のように抽象的なものではなく、言語化されたのがクレドなので、従業員の実務にも直結することが特徴です。
会社経営においては従業員にクレドを周知させることが重要です。
55:SWOT(スウォット)分析
SWOT(スウォット)分析は、「強み(Strength)」、「弱み(Weakness)」、「機会(Opportunity)」、「脅威(Threat)」の頭文字が由来の言葉です。
マーケティング業界では一般的なので、新規事業を立ち上げる際などは必ずSWOT分析を行っているはずです。
自分たちの強み&弱みを理解して、「どうすれば競合他社に勝てるのか?」という方向性が導き出せるので、ビジネスパーソンは覚えておきましょう。
課題を明確にするためSWOT分析を実施する。
56:VRIO(ブリオ)分析
VRIO分析は「Value(経済的価値)」「Rarity(希少性)」「Imitability(模倣可能性)」「Organization(組織編成)」という4つの頭文字が由来の言葉です。
企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」をそれぞれ評価して、自社の競争優位性を分析する手法なのですが、持続的な競争優位性を図る手法なので、長期戦略を策定する場合には有効的でしょう。
VRIO分析によって、当社の競争優位性が理解できました。
57:クラウド・コンピューティング
略して「クラウド」とも呼ばれている考え方です。
一昔前までは、ローカル環境でデータを処理していましたが、それではチームや部署での連携が面倒なので、ネットワーク上にデータを置いたり、いつでも閲覧できるような環境を用意した概念となります。
GoogleのCEOだったエリック・シュミットが提唱した考え方のようですが、ネットワークを表す時に”雲”の絵を使っていたことが言葉の由来です。
例えば、ローカル環境で代表的なのは「Excelシート」で、クラウド環境で代表的なのは「Googleスプレッドシート」といった具合なのですが、クラウドの概念を理解することは、業務効率化に直結するので、必ず理解しておきましょう。
クラウド環境が整備されているので、データはいつでも取り出せます。
58:AI
AIとは、Artificial Intelligence(人工知能)の略語で、「人間のように考えて、人間のように回答できるコンピューター」のことをいいます。
今後も自動運転技術やスマートホームなど、幅広い分野で活用されていくことが予想されています。
そして、アメリカのベンチャー企業であるOpenAIが開発したChatGPT(チャットGPT)の出現によって、AI自体はコモディティ化されつつありますが、これからも進化していくことでしょう。
将来的にはAGI(汎用人工知能:Artificial General Intelligence)にまで進化すると言われているので、もはや人間が要らなくなるかもしれません。
面倒作業はAIに任せよう。
59:シンギュラリティ
シンギュラリティは「技術特異点」と訳される言葉で、人工知能の世界的権威であるレイ・カーツワイル博士が2005年に提唱しました。
ソフトバンク創業者である孫正義も、プレゼンする機会には、しきりに「シンギュラリティ」という言葉を口にしています。
いわゆるシンギュラリティとは、AIが人間の脳を超える転換点のことです。
このポイントは必ずやってくると言われており、現状では2045年が目安だと言われています。
そうなった後の世界がどうなるのかは誰にも分かりませんが、技術の進歩を止めることができないので、シンギュラリティがやって来る心構えだけはしておきましょう。
シンギュラリティがくれば世界は変わる。
60:ディープラーニング
ディープラーニングを直訳すると「深層学習」という意味になりますが、いわゆるコンピューターが自動で学習することを指します。
脳機能の特性に似た数学的モデル「ニューラルネットワーク」と呼ばれる技術を複数の層で使って…
このような難しい話になるのですが、とにかくディープラーニングによってコンピューターはどんどん賢くなります。
そして一般的に、ディープラーニングするコンピューターのことを「AI」と表現しています。
ディープラーニングは何度も繰り返すから効果的。
61:エバンジェリスト
エバンジェリストは本来「キリスト教の伝道師」という意味の言葉です。
しかしビジネス界隈では「○○の専門家」という意味合いがあるので、「テクニカルエバンジェリスト」「セールスエバンジェリスト」などの使われ方をしています。
なので、名刺の肩書きに「エバンジェリスト」と記載している人もいます。
私は会社を代表するセールスエバンジェリストです。
62:アフィリエイト
アフィリエイトとは「成果報酬型の広告」を指します。
例えば、自分の管理するブログやSNSがあったとして、そこにアフィリエイト広告を設置すれば、副業収入が得られるかもしれません。
そのような広告出稿してくれるクライアントを探すのは大変なので、クライアント探しを支援してくれるASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)も存在しています。
ちなみにASPにはアプリケーション・サービス・プロバイダ(Application Service Provider)という意味の言葉もあるので、この辺りは混同しないように注意が必要です。
ASPの代表格といえば、株式会社ファンコミュニケーションズが提供するA8.netですが、その他にもいくつかあるので、ぜひチェックしてみましょう。
これらはウェブサイトが話ですが、店舗を活用した「リアルアフィリエイト」という仕組みもあります。
ビジネスモデルによって効果的な販売チャネルは変わってくるので、その辺りは社内で協議してみましょう。
アフィリエイト収入が10万円を超えた。
63:UX・UI
UXとはUser Experience(ユーザーエクスペリエンス)の略語で、日本語に訳すと「顧客体験」となります。
製品・サービス・システム・ウェブサイトなどの使い勝手を良くし、顧客に対して快適な使い心地や感動を提供したり、印象付けなども含んだ言葉です。
それを実際に実現してくれるのがUI(ユーザーインターフェイス)となります。
つまり、iPhoneで例えれば「直感的に操作できる」というのがUXで、「快適なタッチパネル」というのがUIに当たります。
このサービスは今まで経験したことがないUXを提供してくれる。
64:バズマーケティング
「バズる」や「バズらせる」という言葉を聞いたことがあるはずですが、その語源となった言葉です。
バズ(Buzz)は「蜂がブンブン飛ぶ音」という意味の言葉なので、元々は口コミを活用したマーケティング手法のことを指します。
しかし近年ではSNSなどを活用したマーケティングで使われるケースが増えたので、「一気に拡散させる」という認識が刷り込まれていますが、実際には少しずつ広めていくやり方もバズマーケティングに該当します。
新サービスではバズマーケティングを実施します。
65:ローンチ
ローンチ(Launch)は、ロケットを発射したり、船の推進を意味する英語です。
つまり「サービス開始」や「リリース開始」などの時に使われるので、業種・業態を問わずに活用されています。
新サービスをローンチした。
66:CGM
CGMとは、Consumer Generated Media(コンシューマー ジェネレイテッド メディア)の略語で、「消費者生成型メディア」とも呼ばれています。
一般的には、掲示板やクチコミサイト、グルメサイトなどがそれに当たりますが、Amazon.comにある「口コミ」もCGMの一部です。
ただし、CGMを信頼しすぎるのは危険なので、あくまでも参考程度にしておきましょう。
CGMはユーザーの感想が聞けるので重宝する。
67:デフォルト
デフォルトは本来「何もしない」という意味の言葉ですが、ビジネス界隈では「初期状態」という意味で使われています。
短く省略して「それはデフォなの?」と使われるケースもあります。
しかし、金融業界では「債務不履行」を表す言葉なので、業界によっては意味合いに注意しましょう。
システムのデフォルト設定を教えて欲しい。
68:コンバージョン
コンバージョン(Conversion)は「転換」「変換」などの英語ですが、IT業界では毎日のように使われている言葉です。
例えばWebサイトの成果ポイントである「資料請求」や「お問い合わせ」、ECサイトの購入に当たる部分をコンバージョンと表現しています。
そしてコンバージョンする確率のことを「コンバージョン率」や「コンバージョンレート」と表現しています。
これらはIT企業での頻出語句なので、必ずチェックしておきましょう。
コンバージョンレートが低いので改善しよう。
69:IoT(アイオーティ)
IoTは「Internet of Things」の略称で、「モノのインターネット」という意味の言葉です。
様々なデバイス(テレビや冷蔵庫、洗濯機、照明など)とインターネットを繋げることで、新しい機能やサービスを作り出す概念のことなのですが、スマートホームをはじめとして、インターネットと繋げることで、価値の最大化が出来るということです。
IoTによって、生活が豊かになった。
70:サプライチェーン
サプライは「供給」で、チェーンは「鎖」という意味の言葉です。
なので直訳すると「供給する鎖」ということになりますが、ビジネスとしての概念は「原料から製品化(又はサービス化)し、それを消費者の元に届けるまで」の流れを指します。
ちなみに、サプライチェーンの最適化を図ることを「サプライチェーンマネジメント」と呼んでいます。
弊社のサプライチェーンはとても合理的です。
71:ファブレス
ファブレスとは「Fabrication facility less」の略語で、メーカーなのに製造工場(Fabrication facility)を持たない(less)ビジネスモデルを意味しています。
これまでの製造業と言えば、自前で工場を持つのが当たり前でしたが、現代ビジネスでは逆に「ファブレスが当たり前」となっています。
弊社はアパレルメーカーですがファブレスです。
72:トレーサビリティ
トレーサビリティは、トレース(追跡)とアビリティ(能力)を組み合わせた造語ですが、原材料や製造工場、各工程の製造者や仕入先、販売元などの履歴が追跡できることを指します。
これによってトラブル発生時の原因究明や回収業務が容易になったので、そういった意味では業務効率化にも役立つはずです。
トレーサビリティによって問題解決のスピードが早まりました。
73:OEM
OEMとは「Original Equipment Manufacturer」の頭文字を取った言葉です。
その意味は、製造メーカーが委託を受けて他社ブランドの製品を製造することを指します。
これはかなり汎用性が広い考え方なので、様々なビジネスシーンでOEMは活用されていますが、最も代表的なのは化粧品業界でしょう。
当社の化粧品はOEM製造しています。
74:PB(プライベートブランド)
PBで有名なのは、イオングループの「トップバリュー」や、セブン&ホールディングスがコンビニで販売している「セブンプレミアム」などです。
これらは小売業者が企画&販売しているので、PBの定義はそのように覚えておきましょう。
PBは安いから家計が助かる。
75:エビデンス
エビデンスは英語の「Evidence」が語源になっています。
その意味は「証拠」「根拠」などですが、ビジネスシーンではよく使われている言葉です。
ビジネスパーソンであれば必ず押さえておくべきフレーズなので、ここで覚えておきましょう。
エビデンスを見せてください。
76:クリティカル
クリティカルは「危機的」や「致命的」という意味の英語です。
なので、基本的には致命傷となり得るミスやトラブルのことを指す時に使う言葉です。
クリティカルなミスが発生しました。
77:アジャイル
アジャイルとは「素早い」という意味の英語ですが、これはシステム開発に関する言葉なので、業界が違えば馴染みのないフレーズだと思います。
例えばシステムを開発する場合、要件定義をして、後は納品まで待つと思いますが、もしコミュニケーションミスによって仕様の違うものが納品されてしまうと、お互い時間がもったいないですよね。
そのような事態を防ぐために、都度状況を確認するアジャイル開発というのが、システム業界では一般的になっています。
なので、アジャイルの手法を取り入れれば、大きな失敗が無くなり、失敗のリスクが軽減できるのです。
この案件はアジャイルによって進めましょう。
78:パラダイムシフト
パラダイムシフトとは、これまでの考え方や価値観が180度変わることを指します。
技術革新や革新的なアイデアによって、世の中には度々パラダイムシフトが起こります。
例えばガソリン自動車から電気自動車に主役が移り変わったり、AIの登場などによってパラダイムシフトが起こるのです。
このような流れを読むことがビジネスでは重要だと言われています。
スマートフォンの登場によってパラダイムシフトが起こった。
79:エンパワーメント
エンパワーメントとは、権限を与えて自律的な行動を促す言葉です。
「○○をエンパワーメントする」という使い方は一般的だと思いますが、それは社内でも社外でも通用する言い回しです。
例えば弊社(WEBX)は「営業パーソンをエンパワーメントする」というテーマの事業を行っていますが、「部下のことをエンパワーメントする」という使い方もできるのです。
フリーランスをエンパワーメントする。
80:ファシリテーター
ファシリテーターは、会議やミーティングなどにおいての司会・進行役のことを指します。
ファシリテーターがいれば、コミュニケーションが円滑になるので、とても重要な役割を担っているのですが、「ファシリテーションは苦手」というビジネスパーソンは多いはずです。
そのような人は下の記事をご覧ください。
ビジネスパーソンであれば、ファシリテーションスキルを身につけることは必要不可欠だと思います。
話しやすい雰囲気を作るのもファシリテーターの役割。
81:キャズム
キャズムという言葉は、アメリカの起業家である「ジェフリー・ムーア」が、自身の著書で使った言葉です。
同名の「キャズム」という本がベストセラーになったので、ビジネス用語として浸透しました。

これはイノベーター理論になりますが、世の中にないような製品サービスをリリースした場合、それが浸透するまで”ある程度の時間”を要します。
そのプロダクトが浸透した状態のことを「メインストリームに乗った」と表現するのですが、メインストリームに乗るまでの間にキャズム(深い溝)があると主張したのです。
よって、イノベーターはキャズムを乗り越えなければ、ビジネスを成功させることができないと言われています。
キャズムを乗り越えよう!
82:インタラクティブ
インタラクティブとは「相互作用」や「対話形式」という意味で使われているビジネス用語です。
従来型のマーケティングは、企業が伝えたいことを一方的に伝えるやり方でしたが、近年はSNSが普及したので、双方向のコミュニケーションが求められるようになりました。
よってインタラクティブは、これからのマーケティングを考える上で必要不可欠な単語ということになります。
SNSを使ったインタラクティブな交流が必要だ。
83:プロパー
元々は「正規の」「固有の」「本来の」という意味の英語(proper)なのですが、ビジネス界隈では「新卒からの生え抜き社員」又は「正社員」のことを指す言葉として使われています。
特に人事部門では、中途採用と比較して「あの人はプロパーだ」というような使われ方をしています。
しかしアパレル業界でプロパーといえば「定価」を指す言葉であり、流通業界では「直接卸される商品」のことをプロパーと言っています。
なので、業界によって使い方が異なるのだと理解しておきましょう。
あの人はプロパー社員なので、社内ネットワークが凄い。
84:LTV(ライフタイムバリュー)
LTVは「顧客生涯価値」という意味で使われているビジネス用語です。
具体的には、顧客が取引を開始して、終了するまでに得られる利益のことを指しています。
なのでLTVが高いことは、顧客満足度の高さにも比例していくので、ビジネスを拡大させる上では非常に重要な要素となっています。
マーケティングする上でもLTVが高ければ高いほど、販促費もかけられるので、選択肢が広がることにもなります。
よって、LTVはビジネス上で非常に重要な項目だと言われているのです。
お客様のLTVを上げなければいけない。
85:ストックとフロー
これはビジネス界隈で当たり前のフレーズですが、主に”収益”について話す場合、ストックとフローという言葉で使われています。
- ストック:毎月入ってくる収益のこと
- フロー:1回きりしか入ってこない収益のこと
大枠ではこのような分類になっています。
例えば月額制の動画配信サービスの場合、「ストックビジネス」と言ったり「ストック収益」と表現したりします。
それと比較して、パソコンの販売であれば「フロービジネス」や「フロー収入」と表現したりします。
ただし、フローについては「ショット」や「スポット」と表現することもあるので、これらは全て同じ意味だと理解しておきましょう。
ストックビジネスを作ることが至上命題だ!
86:レベニューシェア
レベニュー(revenue)とは「収益」のことで、シェア(share)は「分ける」という意味ですよね。
つまり成果物から発生した収益を双方で分配するビジネスモデルのことを「レベニューシェア」と呼んでいます。
例えば、ネイティブアプリの企画会社Aに開発人員がいなかった場合、その案件をシステム開発会社Bに持ち込みます。
そしてシステム開発会社Bがネイティブアプリを作り上げ、企画会社Aが販売するような協業スチームでは、売れた収益に応じてA社とB社が折半するレベニューシェアという仕組みが使われています。
レベニューシェアの特徴としては「双方がリスクを負担する」ということになるので、リスク&リターンが均等でなければいけません。
新プロジェクトはA社とのレベニューシェアで進める予定です。
87:スケール
スケール(scale)は「目盛り」という意味の英語なので、「計り」のことだと思われますが、実は「規模」という意味もあるので、「ビジネスを拡大させる」という表現の時に使われているビジネス用語です。
特にベンチャー企業やスタートアップ界隈で使われているキーワードなので、その辺りで活動している人にとっては良く耳にするフレーズだと思います。
1人で始めた小さな会社が、従業員100人にまでスケールできた。
88:ゲームチェンジャー
元々はスポーツ用語なのですが、試合の途中から出場して、一気に流れを変えてしまう選手のことを「ゲームチェンジャー」と呼んでいます。
ビジネス界隈では、これまでの市場環境を一変させる商品・サービスや、それを仕掛ける企業のことを「ゲームチェンジャー」と表現しています。
一般的にゲームチェンジャーはイノベーターなので、かなり革新的なプロダクトや会社ということになります。
ゲームチェンジャーが現れたので、市場環境が激変した。
89:ケータリング
ケータリングとは、料理人が出張してその場で調理する”宅配サービス”の一種です。
企業が開催するパーティー会場やイベントなどで利用されることが多いですが、デリバリーサービスとは異なるので注意しましょう。
デリバリーサービスは、お店で調理した食事を会場へ運ぶだけなのですが、ケータリングの場合には会場で料理人が調理するので、この辺りが違いとなります。
来月のパーティーではケータリングを実施します。
90:ワーケーション
ワーケーションは、ワーク(work)とバケーション(vacation)を組み合わせた造語です。
そのネーミングの通り、観光地などで休暇を取りながら働くことを意味しています。
近年はリモートワークが普及したので、ワーケーションを取り入れる企業が増えています。
従業員にとっても、いつもと違う環境で仕事をしたり、リフレッシュできるので、それが結果的に”生産性の向上”につながっていると言われています。
新企画を考える場合にはワーケーションにしましょう。
91:IPO(株式公開)
IPOは証券用語なのですが「イニシャルパブリックオファリング(Initial Public Offering)」を省略した言葉です。
それはつまり新規上場を意味するので、基本的にはめでたい話となります。
IPOは資金調達の手段なのですが、基本的には株価が上がることになるため、創業メンバーや、投資家などに莫大な利益が流れ込みます。
それと同時に、IPOした会社には数十億円~数百億円のキャッシュが入るので、それが成長ドライブとなって、その後のビジネスを拡大させる原動力となります。
これと比較してPO(Public Offering)という言葉もあります。
POは「公募増資」を意味する言葉なので、すでにIPOしている会社が新株を発行する時に使われています。
取引先のA社がIPOしたらしい。
92:ベンダー
ベンダーは汎用的なキーワードなのですが、一般的には「製品・サービスの供給元」を意味するビジネス用語です。
つまり「メーカー」という意味合いがあるので、様々な業種業態でベンダーが活躍しています。
ビジネス現場での使い方としては、メーカーを意味するキーワードとして「ベンダー」を使っても良いですが、もう少し広いニュアンスの言葉になるので、メーカーという言葉よりも使い勝手が良いと思います。
あの会社は国内大手のベンダーだ。
93:報連相(ホウレンソウ)
報連相は「報告・連絡・相談」を省略した言葉ですが、ビジネスの基本と言われているので、多くは新入社員研修で学ぶはずです。
報連相について詳しく知りたい人は下の記事をご覧ください。
サラリーマンであれば、とにかく「報連相を徹底するように!」と言われるはずなので、報連相を怠ることは懲罰対象にもなりえます。
企業としては報連相を徹底することで、事故を未然に防ぐことができ、リスク管理にも役立ちます。
報連相は必ず行いましょう!
94:OKR
OKR(オーケーアール)は、チーム一丸の状態を生み出す目標管理手法のことです。
Googleやメルカリなどで採用されて有名になったOKRは、まだ認知度がそこまで高くありませんが、徐々に浸透しています。
具体的なやり方は、まず経営陣で全社のOKRを設定し、各部門、各チームはそれぞれ経営陣が決めたOKRに基づき、自分たちのOKRを作成していきます。
その進捗や成果を、毎週お互いに報告しあって、短期間で頻繁に見直すのです。
このようなやり方をすれば、全社員に”会社目標”が浸透し、自分が活躍するポジションとの関連性も理解しやすくなると言われています。
社員の気持ちがバラバラなので、OKRを導入しよう!
95:オンボーディング
オンボーディングを直訳すると「乗り物に乗る」という意味ですよね。
具体的な使い方としては、中途社員などに対して、会社の文化(カルチャー)を理解してもらい、早く職場に馴染んでもらうための入社プログラムを指します。
OJTと違って、早く職場環境に順応してもらうための機会を提供することが目的になっているので、その違いを理解しておきましょう。
最近入社した人とオンボーディングを行って、早く馴染んでもらいましょう。
96:オーソライズ
オーソライズとは「権限を与える」「正式に認める」などを意味している英語です。
なのでビジネスの現場では、公的機関や権限のある人から公認されたり承認されたことを指しています。
これはつまり社会的なお墨付きを得ていることになるので、ビジネスを進めるためには必要不可欠だと言えます。
国際認証機関からオーソライズを得ています。
97:SEO
SEOは「Search Engine Optimization」の略称で、「検索エンジン最適化」という意味で使われています。
ビジネスにおいてはGoogleなどの検索エンジンで上位表示することが非常に重要なので、webサイトを持つ企業であればSEO対策をすることは欠かせないと言われています。
ちなみにSEOと似た言葉には、MEOやLPOなどがあります。
MEOとはMap Engine Optimization(マップ検索エンジン最適化)の略称で、主にGoogleマップ向けの地図エンジンで上位表示させるための施策を指します。
そしてLPOは「Landing Page Optimization」の略称で、サービスの申し込みや資料請求などのコンバージョンがより多く発生するように、ランディングページを最適化する手法のことです。
他にもEFOなど、IT業界には3文字のキーワードが多いのですが、主要なビジネス用語は覚えておきましょう。
弊社のウェブサイトはSEOで上位表示しています。
98:オフレコ
オフレコは英語の「off the record」を省略した言葉です。
元々は報道関係者が使っていた業界用語なのですが、それがビジネス界隈で一般的に使われるようになりました。
ちなみにオフレコの意味は「記録にとどめないこと」「談話などを公表しないこと」「非公式にすること」を意味するので、「ここだけの話ですが…」という時に使いましょう。
この話はオフレコでお願いします。
99:グロースハック
グロースハックは、商品サービスを大きく成長させる一連の仕掛けや仕組み作りのことを指します。
それをする人のことを「グロースハッカー」と呼んでいて、組織の中では非常に重要なポジションとなります。
グロースハックはモノやサービスの機能や設計、内容にまで踏み込んで改善を行い、大きな成長を目的とします。
そのため部署を超えた”大きな権限”が与えらているケースが一般的です。
既存サービスをグロースハックして急成長させましょう!
100:ピッチ
ピッチは、短時間で投資家や決裁者に提案することを指します。
つまりは”短時間のプレゼン”なのですが、5分程度の時間で相手にビジネスアイデアを伝えるということがポイントになっています。
ちなみに一般的なプレゼンテーションとの違いは以下の通りです。
- プレゼン:営業担当者などが行う。時間は30分~1時間。予算の獲得を目的とする。
- ピッチ:起業家が行う。時間は5分程度。出資を目的とする。
この違いを押さえておきましょう。
スタートアップ企業の経営者は、積極的なピッチをするべきだと思います。
ビジネス用語は”重要フレーズ”だけ覚えよう!
ここまで様々なビジネス用語をご紹介してきましたが、あまりに数が多いので覚えきれないと思います。
なので、基本的には”自分の業界がよく使うフレーズ”を覚えれば十分だと思います。
例えば、IT業界であればCV(コンバージョン)やPV(ページビュー)などは頻出フレーズになっているので、IT系の会社に勤めているなら絶対に押さえておくべき言葉だと思います。
しかし、食品業界に勤めている人が理解していなくても問題ないフレーズなので、業界によって必要な知識は変わってくるはずです。
なので「自分の仕事に必要なキーワードだけは絶対に押さえる」という感覚で大丈夫だと思います。
ビジネスパーソンなのであれば、日頃から自己研鑽に励みましょう!