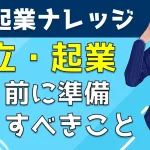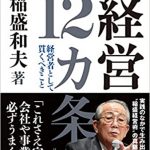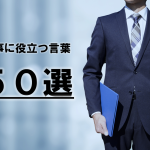ビジネスパーソンであれば「ファシリテーション」という言葉を聞いたことがありますよね。
ファシリテーションは「優れたビジネススキル」のように感じるかもしれませんが、ファシリテーション能力は特別な才能ではありません。
日常生活で使ったり、会議で使うこともできるので、ファシリテーターのスキルは全てのビジネスパーソンが身に付けるべきだと思います。
そこで今回は、ファシリテーションスキルについて解説していきたいと思います。
経営者や事業責任者など、ビジネスリーダーを目指す人はぜひご覧ください。
目次
ファシリテーションとは?
会社員として働いていれば、必ず『会議』に出席する機会があると思いますが、とにかく無駄な会議が多いことに気付きますよね。
- 誰も意見を言わない『しらけた会議』
- 上司ばかりが発言する「一方通行の会議」
- 目的が定まっていない『意味不明な会議』
- 意見が食い違ってばかりの『喧嘩会議』
- 各部署が主張を繰り返す『自己主張会議』
サラリーマンであれば、このような会議に一度くらい出くわしたことがあると思います。
そんな時に「優秀なファシリテーターがいたらなぁ…」と考えたことがあるかもしれません。
下のような『説教会議』は本当に嫌ですよね。







このような説教型の営業会議であれば、もはや『報告』なので、メールを送っておけば済むはずです。
しかし上司が説教したいがために、わざわざみんなを集めて会議を開いているのです。
これは上司が『仕事した気になる為のパフォーマンス』なので、決して生産性が上がることはありません。
このような会議は『無駄会議』の典型例だと思いますが、実はこのような会議を『有意義な会議』に変化させることもできるのです。
そのような場面で求められるのが『ファシリテーター』という存在です。
そもそもファシリテーションとは英語の「facilitate」を語源にしていて、物事や仕事がスムーズに進む、楽になるという意味や、促進する、円滑に進める、手助けする、などの意味が含まれています。
それらの意味を踏まえてファシリテーションを要約すると『参加者の協力を促して、全員が納得する結論を導き出すために支援すること』ということになります。
ファシリテーションのノウハウは会議だけでなく、プロジェクトや組織運営などにも応用できるため、ビジネスパーソンが身に付けておくべきスキルだと言えます。
ファシリテーターの役割とは?
ファシリテーションを推進する人が「ファシリテーター」です。
これだけ聞くと誤解されやすいのですが、実は『ファシリテーター=司会進行役』ではありません。
司会進行役は議題と進行表に従って会議を進めていくだけなので、基本的には参加者に配慮することはありません。
これはセミナーの司会進行役をイメージすればわかると思います。
しかしファシリテーターは、参加者から出てきた意見を整理整頓したり、バラバラな意見をまとめたり、参加者にヒントを与えたりして、会議全体を活性化させる役割があるのです。
例えば先ほどの無駄会議にファシリテーター(以下「FA」と省略)が参加すると、具体的には以下のようになります。







このようにファシリテーターとは、会議の目的が達成されるようにメンバー全員の協力を促し、ミーティング全体をコントロールしていくのです。
これがファシリテーターの役割となります。
ファシリテーションが注目される理由
近年ファシリテーションは注目されていますが、その理由は一体何なのでしょうか?
- ビジネスはスピードが命だから
- 多様化が求められている
- 透明性が求められている
これは当たり前の話ですが、とにかく「①ビジネスはスピードが命」だと言えます。
競合他社も必死なので、早めに手を打たないと、すぐに置いてかれてしまいます。
対応が後手に回ってしまうと、色々な所でトラブルが頻発してくるのです。
そのようなリスクを回避するという意味で、現代ビジネスでは意思決定のスピードが求められているのです。
そして「②多様化が求められている」ことも外せない要因だと思います。
様々な部署、役割、意見などが尊重される時代なので、組織をまとめ上げるにはそれらを統括しなければいけません。
そもそも上司の意見が絶対正しいということもないので、ビジネスのやり方が変わったということでしょう。
そして「➂透明性が求められている」という側面もあるでしょう。
旧態依然の企業経営はトップダウン式でしたが、現在はIT社会なので透明性が求められます。
できる限り情報をオープンにして、「なぜこのような意思決定が行われたのか?」という部分に納得感を持ってもらう必要があるのです。
従来型の会議ではこの部分が満たせなかったため、結果的にファシリテーターのニーズが出てきたのだと思います。
ファシリテーションのやり方
ここから具体的なファシリテーションのやり方について解説していきたいと思います。
まずファシリテーターがやるべきことは、会議の参加者の意思統一です。
『この会議は何を目的にしているのか?』というのをクリアにし、出席者全員に周知させるのです。
ここで重要なことは『自己中心的な意見を控える』ように促すことです。
自己中心的な意見とは以下のようなものです。





この会議では、各自がそれぞれ自分の主張ばかりしていますよね。
それぞれ自分の立場を守るため(社長に怒られたくない、自分の仕事を増やしたくないなど)に、その責任を他担当者へ押し付けようとしているのです。
参加メンバーの目指すべき方向性が一致しておらず、これでは「一枚岩のチーム」と呼べる状況ではないと思います。
なので、ファシリテーターは会議の冒頭で以下のことを明確に伝えなければいけません。
- 会議の目的
- 会議に求める成果
- 参加メンバーが召集された理由
会議の参加者にこれらを伝えて、まずは納得感を持って会議することが必要なのです。
それによって参加者全員が同じ方向を向くので、ファシリテーターの求める成果が出やすくなるのです。
中立的な立場であること
ファシリテーターは中立的な立場でなければいけません。
例えば対立する二つの意見(AとB)があった場合、どちらか一方に加担してはいけないのです。
ファシリテーターは会議全体をコントロールする立場なので、どちらか一方に加担してしまうと公平な会議が実現できなくなります。
なのでファシリテーターとして立ち回る場合には、自分の主観は一旦横に置いておきましょう。
とはいえ、ファシリテーターも自分の意見が言いたいことはありますよね。
その時には、自分の意見を述べても構いません。
ただし、それはあくまでも自分個人の意見であり、ファシリテーターとしての意見ではないことを自覚しておきましょう。
ファシリテーターが「自分の意見は正しい」と決めつけたり、その方向に持っていくように全体を誘導することは、原則的にNG行為なのです。
ファシリテーターは常に中立公平な立場で、会議全体を俯瞰的に見るようにしましょう。
会議をマネジメントする
ファシリテーターは会議の成果を求めなければいけません。
そのために必要なのが会議全体をマネジメントすることです。
具体的には下の4つをコントロールする必要があります。
- 議論の時間
- 議論の内容
- 議論の道筋
- 議論の参加者
特に『議論の時間』には神経を使うはずです。
会議には『所定の時間』が設定されていると思いますが、ファシリテーターは必ずその制限時間を守らなければいけません。
熱くなった参加者は時間を気にせずに意見するケースがあるので、そのような場合には途中で話を遮ることも必要だと思います。
会議に脱線はつきものですが、それを軌道修正させて、タイムマネジメントすることがファシリテーターの腕の見せ所だと言えます。
そう考えた場合「理論の道筋」をあらかじめ想定しておくことが求められます。
「〇〇さんと▲▲さんが参加する会議だから、おそらく着地はこの辺りになるだろうな…」と目星をつけておくのです。
それを想定して時間配分を決めておき、議論が本筋から反れないようにコントロールしていくのです。
そして参加者自体をコントロールすることも重要です。
人間には感情があるので、どうしても感情的になってしまう人が一定数出てきます。
そのような状況でもファシリテーターは冷静に判断し、本筋から逸れないようにコントロールしていくのです。
そして参加者の誰かに非難が集中した場合、ファシリテーターはその人を守る義務も負っています。
会議というのは誰かを非難したりつるし上げる場ではないので、そのようなことに時間が無駄遣いされることを防がなければいけません。
あと会議に対して積極性が見られない参加者を促す役割も担っています。
発言をしないということは「会議に興味がない」「反対意見を恐れている」「何も考えていない」などのケースが考えられますが、ある程度を予測をつけながら参加者全員が活発に意見交換できる場を作り上げるのです。
そのような前提に立った場合、ファシリテーターは参加者全員の属性を把握しておく必要があるはずです。
どのような立場の人で、どれほどの権力を持っていて、どんな性格な人なのか、などをリサーチしておくのが理想的でしょう。
ファシリテーションのコツ
ファシリテーションを成功させるためには、ある程度のコツを身につけておかなければいけません。
ファシリテーションする場面というのは会議や講演会などですが、まずは参加者全員の意見を引き出して『横の広がり』を意識しなければいけません。
そして目的にそぐわない意見が出た場合、その意見を制して会議全体をコントロールしていくことも必要です。





このように意見出しの場面では、様々な意見が様々な角度から出るように、ファシリテーターが自由な発言を促していきます。
もしそれらの意見に反論したり、批判するような人がいればファシリテーターがマネジメントするのです。
年下(又は格下)から発言させる
会議で活発な意見が出なければ結論はまとまりません。
しかし日本人は欧米式のディベートに慣れていないため、なかなか自分の意見を言えない人が多いように感じます。
そんな時、ファシリテーターが日本式のアレンジをしてあげることも大切でしょう。
例えば一番最初に年下の人を指名したり、役職が下の人から意見させるのです。
一番最初に社長や部長などの重役が意見すると、一般職の人はそれに対しての反対意見を言いづらくなってしまいます。
なので、最初に一般職から自由な意見を述べてもらい、その後に重役が意見を述べる…、というのが現実的なファシリテーションなのかもしれません。
意見をまとめる
ファシリテーターは参加者に対して意見を求めますが、それらはバラバラな意見であることがほとんどです。
なので、出された意見をファシリテーターがまとめる必要があります。
その時のポイントは下の3つに集約されていきます。
- 意見の集約
- 意見の関連付け
- 意見のレベル合わせ
『意見の集約』とは、似たような意見をまとめてしまうことです。
社員旅行の行き先について聞いた場合、「ハワイ」と「グアム」が出てきた場合、それを「海外の南国リゾート」とまとめてしまうのです。
これがつまり大カテゴリーということになります。
このような大カテゴリーができたら、今度はそれを関連付けしていきます。
例えば社員旅行の行き先で「温泉地」という大カテゴリーがあった場合、それは果たして「海外の南国リゾート」と対立する意見なのか、それとも関係性が深いのかなど、大カテゴリー同士の関連性を検証するのです。
その過程で「草津温泉」という意見があった場合、それは「温泉地」よりもレイヤー(階層)が下なので、温泉地の下に草津温泉が内在されるようにまとめていきます。
縦方向に深掘りする
先ほど「まずは参加者全員の意見を引き出して『横の広がり』を意識しなければいけません。」とお伝えしました。
それが一通り終わった段階で、次にやるべきことは『縦方向に深掘り』することです。
例えば「南国リゾート」が最有力候補になった場合、その中で沖縄を検討することになったとします。
しかし沖縄には「沖縄本島」「宮古島」「石垣島」など、いくつかの島があり、どこへ行くのかによって内容が変わってきます。
このように深堀りをしていくのですが、ここで注意すべきことは議論を逆戻りさせないことです。
議論が逆戻りし出すとキリがないので、会議の収拾がつかなくなってしまいます。
そして最終的に全員が納得する着地点を探し出し、そこで合意形成するのです。
全員が納得するような完全合意であれば理想的ですが、一部の人が妥協する着地になるかもしれません。
しかしそれでも、目指している方向性が一緒なのであれば、さほど大きな問題にはならないはずです。
重要なのは参加者全員の目指すゴールが同じ方向であることです。
個々人の利害というよりは、会社全体の利益を追求する心構えが重要なのだと思います。
ファシリテーションスキルを磨こう!
ファシリテーションスキルは、ビジネスリーダーを目指す上で必要不可欠な能力だと思います。
アップル創業者のスティーブ・ジョブズは、ビジネスリーダーのことを「Gravitational Force(重力のような力)」と表現しました。
従業員が多くなって、多様性が高まっていくと、それをまとめる『重力のような存在』が必要になるのです。
まさにそれがファシリテーターなのだと思います。
そのようなポジションになるためには、ファシリテーションスキルを磨く必要があります。
その代表例がヒアリング能力だと思います。
つまり相手の話を聴くということです。
きちんと相手のことを見ながら「何が言いたいのか?」を理解して、その内容を要約するのです。
それを何度も繰り返しながら、最終的には会議全体を要約していくのです。
質問スキルを磨く
質問スキルが高い人ほど、優秀なファシリテーターだと言えます。
なぜかといえば、質問は会議の流れを変えたり、参加者の意欲を引き出したり、発言を促すことができるからです。
そのアプローチ方法には大きく2種類のやり方があります。
- オープンクエスチョン(拡大質問)
- クローズドクエスチョン(限定質問)
この2つについて話すと長くなってしまうので、詳しく知りたい人は下の記事をご覧ください。
ファシリテーターは脇役である
ここまでファシリテーションについて解説してきましたが、あくまでもファシリテーターは脇役で、主役は会議の参加者です。
その主役を引き出すためには、上手な話し方や誘導が必要となります。
なので、日頃から大勢の前で話す機会をたくさん持つことも必要でしょう。
それが練習となって、ファシリテーションスキルの向上につながっていくはずです。
もしかしたらプロジェクトメンバーの中でも摩擦が起きるかも知れませんが、それを恐れてはいけません。
ファシリテーターの積極性次第で会議の良し悪しが決まってきます。
この記事を参考にして、ぜひ自分のファシリテーション能力を向上させてください。