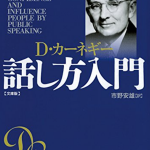日本における証券会社は、リテールやホールセールを有している昔ながらの大手証券会社と、マネックス証券や松井証券、SBI証券に代表されるようなネット証券に分類されます。
ネット証券は先進的な仕組みなので”リテール営業”ではありませんが、大手証券会社ではまだまだリテール営業が盛んに行われています。
そこで今回は、証券会社に就職を考えている人や、ビジネスモデルを知りたい人に向けて元証券マンが解説していきたいと思います。
出来る限り生々しい現場の実態をお伝えしたいと思うので、これから就職活動する人は参考にしてください。
目次
証券会社の営業職とは?
皆さんこんにちは、営業シークの「さの編集長」です。

私は2007年に「大手証券会社(?)」と言われる大和証券に総合職として新卒入社しました。
退職したのが2010年だったので、約3年ほど在籍したことになります。
その期間の業務内容は、個人富裕層を対象とするリテール営業でした。
ちなみに、証券会社の営業職には大きく2種類があるので、ここで押さえておきましょう。
- リテール:証券の販売
- ホールセール:証券の仕入れ
ホールセールは証券会社の”花形職”とも言われますが、IPOする企業から主幹事に指名してもらったり、社債を発行する会社から幹事に指名してもらう為に営業する職種です。
いわゆる仕入れの営業になります。
それと比較してリテール営業とは、仕入れた証券を投資家へ販売する職種になります。
一般的な証券営業とは、この”リテール営業”を指すことが多いはずです。
ちなみに私はリテール営業だったので、顧客層は経営者や医者、弁護士など「地元の名士」と呼ばれる人達、又はキャッシュリッチな法人顧客でした。
そのような人達に対して、株式を提案したり、債券の販売などを行っていきます。
まさにこのような仕事が「ザ・証券営業」という感じですが、私が在席していた当時、会社として一番注力していたのは投資信託(ファンド、ラップ口座、SMAなど)でした。
投資信託には”純資産総額”という重要指標がありますが、これがつまり運用総額を意味しています。
この純資産総額を積み上げることが『証券会社における最重要ミッション』であり、これが積み上がらないと死活問題になってしまうのです。
なぜかと言うと、それは証券会社の収益体制が関係しています。
この辺りを次で解説したいと思います。
証券会社の収益体制を解説!
証券会社の収益は主に”ブローカレッジ業務”で成り立っています。
つまり仲介手数料で稼ぐのです。
例えば株式売買についてですが、株式市場は広く公開されていますよね。
誰でも市場(東京証券取引所など)を通じて売買できますが、そのためには必ず証券会社(=証券口座)を介しなければいけません。
これは大手証券会社でもネット証券でも同じはずです。
つまり市場に注文を流すのは、証券会社の独占業務となっているのです。
それゆえに、注文が入れば入るほど証券会社は儲かるという仕組みになっています。
証券会社の経営者(社長)が「今年の目標株価は○○万円です」とか「今年の株価は上がる」とテレビで語っていますよね。
あれはある意味でポジショントークなのですが、証券売買を活性化させるために言っているのだと思います。
ということで、「ブローカー」と呼ばれる証券営業マンは、とにかくお客様から注文を取り付ける必要があるのです。
それは株式の買い注文でも売り注文でも関係ありません。
債権も同様に売買手数料が発生するので、買い注文か売り注文をしてもらわなければ儲かりません。
このように証券会社の収益体制というのは、売買手数料で成り立っているので、「顧客の預かり資産をいかに動かすか?」がポイントになってくるのです。
このあたりが銀行のビジネスモデルと大きく違う部分だと思います。
しかしその一方で、管轄省庁である「金融庁」は、頻繁な回転売買を禁止するように通達しています。
「回転売買」とは金融商品を短い保有期間で「買って売る、もしくは売って買う」行為を指します。
投資は原則的に「長期投資」が基本となるので、金融庁は回転売買を「良し」としないのです。
そうすると仲介手数料が入らないので、証券会社は困ってしまいますよね。
この問題を解決するために、証券会社と金融庁が一緒になって作り出した商品が投資信託なのです。
つまり、投資信託とはスポット型の収益体制から抜け出すために考え出された「証券会社にとって都合の良い金融商品」ということです。
投資信託の仕組みとは?
ここから具体的に投資信託の仕組みを解説していきますが、投資信託には2つの収益ポイントがあります。
- 買付手数料
- 信託報酬
買付手数料とは、投資信託を購入する時に発生する手数料を言います。
原則的に解約する時にはかからないので、購入がたくさん発生するほど儲かる仕組みになっていますが、ネット証券では「買付手数料無料(ノーロード型)」が出てきているので、今後はこれに頼るのが難しいかもしれません。
そして二つ目の信託報酬…
実はこれが証券会社にとって非常に重要な収益源となっているのです。
信託報酬を簡単に言い換えてしまうと「運用手数料」となります。
投資信託はバスケット取引になるので、それを運用するファンドマネージャーという人がいます。
他にもファンド運営に携わる人がたくさんいるので、そのような人たちの給料を賄う信託報酬(=運用代行料金)が必要となるのです。
そのパーセンテージは様々で、近年は低コスト型も多くなってきましたが、大手証券会社では年間1%~2%がおおよその目安だと思います。
例えばある投資信託Aの信託報酬が1%だった場合、1億円の純資産総額であれば年間100万円の運用手数料が証券会社に入ることになります。
これが証券会社にとってはストック収益(継続収入=不労所得)になるのです。
純資産総額に応じて1%が毎年キャッシュインするのであれば、とにかくその純資産総額を積み上げてしまえば、安定的な経営が実現しますよね。
なので、新規設定の投資信託は1,000億円規模(※大和証券の場合)で設定されることが多く、その募集が完売すれば、毎年10億円のストック収益が確定することになるのです。
これを積み上げる為に、証券会社は手を変え品を変えながら投資信託を新規設定しているのです。
投資信託は解約できない?
よく「証券会社は投資信託の解約をさせてくれない」という噂を耳にしますが、それは事実だと思います。
なぜかといえば、せっかく積み上げた信託報酬が減ってしまうからです。
証券会社の営業マンは”投資信託の販売”が最重要項目に設定されているため、その純資産を減らす行為は営業成績にマイナス効果をもたらします。
なので、証券会社の営業マンはなんとしても投資信託の解約を阻止したいのです。
現役だった頃、高齢のお客様が「1億円分の投資信託を解約したい」と支店を訪れていました。
その担当者はライン課長でしたが、さすがに1億円分の投信解約は支店長の成績にも大きく響くので、支店長と一緒になって一生懸命に解約させないように説得していました。
それでも結局解約となったので、支店長は頭を抱えていたのを覚えています。
先ほどもお伝えしましたが、旧態依然の証券会社のビジネスモデルは「売買手数料=スポット収入」だったので、相場が下落した時に”預かり資産”が動かず、それに伴い「収益も上がらない…」という悪循環に陥っていました。
そのような問題点を解決した画期的な金融商品が”投資信託”です。
なので、証券会社に就職するのであれば、本位&不本位は関係なく、とにかく投資信託を売りまくらなければいけません。
投資信託であれば相場下落時にも信託報酬が入るため、経営の安定化が実現します。
これは経営者にとって非常に重要なポイントとなるので、証券会社の営業マンはひたすら投資信託の販売を命じられるのです。

証券営業はきつい…
証券会社の営業は非常にきついと言われています。
一般的には「3年もてば凄い」と言われるほどなので、どれだけ激務なのかなんとなく想像できますよね。
実際、大和証券時代にさの編集長がこなしていた1日のスケジュールをご紹介したいと思います。
AM6:00 起床
AM6:10 朝ごはんを食べながら、テレビ東京の「モーニングサテライト」を見る
AM6:30 出勤する支度を始める
AM7:00 出勤する為に自宅を出るが、時間がないので移動しながら日経新聞を読む
AM7:20 出社したデスクで日経新聞を読みながら、全世界の株式相場を確認する
AM8:00 全体ミーティングに参加する(基本的には支店長が怒鳴るだけの無駄会議)
AM9:00 株式相場が開くと同時に顧客からの注文が殺到する
AM11:30 前場終了
AM11:45 お昼休憩(昼休憩は原則15分以内、30分休めれば御の字)
PM12:15 休憩から戻り午後の相場に備える(休憩から戻ると顧客からの入電連絡が5件~10件ほど溜まっている)
PM12:30 後場開始
PM15:00 後場終了(ここから訪問営業に切り替える)
PM16:00 顧客宅に訪問して募集物(投資信託や外債など)を提案する
PM17:00 顧客に提案した募集物をインプット(注文)する
PM18:00 本日の業務を日報にまとめる
PM19:00 退社して同僚と飲みに出掛ける
PM23:00 帰宅して就寝
上記のようなスケジュールが基本ですが、上司に飲みへ連れて行かれると午前1時、午前3時に帰宅というのが当たり前でした。
※私個人の感想ですが、とにかく証券会社の人は体育会系なのでお酒を飲む印象が強かったです。
それでも翌朝6時に起きなければいけないので、かなり辛かったですが、少しお酒が残っている方がセールストークは走るので、その方が意外と売れるんですよね。
一番ショッキングだったのは、午前4時まで上司に連れ回されて、ベロベロに酔っ払って帰った結果、次の日5分だけ遅刻してしまいました。
すると、連れまわした本人(上司)は何事もないように出社していて、自分が連れ回したことは蚊帳の外で、とりあえずメチャクチャ怒鳴られたことを覚えています。
私は心の中で「お前が連れまわしたんだろ(怒)!」と感じていましたが、それと同時に「本当に証券会社って体育会系なんだなぁ~」と実感した瞬間でした。
このような愉快な日々を過ごしていましたが、数字の管理は30分ごとなので、上司から30分ごとに進捗状況を聞かれることになります。










これじゃ、借金の取り立てと同じですよね。
お客様に「早く金を振り込め!」と催促することになるので、このような仕事はとてもストレスを感じます。
IPO(新規公開株)の販売をしていた時、お客様が入金日を間違えていて、あと1時間でインプット(注文)の締め切りというギリギリな場面がありました。
そのお客様は高齢な上、足が悪かったため「今からすぐ銀行へ行くのは無理だ」と言われてしまいましたが、インプット(注文)しないと非常にマズいので、その時にはお客様の自宅まですぐ車で行って、郵便局ですぐに振り込んでもらえました。
ギリギリ5分前のインプット(注文)だったので、冷や汗をかいたのを覚えていますが、それと同時に高齢のお客様を連れ回した罪悪感はひどかったですね。
しかもその後、購入したIPO(新規公開株)は大きく値下がりして、お客様にとっては踏んだり蹴ったりでした。
話はそれましたが、後場が終わってからも仕事があります。
退社するまでの間に、投資信託や外国債券の契約を取らなければいけないので、とにかく時間がありません。
5分単位でスケジュール管理しなければいけないので、移動中は常に走っていた記憶があります。
個人的には「証券会社と佐川急便はあまり変わらないな」と思っていました。
それほどきつい仕事が証券会社のリテール営業なのです。
証券会社の営業ノルマは?
まず最初に言っておきますが、証券会社の営業ノルマはとてつもなく重いです。
具体的に言ってしまうと、以下のようなノルマがありました。
- 新規開拓件数
- 預かり資産総額
- 株式売買手数料
- 債券売買手数料
- 新規公開株式の販売(IPO)
- 公募株式の販売(PO)
- 社債の販売
- 個人向け国債の販売
- 仕組み債の販売
- 外国債券の販売
- ファンドラップの販売
- SMAの販売
- 投資信託の販売
- 投資信託の預かり資産額 etc.
一般的な中小ベンチャー企業では1つ2つの目標を追えばOKですが、大手証券会社では10以上のノルマを同時平行で追っていきます。
ここに記載したノルマはほんの一部ですが、これらを全て同時並行でこなしていくのです。
もちろん商品ごとに特性が違いますし、販売手数料やリスクも違ってきます。
それらをすべて暗記(頭に叩き込む)して、お客様へ提案していくのです。
もちろんリスク説明や手数料などを間違えると金商法(金融商品取引法)違反になるので、懲罰対象となります。
よって、証券営業を目指すなら、とにかく数字に強くなければいけません。
例えば、ある投資信託Aの買付手数料は1.3%、信託報酬は1.56%ですが、投資信託Bの買付手数料は3.15%で、信託報酬は2.13%みたいな感じです。
そして債券は年利5.6%などのクーポン(金利)が付きますが、外国債券の場合には為替が関係するのと、スプレッド(為替手数料)も発生するので、かなり計算がややこしくなります。
- 1500万円で社債(金利6%)を買った場合、1年間で受け取れる利子はいくらになる?
- 株価66万円の銘柄を300株購入したらいくらになる?
このような質問をお客様は普通にしてくるので、それをその場で即答しなければいけません。
もちろん電卓を叩いてもOKですが、それでは馬鹿(計算できない証券マン)をさらす羽目になるので、経営者やドクターからは相手にされません。
大切なお金を預ける証券マンなので、優秀な人と取引したいのは当たり前だと思います。
電話営業(テレアポなど)の場合にも全て会話が録音されていて、逐一コンプライアンスチェックされています。
支店長などの手が空いた時に、その通話記録を聞かれて、適時指導が入るので、どんな時にも気が抜けません。
よってストレスで胃に穴が開いたり、うつ病になる人が続出するのです。
これはあくまでも”さの編集長”が現役だった頃の話ですが、40歳オーバーのライン課長がうつ病になって休職したり、30歳半ばの中堅社員がストレスで脳卒中になって倒れたり、新卒社員が飛んでしまうのは毎年の恒例行事でした。
そして、一番きついノルマが「募集物」と呼ばれる商品です。
証券発行は”発行体”からすると資金調達の手段なので、新規発行する場合には「○○までに売り切らなければいけない」という期限が設けられています。
例えば、新発社債や新規公開株、新規設定の投資信託などが代表的だと思います。
これらはすべて 「募集物」と呼ばれていて、所定の期日までに売り切らなければいけないのです。
「募集物」は各営業マンごとにノルマが按分されていて、営業マンAは3,000万円、 営業マンBは5,000万円という具合に個人ノルマが設定されています。
証券会社ではこの個人ノルマを売り切らないと、とんでもない目に合います。
全体ミーティングでは「ダメ営業マン」とさらし者にされ、上司からは30分置きに罵倒されることになるのです。
しかし、その募集物だけに注力していると、「○○の進捗はどうなっているんだ!」とか「▲▲の数字ができてないぞ!」と怒鳴られるのです。
証券会社には注文時間という制約がある為、本当に5分単位(どんなに緩くても10分単位)でスケジュールを調整しなければいけません。
なので、ゆっくり昼食することなどできませんし、お客様とダラダラ会話することもできません。
このような状況に耐えうるだけの強靭なメンタルと、常に走り続ける(=リアルに走ること)フィジカルを持っていなければ、証券営業は務まらないのです。
このような状況に耐えきれなくて、入社したほとんどの営業マンが退職していきます。
ちなみに、さの編集長の営業同期は2,000人もいましたが、私が退職する3年目には1,500人ほどが既に辞めていました。
とんでもない離職率だと思いますが、これが普通だったのです。
証券営業は地獄の日々…
さの編集長が証券会社に入社したタイミングは2007年なので、金融大不況が来る2008年のリーマンショックとほぼ同時期でした。
なので、証券会社に入社する時期としては最悪期だったと言えます。
どんな金融商品を販売しても全て下がっていくので、顧客からは「詐欺師!」とか「騙された!」なんて言われることが日常茶飯時で、「もう電話してくるな!」とか「顔も見たくない!」なんてことはしょっちゅうでした。
お客様の家のインターホンを押した時、木刀を持って出てこられた時には殺されるかと思いましたwww
それもこれも相場が悪かったせいなのですが、募集物に限ってはそう割り切ることができません。
先ほどもお伝えした通り募集物には期日があるので、とにかく売り切らなければいけないのです。
なので、たとえ自分が「これは微妙だな…」とか「こんなの儲かるわけない」と思っていても、自分なりにセールストークを組み立てお客様に売り込まなければいけません。
正直に言ってしまうと、自分では絶対買わないような商品ばかりだったと記憶していますが、本社の企画部が一生懸命に考えた商品なので、そこは割り切って頑張る必要があると思います。
実際、証券会社の人間は募集物に手を出すことはありません。
そもそも投資信託すら買わないのです。
職業上、個別株の売買が自由にできないので、仕方なく投資信託を買っているケースはありますが、もし株式の売買制限がなければ、証券会社の社員は誰も投資信託なんて買わないでしょう。
それほどデメリットが大きいと認識している商品ばかりを販売するので、とんでもないストレスを背負うことになります。
新興国通貨建ての外国債券(トルコのリラ債)を販売してた時ですが、表向きは「買いましょう!」と提案をしながら、心の中では「頼むから買わないでくれ!」と祈ってることもありました。
結局お客様は証券マンを信頼しているので買ってしまうのですが、帰りの車中では大きなため息をついたことを覚えています。
あの時、リラ債を1000万円分購入していただいたお客様がいましたが、今は為替が1/10(2023年1月現在)になっているので、その資産価値は100万円以下に値下がっているはずです。
「投資は自己責任」と言えば簡単ですが、個人的にそれは無責任だと思っています。
やはり営業職なので、本当に自信のある商品だけを提案するべきなのですが、募集物があるのでネガティブだったとしても売らなければいけないのです。
当時の支店長よく「買うのを決めるのはお客様。だから損しようが儲かろうがそんなの知ったこっちゃない。とにかくお前らは提案しろ!」と叫んでいましたが、内心では「それはちょっと…」と感じていました。
ある支店のトップセールスと立ち話した時、その人が「毎日高いビルを探すようになるよ」と言っていました。
いざとなったらそのビルから飛び降りて楽になれるからです。
相場が悪いとこのような日々が続くので、生き地獄のような毎日を経験することになるでしょう。
自分の存在価値がわからず、苦悩することもあると思います。
しかし「お客様のため」と自分自身を奮い立たせて、日々仕事に邁進しなければいけないのです。
証券会社の営業は年収が高い
証券会社の営業はとても辛い仕事ですが、原価がないビジネスなので、とても儲かる商売だと言われています。
特に投資信託などは、顧客が儲かろうが損しようが関係なく”信託報酬”が入ってくるので、それが給料にも反映してきます。
証券会社の営業マンは年収が高いと言われていますが、実際そうだと思います。
特に大手企業の場合には福利厚生が充実しているので、飲食代以外の生活費がほとんどかかりません。
例えば”さの編集長”の場合には、家賃、水道光熱費、交通費、インターネットなどの費用を全て会社が負担してくれたので、毎月の給料がまるっと可処分所得になっていました。
さすが大手企業ですよね。
さらに、100年に1度の金融大不況と言われる状態でも、半年に1回のボーナスは100万円以上出ていました。
正確に言うと200万円弱でしたが、世間の平均ボーナスが50万円とかゼロなんて言われていた時期なので、大手証券会社の凄さはそのような時に実感できると思います。
※日系の証券会社でも、営業成績さえ良ければ十分稼げます。
もちろんボーナスも全て可処分所得に入っていくので、年間の可処分所得は500万円以上になると思います。
つまり月当たりに直すと「500万円÷12ヶ月=約41万円」という計算になります。
毎月40万円も自由に使えるので、毎日1万円使ってもまだ余りますよね。
入社3年目でこれだけ稼げるのは金融業界ならではと言えるでしょう。
しかもこれは金融大不況といわれたリーマンショックの時代なので、それ以外の時には倍程度になってもおかしくありません。
なので営業職として稼ぎたい場合、証券営業を志望するのはとても合理的な判断だと思います。
証券会社って実際どうなの?
ここまで証券会社に勤務した実体験をご紹介してきましたが、そのような経験をして「実際どうだったの?」というのは気になるポイントだと思います。
結論から言ってしまうと、新卒で証券会社へ入社して良かったと思っています。
その理由は以下の通りです。
- ビジネスマナーが身に付いた
- 営業ノルマを達成する意識がついた
- 「体育会系」の意味が理解できた
- ストレス耐性ができた
- クソみたいな上司がいることを知った
- ファイナンス知識がついた
大手企業は「とにかく研修が充実している」ので、ビジネスマナーの基礎が身に付きます。
これは今でも大きかったと感じます。
なので「新卒では大手企業かベンチャー企業か、どちらに就職するべきか?」と質問された場合、間違いなく「大手企業へ行け」と即答します。
さの編集長は大和証券を退職した後にITベンチャーへ転職しましたが、研修制度の差は歴然としていました。
むしろ、ベンチャー企業へ新卒入社した社員(後輩)を「可哀想」だと感じていました。
なので新卒であれば絶対に大手企業を目指すべきだと思っています。
そして、大手企業には絵に描いたような”クソ上司”がいるので、それを経験するのも良いと思います。
もはや半沢直樹の世界観ですが、自分の保身ばかりを考えていたり、パフォーマンスで怒ったり、支店長にゴマすりばかりするような上司が本当にいるのです。
そのような経験は反面教師となるので、今でも大変役立っています。
そして一番良かったなと感じるのが「ファイナンス知識」が身に付いたことです。
企業経営をする上でファイナンスの知識は必要不可欠だと言えます。
しかし、多くの経営者はファイナンス知識がないため、CFOと呼ばれる人を探さなければいけません。
でも証券会社出身であれば、CEOとCFOを兼務できるので、とても経営効率が良くなるのです。
エクイティファイナンスを実施するスタートアップ企業を経営したいのであれば、絶対にファイナンス知識が求められるので、証券会社や銀行など金融機関に勤めるのが良いでしょう。
良くも悪くも色々な経験をした証券会社ですが、まとめてしまうと「とても有意義な時間だった」と思っています。
なので「証券会社に入社したい!」と考えている場合には、個人的にオススメしたいと考えています。
ただし注意して欲しいのは、きちんと『自分なりのキャリアアップ』を考えておくことです。
最初は営業職だったとしても、その後に企画部や債券部、エクイティ部、人事部など、大手企業にはたくさんの部署があります。
海外支店もあるので、海外勤務を希望するのも良いでしょう。
入社して2年目ぐらいには「将来はどの部署に行きたい?」と上司から聞かれるようになります。
その時に初めて考えるのではなく、一番最初の段階から「どのようなキャリアを描きたいのか?」は考えておくべきだと思います。
証券会社に入社する人は「東京大学卒業」「早慶上智卒業」「関関同立卒業」などが当たり前(MARCHが最低ライン)なので、とにかく地頭のいい人が多いです。
そのようなライバルを押しのけながら出世しなければいけないので、ひたすら勉強する毎日だと思ってください。
ファイナンシャルプランナー(FP)試験は当たり前ですが、日商簿記や証券アナリスト、中小企業診断士まで幅広い知識が求められます。
節税対策についても知らなければ、富裕層からは相手にされません。
野村證券含めて、なかなかライバルは手強いので、並大抵の努力では勝てないと思っておきましょう。
証券会社のトップセールスになる方法
せっかくの機会なので、最後に「証券営業でトップセールスになる秘訣」をお伝えしたいと思います。
当時はあまり分かっていませんでしたが、今では証券営業でトップセールスになるやり方が明確に理解できています。
もし私がもう一度新卒営業としてチャレンジできるなら、間違いなく全社No.1のトップセールスになることでしょう。
証券営業のトップセールスを目指したいのであれば、まずターゲットを絞り込んでください。
ターゲットとなるのは地元の名士や富裕層だけです。
それ以外の顧客は時間がないので問答無用で切り捨ててOKです。
小さい顧客を開拓するのは簡単ですが、対応工数と時間が取られるわりに収益へは結びつきませんし、どうせ引き継ぎでもらうことになるので、わざわざ自分の時間を割いて開拓する必要などありません。
その場しのぎ、視点の低い営業をするのではなく、もっと大きなビジョンを描きましょう。
地元の名士や富裕層はビジネスの成功者であるため、様々な事業を展開しているはずです。
なので、多少の不器用さはあったとしても、ある程度対等なレベルまで達しなければ相手にされません。
つまり「セールス(売り込み)」ではなく「営業(課題解決)」をするべきなのです。
一般的な証券営業マンは「株を買いましょう!」とか「投資信託を買いましょう!」という提案ばかりしています。
でもこれじゃダメです。
お客様の悩みは”資産を守る”ことだけではないので、もっと色々なビジネスの話をするべきだと思います。
- 他社で上手くいっている社員採用の事例をお伝えしますね。
- 安くていいオフショア開発の会社を知ってますよ。
- 燃料費を下げられるお得な耳寄り情報があります。
- シナジーのありそうな経営者がいるのでご紹介させてください。
- 御社の製品を販売したい会社があるので、お繋ぎしますね。
このような話であれば、多少なりとも経営者は興味を持ちますよね。
営業活動とは「顧客の課題解決」なので、決して株式の売り込みだけではありません。
お客様の話に親身に耳を傾け、役立つソリューションを提供すれば、そのお客様はあなたのことを頼りにしてくれるはずです。
つまり「大和証券の○○さん」というネームプレートが外れて、「優秀な営業の○○さん」という認識になるのです。
そうすれば知り合いの経営者友達を紹介してもらえますし、一緒にゴルフへ行ったり、飲み友達にもなれるはずです。
「社長の友達は社長」という言葉を聞いたことがありますよね。
でもその深堀りを上手くできている営業マンは少ないと思います。
なぜかといえば「お知り合いを紹介してください!」ばかりを言っていて、相手のメリットを考えていないからです。
自分のメリットばかり伝えても、相手は紹介してくれるはずがありません。
成功者と同じ立ち位置になって、お互いにメリットを感じれば、自然と紹介は起こるのです。
「この営業マンは○○さんのビジネスにも役立つ優秀な人だから、ぜひ紹介してあげよう!」
このように思ってもらうことが重要なのです。
そうすると資産の悩みも色々相談されるはずなので、その時に初めて本業の提案をすれば良いだけです。
これを実現する為にはたくさん読書をしたり、色々なビジネスパーソンと交流して情報収集をするべきでしょう。
そして異業種交流会にも積極的に参加していきましょう。
交流会の参加費は数千円程度なので、それは投資だと割り切って、とにかく人脈を広げていくのです。
そして同じく富裕層向けにビジネスをしている人と仲良くなりましょう。
例えば「保険の営業マン」「不動産の営業マン」などが代表的です。
一人で営業していると「1馬力」ですが、同じ富裕層向けにビジネスをしている人と組めば「3馬力」にも「10馬力」にもなります。
営業活動では”戦術(勝つ為の手法論)”が重要となりますが、決して一人でやらなければいけないわけじゃありません。
頭の固い”脳筋営業マン”が多いと感じていますが、営業活動は周りを巻き込みながら「多馬力」でやってもいいのです。
とにかく重要なことは顧客目線に立つことです。
お客様(経営者)のビジネスにとって「何がメリットになるのか?」を真剣に考えましょう。
経営者は孤独なので、一生懸命に自分のビジネスを手伝ってくれる人を無下にすることはありません。
- 人材採用に困っている⇒求人に強い企業を繋ぐ
- 資金調達に困っている⇒ファイナンス知識豊富な会計士を繋ぐ
- 販路拡大したい⇒地方の有力な販売会社を繋いであげる
このような動き方をしてくれる人は、もはや”ビジネスパートナー(=頼りがいある人)”なので、自分の資産をあなたに預けてくれるはずです。
このロジックが理解できていれば、新規口座開設&預かり資産増加は難しくないでしょう。
口座にお金が入ってしまえば、その後の提案は自由自在です。
お客様の資産状況をきちんとヒアリングし、適切なポートフォリオを設計するだけです。
このロジックが理解できた人は、自分が”事業主”であることに気付いたはずです。
会社という枠を飛び越えて、お客様の課題解決のために様々なソリューションを提供することは、自分でビジネスを組み立てることです。
だから「サラリーマンは自分の会社を持て」と言われているのです。
もちろん副業NGであれば会社は持てませんが、現実味というよりは考え方の話です。
ビジネスとは相手の課題を解決することなので、そのような動き方はもはや”事業主”と言えるのです。
預かり資産1億円のお客様、かつアクティブな顧客が10人(1億円×10人=10億円)もいれば、一般的なリテール営業ではトップセールスになれるはずです。
少ない人数であれば、毎月一回は定期面談をして、きめ細かなフォローアップもできるので、さらに信頼感が増していくはずです。
つまり、他の細かい顧客は必要ないということです。
このような顧客層を開拓するのには1年もあれば十分だと思います。
大学在学中から人脈形成を始めて、すぐにアクセル全開できるように準備しておきましょう。
まとめ
証券業界は「資本主義の権化」といえるような会社です。
そういった意味では、資本主義を理解する為には最適な場所だと思います。
また企業経営に欠かせない「ファイナンス」の知識を得ることができる貴重な場所にもなります。
なので「将来は独立起業したい!」という人にも向いているはずです。
とてもきつい仕事ですが、そのぶん得るものはあるので、「株取引が好き!」とか「たくさん稼ぎたい!」という人であれば、証券会社を志望するのは悪くない判断でしょう。
特に新卒の場合には一生を左右する可能性があるので、十分考えながら就職先を選んでください。