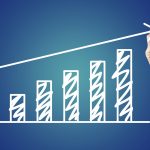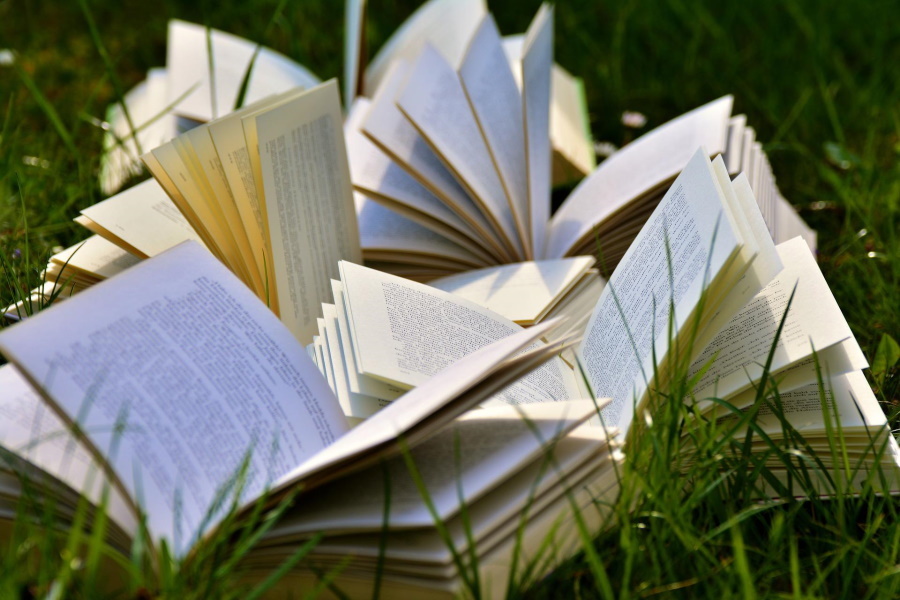
ことわざは身近な言葉なので、普段から使っている人は多いはずです。
しかし、諺の数は多いので、ある程度は整理整頓した方が良いと思います。
そこで今回は「座右の銘にしたいことわざ一覧」というテーマで解説していきたいと思います。
ビジネスや仕事で使えることわざを厳選したので、経営者やフリーランス、サラリーマンまで幅広くご覧ください。
座右の銘にしたい「ことわざ」一覧
案ずるより産むが易し
【意味】前もって物事を心配するより、実際にやってみると案外簡単にできること。
元々は妊婦を励ます言葉でしたが、現代では「決断する為の言葉」として使われています。
この諺を知っていれば、行動する勇気が湧いてくるかもしれません。
好いたことはせぬが損
【意味】好きなことをしないのは損だ。
どうせ働くなら、楽しく働きたいですよね。
そのためには、自分の好きなことを仕事にしなければいけません。
まさにそれを言い表した名言だと思います。
選んで滓(くず)を掴む
【意味】選り好みをしすぎると、かえって悪い物を掴むということ。
滓(くず)とは不要物や食べかすのことを指します。
つまり選びすぎると、かえって損をするということです。
鉄は熱いうちに打て
【意味】物事は情熱があるうちに着手すべき
これは仕事で結果を出すために欠かせない考え方だと思います。
何事も鉄は熱いうちに打った方が良いのです。
身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ
【意味】命を投げ打つ覚悟があってこそ、物事は成就できるということ。
ビジネスをする上で命を張る必要は本来ありませんが、それくらいの覚悟がなければ、大事は成し遂げられないと思います。
偉業を成し遂げたいと思っている人は、このことわざを座右の銘にしましょう。
志ある者は事竟(ことつい)に成る
【意味】志がしっかりしていれば、困難や挫折があっても最後には成し遂げられること。
志とは「ビジョン」のことです。
将来の姿が鮮明に見えていれば、後はまっすぐ突き進むだけなのです。
心頭を滅却すれば火もまた涼し
【意味】心の持ちようでどんな苦難もしのげること。
「怒り心頭」という言葉もありますが、心頭とは「心の中」という意味です。
何事も考え方次第で、結果は変わってくるのです。
浮き沈み七度(ななたび)
【意味】長い人生の間には好調もあれば不調の時もあること。
七度とは「7回」という意味ではなく、「多数」を意味しています。
人生いろいろありますが、あまり悲観的になる必要はないと思います。
一の裏は六
【意味】巡り合わせが悪い後には必ず良いことがあること。
サイコロで言えば、イチの目の裏側はロクですよね。
この諺は「表裏一体」という四字熟語にも通じている気がします。
座右の銘にできる四字熟語は下の記事でご覧ください。
碁で負けたら将棋で勝て
【意味】あることで失敗しても、他のことで取り返せること。
一度失敗したからといって、それは全く問題になりません。
人生は長いので、何度だって挑戦できるのです。