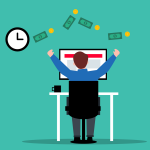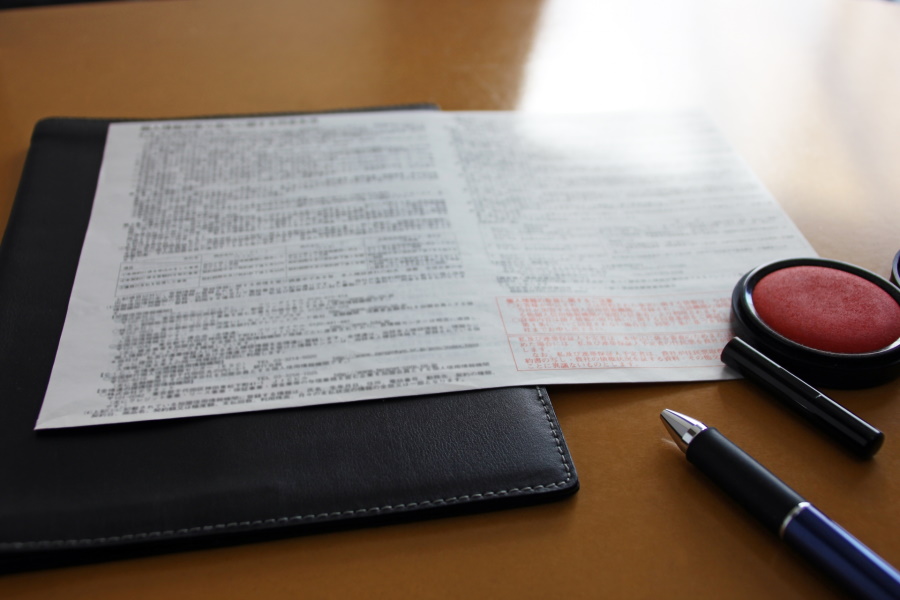
※本ページはプロモーションが含まれています。
販売代理店として活動するために欠かせないものが「代理店契約書」です。
今後のビジネストラブルを避ける為にも、代理店契約をきちんと締結しておきたいものです。
そこで今回は代理店契約する時のポイントや、注意事項、そもそも「代理店とは?」という基礎知識までをおさらいしたいと思います。
フルコミッションで働いている人や、これから独立・起業する人にも有益な情報なので、ぜひご覧ください。
目次
代理店の種類とは?
代理店という言葉はビジネスの現場で一般的に使われていますが、その意味を正確に理解できている人は少ないと思います。
そもそも代理店という言葉は総称なので、その実態は下記のように様々な種類が存在しています。
- 販売代理店
- 取次店
- 総代理店
- 紹介店
- 特約店
- 販売店 etc.
なので、代理店制度の構築時には、それぞれの特徴を把握した上で契約書を作成しなければ後々トラブルになりかねません。
この辺りは十分注意するべきポイントですが、まずは一般的な代理店制度を理解すべきなので、ここから代理店スキームを解説したいと思います。
ここで紹介する6つは主な代理店制度なので、とりあえずこの6種類を理解すれば大丈夫だと思います。
もう少し細かい代理店制度を把握しておきたい人は、後で下の記事をご覧ください。
代理店の種類1:販売代理店
代理店と言えば”販売代理店”を思い浮かべる人が多いと思いますが、一般的に「代理店」といえば販売代理店のことだと思って間違いないでしょう。
販売代理店とは”販売契約まで担う代理店”を意味しているので、最も代理店側の業務負荷が大きいビジネススキームだといえます。
販売代理店の仕組みは一般的に認識されているはずなので、細かい部分までは説明不要だと思います。
代理店の種類2:取次店
取次店は代理店制度の一種ですが、名前の通り「取次すること」を業務内容にする代理店スキームになります。
取次業務とは「お客様からの申込書や契約書を取り次ぐこと」を意味するので、契約の媒介までが業務内容となります。
なので、契約締結後の顧客フォローやサポート業務まではやらないことが一般的です。
詳しい内容は下の記事をご覧ください。
代理店の種類3:総代理店
総代理店は”代理店のまとめ役”を意味しています。
代理店制度では、一次店、二次店、三次店…といったピラミッド型の組織を構築していきますが、節目節目でまとめ役や調整役が必要になってきます。
そのような役割を担っているのが総代理店になります。
通常、総代理店はメーカー指定の1社が担うというケースが多いのですが、詳しい内容は下の記事をご覧ください。
代理店の種類4:紹介店
代理店制度の中でも一番ライトな取り組みが「紹介代理店」です。
紹介店とは名前の通り「見込顧客の紹介」を業務内容にした代理店スキームになります。
紹介するまでが業務内容なので、提案やクロージングは本部が行います。
よって「個人的な副業でもOK」という代理店スキームが紹介店になります。
一般的には「紹介営業」と呼ばれていますが、最近では「リファラル営業」とも呼ばれることも増えてきました。
詳しい内容は下の記事をご覧ください。
代理店の種類5:特約店
特約店とは、メーカーと特別な契約を交わした代理店スキームになります。
例えば、
- 看板にメーカーのロゴを掲示できる
- 特別条件を提示される
など、その条件は様々です。
一般的には”優遇された条件”を提示される代わりに、多少のノルマが課せられるなど、基本的には相対契約となります。
詳しい内容は下の記事をご覧ください。
代理店の種類6:販売店
販売店のスキームを利用する相手は、主に小売店などが対象になってきます。
名前の通り販売することを目的にした代理店スキームなのですが、販売代理店と同義に扱われることもあります。
しかし、販売代理店は訪問営業スタイルの代理店を指すことが多いのに対して、販売店は来店型のスキームを指すことが多いのが特徴的です。
また商材仕入れをするのが一般的なので、無在庫販売はあまり見かけません。
詳しい内容は下の記事をご覧ください。
”代理店契約”と”業務委託契約”の違いとは?
代理店と業務委託は一般的に混同しやすいと言われています。
実際、代理店制度を構築する段階で、
- 代理店契約にすべきなのか?
- 業務委託契約にすべきなのか?
で迷う人も多いと聞きます。
それでは、この2つの違いとは一体どのような部分なのでしょうか?
まず代理店についてですが、代理店とは”商材販売する外部パートナー”を意味しますので、販売1件につき●円といった感じの代理店マージンが提示されます。
そして、あくまで一般論になりますが、業務委託と比較してノルマが課せられることが多いのが代理店になります。
また、販売したお客様に対するフォローなど”継続取引”を前提とした契約にも利用されています。
それと比較して、業務委託の場合には”スポット”で利用されることが多い契約形態になります。
つまり”継続取引”を前提にしてないことになります。
例えば「▲を制作して欲しい!」といったクリエイティブな依頼にも利用されていますが、このようなケースでは納品物があるので、それを納めたら業務終了となりますよね。
そのようなスポット利用で業務委託の契約形態は活用されています。
大枠ではこのような違いがあるので、どちらが自社に適しているかを見極めた上で、契約書を用意するのがおすすめです。
もう少し詳しく知りたい場合には、下の記事をご覧ください。
代理店契約のやり方
代理店契約を締結するには代理店契約書が必要になります。
司法書士や弁護士などのプロフェッショナルに契約書作成を依頼するのも良いですが、1契約書あたり10万円~30万円ほどのコストがかかりますし、ベンチャー企業にとっては手痛い出費になるはずです。
なので、大企業でない限り【代理店契約書は自社で作成する】のが基本になると思います。
ちなみに、この記事の最後に【代理店契約書の雛形】を設置しておきますので、それをダウンロードして作成すれば簡単かもしれません。
代理店契約書を自前で用意するのもOKですが、きちんと弁護士に確認してもらう事だけは怠らないようにしましょう。
契約書の確認作業は、後々のトラブル防止にも役立つので必ず行うべきです。
実際に代理店契約する場合には、お互い記名捺印して契約締結することになります。
ただ、”書面を取り交わさないといけない”という法的な決まり事はありませんので、最近では電子契約で済ませてしまうケースが多くなっています。
実はこのような契約形態にすることには大きなメリットがあるのです。
そのメリットについて、次の項目で解説していきたいと思います。
印紙税が0円(無料)になる
これは法律で明記されていることですが、代理店契約を締結する場合には、契約書1通につき収入印紙4,000円を貼らなければいけません。
一般的には契約書は双方1通づつ保管することになるので、2通で8,000円の印紙税が必要なのです。
これは国税庁のホームページにもしっかりと明記されているので、事前にチェックしておきましょう。
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm
それを前提にした場合、代理店1社開拓する毎に8,000円の事務コストが発生することになります。
つまり、
- 代理店10社で80,000円
- 代理店100社で800,000円
ということになります。
意外とバカにできないコストですが、電子契約にしてしまえばこの印紙税が不要(0円)になるのです。
その理由はとても明快で「印紙を貼る契約書が存在しない」からです。
実際弊社(WEBX Inc.)でも弁護士に確認した経験がありますが、弁護士の回答は「印紙を貼るモノが無いからしょうがないよね~」という見解でした。
ある意味ではグレーゾーンをついた財テク(コスト削減方法)といえますが、合法的なやり方なのでこれはオススメです。
もし良ければ電子契約の導入も検討してみてください。
代理店契約で注意すべきこと
代理店契約はビジネス文書なので、適当な契約書では後々問題になってしまいます。
契約書を弁護士に確認してもらうのは勿論ですが、基本的に入れておいた方が良い条項というものが存在するので、ここでは代理店契約に入れておくべき基本条項をご紹介したいと思います。
1.代理店の業務内容
代理店にお願いしたい業務内容を具体的に記載しておきましょう。
この条項はビジネスモデルの根幹になる重要事項なので、できるだけ細かく記載することが理想的です。
お互い認識のズレが生じないように、具体的な仕事内容まで記載するのがおすすめです。
後々で言った言わないの”水掛け論”になるのを防ぐ狙いもあるので、この部分は注意深く確認しましょう。
2.有効期限
代理店契約の有効期限に関する条項です。
一般的には1年毎の自動更新が多いのですが、特に決まりはないので、自由に設定して構いません。
但し、この期間を長くし過ぎると、後々問題になるケースも散見されますので十分ご注意ください。
雛形としては下のような文章になります。
第●条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、契約締結した日を起点として1年間とする。
2.本契約は、双方から解約の申し出がない限り同条件で自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。
3.報酬条件
代理店に支払う報酬(マージン)の部分です。
どのような業務に対して、いくら支払うのかを明記するのですが、報酬金額が曖昧ではトラブルになってしまうので、しっかりと明記しましょう。
- 税抜き額なのか?
- 振込手数料はどうするのか?
- インセンティブはあるのか?
なども抜かりなく記入することが大切です。
また、支払い期日についても明記しますが、場合によっては戻入規定を設けるケースもあるので、この辺りは代理店と相談してみましょう。
代理店マージンの戻入については、下の記事にまとめているので後でご覧ください。
4.損害賠償
損害賠償の条文は、本部や代理店がミスしたことによって、経済的な損失が発生した時の為に記載しておきます。
損害が発生するケースには様々なパターンが想定されるので、できる限り全てを網羅できるような条文にしましょう。
雛形としては下のような文章になります。
第●条(損害賠償)
1.両者は本契約を履行する上で、故意又は過失にかかわらず相手方に損害を与えてしまった場合、通常かつ直接の範囲で当該損害を賠償する。
2.本条は本契約の終了後も有効に存続するものとする。
3.両者は…
5.解約定義
「代理店契約の締結」があれば「代理店契約の解除」もありえます。
解約する際に揉めないよう、予め解約事項も明記しておくことが大切です。
解約の際には、
- 債務をどうやって精算するか?
- ストック収入はどうなるのか?
- 既存顧客はどうするか?
など様々な問題が出てきます。
この辺りも想定した上で、条文を作成するようにしましょう。
第●条(本契約の解除)
- 本契約は、書面で申し出ればいつでも解除できるものとする。
- 両者は、本契約を解除する場合、お互いに有する債務を速やかに精算し所定の期日までに支払うものとする。
- 両者は、以下の各号に相手方が該当していると判断した場合、通常の手続きを経ずに本契約を解除することができるものとする。また、それに係わる損害等が相手方に発生した場合でも、一切の責任を負わないものとする。
① 本サービスの事業廃止や売却が決まったとき。
② 契約時に相手方が虚偽の情報を申告していたことが発覚したとき。
③ 手形、小切手の不渡りのため手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又はこれに類する事態が生じたとき。
④ 監督官庁より営業の取消・停止等の処分を受けたとき。
⑤ 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申し立て等を受けたとき。
⑥ 支払停止、支払不能、若しくは債務超過の状態、又は破産、会社更生手続き及び民事再生手続き、特別清算手続き等の倒産処理手続きの状態にあるとき。
⑦ 会社や事業の信用状況が著しく悪化したとき。
⑧ 法人形態、又は事業を事実上、解散・廃業したとき。
⑨ 相手方(従業員を含む)が反社会的勢力に属している、又は関係していると判断できたとき。
⑩ その他、通常業務の遂行に支障をきたす恐れがあると判断する相当の事由が生じたとき。
代理店契約書の雛形をダウンロードしよう!
ここまで読み進めた人は、代理店契約書のポイントが十分理解できたと思います。
あとは代理店契約書を用意して、代理店募集をするだけです。
代理店募集をする時には、代理店募集サイトを活用していきましょう!
営業シークでは”紹介代理店”の契約書雛形をご用意していますが、「代理店契約書は雛形」だけでなく、「パートナーセール虎の巻」も無料配布しておりますので、それらを手に入れたい代理店担当者の人は下のLINE登録(0円)をお願いします。
※契約書の雛形はMicrosoft Word(マイクロソフト・ワード)でDLできます。
※代理店契約書は雛形なので、最終的には弁護士などへ確認依頼することをお勧めします。

まとめ
ここまで、代理店契約について解説してきました。
代理店契約書はあくまでも手段に過ぎないので、決して契約締結が目的ではありません。
最終的な目的とは”代理店に販売してもらうこと(=代理店が儲かること)”なので、代理店が売りやすい仕組み、代理店が売りたくなる契約内容にすることが大切です。
契約書は最初に作ったもので完成ではありませんので、常にPDCAを意識しながら改善していきましょう!