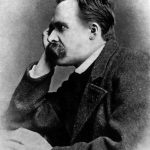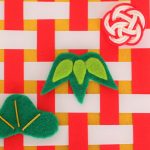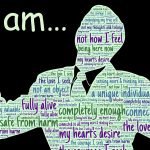愛せなければ通過せよ。
これは「変人」と呼ばれた哲学者ニーチェの言葉です。
人生では様々な人たちと出会いますが、そこでフィーリングが合わないと思ったら、無理して付き合うのではなく、そのまま素通りしてみましょう。
「一期一会」という言葉もありますが、それに固執していては前に進むことができません。
激怒している時には何もするな。
嵐の海に漕ぎ出すようなものだ。
この名言は、生きる上でとても役立つ言葉だと思います。
「アンガーマネジメント」という言葉がありますが、上手に生きるためには怒りをコントロールしなければいけません。
なので、もし怒りの感情がコントロールできない場合、「とにかく今は何もしない」という判断もアリだと思います。
人間の怒りは、10秒放置するとほとんど治まるそうです。
たった10秒沈黙するだけで「無用なトラブル」は避けられるので、ビジネスパーソンは覚えておきましょう。

人間というものは、ちょっと隙のあった方が、人に好かれるものだ。
一点の隙もない人間よりも、どこか隙のある人の方が好かれる。
なんとなく完璧な人間は可愛げがないですよね。
人から良く見られようとして、自分を綺麗に着飾ったり、演出する人は多いと思いますが、それが逆に人を遠ざけているのかもしれません。
色々難しく考えずに、”素の自分”を見せるのがいいと思います。
誰からも好かれる人ほど、深くは好かれない。
「赤と黒」という歴史的名著を残したスタンダールの名言です。

表面上で付き合う人とは、決して深い関係性にはなれません。
日本にも「八方美人」という言葉がありますが、誰にも良い顔をする人はスキがないので、相手も隙を見せようとしないのです。
金が無いから何もできないという人間は、お金があっても何もできない人間である。
人間は何かしらの理由をつけて、自分自身を正当化しようとします。
- やったことがないからできない
- お金がないからできない
- 時間がないからできない
これらは代表的な言い訳でしょう。
しかし本当にこれらが理由があるからできないのでしょうか?
もちろんそんなことはありませんよね。
勇気を持って行動しないからできないだけです。
死は人生の終末ではない。
生涯の完成である。
「死」は人生において終着駅のような気がしています。
死ぬことは肉体的な終わりを意味するのですが、決して”魂”が死ぬことはありません。
自分が死んだ後も魂は生き続けて、「自分の人生は何だったのか?」を後世に伝えてくれます。
つまり「死」をもって人生が完成するので、「画竜点睛」のような役割があるのです。
生は全ての人間を水平化するが、死は傑出した人をあらわにする。
人間が生まれた時、家柄の違いはあるとしても、肉体的な能力やスキル、経験値は同じ地点からスタートするはずです。
「生」はみんな同じスタートラインから始まりますが、「死」にはそれぞれ違いがあるということです。
- 社会を変えるような偉業を成し遂げた起業家
- 一つの会社で勤め上げ、会社の発展に貢献した会社員
- 人の命をたくさん救った医師
目的がなくダラダラ過ごしていた人と違って、「死」は頑張って生きた人の人生をあらわにするのです。
死は生の対極としてではなく、その一部として存在する。
「生」と「死」という言葉がありますが、実際には「生」の一部として「死」が存在しています。
この言葉の意味は、人間は死ぬために生きているのではなく、生きた結果、死ぬということです。
つまり「生きる」ということが主なので、自殺などもっての他なのです。
このところずっと、私は生き方を学んでいるつもりだったが、最初からずっと、死に方を学んでいたのだ。
いかにも、年齢を重ねた人が言いそうな名言ですよね。
若いうちは「人生を通じて何を成そうか?」ということばかり考えてしまいますが、死が近づくにつれて、「どう死ねばいいのか?」を考えるようになります。
そうすると気付くのですが、「人生とは生きる意味を探すのではなく、死に方を探す旅なのだ」と…
あなたの人生を集約した、墓石に刻む短い言葉は何でしょうか?
大事を成したい人は、常にこのような考え方を持ちましょう!
生きた、書いた、愛した。
シンプルイズベストを体現したような名言だと思います。
スタンダールは「赤と黒」を書いた著名な小説家ですが、その人生を端的に表すと、この言葉になるのだと思います。

「生きた」の部分は誕生を意味していて、「書いた」は小説家として良作を世に残した自負を表しています。
そして「愛した」には「死ぬまで…」という枕詞が付く気がします。
つまり、生と死で小説家としての人生を挟んだのです。
そう考えると、とても美しい構成の名言だと思います。