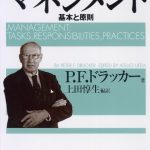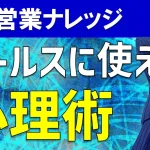外勤営業は、営業職の中で最も就業人数が多い職種だと思います。
まさに「営業職=外回り営業」くらいのイメージになっているのが普通ですよね。
そこで今回は、外勤営業の仕事内容や役割、年収などについて解説していきたいと思います。
これから営業職として就職する人や、すでに活躍している営業パーソンまで幅広くご覧ください。
目次
外勤営業とは?
外勤営業とは会社の外で行う営業活動のことをいいますが、「外回り営業」や「フィールドセールス」と呼ばれることもあります。
しかし、それらはどれも同じ意味です。
店舗やオフィスの中で営業をする”内勤営業”と区別されているケースも多く、”外回り営業専門”という営業マンも決して珍しくありません。
法人相手(BtoB)の場合にはお客様のオフィスに出向いてセールスしますが、戸建て住宅などをターゲットにしているBtoC営業の場合、個人宅を尋ねるという違いがありますが、両方とも外勤営業にあたります。
その外勤営業のやり方には様々なパターンがあって、
- 顧客ニーズに応じて対応するフォローアップ営業
- アポ無しセールスを実行する飛び込み営業
- 定期的に同じお客様を訪問するルート営業
など一概に外勤営業と括るには範囲が広すぎるかも知れません。
外勤営業の仕事内容
外回りの基本は「対面営業」なので、テレアポ営業は後回しにされるケースが多いです。
しかも新規開拓するときには、テレアポよりも手っ取り早い「飛び込み営業」を活用する場合もありますが、飛び込み営業との相性は商材によって変わるので、そのあたりはよく検討した方が良いと思います。
どちらにしても「しんどい仕事」と言われている外勤営業ですが、その反面大きなメリットがあるのです。
それは年収が高いことです。
外勤営業の年収は、売り上げに応じて決まる「歩合制」になっているケースが多いので、実績さえ出せば、年収1,000万円を超えるケースが少なくありません。
逆説的に言ってしまうと「しっかり実績を出さない限り稼げない仕事」とも言えるので、ある意味ではハイリスクハイリターンとも言えるでしょう。
また、フィールドセールスが大半を占めているような会社では、営業事務がサポートしてくれるケースが多いので、
- 見積書の作成
- 請求書の作成
- 契約手続き
などの事務的な業務は他の人に任せることができます。
なので、営業に専念したい人や、事務処理の負担を軽くしたい人には向いている営業職なのかもしれません。
外勤営業はきつい?
外勤営業は”きつい仕事”といわれているので、営業未経験の人は「果たして自分に務まるのか?」と不安になるかも知れません。
営業職という仕事は「顧客第一主義」を貫かなければいけないので、たとえお客様から理不尽なことを言われても、相手の気分を害さないように立ち振る舞う必要があります。
そのような対応をするだけでもストレスは溜まっていくので、結果的に”きつい仕事”と言われてしまいがちなのです。
外勤営業は”営業ノルマ”がきつい
外勤営業は「営業職」なので、当然のように営業ノルマが課されます。
しかしノルマは簡単に達成できる数字ではなく、少し高めで設定されているのが実態なので、それを達成する為には、営業日をフル稼働しなければノルマ未達成になってしまいます。
なので、営業職は簡単に仕事を休むことができません。
もし風邪で休んだりしても、あなたのノルマを肩代わりしてくれる人はいないので、自分が辛くなるだけです。
この辺りも「きつい」とか「しんどい」と言われる所以かも知れません。
外勤営業は体力的にきつい
外勤営業の場合には、フィジカル的な面でも”大変な仕事”と言われています。
連日のように多くの客先に向かう為には、それなりの体力を消耗しますし、健康な身体でなければいづれガタがきてしまいます。
特に夏場の外回り営業は最悪で、30度を超える真夏日に長袖の上下ブラックスーツを着るなんて、正気の沙汰ではありませんし、熱射病になる危険性があるにもかかわらず、汗まみれになりながら、街中を歩き回らなければいけないのです。
そのような努力をしても、全く売り上げが増えないということもあり、「こんな仕事はもう辞めたい!」と思ってしまう人もいるほどです。
それでも乗り切れるだけの気合と根性が求められる仕事なのです。
そういった意味では身体が丈夫で、気合い&根性論が大好きな体育会系の人に向いている職業だと思います。
外勤営業の”きつさ”はどの業界でも同じ?
このような外勤営業の厳しさは業種業界によっても大きく異なります。
きつい業界の場合には、朝から晩まで飛び込み営業をし続けますが、それでもノルマが達成できないなんてケースもあります。
また、ターゲットが個人か法人かによっても違いがありますが、どちらかというと、法人営業の方がルート営業などのルーチンワークになりやすいので、楽だという意見もあります。
個人営業の場合には、お客様の感情論に振り回されたり、商材によっては「全然売れない…」ということも十分あり得ます。
売れる製品サービスなら契約が取れますが、よくわからない学習教材や貴金属の販売だったりすると、売るのに嫌気が差してしまうかもしれません。
このように外勤営業がきついのは確かですが、会社や商材の選び方次第で、ある程度は軽減される場合もあります。
なので、
- 会社の営業方針
- 商材の特徴&強み
は外勤営業として就職する前に、最低限押さえておきたいポイントだといえます。
外勤営業と内勤営業の違いとは?
外勤営業に対する職種には”内勤営業”があります。
外勤営業はフィールドセールスとも言われていて、「現場で営業活動をしている人」だというのはここまで解説してきた通りです。
現場でお客様と対面して、商品サービスの提案をするのが営業マンだと思っている人にとっては、「内勤営業とはどんな仕事なのか?」と疑問になるかも知れません。
そこで、外勤営業と対比されることが多い「内勤営業」についても解説しておきたいと思います。
内勤営業とは?
内勤営業をざっくり解説すると「オフィス内でセールス活動する営業職」という仕事になります。
例えば、新規開拓でよく用いられている「テレアポ営業」は、典型的な内勤営業のスタイルだと思います。
このような電話営業は、オフィス内にいてもできる営業活動なので「インサイドセールス」と呼ばれることもあります。
電話だけでなく、メールやチャット、web商談システムなどのITツールを駆使したセールスも同じで、営業活動の中核として位置づけられています。
カウンターセールスも内勤営業
内勤営業には、カウンターセールスという営業スタイルもあります。
カウンター営業が活用されている場所は”来店型の店舗”が多く、見込み客が来店したら、そのお客様を接客するというスタイルがとられています。
カウンターセールスについて知りたい場合には下の記事をご覧ください。
典型的なのは旅行代理店で、ツアーや航空券などを探している顧客が訪れた際に希望を聞いて最適なツアーや航空券を提案してくれます。
他にも保険ショップや不動産屋、銀行や証券会社、携帯電話のショップや貴金属の買い取りなど、カウンターセールスが活躍している業種業界はたくさんあります。
電話やメールによる受付営業についても同様で、顧客の求めに応じてセールスを行うのが特徴的です。
このように自分からお客様を訪問しなくても、見込み顧客の方から寄ってきてくれるので、「外勤営業ほどの辛さは無い」と言われています。
これらは「インバウンド営業」とも呼ばれており、webマーケティング(集客)が強かったり、ブランディングや広告宣伝が上手くいっている会社では、内勤営業が採用されているケースが多くなっています。
これからの時代は「インバウンド営業が主流」と言われているので、気になる人は下の記事もチェックして下さい。
外勤営業のコツとは?
外勤営業を担う営業マンが成功するためのコツは、良質な既存顧客を大量に獲得することです。
外回り営業をしながら新規開拓をしていくのは、かなりの労力や時間がかかってしまうので、効率的な営業活動ができません。
なので、セールスの仕組みを構築することが必要になります。
その為に必要なことは「業務を分業化する」ことです。
例えば営業マン1人で下記の業務を全て行うのには、どうしても限界があると思います。
- リスト作成
- テレアポ
- 訪問営業
- クロージング
- フォローアップ営業
- クロスセル営業
これを最大化させる為には2つの選択肢しかありません。
- webマーケティングを実施する
- 営業アウトソーシングを活用する
この2つについて詳しく解説していきたいと思います。
webマーケティングを実施する
webマーケティングとは、インターネットを活用した広告宣伝などを意味しています。
その目的は「集客すること」ですが、そのやり方はたくさんあります。
具体的には、
- SEO対策
- リスティング広告(PPC広告)
- SNSマーケティング
などが代表的だと思います。
広告宣伝費を投入することによって、効果(問い合わせや資料請求など)を求める方法なので、実際に人が動くことはありません。
インターネットの良いところは、24時間365日ずっと集客し続けてくれることですよね。
つまり、それを言い換えると「24時間フル稼働で働いてくれる営業マン」ということになります。
このwebマーケティングを上手く活用することで、自分は動かなくても見込み顧客が入ってくる仕組みが出来上がります。
営業マンが個人的に実施するのはハードルが高いはずなので、会社として実施できるように社内調整することをオススメします。
営業アウトソーシングを活用する
営業アウトソーシングの方法はいくつかありますが、代表的な方法としては
- 営業代行
- アポイント代行
- 代理店展開
- リファラル営業
などが挙げられると思います。
どれも外部の営業リソースを活用する方法なので、営業活動を最大化することができます。
しかし本格導入するにはコストが掛かる施策になるので、ある程度の予算が必要だと思います。
中には無料トライアルできるケースもあるので、まずは色々なサービスに問い合わせてみることをオススメします。
外勤営業は手当が多い
外勤営業と聞くと「年収が高い職業」というイメージがあるかも知れませんが、実際はそんなことありません。
しかし、収入が高い職業であるのは確かだと思います。
このような矛盾が生じてしまう理由は、インセンティブ制や歩合制が設けられているからです。
営業職は固定給である基本給を低めに設定しているケースが多いので、インセンティブがもらえなければ決して高収入とは言えないのです。
そのようにしている理由とは、実績を出していない営業マンに、多く還元しないようにする為です。
営業職とは、良くも悪くも数字(成果)が重要な職業です。
もし契約が獲れない場合には、会社から「仕事をしてない人」とみなされるので、そのような人には少ない給料を支払いたいというのが、経営者の本音だと思います。
このようなケースで便利な仕組みが「歩合制」や「インセンティブ制」の給与体系なのです。
企業にとって営業とは「新規顧客を獲得して売り上げを獲ってくること」であり、大きな予算を持ってきた営業マンには相応の報酬を出すというスタンスが基本になっています。
その指標は、
- 売上
- 粗利
になっている場合もあれば、
- 契約件数
- 受注件数
などによって決められていることもあります。
いずれにしても実績を出すことによりインセンティブを受け取れるようになるので、大きな収入を得られるようになっていきます。
このような報酬形態であれば、やった人にだけ還元すれば良い仕組みになるので、できない営業マンの年収を低く抑えることができます。
ある意味では「成果主義」ともいえる仕組みが、外回り営業では一般的になっているのです。
残業や時間外手当も多い
営業職にはインセンティブが支給されますが、それにプラスして残業代も出るとなれば、年収1,000万円を超えるケースも決して珍しくありません。
営業職というのは「勤務時間だけ働いていればそれで受注が量産できる」というわけではありません。
例えば、休日に顧客から電話がかってきて、追加発注を依頼されることもあるでしょう。
その時に「今日は休日なので…」なんて野暮な対応をしていると、クライアントは「対応が良くないなぁ」と感じて、競合他社に鞍替えしてしまうかもしれません。
営業職はクライアントと一緒に伴走するパートナーのような立ち位置なので、自分主体ではなく顧客主体で動かなければいけないのです。
そう考えた場合、休日だろうが勤務時間外だろうが顧客対応する必要があるはずです。
なので、必然的に残業代が多くなったり、時間外手当が支給されたりするのです。
その辺りをきちんと管理している大手企業は、取引先との会食さえ残業扱いにしてくれるケースがあります。
確かに、取引先との会食は単なる食事会ではなく、営業活動の一環なので、時間外手当が支給されても妥当な気がします。
そういった意味でも、オン/オフ関係なく仕事ができる人は営業職に向いているでしょう。