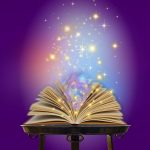ビジネスの現場でしばしば話題になるキーワードが「達成率」です。
社内会議やミーティングでも頻繁に飛び交っている用語なので、社会人なら正確に理解しておきたいですよね。
そこで今回は、達成率と進捗率にフォーカスして解説していきたいと思います。
目標達成する為のコツも解説しているので、セールスパーソンはぜひ参考にしてください。
目次
達成率の計算方法とは?
どんな仕事をするにしても、目標設定することは「ビジネスの基本」だといえます。
そのような基本だけでなく、ビジネスパーソンとして成功する為には、目標設定した値を管理することも求められます。
つまり、現状の達成状況を確かめるという意味の“達成率”という指標を用いるのです。
この計算式は、「実績÷目標×100(%)」というものになります。
具体的な計算方法に触れていきましょう。
もし仮に100万円を目標数値にしていた場合、300万円を達成した時は、
「300÷100×100=300」となり、達成率は300%になります。
また、100万円の目標数値で70万円を達成したときには、
「70÷100×100=70」となり、達成率は70%になります。
これは本当に基本的な計算なので、まずはこの部分を理解しましょう。
増減率の計算方法とは?
達成率と似た言葉に“増減率“があります。
増減率とは“前期比“や”前年度比“など何かを比較対象にする場合に使用されています。
この増減率にも計算方法があるので、ここで押さえておきましょう。
増減率の場合は、「実績値÷前年同期の実績値×100(%)」が計算式になります。
具体的には、今期の実績が100万円、前年同期の数字が200万円だった場合
「100÷200×100=50」となり、前年同期の達成率は50%ということになります。
達成率と大して変わらないので、こちらも覚えやすいですよね。
達成率を管理するメリットとは?
仕事する上で、達成率を計算することには大きなメリットがあります。
それは、業務スケジュールを管理できることです。
達成率というカタチで数値化すれば、
- 今のままでいくと、どう着地するのか?
- この業務スピードではどれくらいの時間が必要か?
などが計算しやすくなるので、業務の効率化に役立ちます。
また、進捗率の管理にも使えるはずです。
例えば、複数人のチームで取り組んでいる状態でも、
- どのタスクが遅れているのか?
- どこに人員や予算を多く割くべきか?
ということを瞬時に判断できるようになります。
過去と比較をした現状把握、そして目標管理をする達成率は従業員のモチベーションアップにもつながるはずです。
なぜかといえば、「自分たちがどれだけの結果を残したのか?」ということが明確な数値に表れるからです。
このようなメリットがあるので、達成率は必ず管理しておきましょう。
達成率と進捗率との違いを徹底解説!
ここまで達成率について解説してきましたが、よく達成率と混同される言葉に「進捗率」があります。
達成率は、設定した目標に対して「どれぐらい達成しているのか?」を確認する指標ですが、予定している計画に対して「進行が遅れているのか?進んでいるのか?」を把握するのに用いられる指標が進捗率です。
…と言っても、これではわかりにくいですよね。
もう少しわかりやすくまとめると下のようになります。
- 達成率:ゴールに対してどれくらい達成しているのか?
- 進捗率:スタート地点からどれくらい進んでいるのか?
つまり、計測開始する最初の地点が、
- 達成率:ゴールから見る
- 進捗率:スタートから見る
という具合に違っているのです。
なので、
- 達成率は青天井
- 進捗率はゴールが天井
ということにもなります。
つまり、達成率の場合には、
- 50%達成
- 100%達成
- 150%達成
という具合に100%を超えることがあるのに対し、進捗率は”100%”を超えることがありません。
進捗率の計算方法とは?
進捗率は、達成率と並んで「業務の効率化には必要不可欠な指標」と言われているので、ビジネスの現場でも良く使われています。
また、複数の業務を並列担当するビジネスパーソンは、進捗率を使ってタスク管理することが求められるはずです。
きっとこの数字を見ながら作業の優先順位を決めているという人も多いはずです。
さて、ここから進捗率の計算方法について触れていきますが、その計算式は「実績÷目標×100(%)」になります。
具体的には「10日間で300万円の売り上げ目標」を設定した場合、5日間で150万円の進捗具合では「進捗率50%」ということになります。
150万円÷300万円×100=50%
進捗率の計算は、達成率とそんなに大差があるものではありません。
時間軸が必要
進捗率を管理する場合、もっと正確に計算する為には”時間軸”を取り入れなければいけません。
進捗率の計算式は、「実績÷目標×100(%)」だとお伝えしました。
具体的には、10日間で300万円の売り上げという目標設定した場合、5日間で150万円の進捗具合では「進捗率50%」になりますよね。
しかし、10日間で300万円の売り上げという目標設定した場合、3日間で150万円、もしくは9日間で150万円だった場合の進捗率はどうなるのでしょうか?
その計算式は以下の通りです。
実績/経過日数÷目標/期限×100(%)
この計算式に当てはめてみると、以下ののような計算式になります。
150万円/3日間÷300万円/10日間×100(%)=166%
つまり、このペースで売り上げを追っていけば達成率166%になるので、進捗率100%に到達して「ノルマ達成」することが理解できるはずです。
それでは「150万円/9日間÷300万円/10日間×100(%)」ではどうでしょうか?
その答えは「達成率55%」なので、このペースでいくと未達成になることが予想されます。
このように、今の現状を把握して、将来を予測する為に進捗率は活用されています。
粗利達成率で管理すべき?
達成率という指標がある一方で、達成率に粗利を使用した「粗利達成率で管理すべきだ!」という意見もあります。
粗利とは、直接的な売上高から売上原価と呼ばれる仕入れや製造に用したお金を差し引いた数値のことです。
例えば、ラーメン1杯を提供する為には、
- 麺や具材の食材費
- スープを作る具材費
などの食材費が掛かりますよね。
売上から、これからの原価を差し引いた値が”粗利”なのです。
つまり売上だけで見た場合は、「原価が含まれているので、一見しただけでは利益が出ているのかわからない」というのが理解できるはずです。
粗利は損益計算書(P/L)などで売上総利益として扱われていて、企業の利益計算において中核的な存在になっています。
この粗利からさらに人件費や経費などの販管費が差し引かれて営業利益になり、そこから税金などが引かれて純利益となります。
このような観点からも「粗利で達成率を計算する」というのには一定の合理性があるように思われます。
例えば、あなたの会社に営業マンが3人いたとします。
その3人の売り上げ金額が以下の通りだったと仮定します。
- 営業マンA:売上500万円
- 営業マンB:売上400万円
- 営業マンC:売上800万円
これだけを見ると、なんとなく営業マンCが優秀のように見えますよね。
しかし原価を見てみると、
- 営業マンA:原価300万円
- 営業マンB:原価50万円
- 営業マンC:原価500万円
だったとします。
売上から原価を差し引いてみると…
- 営業マンA:売上500万円-原価300万円=200万円
- 営業マンB:売上400万円-原価50万円=350万円
- 営業マンC:売上800万円-原価500万円=300万円
という具合になります。
つまり、本当に会社へ貢献して稼いでいたのは「営業マンBだった…」ということです。
この事実は売上だけを見ていてもわかりませんよね。
ビジネスの現場では良くある話なので、経営者や事業責任者の人は押さえておきたいポイントになります。
このように粗利を使って計算する場合には、純粋に利益だけを追求しやすいというメリットがあります。
粗利を軸に達成率を計算して、事前に設定した一定以上の額を達成し続ければ、余程のことがない限り会社は成長し続けることになります。
なので、粗利額をKPI(Key Performance Indicator)として設定するケースもあるほどです
KPIを利用した場合、目標が曖昧なモノや主観的なモノにならないので、組織の改善点を探すことが容易になります。
達成率がマイナスになる理由
意外かもしれませんが、達成率というのは必ずしもプラスだけではなく、マイナスになる場合があります。
営業マン個人レベルで言えば、目標200万円に対して、50万円の達成であれば達成率25%なので、たとえ未達成だったとしても達成率はマイナスになりません。
つまり達成率がマイナスになるということは、0円未満の達成にならないとあり得ないのです。
これが何を意味するのかというと、会社単位、事業単位でみた場合に赤字であることを意味しています。
例えば、事業を立ち上げたばかりの頃は初期投資がかさんでしまいますよね。
それが原因で赤字になってしまったり、返品や契約破棄といった問題によって、実績となるはずだった数値が減ってしまった場合は達成率がマイナスになり得ます。
このようにマイナス達成率は計算によって求められますが、計算式や目標設定が通常のプラスによる達成率とは異なります。
非常に稀なケースですが、目標設定においてはそもそもマイナス予算でスタートしていた場合などでは、目標も赤字を減らすという意味でマイナススタートになります。
そして、実績も多くの場合でマイナスの数値を用います。
そうすると、あとは通常の正数字と同じように計算するので、マイナスの達成率が求められるのです。
エクセル管理をしている場合では、マイナスの達成率を計算する上で関数を使用するのが便利だと思います。
使用する関数は、数値の絶対値を求められるABS関数です。
ABS(目標額ー実績額)/ABS(目標額)というのが基本的な計算式となり、その他にも1+(実績額ー目標額)/ABS(目標額)などで求めることができます。
しかしながらマイナスの達成率を計算するというのは、本来のエクセルの役割を越えているので、もしかしたらまったく違う数値が出てしまうこともあり得ます。
この辺りには注意しましょう。
達成率を上げるコツ
営業パーソンは常に達成率100%を求められるので、「どうすれば達成率100%を維持できるか?」と日頃から考えていることでしょう。
これは難しいように感じますが、実は非常にシンプルな話なので、ここで触れておきたいと思います。
達成率を上げる為のコツというのは、今の実績と見込み顧客をしっかり管理して、日々の進捗率も管理することです。
闇雲にセールスするのではなく「常に達成率から逆算して考える」のが良いでしょう。
例えば、先月から持ち越した見込客数が10人いたとしても、今月の目標を達成するには合計15人の受注が必要だったとします。
つまり、現状の見込客10人を全て受注したとしても達成率66%なので、これでは未達成になることが確実ですよね。
しかも、現状の見込客10人を全て受注(100%受注)するなんて芸当は、普通のセールスパーソンにはできません。
この見込客の受注率が50%だった場合、見込客10人でも5人しか受注できないことになります。
さて、これで数字が出揃いました。
今月の目標15人を達成する為、以下の課題が浮き彫りになりました。
- 現状では5人しか受注できない
- 残り10人の新規受注が必要
それでは、残り10人の新規受注を獲る為に、何人の見込顧客が必要なのでしょうか?
先ほど受注率50%とお伝えしたので、勘が良い人はもう気付いていますよね。
残り10人の新規受注を獲る為には20人の見込客が必要です。
これでやるべきことが出揃ったはずです。
- 現状の見込客10人のうち5人を受注する
- 20人の新規見込客を見つける
今月中の受注を目指すなら、20人の新規見込客は月中旬頃までに探し出したいところです。
またシナリオ通りに行かない時のリスクヘッジとして20%~30%アップ、つまり25人くらいの新規見込客を探しておいた方が無難だと思います。
営業活動とは個人戦なので、誰に言われるでもなくこのような「目標達成シナリオ」を自分一人で組み立てなくてはいけません。
チームメンバー全員で取り組む案件の場合は、
- 誰がどの業務を担当するのか?
- 誰がいつまでに行うのか?
といった交通整理も必要となります。
また、例え目標未達成になってしまった場合でも、俗にいうPDCAサイクルを回しながら原因を特定し、次に向けて改善することも重要です。
もしもあなたがプロジェクトやチームリーダーを任せられるような立場の人間であれば、なおさらのことです。
- 目標達成することでどれだけ見返りがあるのか?
- 目標達成すると将来的にどうなるのか?
などを明確化させることでモチベーションアップにも繋がっていくでしょう。