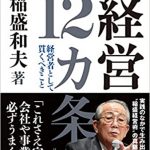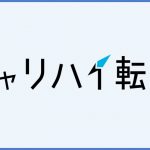柳井正(やないただし)は、実質的なユニクロの創業者であり、日本を代表する経営者です。
元々は父親である柳井等が経営していた「メンズショップ小郡商事」がファーストリテイリングの母体となっていますが、1972年に息子である柳井正が入社し、1984年にユニクロの第1号店を出店しました。
その後、柳井正が社長に就任し、全国展開を推し進めたのです。
その結果1994年には広島証券取引所に株式を上場、1997年には東京証券取引所に株式を上場させ、名実ともに一流企業の仲間入りを果たしました。
そのような人物なので、ビジネスにまつわる名言もたくさん残しているのです。
そこで今回は、ユニクロが飛躍する立役者となった”柳井正”の名言をご紹介したいと思います。
ビジネスパーソンはぜひご覧ください。
柳井正の名言集まとめ
「増収減益」というパターンは、売り上げは伸びるが利益が上がらないどころかダウンしてしまうという、あらゆる面の効率が悪くなっているから起こるのだ。
積極投資している時の「増収減益」であれば問題ありませんが、通常運転している状態で「増収減益」というのは大問題です。
それに気づいた場合は、すぐに修正した方が良いでしょう。
ぼくには安定成長志向が満足できない。
柳井正は実質的な「ユニクロ創業者」なので、基本的なスタンスは急進派です。
「会社はそう簡単には潰れない」と考えていて、博打(バクチ)のような投資も時々するそうです。
2001年8月期を頂点にして、フリースブームが去ったとはいえ、そのブームのおかげで「ユニクロ」が一般的に認められた存在になったのは事実だ。
この時のフリースブームは凄まじく、連日テレビでも取り上げられていました。
「ユニクロのフリースを着るのがカッコイイ!」というトレンドができたので、一気にユニクロが躍進したのです。
人間の成長でも同じだと思うが、結果的には経営の安定成長はあるけれど、初めに高い目標を持ってチャレンジする人しか成長できないはず。
初めから安定成長はありえません。
人間も企業も”高い目標”を掲げて、それに向かってがむしゃらに行動すれば、自ずと結果はついてくるはずです。
業界内の一般的な考え方によれば、服の需要がこれだけあるとしたら、それを業界内の人たちでいかに奪い合うか、その限られた市場を中心にして考えている。
限られた狭い市場の中で、財布を奪い合っても、ビジネスは拡大していきません。
なので、ユニクロでは初めから”グローバル競争”を目指して、GapやH&M、ZARAと戦える会社作りを目指していたそうです。
世界一のユニクロ、ファーストリテイリングを実現する。
「世界一」を掲げる経営者は、大企業の社長にも少ないはずです。
もちろん表面上は「世界一を目指す!」と言っているかもしれませんが、それは虚栄のようなもので、ほとんどの人は建前だと思います。
本音で「世界一」を掲げることができる経営者は本当に貴重ですよね。
会社経営においては、会社も個人も「成長しなければ死んだも同然だ。」と私は確信しています。
これは100%共感できる名言ですね。
ビジネスパーソンは「成長しなければ死んだも同然だ。」を座右の銘にしましょう!
パラダイムの転換は、企業にとって絶好のチャンスです。
ビジネス環境は常に変化していきます。
その変化はピンチになりますが、チャンスにもなりえるので、上手に活かしていきましょう!
ビジネスの世界では、早く駆け抜けないとそこには死が待っています。
ビジネスにおいてスピードはもの凄く重要です。
これはAmazon創業者であるジェフ・ベゾスも同じことを言っているので、気になる人は下の名言集をご覧ください。
現場、現物、現実
柳井正は”徹底的な現場主義”を掲げている経営者なので、以下のような質問をしています。
- 現場を誰よりも熟知していますか?
- 問題点や回答を現場で見つけていますか?
- 現物を手に取って、自分の目の前で商売していますか?
机上や本部に答えはないので、経営者はこのような質問を常に自分自身へ投げかけて、自分の行動を改めましょう。
不遜な言い方かもしれないが、減収減益決算になってぼくは逆にホッとした。
これは上場後初の「減収減益」決算になった時の言葉です。
フリースが爆発的なヒットになったので、ある意味では決算がバブル化していたそうです。
正常の”成長”ではなく”膨張”に近い決算だったので、それが正常に戻ってホッとしたということです。
増収増益が続いて有頂天になるのではなく、その理由をきちんと把握することが経営者には求められるのだと思います。
会社というのは、何も努力せず、何の施策も打たず、危機感を持たずに放っておいたらつぶれる、と考えている。
何もしないということは”現状維持”なので、「会社は現状維持だと倒産する」ということです。
資本主義において現状維持は相対的に”衰退”を意味するので、いずれ会社は潰れてしまうのです。
危機、つまりリスクを裏返すとプロフィット、要するに利益に通じる。
会社経営では、危機は利益と同義語なのだ。
これは百戦錬磨の経営者ならではの名言ですよね。
柳井正は「危機と聞くとどうしても”不安”と同一視してしまう人がいる」と言っていますが、危機感を”不安”と勘違いしていたら会社経営はできないそうです。
つまり「ピンチはチャンス」という言葉通りですね。
常に自分たちがやっていることが間違っているのではないかと問いかけながら、一切他人に甘えることなく経営していかなくてはならない。
稀に他人へ頼り切っている経営者を見かけます。
- ウチの会社の顧問に紹介してもらおう!
- ウチの会社の投資家の人脈を活用しよう!
- 有力な販売代理店がいるから大丈夫!
もちろんこれらは素晴らしい話なのですが、経営者はそれに頼り切ってはいけません。
事業とは「あくまでも自分の手で切り開かなければいけない」と考えています。
ユニクロは、低価格をやめます。
これは2004年に全国の新聞で宣言したキャッチコピーです。
ユニクロは上質なカジュアルウェアを最低価格で提供しようと考えていましたが、それによって「ユニクロは安物」という間違った認識が広がってしまったそうです。
なので、これまでよりもさらに品質を上げて、価格を上げていく戦略に舵を切ったのですが、価格を下げる努力をやめたわけではありません。
考え方としては、「まず第一優先に品質を求めて、それに見合う最低価格を設定する」ということになります。
一般的な小売業では「まず販売価格(=欲しい売上や利益)を決めて、それに見合う範囲の原材料でまかなう」というやり方なので、全く逆のアプローチですよね。
なので、このキャッチコピーの裏側には「絶対に良い商品を売るので、ぜひ買ってください!」というユニクロの自信が隠れているのです。
スキニージーンズでは成功したのだが、その次に出したワイドジーンズでは失敗した。
一流の経営者と呼ばれている柳井正でも、ビジネスの勝率は”一勝九敗”だそうです。
そのことを本にまとめているので、もしよければご覧ください。

サラリーマンではなく、自分自身で考え行動する自律・自立型の社員(ビジネスマン)を会社内で育成しなければ会社は成長しない。
これは多くの経営者が語っていることです。
社員全員が当事者意識を持って、まるで個人商店主のように振る舞うのが理想的だそうです。
それを仕組み化したのが、京セラ創業者の稲盛和夫が考案したアメーバ経営です。
アメーバ経営について知りたい人は下の記事をご覧ください。
ユニクロの商品が売れたとしても、たまたま「低価格だから売れた」というのであれば将来性は全くない。
ユニクロが品質を求める理由が、この言葉に凝縮されています。
「品質が悪くて、ただ”安い”だけの商品を売ることは楽しくない」と柳井正は語っています。
本来、仕事というのは自分で作り出していくべきものである。
柳井正は「指示待ちのサラリーマンが多すぎる」と危惧しています。
この金言の通り、自ら率先して取り組んだり、自ら創造するのが”本当の仕事(=価値)”なので、単なる作業をしている人は考え方を改めるべきだと思います。
仕事はやればやるほどいろんな発見があり、仕事の目的である「顧客のため」にやるべきことが山ほど出てくるものなのだ。
これは「仕事が楽しい!」と言える状態だと思います。
このような働き方を目指しましょう!
自分が部下に命令するだけで、自分の仕事は終わった気になっている。
これはマネジメントについて語った名言です。
マネジメントは難しいですが、そのやり方を知りたい人は下の記事をご覧ください。
成功の復習をしても、環境が絶えず変化していく中では同じような方法では成功しないのだ。
昨今はIT化の流れがあるので、とにかくビジネスのスピード(=変化)が速くなっています。
なので、ビジネスの再現性もなくなっており、「○○すれば成功する!」という絶対的な法則もありません。
よって、現代ビジネスで成功するための秘訣とは、とにかくたくさんのトライ&エラーを回転させて、死なない程度の失敗をたくさん経験し、環境の変化に対応する(=ピボットする)勇気を持つことだと思います。
仕事というものは、自分の専門分野のことだけ考えれば良いのではなく、部門を超えてどんな影響を与え合うか考え調整しながらやるべきものである。
これは”企業経営”について語った名言だと思います。
プロパーで社長になる人は「営業出身が多い」と言われるのは、ここに理由があります。
営業職の人は顧客と折衝する立場にあるので、一番川下に位置していますよね。
そこからOJTで少しずつ川上の方に上っていくのですが、すると必然的に全ての部門の関連性が見えてくるので、企業経営する為のスキルが自然と身に付いてしまうのです。
SPAであれば原価がダウンするから儲かるという単純なことではないのだ。
ユニクロの強さはSPAにあると言われています。
SPAとは、ファッション商品の企画から生産、販売までの機能を垂直統合したビジネスモデルで、日本語では「製造小売業」と訳されます。
ちなみにSPAとは、商品企画から販売まで全ての流れを一社で回している仕組みのことです。
一般的な小売業では、「発注した商品を全て買い取るリスクはありますが、大量にロット発注するのでコストが下がり、その結果売値も下げられる」と理解されているはずです。
SPAも同じく「大量の原材料を仕入れして、それを海外の工場で糸紡ぎして、また別の海外工場で織る」というやり方なのですが、SPAにする本当の強みというのは「PDCAを自社完結で回せる」という部分のようです。
つまり「この商品よりも、こういう企画の方が売れそう」という仮説があった場合、実際に売ってみないと分かりませんよね。
一般的な小売業はそれを予測しながら「ギャンブル的に仕入れて売る」という作業を繰り返しているのですが、SPAの場合にはもし売れなかったとしても「少し改善してまた売ってみる」というテストができるので、成功するまで何度でもチャレンジできるのです。
このように圧倒的なスピード感を持ったマーケティングが実施できるのが”SPAの強み”だと語っています。
悪い意味での大企業とは、つまり意思決定が遅く環境に対応できずにもがいている、図体の大きいだけの企業である。
かなり辛辣な表現ですが、確かにこの通りかもしれません。
これを解決するためには、組織を細かく分断して、各人に裁量権を持たせなければいけません。
そのやり方にはアメーバ経営やカンパニー制度などがあるので、やる気さえあればきっと解決できると思います。
経営者は暴走している最中、自分の姿が見えていない。
ワンマン経営者であれば、時には暴走することもあるでしょう。
そんな時には誰かが社長を牽制するべきだと思いますが、実は「会社内の人間には難しい」というのが実態です。
そんな時に役に立つのが社外取締役だと言われています。
リーダーシップの強い経営者がトップの場合、牽制役として社外取締役を設置するのが良いでしょう。
不正や不祥事が発生したら、「我々はこれを大きな問題として認識し、こういうふうに解決し、今後発生しないようにこのように予防策を講じる」と宣言する。
不祥事が発覚したら、それを隠してはいけません。
もちろん感情的に反論したり、「大企業だからこれぐらいあるさ」と開き直ってもいけません。
テンプレ的な対応でも構わないので、上記のように対応しましょう!
ちょっとした考え方の違いが、商品の可能性を大きく広げる。
これは大ヒットしたヒートテックについて語った名言ですが、元々ヒートテックはスポーツ用途の肌着をファッションウェアに変えたものです。
世の中には、中身が同じなのにパッケージを変えただけで大ヒットしたり、商品とパッケージは同じなのに”商品名”だけを変更して大ヒットした事例もあります。
セールスとマーケティングはセットなので、そのような視点で自社プロダクトを見た方が良いと思います。
商売をする上で、お客様を常に観察するということは非常に大事なことだ。
お客様をじっくり観察すれば、必ず顧客ニーズが見えてきます。
それが引いては”顧客第一主義”に繋がっていくので、ビジネスにおける最も重要なポイントだと思います。
柳井正は「論理的な考えも大事だが、商売人はまず肌で感じないといけない」と語っています。
その商品を見た途端、「あっ、これは自分が欲しかった商品だ!」とその場で思ってもらわなければならない。
店舗にフラっと立ち寄るお客様のほとんどは、「何かお得な商品があるかも」とか「ひょっとしたらいい商品があるかも」というのを期待していますが、具体的なイメージを持っている人は少ないはずです。
なので、魅力的に見える売り場作りを考えなければいけません。
ワクワクする売り場作りについては下の記事をご覧ください。
チラシは「お客様へのラブレター」と考えれば分かりやすい。
ユニクロといえば、折込チラシですよね。
チラシをラブレターにたとえるなんて、シュールですがセンスがあると思います。
「全然売れない」という経験をしないと、商品は陳列しておけば勝手に売れていくものと錯覚する。
これは売れているお店ほど陥る罠だと言われています。
売れている時には「努力しなくても売れるじゃん」と錯覚するので、自ら現状維持(=死)を選んでしまうのです。
そうするとビジネスは衰退して、いずれ倒産することは先ほど述べた通りです。
まとめ
ここまでファーストリテイリング創業者である柳井正の名言をご紹介してきました。
仕事に関する格言ばかりだったので、きっとビジネスパーソンには役立つと思います。
仕事に役立つ金言を探している人は、ぜひ下の記事もご覧ください。