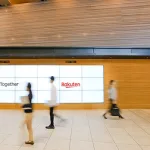※本ページはプロモーションが含まれています。
個人企業という言葉は「個人事業主」や「フリーランス」を指すフレーズとして使われています。
そのような個人事業から法人成りするには様々なステップがあると言われているので、今回は個人事業主&法人代表者(法人設立)の両方を経験した”さの編集長”が、個人事業主として独立するメリット&起業する方法について解説したいと思います。
目次
独立・起業は難しいの?
今まで会社に勤めていて、ゆる~いサラリーマン人生を送っていた人だったとしても、ある日ふと「独立・起業したい!」と思うことがあります。
このように考える理由は様々だと思いますが、独立・起業を意識する人は総じて”優秀な人”が多い気がしています。
そのような優秀な人が会社を辞めて、いざ独立・起業するとき、大きく分けると2種類のアプローチ方法があると言われています。
- 個人企業(個人事業主)として独立する
- 法人登記をして事業会社を設立する
独立・開業するのであれば、なんとなく法人登記した方が良い気がしますが、実際にはそんなことありません。
個人事業主であろうが法人であろうが、仕事をして稼いだ所得をきちんと申告して、ちゃんと税金を支払えば、結論としてはどちらでも良いのです。
ただ「開業届を出して個人事業主になるか?」「法人登記をして会社にするか?」には、どちらもメリット&デメリットがあることは事実です。
なので、継続的な事業として続けていきたい人は、「どちらの事業形態で起業した方がメリットがあるのか?」を慎重に選ぶ必要があると思います。
まずはこの部分に触れていきたいと思います。
個人事業には開業届が必要
個人企業として独立するのはとても簡単ですし、届出費用も無料なので、あまり肩に力を入れる話ではありません。
自分がビジネスを立ち上げたいエリアを管轄する税務署に出向いて、「個人事業の開業・廃業等届出書」(いわゆる開業届)を提出するだけなので、ある意味では拍子抜けしてしまうかも知れません。
そこに記載する内容は、納税地や氏名などの基本情報と事業に関する記述だけなので、たった1枚の書類を提出するだけです。
しかも記入方法は役所窓口の人に聞けば教えてもらえるので、全然難しくありませんし、提出した書類に不備がなければ、その日から個人事業主として活動することもできます。
あまりに手続きが簡単すぎて、むしろ拍子抜けするほどですが、これで晴れて個人事業主になることができます。
開業届を提出するということは、なんとなく大きな人生の転機になるような気がしますよね。
実際に開業届を提出するときには、役所窓口の人から「記念に開業届の写真は撮りますか?」と聞かれるほどなので、多くの人がそのような転機だということを理解しているのでしょう。
ただし、個人事業主として独立したからには、「自分は経営者(社長)」であるという自覚を持たなければいけません。
個人事業主というのは「自分自身でビジネスする人」を指す言葉です。
なので、仕事をする上でのミスやトラブル、事故などは全て自分の責任になるということです。
もちろんサラリーマンと二足のわらじで開業する人もいますが、もし個人企業として活動するなら「本業は会社員だから…」という甘えは許されません。
もしあなたが専業のフリーランスなら、社会保険や残業代、給与&厚生年金などの保証はありませんし、自分や家族の生活を守るのも、全て自分自身の手にかかっています。
その代わり、個人事業主として働いて得た報酬は全て自分のものになるということです。
これはつまり「リスクを負うからリターンが得られる」ということなので、個人事業主はそのリスクを受け入れなければいけないということです。
税務署に認められる範囲で、経費(所得を得るために必要と見なされるお金)も自由に使うことができるので、もちろん企業会計についても最低限勉強しなければいけませんが、自分のやりたい仕事で所得を得るのは、個人企業として独立する大きな魅力だと言えます。
まずは下のような書籍を読んで、コツコツと勉強していきましょう。


個人企業と法人企業の違いは?
先ほど「個人事業主であろうが法人であろうが、結論としてはどちらでも良い」とお伝えしましたが、個人企業と法人企業の違いは手続きと税制上のメリット&デメリットにあるので、ココで押さえておきましょう。
個人企業の開廃業が税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を出せば済むのに比べて、法人企業は法人登記をしなければいけません。
この登記手続きはかなり複雑で、手間もかかるので厄介だと言えます。
しかも、登記費用は全て自分でやったとしても約30万円(株式会社の場合)ほどかかるので意外と高額なのです。
また、会社を設立するために銀行口座の開設や、代表印の作成、会社情報が記載された封筒の準備なども必要です。
あくまでもざっくりとまとめましたが、法人設立する場合にやっておくべき準備は下のようにたくさんあるのです。
- 会社印鑑の作成
- 銀行口座の開設
- 会社情報入りの封筒作成
- 名刺デザインの発注
- 名刺の印刷
- 販促資料の作成
- 契約書の作成(販売契約書、代理店契約書、業務委託契約書など)
- ドメインの取得
- サーバーの契約
- ホームページの制作
- 電話番号の取得
- メールアドレスの取得
- 法人SNSページの開設(Facebook、Twitter、Instagramなど)
- 法人クレジットカードの新規作成
- PayPalアカウントの作成
- 会社事務所の手配
- 商標登録の届出
- 各種許認可申請 etc.
ちなみに、上記は「営業シーク さの編集長」が実際に起業する際に行った手続きの一部です。
「やっぱり法人設立の手続きは多いな…」と感じたかもしれませんが、実は個人企業と法人企業での手続きにはほとんど違いがありません。
もちろん開業届1枚で成立する個人事業主と、法人登記する事業会社ではやり方が違いますが、たとえ個人事業主だったとしても、名刺は必要ですし、契約書の準備、ホームページも必要だと思います。
そう考えた場合、個人企業と法人企業にする大きな違いというのは、おそらく"信頼度"の違いだと思います。
やはりフリーランスとしてビジネスしている人と、法人成りして事業を行っている人では信頼度が違いますよね。
これはあくまでも個人的な見解ですが、法人化している方がステークホルダーが多くなるので、仕事に対するコミットメントが強くなるような気がします。
会社を設立してからこれまで様々な方(個人企業&法人企業)と取引してきましたが、未入金や未払いになるのは圧倒的に”個人企業”の方が多いです。
※トラブルを起こすイメージとしては「個人企業:法人企業=9:1」くらいの割合。
このような実態があるので、多くの企業は個人事業主との商取引を望みません。
しかし法人登記の手続きは色々と面倒なので、もし一人で独立する時には、まず個人企業から始めるという判断でいいと思います。
実際に営業シーク さの編集長は、会社を退職してから半年間は個人事業主として独立開業していました。
その後、事業へのコミットメントを強めるため、WEBX Inc.の設立に至っています。
合同会社という選択肢もある
会社設立する際、「株式会社」以外にもたくさんの選択肢があるので、それも知っておくべきだと思います。
その代表例が「合同会社」です。
合同会社とは法律で認められた法人形態なのですが、株式会社と比較してあまりメジャーではありません。
合同会社という仕組みは後からできたので、まだまだ一般的ではないかもしれませんが、実は外資系のAppleやGoogle、Amazonなど名だたるグローバル企業は合同会社として登記されています。
外資系企業の場合には、合同会社にした方が会計上のメリットがあるので、そちらを選択しているのです。
それでは日本の企業が合同会社を選ぶメリットは何なのでしょうか?
それはまず設立費用にあると思います。
株式会社を設立するのに30万円ほどの費用が掛かりますが、合同会社は6万円ほどで法人登記できるのです。
これだけでも、資金の乏しい設立当初は助かりますよね。
しかしそのようなメリットがあるのにも関わらず、合同会社があまり選択されていないのには様々な理由があります。
- 世間的なイメージが悪い
- 事業規模が小さいと思われる
- お金がない会社だと思われる
- 合同会社では取引できない場合がある
- 資金調達が難しい
これはあくまでも一般論になりますが、株式会社と合同会社を比較した場合、どうしても合同会社の方がイメージが悪くなります。
そのようになる理由は様々ですが、あまりメジャーではないことと、ビジネス規模が小さいことが挙げられます。
外資系のグローバル企業は別ですが、日本で展開している一般的な合同会社は、総じて事業規模が小さいことが特徴的です。
もちろん中には合同会社DMM.comのような例外企業も存在していますが、ほとんどの会社は小規模なビジネスをしているはずです。
そして資本金も小さいので、「合同会社とは取引しない」という企業まで存在しています。
そして一番大きなデメリットと言えるのが、株式を発行した資金調達(エクイティファイナンス)ができないことです。
これはよく言われるビジネス格言ですが「企業経営とはヒト・モノ・カネである」という言葉がありますよね。
この企業経営にとって重要なポイントになる「カネ(お金)」の調達手法が、合同会社にすることによって制限されてしまうのです。
これは企業経営者であれば理解できると思いますが、とても大きなデメリットになり得ます。
合同会社を経営する場合には、
- 知人友人などからの借入
- 銀行からの借り入れ
というデットファイナンスしか選択肢がないので、基本的には綺麗な財務諸表(黒字決算)にすることが求められます。
なぜかといえば、財務諸表が綺麗でなければ銀行(BANK)はお金を融資してくれませんし、経営状態が良くない会社にお金を貸してくれる人は少ないと思います。
つまり、営業キャッシュフローが常に回っている”健全経営”をする自信がなければ、合同会社で設立することは絶対に避けるべきだと言えます。
株式会社 ⇒ エクイティファイナンス(新株発行)ができる、赤字決算にできる
合同会社 ⇒ エクイティファイナンス(新株発行)ができない、赤字決算にできない
この他にも、合同会社では「代表取締役」という肩書が使えないので、名刺の肩書きは「代表社員」になります。
しかし「代表社員」という言い回しがカッコ悪いので、名刺では「代表取締役」とか「CEO」という表記にしているケースが目立ちますが、それは嘘なので避けた方が無難です。
このような表記にするということは、裏を返せば「自分自身でも合同会社のデメリットを実感している」ということにもなるので、とてもかっこ悪いですよね。
このような諸々の理由があって、私は最初から株式会社にすることを躊躇しませんでしたし、合同会社にすることは避けました。
知人から「最初は合同会社にしようと思う」と聞くと、必ず「本気でビジネスしたいなら、最初から株式会社にするべき」とアドバイスしています。
そしてビジネスを始めてわかったことですが、やはり個人事業主と同様に合同会社の未入金、未払いがとても目立ちます。
このような人たちは「合同会社全体の印象を悪くしている」ので、もしあなたが誠実にビジネスをしていたとしても、ただ単に「合同会社である」というだけで印象が悪くなってしまうはずです。
これでは営業活動も最大化できないので、とても大きな機会損失になる可能性があります。
個人事業主から法人化するタイミング
最初は個人企業として独立開業し、その後に法人化するのであれば、そのタイミングはいつが良いのでしょうか?
先ほど解説したように「事業にコミットメントするタイミング」でも良いと思いますが、一般的には個人事業主としての売り上げが”800万円ほど”になったタイミングだと言われています。
個人事業主と比較して、税制上のメリットは法人企業の方が大きくなります。
まず個人企業は所得税を納めるのですが、累進課税で4,000万円以上は最大税率の45%がかかります。
それに比べて、法人税は最高で23.4%(平成30年4月1日以後の開始事業は23.2%)です。
よって、所得が大きくなるほど個人企業の方が税金を多く納めることになります。
その一方、個人企業が赤字の場合、税金を支払わずに済みますが、法人は赤字でも税金を払う必要があります。
また損益通算については個人企業は3年で、所得の種類によっては別計算になりますが、法人企業は9年で事業分野に関わらず通算できます。
経費についても法人企業の方が認められる範囲が広く、節税効果については法人企業の方がかなり有利になります。
これらは諸条件にもよりますが、概ね「年収(売上)が800万円を超える辺り」から法人成りした方が税率が小さくなると言われているので、そのようなタイミングで法人成りを検討しましょう。
個人事業主のメリット
今サラリーマンとして働いている人は、独立・起業して自由に働くことに憧れがあると思います。
フリーランスになってしまえば、毎日満員電車に揺られることもありませんし、自分の好きな時に働けて、好きな時に休めます。
このように、個人事業主になるメリットは大きく4つあると言われているので、ここで解説しておきたいと思います。
メリット①:自由に仕事できる
メリットの1つ目は、自分の好きな仕事を自由に選択できることです。
「好きなことで生きていく!」というキャッチフレーズは、とても響きが良いですよね。
会社員であれば上司の指示には従わなければいけませんし、雇用主である社長の意向を無視して働くことはできませんが、個人事業主であれば自分が全責任を負うので、自分のやりたい仕事だけに専念できます。
よって、自分がやりたいことだけを優先して、やりたくないことは「一切やらない!」と決断することだってできるのです。
サラリーマンにはこのような自由がないので、この点は個人事業主のメリットだと言えます。
メリット➁:年収がアップする
2つ目は、働いて得た所得が全て自分のものになることです。
営業職の人は日々実感していると思いますが、「自分が今月売り上げた1,000万円がそのまま給料になったらいいのになぁ」と妄想したことがありますよね。
ハイリスク&ハイリターンのフルコミッションという働き方でも、売上の100%がマージンになることはあり得ません。
会社員はボーナスなどの査定で、ある程度仕事の内容を評価してもらえますが、基本的に給料は定額支給になります。
しかし、個人事業主は自分の裁量で収入を増やして、所得に応じた税金を払えば、残りは全て自分の所得にできます。
なので、もし今月1,000万円を売り上げたなら、その1,000万円を自由に使うことができるのです。
もちろん事業に失敗した場合、莫大な借金を背負うリスクはありますが、成功すれば会社員時代より多くの収入を得ることができるでしょう。
この点は独立起業することの魅力と言えるでしょう。
メリット➂:自由に副業ができる
3つ目は副業をしたり、不動産投資をしたり、収入源を複数持てることです。
働き方改革により、副業を解禁する企業も出てきましたが、まだまだ副業禁止にしている企業は多いですよね。
しかし個人事業主はサラリーマンと違って、面倒な就業規定が無いので、自由に副業することができます。
また、所得が増えれば余剰資金で株式投資や不動産投資をして、不労所得を増やすこともできるのです。
もちろん会社員も投資することはできますが、あまり規模が大きくなってくると会社の副業禁止規定に抵触するリスクがありますし、いちいち会社に申請するのも面倒ですよね。
会社員が個人事業主ほど自由に副業できることはないでしょう。
メリット④:節税効果が抜群
4つ目は様々な節税ができることです。
青色申告を申請して、複式簿記による帳簿付けは必要ですが、青色申告特別控除額65万円を収入から控除できることは魅力的だと思います。
また税務署を納得させる根拠さえあれば、ほぼ上限なく事業経費を収入から差し引くことができるのです。
やはり経費処理による節税効果は抜群で、サラリーマン時代には考えられないほどのメリットがあります。
その方法は様々なものがあるので、ネットや本などで調べた知識を活用すればかなりの金額が節税できるでしょう。
経費処理しやすくする為、まずはAmazonビジネスなどに登録しておくのもおすすめです。
脱税は違法行為なのでやってはいけませんが、節税は積極的にやるべきだと思います。
もし独立起業を考えている場合、節税に関する本をたくさん読んでおきましょう!


個人事業主は副業すべし!
サラリーマンの副業は就業規則で禁止している企業が多いのですが、個人事業主は本業がおろそかにならない限り副業に取り組むべきだと思います。
特に独立してから事業が安定するまでの時期は、収入面で苦労することが多いので、ある程度は副業収入で補うことも必要になります。
個人事業主は自分で仕事の配分を行なう為、副業する時間を作りやすいので、もし隙間時間ができるなら積極的にサイドビジネスをするべきだと思います。
そのような副業がきっかけになって本業につながるケースもありますし、大きなビジネスチャンスが訪れることもあるのです。
収入の多様化はリスクヘッジにもなるので、独立開業する場合にはぜ検討してみてください。
個人事業主におすすめの副業
個人事業主がすべき副業は、じっくり考えた方が良いと思います。
例えば、データ入力やアルバイトなどはあまりおすすめできません。
先ほどもお伝えしましたが、個人事業主というのは経営者になります。
経営者とは、資本を使ってビジネス展開する人のことを言います。
つまり、労働集約型の働き方はしないのです。
労働集約型とは「1時間で時給1,000円」とか「月給30万円」というような働き方を言います。
それは労働力を提供する代わりに対価を得るという働き方なので、いわゆる「労働集約型」ですし、サラリーをもらっている会社員の働き方です。
それと比較して、経営者の働き方は「資本投下型」です。
会社員の働き方 ⇒ 労働集約型
経営者の働き方 ⇒ 資本投下型
「自分は働かずに、人(又はお金)に働いてもらうことで収益を得る」というのが、本来の経営者なのです。
そう考えた場合、個人事業主も経営者なので、資本投下型の働き方に、頭の中を切り替えなければいけません。
とはいっても、最初から事業資金が潤沢にあるということはないはずなので、まずはコツコツと労働集約型で働くしかないかもしれません。
そんな時には、本業の隙間時間でも働ける在宅ワーク、アフィリエイト、クラウドソーシングなどが向いているでしょう。
投資関連は資金がネックになりますが、株式投資なら少額から始められるので、手元資金に余裕があれば、本業に支障が出ない範囲で積極的にすべきだと思います。
副業探しに使えるサービスはたくさんあるので、ここでその一部をご紹介しておきます。
法人化の手続きはどうやる?
最後に、法人化の手順を株式会社設立の例で簡単に説明しておきたいと思います。
個人事業が順調に拡大していった場合、いづれ法人化することになるはずです。
なので、今のうちに法人成りするための手続きを理解しておきましょう。
会社定款を作成する
まず最初にすべきことは、会社定款を作成することです。
定款は会社の基本的な運営規則を書面にしたものなので、それは会社法に則って作成する必要があります。
株式会社の場合には、定款に法的拘束力を持たせるため、公証人による認証が必要になります。
公証人の認証を受ける為には、最寄りの公証役場に出向きましょう。
資本金を入金する
定款認証を受けて、定款の謄本が出来上がったら、次に資本金の出資を実行します。
この時点では、まだ会社設立されていないので会社の銀行口座がないので、事業主本人の口座に資本金を払い込みます。
「自分で自分の銀行口座へ振り込む」という作業は違和感を感じますが、通帳に記帳することが重要なので、この手続きは単なる作業だと理解しましょう。
この時の口座は「本人名義の口座(口座の一致)」でなければいけないので、その部分は注意しましょう。
法人の登記申請を行う
最後に設立登記を行ないますが、法務局がホームページで公開している「株式会社設立登記申請書」をダウンロードして、その内容に沿って記入していけば大丈夫です。
書類のダウンロードはこちら:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html
書類の届出先は、自分が会社の「本店」を設立する地域を管轄する法務局になります。
自分のエリアを管轄している法務局がわからない場合には、ホームページで確認しておきましょう。
管轄を探すならこちら:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
「株式会社設立登記申請書」と定款以外にも、申請内容に応じて必要な添付資料があるので、この辺りは事前に調べておくことが大切です。
とにかく法人登記にかかる書類はとても複雑なので、自分で申請するには大変な作業ですが、もし嫌な場合には行政書士へお願いするのも手だと思います。
しかし未経験者ができない手続きではないので、法務局の窓口で登記相談をしながら手続きするのもおすすめです。
どんなに入念な下調べをしたとしても、書類ミスが出てしまって、おそらく3回~5回ぐらいは法務局に行く羽目になると思います。
※さの編集長は自分で法人手続きをしましたが、法務局へは5回も行くハメになりました…
法人登記に伴う費用は、前述したように約30万円ほど掛かりますので、あらかじめ事業予算として確保しておきましょう。
まとめ
個人事業主としてビジネスを始めることは、きっと人生の転機になるはずです。
自分自身が”社長”になることには達成感があると思いますが、そのぶん責任も重大です。
会社の同僚など、周りからの助けは一切期待できないので、全て自分一人で解決していかなければいけません。
「事業を興す」ということは、それだけ大きな覚悟が求められるので、しっかり準備しておきましょう!