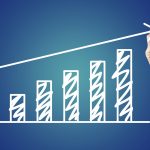営業職は「残業が多い仕事」だと言われていますが、それには営業独特の働き方や仕事内容が関係しています。
そこで今回は、「営業職の残業はなぜ多くなるのか?」という疑問について、また業務内容やみなし残業などもわかりやすく解説していきたいと思います。
既に営業職として活躍している人だけでなく、これからセールスに転職したい人もぜひご覧ください。
営業職は残業が多いの?
営業職は残業が常態化している職種なので「きつい」とか「大変」と言われることが多い職業だと思います。
他の職種でも連日残業している職種はたくさんありますが、営業職の場合には残業続きが常態化していますよね。
残業はもともと仕事の延長線なので、あくまでも労働時間にカウントされていきます。
企業から求められている仕事をこなせていない場合、その社員は残業を指示されることになりますが、その間はもちろん”割増賃金”を含めて給与が発生することになります。
営業ノルマが残業原因になっている
営業職の場合には明確なノルマや予算が定められているため、残業せざるを得ない状況に陥りやすいと言われています。
ノルマがどのように設定されているかは会社によって異なりますが、一般的には毎月これだけはクリアしなければいけない最低基準(営業予算)が定められているので、それが営業スタッフごとの”採算ライン”となっているのです。
それは売上金額で定められていることもあれば、契約件数、粗利金額などで決まっていることもあり、現場で何が重視されているかによって営業ノルマは多少違ってきます。
ただ、そのノルマが達成できないと減給になったり降格させられるなど、自分にとっての不利益となるため、ノルマ未達成の状況で月末が近づいてくると、気軽に帰宅することができず、毎日残業して目標達成するために邁進しなければいけません。
そうならないように月初から必死に働いている営業パーソンはとても多くて、結局いつも忙しくなってしまうのです。
営業職には残業代が出ない!?
たとえ営業職に配属されても「残業した分だけ残業手当が出るから全然大丈夫!」と思っている人がいるかもしれません。
しかし「働いた時間に見合うだけの残業代が出ない現場が多い」という事実を知っておいた方が良いでしょう。
それどころか「そもそも残業代すら出ない…」というブラック企業もたくさんあるので、営業職への就職を目指す人は注意が必要です。
このような待遇になってしまうのは、営業という仕事内容が特殊だからです。
先ほども少し触れましたが、セールス職にはほぼすべからく”営業ノルマ”が設定されています。
このノルマは絶対に達成しなければいけない数字なので、営業職は死に物狂いで達成する方法を日々考えていることでしょう。
なぜかと言えば、営業ノルマが達成できないということは、営業職にとって「仕事をしていない」ことと同義になるからです。
営業職に求められることは「売上を作ること」なので、与えられたノルマが達成できていないと、売上も作れないことになります。
そのような事実は社内共有されてしまうので、周りからの冷たい視線に耐えられない人もいるはずです。
このような事情があって、営業職の人は自ら進んで残業してでも「絶対にノルマを達成したい!」という気持ちになるのです。
それでも一定数は”ノルマ未達成”の営業スタッフが出てきてしまうというのが経営者の悩みのタネになっています。
このような状況を、営業マンは会社視点(経営者の目線)で考えてみる必要があると思います。
経営者が従業員へ支払う給与というのは、端的に言ってしまうと「労働力の提供」に対して支払われています。
つまり指示した仕事をこなしてくれた対価として給料が支払われるのです。
そのような観点で見た場合、ノルマ達成できない営業職の人は仕事をしてないことになるので、支払った給与に見合うだけの労働が提供できてないことになります。
そのような状況なのに営業職の人が「自分が提供できなかった労働力を提供したいので、超過する分の残業代を別でください!」と言ってきたら、経営者はどう感じるでしょうか?
- ノルマ未達成の無能営業マンに約束通り月給を支払ったのに、さらに残業代まで要求されている。
- 仕事が出来ないなら、自分の費用と責任で業務遂行するべきではないか?
- なんでダメ営業マンの仕事をフォローするのに私が身銭を切らなければいけないのか?
もしあなたが雇用主なら、このように憤慨するはずです。
このような状況を外注先でイメージしてみると、大きな矛盾に気が付くはずです。
外注先の営業代行会社に月50万円の業務委託費を支払いました。
依頼した業務内容は「30日間で新規受注10件を獲ること」です。
新規受注10件をコミットメントしていましたが、30日間経過した段階で新規受注は6件という着地になりました。
残り4件が不足しているので、営業代行会社は追加予算として30万円を請求してきました。
いかがでしょうか?
普通の感覚を持ち合わせているのであれば、この営業代行会社は正気ではないと思うはずです。
営業職の人が残業代を請求するということは、このような感覚と似ているのです。
このようなロジックが理解できている当事者意識のある営業パーソンは、あえて残業代を申請せずに、サービス残業をしながらノルマ達成することを目指しています。
もちろんサービス残業を推奨するわけではありませんが、実態としてこのようなケースが多いはずです。
正当な手続きを踏めば残業代は申請できると思いますが、なかなかそれを申請しづらい職種が営業職なのです。
なので営業職として働くのであれば、基本的に「残業代は出ない」ものだと考えた方が無難だと思います。
このような結果になるのは、自分の力不足が大きな要因になっています。
ただ逆説的に考えれば、フルパワーを発揮してノルマ達成さえすれば、いつでも仕事を休めるというメリットもあります。
営業職は経理や総務のような『労働集約型の働き方』ではないので、月初5日でノルマ達成ということも十分あり得ます。
そんな時には有休を使ったり、昼間からカフェでゆっくりお茶して過ごすこともできるのです。
もちろんノルマ達成している状態であれば、誰から文句を言われる筋合いもありません。
ビジネスパーソンとしてそのような働き方が正しいかどうかは別として、ロジック的にはそういうことになります。
外回り営業しても残業にならない!?
営業活動は顧客主体なので、必ずしも一般的な就業時間帯に仕事をすれば良いというわけではありません。
お客様が「土日に来て欲しい!」というなら、その要望に応じて出向かなければいけませんし、夜遅くや朝早くにしか対応できないと言われたら、その時刻でも訪問しなければいけないのです。
もちろん自分の判断で「土日は一切対応しません」ということもできますが、それでノルマ未達成になっているのであれば目も当てられません。
そのような働き方は”お金のために働いている”状態なので根本的に間違っていて、更なる高みを目指すビジネスパーソンの動き方としてはふさわしくありません。
仕事をする理由は、あくまでも”自分自身のため”であるべきだと思います。
自分自身のキャリアを考えたり、自分自身を成長させるために仕事するべきなのです。
少し話が逸れましたが、お客様が土日に来て欲しいと言うのであれば、残業代は出ないかもしれませんが、できる範囲内で極力対応した方が良いと思います。
例えば、休日にお客様から電話が掛かってきたとします。
その電話がもし追加発注の連絡だった場合、営業マンにとっては吉報だと言えるでしょう。
そして、この電話対応を残業代(休日手当)として請求する営業マンは現実的にいないはずです。
電話が夜中にかかってきたり、休日の早朝にメールが届くこともあるでしょう。
それらへ迅速に対応することで、顧客からの信頼を勝ち取っていくのが営業職の務めとも言えます。
正規の時間に働いた分については残業代を出す企業もありますが、このような臨時の対応については、残業代はあってないようなものが現実だと思います。