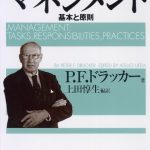伊藤雅俊は株式会社イトーヨーカ堂の創業者であり、1924年東京生まれの実業家です。
もともとイトーヨーカドー(イトーヨーカ堂)は、叔父が東京浅草で経営していた羊華堂洋品店の暖簾分け店として始まりました。
その時には実兄が経営していたそうですが、持病によって兄が亡くなった為、1956年にその会社を伊藤雅俊が譲り受けて社長となります。
その後は本格的なチェーン展開を目指し、1958年には株式会社ヨーカ堂を設立しましたが、1992年の総会屋事件で引責辞任することになりました。
それをきっかけとして直部下だった鈴木敏文に経営権を譲った後、皆さんご存知のセブンイレブンというビジネスモデルが大躍進して、デニーズ、セブン銀行などの新規事業を次々と立ち上げ、現在のセブン&アイホールディングスの礎となりました。
実質的に事業を成長させたのは鈴木敏文ですが、その創業者である伊藤雅俊と二人三脚だったことは有名な話です。
そこで今回は、イトーヨーカドー創業者である伊藤雅俊の名言集をご紹介したいと思います。
伊藤雅俊の名言集まとめ
お客様は来てくださらないもの。
お取引先は売ってくださらないもの。
銀行は貸してくださらないもの。
これは伊藤雅俊が考えていた『商売の基本』です。
一番大切なのは”信用”であり、その担保となるのは、人間としての誠実さ、真面目さ、真摯さだと考えているようです。
どんな商売でも、資本が大切なことは言うまでもありません。
経営者の中には”資本”と”負債”の違いがわからない人もいます。
もしこれからビジネスを始めるのであれば、この違いは明確に理解しておいた方が良いと思いますので、それを理解したい人は下の記事をご覧ください。
創業以来、現金仕入れに徹し、支払いの期日があるお金を自由に使える資本と考えたことはありません。
これは企業経営にとって重要な「回転差資金」について語った名言です。
例えば原価60万円、売価100万円の商品を小売りした場合、手元には100万円の現金が入りますが、実際の利益は40万円(100万円-60万円)ですよね。
しかし買掛金で仕入れをすれば、しばらくは手元に60万円が歩留ることになります。
この60万円が「回転差資金」と呼ばれているのです。
多くの経営者は手元にある100万円(60万円+40万円)を自分のお金だと勘違いして、毎晩飲み歩いたり、無計画な投資をしてしまうそうですが、伊藤雅俊は経営実態を把握したかったので、原則的に買掛をせず現金支払いしていたそうです。
利息が経費で落ちる借金と違い、税引き後利益から配当金を支払わなければならない資本のコストは相当高いのです。
一般的に「デッドファイナンスよりもエクイティファイナンスの方が調達コストは高い」と言われます。
これはまさにその通りなのですが、伊藤雅俊の名言を見ればその違いが良く理解できますよね。
企業会計において、借入利息は経費処理できるのですが、株主に支払う配当金は”税引き後利益”から支払うことになるので、「調達コストが高い」と言っているのです。
人の世では、壊れたり、価値が減じることのない、信用という無形の資本こそが大事だということです。
これは経営者に伝えたい名言No.1ですね。
「正直者が馬鹿を見る」という格言もありますが、ビジネスにおいては「正直者は必ず得をする」のだと思います。
一人でも多くのお得意先を増やすことが商売の基本です。
まずお客様になっていただくこと、そしてお客様に満足していただくこと、そうすればお得意先になってくれるはずです。
とても簡単な方程式なので、必ず実践しましょう!
「シェアホルダー」とか「ステークホルダー」などのカタカナ文字の氾濫に惑わされる必要はありません。
ビジネスとは、ただ単に顧客満足度を高めて、お客様から「ありがとう」と言われる商品・サービスを提供し、その対価を受け取るというだけです。
様々な利害関係者がいたり、目指すべき数値目標があるかもしれませんが、究極的にはお客様が喜んでさえくれれば、それがビジネス全体へと波及していくはずです。
小売業は立地産業であり、生活産業です。
小売業は地域社会に貢献することを求められるので、その企業の盛衰が、その地域の盛衰にも繋がっていきます。
そう考えた場合、小売業と地域社会は”運命共同体”であり、かなり責任重大であることが理解できますよね。
お客様を中心に、社員、取引先、地域社会などの様々な要素で成り立っている商売の結果が利益。
よくある愚問に「ステークホルダーの中で優先順位をつけるとしたらどうなりますか?」という質問があります。
もちろん優劣をつけることはできませんが、あえて優劣をつけるとした場合「まずお客様、そして次が社員、取引先、地域社会、最後が株主」という順番になると伊藤雅俊は語っています。
なぜかといえば、株主に満足していただくためには、まずお客様に満足してもらわなければいけないからです。
この逆は絶対にありえないので、至極当たり前の順番だということです。
激しい競争の中で、脇目も振らずに必死になってお客様と市場の変化を追いかけなければ、生き残れないのが先進国の商売の難しさです。
日本はモノ余りなので、何でも簡単に売れるような時代ではありません。
だからこそ顧客ニーズを把握して、しっかりとしたマーケティングを実践しなければいけないのです。
これはセブンイレブン創業者の鈴木敏文と同じ意見みたいですね。
私は欧米の小売業の何人もの先達から、「多角化はするもんじゃない」と何度も忠告され、その戒めを肝に銘じてやってきました。
伊藤雅俊は多角化の難しさについて「商売は似ているようで全て違っており、人間は違う仕事をいくつもこなせるほど器用ではない」と語っています。
だからこそ多角化を成功させた鈴木敏文について、「私よりもビジネスセンスがある」と評価しているのです。
経済が成熟して低成長になれば、本業専念、一業専念ということが重要になります。
あっちこっちに手を出していては、経営リソースが分散してしまいます。
経済全体が成長している良い時期であれば問題ありませんが、低成長時代において多角化は正しい戦い方と言えません。
それでは最大効率化できないので、選択と集中を行いましょう!
商売に栄枯盛衰はつきものです。
永久に繁栄する商売などありません。
ビジネスに栄枯盛衰がある理由とは『環境が変化するから』です。
顧客ニーズ、社会情勢、競合他社の動向など、様々な要素が複雑に絡み合いながら、ビジネス環境は常に変化しています。
だからこそ経営者は日々改善(アップデート)することが求められるのです。
商業の魅力は、自由であるということです。
この言葉から、伊藤雅俊は商売を楽しんでいたことが伺えますよね。
商売人は自立しているのですが、自立しているからこそ自由があるのです。
そして自由には責任が伴うので、経営者は社会的責任を意識しましょう!
お客様あっての商売が、厳しいものであることは言うまでもありません。
これはあくまでも個人的な主観ですが、本当に商売は難しいと思います。
しかしその一方で「とても面白い」とも感じています。
スモールビジネスでもいいので、何か一つ自分で商売を始めてみることをおすすめします。
小売業の自由度が高いのは、売る相手が企業である製造業や卸売業と違い、個人のお客様を相手にする商売だからです。
個人向けビジネスのことを「toC」と呼んで、法人向けビジネスのことを「toB」と呼びますよね。
個人向けビジネスは裾野が広い、かつ自由度が高いのですが、その一方でお客様を選べないというデメリットもあります。
法人向けビジネスであれば「取引停止」ということもできますが、個人向けビジネスの場合には、お客様が勝手に入ってくるので、相手を選ぶことができません。
だからこそ常に明るく元気に、誠実な接客が求められるのだと思います。
小売業は人と人との商売ですから、一番大切なのは社員の質です。
伊藤雅俊が社員教育を徹底していたことは有名な話ですよね。
勤務中だけでなく、会社へ通勤する際に「背広を脱いだら肩にかけるのではなく、必ず脇に折りたたんで持つこと」「通勤途中にタバコを吸うことは厳禁」など、たくさんのルールがあったそうです。
これらはすべて『いつもお客様から見られている』という前提に立っているのですが、先ほど解説したように『地域社会と会社は運命共同体』という考えにも基づきます。
小売業者は、その存在を地域社会から認められてこそ、初めて企業経営ができると考えたのでしょう。
商売が軌道に乗ってくると、お客様が来てくださるのが当たり前と思うようになって感謝の気持ちや謙虚さが薄れ、自分の力で成功をつかんだのだという驕りが生まれます。
これは当たり前の現象なのですが、だからと言って良いはずありません。
いつでも創業当時の気持ち(初心)を忘れずに、謙虚な姿勢で商売しましょう!
自分の力を過信し、傲慢さに気づかなくなった時が危機の始まりです。
「ビジネスが「順風満帆だ!」と感じた時ほど危険」と言いますよね。
これは数多くの経営者が口を揃えているのですが、独立・起業を目指す人はこの言葉を肝に銘じておきましょう!
私はP・F・ドラッカー先生の知遇を得て、先生が歴史と社会と企業の素晴らしい観察者であることを知りました。
ピーター・ファーディナンド・ドラッカーとは、有名なオーストラリア人の経営学者です。
ドラッカーの考え方は経営者が学ぶべき知識だと思いますが、たとえば有名な言葉には「企業の本質とは顧客を創造することである」というものがあります。
他にも「唯一絶対の指標となるものは人口動態である」など、数多くの名言をたくさん残しています。
ドラッカーの経営理論を知りたい人は下の記事をご覧ください。
日本中から人が集まる一等地の商売は、黙っていてもお客様の方から足を運んでくださるのだから、競争はあっても楽です。
楽な商売を経験してしまうと、難しい商売に手を出そうとならなくなります。
そうするとビジネスは徐々に衰退していき、やがてその企業は消滅してしまうのです。
だからこそ『難しいチャレンジ』から始めることを伊藤雅俊は推奨しています。
創業は大変なことですが、守勢(守成)も創業に劣らず大変なことだと言われる所以です。
創業と守勢は、有名な中国古典『貞観政要』の中で最も有名な言葉の一つです。
貞観政要は「リーダーが読むべき名著」と言われている本なので、気になる人は下の記事をご覧ください。
私は人に縛られるのも、人を縛るのも嫌いな人間です。
伊藤雅俊は自分自身のことを「自由人」と呼んでいます。
しかし自由であるということは、その分社会的責任も大きくなるので、恐怖と表裏一体であることは間違いありません。
伊藤雅俊は「商人には算盤と始末と才覚が必要だ」と語っています。
算盤(そろばん)といえば渋沢栄一ですよね。
渋沢栄一の名言集は下の記事をご覧ください。
鈴木敏文と二人三脚で築き上げた
ここまで伊藤雅俊の名言集をご紹介してきました。
伊藤雅俊はイトーヨーカドー創業者なのですが、日本を代表する小売業者「セブン&アイホールディングス」の礎を創ったのは、部下である鈴木敏文だと言われています。
イトーヨーカ堂という企業のNo.1が伊藤雅俊で、No.2が鈴木敏文という組織図だったのですが、鈴木敏文の方がマネージメント能力が高く、ビジネスセンスも秀でていたそうです。
なので伊藤雅俊やイトーヨーカ堂という企業を理解する上で、鈴木敏文について知っておくことは必須事項だと言えます。
その名言集は下の記事をご覧ください。