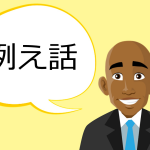マルクス・トゥリウス・キケロは紀元前100年頃に生きた、古代ローマの人物です。
政治家であり哲学者でもありましたが、「古代ローマ最強の弁護士」という異名を持つほど偉大な人物なのです。
実際に、イタリアのローマにある裁判所の前には『キケロの銅像』が立っているほどです。
そこで今回は、マルクス・トゥリウス・キケロの名言集をご紹介したいと思います。
キケロの思想を理解する為にも役立つので、ぜひご覧ください。
キケロ(キケロー)とは?
マルクス・トゥリウス・キケロは、古代ローマの哲学者にして、弁論家であり、偉大な政治家でもあります。
誠実であるのはもちろん、高潔な人物としても知られていました。
キケロが活躍した時代は、共和政ローマ末期の、いわゆる「内乱の一世紀」にあたります。
つまりカエサル(シーザー)、ポンペイウス、クラッススがいた「三頭政治」の時代ということです。
キケロは「共和制」を熱心に支持していたので、結果的にカエサルから追放される羽目になりました。
共和制また共和国・共和政は、国家元首などに君主を持たない政治体制である。共和制では、国家の所有や統治上の最高決定権を個人ではなく人民または人民の大部分が持つ。共和制の中に、特に民主主義を国の基本的な原則として重視する制度は民主共和制と言い、この制度を採用する国は民主共和国と言う。
カエサルが暗殺された後、政界で起きた内乱に巻き込まれ、最後にはアントニウス一派によってキケロも暗殺されましたが、キケロは「共和政ローマ」というグローバルな視野を持ち、世界国家の構想を打ち出した重要人物だと言われています。
キケロの名言集まとめ
人々から賞賛される最も近道の方法を教えよう。
「私は人々からこう思われたい」という理想像をまず思い描く。
そして、その理想像どおりに振る舞うことである。
とてもシンプルな考え方ですが、実践するのは難しいですよね。
しかしこれが理解できれば、きっと実践することもできるはずです。
賢い人とは、死が穏やかな世界への旅立ちだと信じられる人である。
だから、彼は死が近づいても慌てふためくことがない。
これはストア派らしい名言だと思います。
正確に言えば「キケロはストア派ではありません」が、限りなくストア派に近い考え方を持った人物です。
ストア派は「死を恐れることがない」ので、決して慌てふためくこともないのです。
ストア派は、前300年ごろキプロスのゼノンが創始し、ローマ時代まで続いたギリシア哲学の一派です。ゼノンが彩色柱廊(ストア・ポイキレ)で学を講じたので、この名前がつきました。ストア派では、「世界は普遍的ロゴス(世界理性)によって合目的的に支配されている」とする自然学説に基づいた実践知を説いているのが特徴です。
「大切な思い出はいつまでも忘れない」と思い込んでいる者は、自分の記憶力に自惚れている。
人の記憶力はそれほど優れてはいない。
キケロ曰く「記憶は繰り返し甦らせないと消失する」ので、大切な記憶であればあるほど”甦らせる努力”をするべきということです。
人は楽しみがなければ我慢ができない。
楽しみがなければ、前向きに働けませんよね。
これはマネジメントする立場のリーダーが知っておくべき名言だと思います。
孤独はあらゆる楽しみを奪ってしまう。
キケロは「食べ物は十分にあり、生活に必要なものがすべて揃っているが、周りに人影が全く見えない」という状況を想像して欲しいと語っています。
孤独というのは、人生における楽しみを奪ってしまう可能性があるのです。
年を取ると忘れぽくなるけれど、それは記憶力の衰えではない。
年をとっても、己が執着していることは忘れないものだ。
つまり、年を取って忘れぽくなるのは、記憶力が衰えたからではなく、執着心や好奇心が衰えたからに過ぎない。
キケロは「老人がカネの隠し場所を忘れたというのは聞いたことがない」と言っています。
その一方で、若い人でも物忘れすることはあります。
そのことから分かるのは、年齢が問題なのではなく”執着心(=情熱)”があるかないかだと思います。
友情には、二つの原則がある。
第一に、友に誠実であること。
第二に、友にも誠実さを求めること。
馴れ合いの関係ではなく、お互いに切磋琢磨できる関係性こそが”本当の友情”だとキケロは語っています。
友情を抱くと人は寛大になり、物惜しみをしなくなる。
本当の友情は、相手に見返りを求めることがありません。
真の友情とは「ただそれがあるだけで十分」と言えるものだと思います。
他人を非難すると、自分の心が汚れる。
SNSでの誹謗中傷が社会問題になっていますが、『他人を非難すること』に喜びを持ってはいけないとキケロは語っています。
他人を非難するということは、自分にとってのメリット(自己成長など)がなく、「他人を傷つけた(=他人から恨まれた)」というデメリットだけを被るハメになります。
友が過ちを犯したなら、忠告するべきだ。
本当の友達だからこそ言えることがあると思います。
友達にとっては”耳の痛い話”かもしれませんが、それを”喜び”だと感じてくれる人が、本当の友人なのだと思います。
礼儀作法に則った厳格な態度の交際は、品格が感じられて立派なものだ。
年齢を問わず、ビジネスパーソンの中には”タメ口”を使う人がいますが、そのような行為は絶対にやめましょう。
相手に不快感を与えるだけでなく、ビジネスチャンスを失う可能性も高いので、自分にとってデメリットしかありません。
個人的な経験値からも言えますが、タメ口を使うビジネスパーソンは、多くのケースで無用なクレーマーとなります。
なので、弊社(WEBX Inc.)ではタメ口を使う方との取引は、丁重にお断りしています。
明日への不安は、当人の臆病さによる。
これは真理を言い当てた名言だと思います。
自分に自信がなければ、前進することもできません。
カラ元気やブラフでも構わないので、絶対に自信を持つようにしましょう!
人とは、常に愛を求め、愛の喜びを求める生き物だ。
この考え方はとても前向きだと思います。
人との出会いをポジティブに考えられるので、ビジネスパーソンはこのような考え方になるべきでしょう。
幸福を共有することは簡単だ。
しかし、不幸を共有することは、実に厄介でやりきれない。
何かトラブルが起こると、「突然周りから人がいなくなる」という話を聞くことがあります。
そうなってしまう理由は、周りの人が不幸の連鎖を恐れるからです。
自分の身にも不幸が降りかからないように、リスクヘッジするイメージで少し距離を取ろうとするのです。
そんな時でも距離を取らない人は”本当の友人”であり、心から信頼出来るパートナーでしょう。
意欲と美徳のどちらかを失うなら、美徳が残った方が、人としてずっといい。
美徳とは「誠実さ」と言い換えることができます。
意欲と美徳は両方あった方が良いですが、人間として正しい生き方ができるのは”美徳”を持った人だと思います。
人間は快楽を求めて、物を欲する。
だが、それが「自分の快楽」ではなく「家族の快楽」の為ならば、良い欲望である。
これはとても共感する名言です。
人間の幸せを突き詰めると、それは『他人のために生きること』だと思います。
まさにそれを体現したような格言だと思います。
お前が「私は今幸福だ」と思うなら、それと同時に「私は今見誤っているかもしれない」と疑うことだ。
キケロは「幸福は盲目である」と語っています。
悲しい現実ですが、『全ての人類が自分を祝福してくれる』ことなどあり得ないのです。
私は肉体が滅んでも、魂は不滅だと信じている。
人間の肉体はいづれ朽ち果てますが、魂だけは”不滅”だと言えます。
例えば、坂本龍馬は現代でも大人気で、大河ドラマ(龍馬伝)にもなっていますよね。
すでに坂本龍馬は死んでいますが、これからも「坂本龍馬」という名前は言われ続けますし、成し遂げた偉業(諸説ありますが…)も語り継がれるはずです。
つまり現代でも、坂本龍馬の想いに共感する人がいたり、坂本龍馬について語ってくれる人がいれば、坂本龍馬が死ぬ(=忘れ去られる)ことはないのです。
人が本当に死ぬ時というのは、生きている人達から忘れ去られた時だと思います。
そのような状態にならなければ「魂は不滅」だと言えるでしょう。
老人の不機嫌は、心ない若者を排除するのではなく、受け流すことで是正される。
「老害」という言葉もありますが、なんとなく「老人は常に不機嫌」という印象がありますよね。
その理由をキケロは、「若者が老人をバカにしたり、軽んじたりするからだ」と語っています。
このような状況を改善するためには、「老人が若者の声を聞き流すべきだ」とも言っています。
なぜならば、老人の方が人生における経験値が多く、器(器量)も大きいからです。
世知辛い日々を重ねていけば、心がすさみ、夢もなくなる。
このような生き方は辛いので、必ず「夢を持つ」ことをキケロは推奨しています。
自分の熱中できる何かを持ち続ければ、人生は楽しくなるのです。
無駄に過ごした年月の記憶は、老後を慰める思い出には決してならない。
人生を後悔しても後戻りすることはできません。
特に人間は「やらなかったこと」ほど深い後悔が残ると言われています。
後で後悔しないような生き方をしましょう!
私は次のような人を尊敬する。
忠実である人。
純粋である人。
正義の道を歩む人。
欲張りでない人。
厚かましくしない人。
そして大切なことに挑む時は、きっと頑固な人。
このような人が『人間として成熟した人物』なのだと思います。
人間は、人間にとって、幸せをもたらしてくれる最高の宝であると同時に、害悪をもたらす最大の元凶でもあるのだ。
「世の中の悩みは、ほぼ全て人間関係が原因である」とアルフレッド・アドラーは語っています。
有名な心理学者「アドラー」の考えにも近いので、ぜひアルフレッド・アドラーの名言集もご覧ください。
愛に基づかない関係は不安定である。
中でも、暴力の恐怖による服従ほど破綻しやすい関係はない。
共産主義や社会主義の国は「恐怖による支配」をやりがちですよね。
そのようなマネジメントは不安定なので、絶対に避けましょう。
死後の名声など気にするな。
生きて善をなしている実感こそが、お前の世界の存在であり、お前の喜びである。
「今を全力で生きろ!」という強烈なメッセージを伝えている名言だと思います。
眠ることに喜びを見出すのはやめよ。
眠っている時の人は何もなし得ない。
何もなし得なければ、死んでいるのと同じである。
眠ることが大好きな私が「ドキッ」とした名言です。
確かに、眠ることは「何かを成し遂げるための体力を養う手段」に過ぎないと思います。
国同士でも人同士でも、争いが起これば、解決手段は二つある。
話し合いは、人間だけにできる手段である。
暴力は、野獣が行う手段である。
弁護士として活躍していたキケロらしい名言ですよね。
話し合いは人間だけの特権なので、「まずはその特権をとことん利用しなければもったいない」とキケロは語っています。
人間は、物事を知るには時間がかかると、重々承知するべきだ。
短いですが、とても奥深い名言だと思います。
昨今はインターネット環境が充実しているので、上辺だけの知識ならいくらでも吸収できます。
しかしそれは”智恵”にならないので、全く役に立たない知識となるのです。
社会にとって最も忌まわしい人間とは、誠実でない野心家である。
誠実でない野心家は、目的のためなら手段を問いません。
犯罪すら犯す可能性があるのです。
そのような人はいづれ退場するハメになるので、「誠実さ」だけは持ち続けましょう。
絶対の正義とは絶対に嘘であり、従って絶対の不正なのである。
とても哲学的な名言ですよね。
キケロは「絶対的な正義だと確信したら、即座にそれを捨てよ」と言っています。
キケロにとっての”正義”とは「より正しい(=マシ)」ということなので、本当の正義だと断言することができないのです。
なかなか奥深いですよね。
キケロは偉人の一人
ここまで「古代ローマ最強の弁護士」と呼ばれたキケロの名言集をご紹介してきました。
世界の歴史を代表する偉人なので、ビジネスパーソンであれば「キケロ」という名前ぐらいは知っておくべきだと思います。
他にも世界の偉人達が残した名言を知りたい場合には、下の記事をご覧ください。