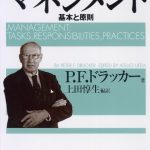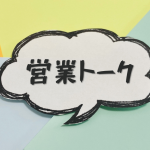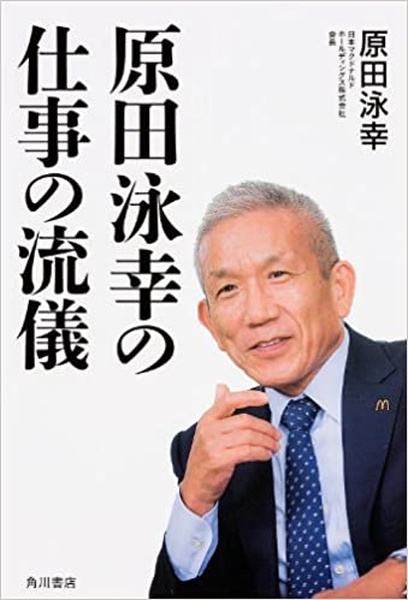
原田泳幸(はらだえいこう)は、良くも悪くも度々話題になる人ですよね。
様々な企業の社長やCEOを歴任した人物なので、ビジネスパーソンであれば名前ぐらいは聞いたことがあると思います。
そこで今回は、原田泳幸の名言集をご紹介したいと思います。
原田泳幸の経歴
原田泳幸(はらだえいこう)は、1948年に長崎県で生まれました。
東海大学工学部を卒業後、1972年に日本NCRへエンジニアとして入社します。
その後、横河ヒューレット・パッカード(現・日本HP)、シュルンベルジェグループなどを経て、1990年にアップルコンピュータージャパン(現・Apple Japan)へ入社します。
1997年にアップルジャパンの代表取締役社長へ就任し、スティーブ・ジョブズと共に経営改革を実施。
そして「iMac」を大ヒットさせた後、2004年に日本マクドナルドホールディングスのCEOとして入社します。
「マックからマックへ」という言葉が流行するほど、その時は注目されました。
マクドナルドでは、100円マックや24時間営業など業界に革新を与える施策を断行し、クォーターパウンダー、メニューの廃止など、数々の斬新な施策を打ち出しました。
その結果、7期連続でマイナスだった既存店売上高を、一転して8期連続のプラスにさせて、同社をV字回復させたのです。
その経営手腕は評判が高く、日本を代表する「プロ経営者」として認知されています。

原田泳幸の名言まとめ
「非常識なことを常識にしてやろう」、そういったチャレンジでした。
これはファーストフード業界で、まだ誰もやったことがない新しい施策を実行したときの話です。
- 地域別価格
- 100円マック
- 24時間営業
非常識には「イノベーションの種」が隠されています。
一見非常識だと思われることだからこそ、チャレンジする価値があるのです。
本来、知識やお金は手段です。
たくさんの知識やお金を持っていても、それを活用できなければ”宝の持ち腐れ”です。
それらはあくまでも手段(ツール)なのだと理解しましょう。
目の前の数字に一喜一憂せず、大きな流れで数字を見極めることが肝心。
原田泳幸はマクドナルドCEOに就任した後、まずは「構造改革」に着手したと言っています。
目の前の500億円という売り上げを捨ててでも、433店舗を閉鎖し、経営の合理化を図ったのです。
これができたのは、物事を俯瞰的に見ることができる『プロ経営者』として参加できたからでしょう。
過去と同じレベルのビジネスでは、競争は勝ち抜けません。
これは次々と矢継ぎ早に新しい施策を行った理由について語った名言です。
「マクドナルド」という巨大企業に転職した時、外部環境の変化に対応できていないマクドナルドに対して、強い危機感を感じたそうです。
最終目的はKPIの数値ではなく、売上です。
外資系企業がKPI(Key Performance Indicator)を重視しているので、それを真似して数多くの日系企業がKPIを設定しています。
しかし、KPIを重視しすぎると”思考停止”になるので注意しましょう。
「思いつき」と違って、「ひらめき」というのはずっと考えているからひらめくものです。
とてもわかりやすい名言ですよね。
何事も真剣に考えるからこそ、成長できるのだと思います。
現場のやる気をうんと引き出すには、こちらの情熱が大切なのです。
これは誰もが経験すると思いますが、部下を動かすのは難しいですよね。
リーダーシップを発揮するためには「情熱」が必要だと思います。
リーダーシップの意味が分からない人は、下の記事をご覧ください。
利口そうに見えて利口なやつ。
バカな振りして利口のやつ。
利口そうに見えてバカなやつ。
バカな振りしてバカなやつ。
ほとんどの人はこの4種類に分類されますが、1番良いのは「バカな振りして利口のやつ」です。
そして次に良いのは「バカな振りしてバカなやつ」です。
3番目が「利口そうに見えて利口なやつ」で、4番目が「利口そうに見えてバカなやつ」です。
自分が何番目なのか再認識してみましょう。
ビジネスとは、マーケットを作ること。
”経営学の父”と呼ばれたピーター・ドラッカーは、「顧客を創造すること」がビジネスの本質だと言いました。
その名言に通じる言葉だと思うので、ぜひピーター・ドラッカーの名言集も確認してみてください。
売上の結果とは、売れた数字か、売った数字か。
これはビジネスパーソンに伝えたい名言No.1ですね。
ほとんどのビジネスは、ただ競合他社と争っているだけです。
つまり、限られたパイを奪い合って、結果的に”売れた”というだけの「マーケット・シェア・ゲーム」になっているのです。
そうではなく「顧客を創造する」という視点に立てば、きっとビジネスは成功すると思います。
経営というのは、全ての相反する要素を満たそうとする矛盾を追いかけることです。
矛盾だらけの中で経営をしているわけです。
例えば、顧客満足度を上げるために社員を増やすというのは、コスト削減と矛盾しますよね。
客単価を上げようとして値上げすると、今度はお客様が減りますよね。
このように、様々な矛盾を全て追うのが企業経営の実態なので、上司の指示も「矛盾しているのが当たり前」と考えるようにしましょう。
顧客心理というのは難しいもので、商品が優れているからといって必ず売れるわけでもありません。
これは完全同意できる名言ですね。
美味しい料理を提供しているから”繁盛店”になるとは限りません。
美味しい料理を提供するのは”セールス”なので、見込み顧客を集める”マーケティング”とセットで考えなければいけません。
この思考回路が抜けている営業パーソンは、トップセールスになることができないはずです。
値上げの理由は、「おいしくなったから」が正解。
原材料が云々…、燃料費が云々…、人件費が云々…
そのような御託を並べても、お客様には伝わりません。
もし値上げした理由を聞かれた場合には、「さらにおいしくなったので、ぜひ一度試してみてください!」とシンプルに伝えるのが正解だと思います。
マーケティングは想像の世界だから、教科書はないと思わないと駄目です。
マーケティング理論を学ぶことはできますが、現実はもっと複雑なので、教科書通りに進むはずありません。
マーケティングに正解はありませんが、「顧客ニーズ(課題)は何なのか?」「どうすればお客様はワクワクするのか?」などを追求すれば、きっと答えは見つかるはずです。
過去の成功体験からは、新しいモノは生み出せない。
過去の成功体験にしがみついている状態は、ぬるま湯に浸かっている状態と一緒です。
改善しようと努力するからこそ、イノベーションは起こるのです。
日本は人を雇い、アメリカはスキルを雇う。
これからの時代の経営者は、このような考え方になるべきだと思います。
つまり「スペシャリスト」を雇うということです。
その流れを踏まえて、労働者側もスキルアップを目指しましょう!
日本の弱点は人材の流動性のなさです。
今では転職が当たり前になりましたが、依然として変わらないのが解雇事由のキツさです。
日本では労働者保護という観点が強いので、企業側の都合で従業員を解雇できないのです。
これは日本の弱点であり、弱みであると思います。
完成品より「未完成品」の方が面白い。
自分のことを「未熟だ」と思うのは勝手ですが、実はそれが魅力なのかもしれません。
とにかくスピードを優先しました。
戦略も組織もどれが正しくて、どれが間違いというのはありません。
どれを信じて選択するかという話でしょう。
これはビジネスパーソンが参考にするべき名言だと思います。
やり方に正解などなく、仮説を立てて行動し、結果を分析し、それを改善して、また実践するしかないのです。
これはPDCAサイクルの回し方につながる話ですが、詳しく知りたい人は下の記事をご覧ください。
会社の改革では、まずリーダーシップをもって、会社の空気を変える意思や情熱を示すことが重要です。
リーダーシップを発揮するのは難しいですよね。
リーダーシップについて知りたい人は下の記事をご覧ください。
ブランドというのは一人のカリスマが中心になって、徹底的にその価値の一貫性を追求しなければなりません。
これはスティーブ・ジョブズと一緒に仕事をしていた、原田泳幸ならではの名言だと思います。
「パソコンを必要とする人には売らない」という斬新な戦略をとったジョブズは、やはりカリスマ経営者だったのでしょう。
スティーブ・ジョブズの名言集は下の記事をご覧ください。
販売店にリベートを渡しても、お互いの横同士の価格競争、ポイント競争で消耗戦をやっている訳ですよ。
アップルジャパンの社長に就任した時、全ての販売代理店に対して「安い」とか「割引」というプロモーションを禁止するように通達したそうです。
「売れた or 売った」の名言でも解説しましたが、パイの奪い合いは意味のない競争なので、そのような戦い方をやめたそうです。
Apple Storeのエレベーターの音が出ないということも、アップルの世界共通の哲学ですね。
Apple Storeの階段をガラス貼りにするということも同じです。
全て彼(スティーブ・ジョブズ)のDNAなわけです。
Appleは「スティーブ・ジョブズ」というカリスマが作り上げたブランドであり、独自性のある世界観だと思います。
ジョブズの英語名言集は下の記事をご覧ください。
「世界で売れるもの」しか「日本で売れるもの」になりません。
日本は巨大なマーケットです。
首都東京の経済圏は、人口1000万人以上なので、世界上位に入りますよね。
なので「日本で売れるもの」は「世界で売れるもの」になり、その逆も然りなのです。
マクドナルドには、未だにレイ・クロックのDNAが残っている。
創業者のDNAがずっと残っている企業は強い。
レイ・クロックは、マクドナルド兄弟から「マクドナルドのフランチャイズ権」を買い取り、世界ナンバーワンのファーストフード店に育てあげた人物です。
レイ・クロックの自伝も発売されているので、もし良ければ一度読んでみてください。

伝わらない最大の障害は、階層的な組織。
会社組織が複雑になるほど、伝言ゲームの様相を呈してきます。
そうするとスピード感も鈍るので、できるだけフラットな組織を目指した方が良いと思います。
日本を代表する名経営者の名言を知りたい人は下の記事をご覧ください。
マクドナルドのビジネスモデルは凄い
ここまで原田泳幸の名言集をご紹介してきました。
原田泳幸は、いわゆる「雇われ経営者」なので、起業家とは少し”毛色”が違います。
プロ経営者として「どうすれば企業価値を最大化できるか?」という視点に立って、短期&長期的な視野で戦略策定しているのです。
それらを実行する上で、必要不可欠だと言われるのが「創業精神」を理解することです。
ビジネスパーソンであれば知っているはずですが、日本マクドナルドを創業したのは藤田田(ふじたでん)です。
藤田田の創業精神を理解して、マクドナルドのビジネスモデルを理解しなければ、日本マクドナルドの経営者は務まりません。
マクドナルドのビジネスモデルは秀逸なので、その辺りを知りたい人は下の記事をご覧ください。