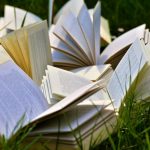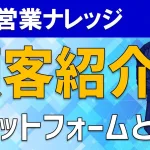荘子は中国戦国時代の宋の蒙に生まれた思想家で、道教始祖の一人とされています。
荘子の読み方は「そうし」や「そうじ」ですが、道教の始祖といえば老子も同じですよね。
老子の名言を知りたい人は、あとで下の記事もご覧ください。
荘子は、老子が考えた難しい道教思想を、楽しくわかりやすい内容に昇華させました。
そこで今回は、儒教家である荘子の名言集をご紹介したいと思います。
管理職やビジネスリーダー、教師など、人の上に立つ人は無為自然を理解して、平等性や多様性を追求しましょう!
荘子の名言集まとめ
もの、あれに非(あら)ざるはなく、もの、これに非ざるはなし
この名言は「見方によって物事は変化する」ことを言っています。
例えば、一昔前までは一つの企業で定年まで勤め上げる「終身雇用」が当たり前でしたが、今は転職するのが当たり前の時代です。
そしてローンを組んで自家用車を購入することがステータスでしたが、今の若い人は自家用車を購入することをせず、シェアリングカーで満足しています。
このように、時代の流れや環境の変化に応じて判断は変わるので、広く長い視野で物事を見るべきだと言っているのです。
天地は一指なり、万物は一馬なり
この言葉は万物において「優劣の差がない」ことを語っています。
例えば、誰の人差し指であっても同じ動きをしますよね。
馬の動き方も一緒で、4本の足を使って上手に走ります。
これは天地自然が作ってくれた創造物なので、優劣はなく、全て平等だと言うのです。
それはもちろん他人の指でも同じです。
「あれは俺の指じゃない」と言うのではなく、全く同じ機能を持った自然の創造物なので、全てに対して敬意を払うべきなのです。
道は通じて一たり
人間はそれぞれ”自分の人生”を歩いているように感じますが、俯瞰的な視点で見ると、地球は一つの生命体であり、その上で生きている人間は細胞のようなものです。
なので、地球という生命体が生きていくと仮定した場合、全ての人間の命は一つに繋がるのです。
よって、みんな平等であり、みんな尊いと言えるのです。
水を積むこと厚からざれば、則ち大舟(だいしゅう)を負うに力なし
水の深さが足りないと、大きな船を浮かべることはできませんよね。
この名言が言っている「水の深さ」とは、心の広さのことです。
心を広く、余裕を持たなければ、大事を成し遂げることはできないのです。
五百歳をもって春となし、五百歳をもって秋となす
荘子は冥霊(めいれい)という架空の木を例に挙げました。
この木の春は500年間あり、秋も500年間あるそうです。
そう考えた場合、春夏秋冬を一回りするのに2000年かかる計算になり、100年間生きたとしたら20万年もの時間になります。
人間の一生は70~80年ですが、もし自分がこの木になった場合、今抱えている悩みなど一瞬のうちに消え失せると語ったのです。
世を挙げて之を誉むるも、勧(つと)めるを加えず
この言葉は「褒められても決して自分の力を過大視して、いい気になりすぎてはいけない」という格言です。
要するに「調子に乗るな」ということですが、これは自然に生きる為に必要不可欠な考え方だと思います。
至人(しじん)は己なし
この言葉は「本当に充実した人間には、自己主張がない」という意味です。
荘子が理想とする人間は、大自然と心を一つにして生きる人のことです。
まさに達観した至人と言えるでしょう。
時雨(じう)降りたるに、而も、なお浸灌(しんかん)す
この言葉は「待ちに待った雨が降ってきたのに、そこへ更に水を撒くと水浸しになる」という意味です。
これはつまり人間の欲望について語った名言なのです。
人の欲望は果てしないので、「ほどほどで十分」という気持ちが大切だと思います。
大を用うるに拙(せつ)なり
一見すると大きくて使い物にならないモノだったとしても、有効な使い方があることを諭した名言です。
これは人材登用にも使える話なので覚えておきましょう。
朝三暮四(ちょうさんぼし)
これは猿にトチの実をあげる逸話からきた名言です。
ある猿回しがトチの実を、朝3つ、夕方4つあげるとサル達に伝えたところ大反発が起こったそうです。
しかし朝4つ、夕方3つと伝えたところ、猿たちは大喜びしたそうです。
どちらでもトチの実の数は7つで変わりないですよね。
つまり「どちらでも良いのではないか」という余裕があれば、そもそも争いは起きないことを諭したのです。
心は固(まこと)に死灰(しかい)のごとくならしむべし
一度消してしまった灰は、もう二度と燃えませんよね。
自分の心を死灰のようにすれば、腹が立つこともなくなるのです。
これはアンガーマネジメントに通じる話なので、怒りっぽい人は下の記事もご覧ください。
吾、我を喪(うしな)えり
吾と我はどちらも「われ」と読みますが、その意味は全く違います。
- 吾=生まれたままの自然な自分
- 我=生きる上で経験したことや知恵を持った自分
人間は損得勘定で物事を考えたり下心を持ちますが、我を捨てて、自然のままに生きる「吾」を推奨したのです。
未だ天籟(てんらい)を聞かず
天籟とは「自然の音」を意味しますが、風の音や川の音、虫の声や草木が揺れる音などを指します。
人間は様々なしがらみの中で生きていますが、自然にはそんなものありません。
そのような面倒がないから、迷いも生じません。
天籟に耳を傾ける余裕を持ちましょう。
井鼃(せいあ)はもって、海を語るべからず
この名言は「井の中の蛙、大海を知らず」の語源になった有名な言葉です。
ことわざが好きな人は下の記事もご覧ください。
蟷螂(とうろう)の斧
蟷螂とはカマキリのことです。
カマキリの手にある斧は昆虫界の脅威ですが、ライオンと対峙した場合には全く通用しません。
これと同じように、人間界で知恵や権威をふりまわしても、大自然の真理にはかなわないのです。
知らざる所に止まる
自分が知らないことは、正直に「それは知らない」と言える人の方が賢明です。
知ったかぶりはバカをみるので、ビジネスパーソンは注意しましょう。
夢に胡蝶(こちょう)となる
荘子は自分が蝶になって飛んでいる夢を見ました。
その時は本当に蝶の気分でしたが、夢から覚めると「自分は荘子である」と気付いたそうです。
この話を聞くと、多くの人は「蝶は夢で、荘子が現実だ」と言いますが、荘子はどちらも自分であると考えたのです。
蛇の鱗、蝉の翼
蛇は前進する時に鱗を動かします。
蝉は飛ぶ時に翼を使います。
「蛇と蝉はどうやって動いているのか?」
そのような答え探しを、荘子は「どうでもいいこと」と一刀両断したのです。
自然が創造した生き物は、自然の摂理に基づいて動いている…
ただそれだけが事実だと語ったのです。
技より進む
これは「技術よりも大切ことがある」という名言です。
技術の習得は大切ですが、その過程に一番大切なことが隠されているのです。
樊中(はんちゅう)に畜わるるを求めず
樊中とは「かごの中」という意味です。
鳥は自分で餌を探し、暑さや寒さに耐えながら生活しています。
しかし、決して樊中(かごの中)で過ごしたいとは思わないはずです。
なぜかと言えば、自由に生きるのが一番楽しいからです。
時に安んじて順に処(お)る
荘子は、生きることも死ぬことも自然の流れだと考えました。
一般的に死ぬことは「悲しいこと」と解釈されますが、そのような感情は本質でないと言っています。
天から授かった命を全うし、去っていくのは自然の摂理なので、人間が死んだ時には”心から合掌して祝う”ことが正解なのです。
憂(うれい)あれば、則ち救われず
心が乱れると、何も解決できません。
心の平静を保つ為には、周りに影響されない精神力が必要だと思います。
内直(うちなお)くして、外曲がる
これは「信念を持ちつつ、世間に合わせる」という意味の名言です。
「内剛外柔(ないごうがいじゅう)」とも言いますよね。
このような四文字熟語が好きな人は、ぜひ下の記事もご覧ください。
外の曲(きょく)なる者は、人と之徒(これと)たるなり
曲なる者とは、礼儀正しくお辞儀をする人のことを言います。
つまりこの言葉が伝えたいのは「礼儀正しくすれば人と仲良くできる」ということなのです。
※ちなみに曲の対義語は直です。
美の成るは、久しきに在り
良い結果が出るまでには、長い時間がかかります。
人は「できるだけ短時間で結果を出したい」と考えますが、実際には紆余曲折しながら成功まで至るのです。
近道は無いのだと心得ておきましょう。
可不可(かふか)をもって一貫となす
可不可(かふか)は「可と不可」という意味です。
つまり善と悪、良い悪いは同一(本質的には同じ)だと思える人になりなさいという意味なのです。
そもそも善悪という判断は人間が作り上げた概念です。
無為自然の中に善悪という判断はなく、常に中正であるということです。
和して唱えず
この言葉は、他人の意見を聞く時、和やかに同調して、自分の主張をあまりしないことを意味しています。
そのような人は全てにおいて寛容なので、争いも避けられるのです。
喜怒四時(きどしじ)に通ず
喜ぶべき時は喜んで、笑う時には大笑いをし、怒るべき時は怒るのが自然人です。
そのような人が「人間らしい」と言われるのです。
自ら其の適を適とす
これは天職について語った名言です。
自分に合った仕事を探すのは難しいですが、それを求めるのが人生(生きること)でもあるのです。
万化(ばんか)を楽しむ
人生は順風満帆とはいかず、様々なトラブルが起こりますよね。
でも、季節の変化を楽しむように、人生の変化も楽しみましょう!
木鶏(もっけい)に似たり
木鶏とは「木でできた鶏」のことです。
作り物なので、もちろん動きませんし、表情もありません。
それくらい平穏な態度の人は争いごとにも巻き込まれません。
そのような態度で過ごすことを推奨したのです。
白駒(はっく)の郤(げき)を過ぐるがごとし
「人生は、あたかも白い馬が走り去っていくような短い時間なので、すぐに過ぎ去ってしまう」という意味の言葉です。
あっという間の人生なので、どう生きるべきか真剣に考えましょう!
蝸牛角上(かぎゅうかくじょう)の争い
これは「カタツムリの角の上で争うこと」を意味した言葉です。
カタツムリの角の上はとてつもなく狭いので、そのような小さい範囲(身内や友人間)で争っている人を揶揄したのです。
人を愛するや己(や)むことなし
これは宗教家らしく「愛」について語った名言です。
聖人は人を愛しますが、それは自然の原理なので、当たり前のことだと言ったのです。
愛について語った宗教家といえばイエス・キリストですよね。
キリストの名言集を見たい人は下の記事をご覧ください。
荘子の思想観
ここまで読み進めた人は、荘子の思想が理解できたはずです。
- 右か左か
- 善か悪か
- 大か小か
このような争いを無駄だと感じ、中立の立場を貫いたのが無為自然という考え方です。
世の中に存在するものはすべて大宇宙が創造した賜物なので、それを否定することはせず、全てを自然に受け入れるのです。
ある意味では達観した考え方ですが、それも儒教家らしいですよね。
同じく有名な宗教家に、仏教を開いた釈迦という人物がいます。
釈迦の名言と比較してみるのも面白いので、ぜひ下の記事もご覧ください。