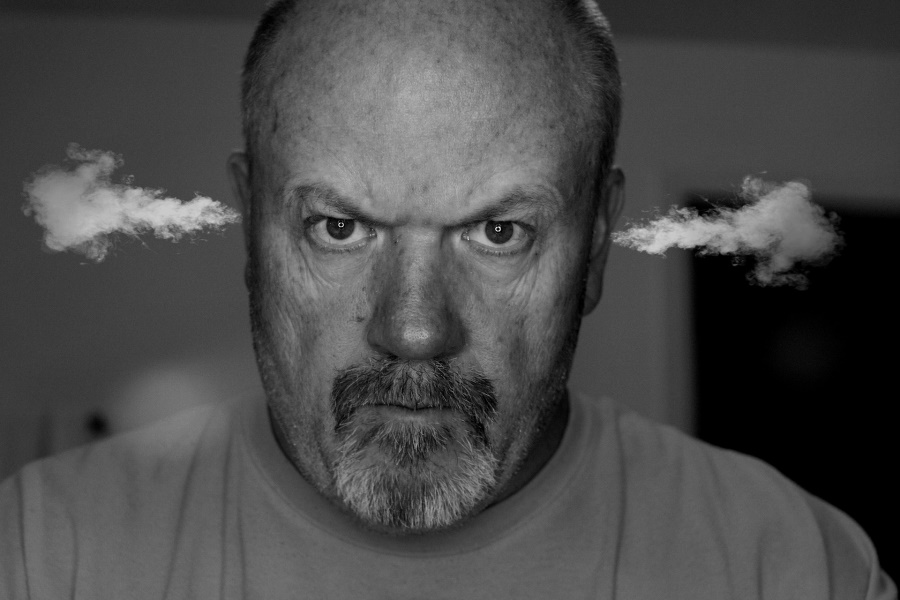
日本において、アンガーマネジメントはまだ馴染みありませんが、その認知度は徐々に向上してきています。
企業では管理職(マネージャーなど)がアンガーマネジメントのやり方を身に付けたり、一般家庭の主婦が子育てするためにアンガーマネジメントを学ぶケースもあるでしょう。
このような日常生活において、アンガーマネジメントはとても重要なノウハウになるはずです。
そこで今回は「アンガーマネジメントによって怒りをコントロールするやり方」について解説していきたいと思います。
目次
アンガーマネジメントとは?
アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで始まった「怒りの感情」をマネジメントするための方法です。
アンガーマネージメントと聞くと、なんとなく「怒りっぽい人が怒らなくなるのかな?」と感じますが、実際にはそうではありません。
アンガーマネジメントができている人であっても、もちろん怒ることはあるのです。
その「怒りの感情」をコントロールするトレーニングこそが「アンガーマネジメント」の本質です。
怒りは外部に発せられる感情ですが、決して有害なものばかりではなく、自分の身を守るために発せられる怒りもあります。
なので怒りの感情をゼロにすることは逆に危険で、「怒りの感情がある前提でコントロールする」ことを目指した方が良いのです。
パワハラの原因にもなっている
会社という狭いコミュニティの中では、たくさんの問題が発生しています。
特に近年注目度が高まっているのが「パワハラ問題」についてです。
個人主義が台頭し、多様性を重視する現代では、パワハラがとても大きな問題になってしまいます。
なので、社内研修でパワハラに関して教わる場合、必ずと言っていいほどアンガーマネージメントにも触れているはずです。
なぜかと言うと、怒りの感情はパワハラが発生する一因にもなり得るからです。
快適な職場環境を実現するためには、絶対にパワハラを起こしてはいけませんし、それを撲滅しなければいけません。
そのためにはアンガーマネジメントが効果的なのです。
怒りはコントロールできる?
アンガーマネジメントする前に、まずは「怒り」という感情について理解しなければいけません。
そもそもなぜ人間は怒るのでしょうか?
人間が怒るシチュエーションというのは、何かに不平不満があったり、自分の尊厳を傷つけられたり、自分が考える正義に反した時だと思います。
しかしそのようなタイミングがあったとしても、いきなり激怒する人は少ないと思います。
例えば会社のランチタイムにコンビニエンスストアでお弁当を買ったとします。
お店を出た後、コンビニエンスストアで買ったお弁当に割り箸が入っていなかったとしても、ちょっと戻ればいいだけなので、その出来事に対して激怒する人はあまりいないですよね。
しかし、朝起きて夫婦喧嘩をしていたり、会社へ移動する満員電車にストレスを感じたり、午前中にミスを犯して上司から?責されていたとします。
すると本人の気づかないところで怒りゲージが溜まっていき、それがコンビニエンスストアの「割り箸忘れ」に対して爆発することがあるのです。
これはコップの水をイメージすると分かりやすいと思います。
コップの水は一方的に溜まっていって、ある地点まで達するとこぼれてしまいますよね。
怒りの感情もこれと同じなのです。
なので、時々コップに穴を開けたり、斜めに傾けてこぼさないと、怒りの感情が溢れ出して大変なことになります。
このようなコップに溜まっている感情のことを「第一次感情」と呼んでいて、そこから溢れ出した怒りの感情を「第二次感情」と呼んでいます。
つまりアンガーマネジメントとは、コップに溜まっていく「第一次感情の量」をコントロールすることなのです。
怒りのタイプを診断しよう!
アンガーマネジメントをするためには、自分の怒りタイプを理解することも大切です。
問題になりやすい怒りのタイプには大きく分けて4種類あるので、自分がどのタイプに当てはまるかを確認しておきましょう。
- 頻度が高い怒り
- 強度が強い怒り
- 持続する怒り
- 攻撃性を伴う怒り
「頻度が高い怒り」とは、常にイライラしてることを言います。
このような人は、怒りの発生頻度が多すぎるため、つい周囲の人に当たってしまうのです。
そして「強度が強い怒り」とは、周りへの当たり方が強烈な怒りのことを言います。
強すぎる怒りは「暴力」というカタチで現れてしまうケースががあるので、注意しなければいけません。
そして「持続する怒り」とは、いつまでたっても怒りの原因が忘れられず、引きずってしまうような怒りのことを言います。
この怒りは数ヶ月間、もしくは数年間引きずるケースもあるので、とんでもない量の怒りが蓄積されてしまうのです。
そして最後の「攻撃性を伴う怒り」ですが、この感情は最も厄介な怒りだと思います。
怒りをコントロールすることができず、突発的な感情に身を委ねてしまったり、それが暴力という形で表に出てしまうのです。
しかも、その暴力は自分へも向けられることがあります。
その顕著な例が「自殺」なのです。
怒りタイプの対処方法
先程、問題がある怒りのタイプは下記4種類だと解説しました。
- 頻度が高い怒り
- 強度が強い怒り
- 持続する怒り
- 攻撃性を伴う怒り
それでは次に、この4種類の怒りに対処する方法について解説していきたいと思います。
まず「頻度が高い怒り」ですが、この人はいつもイライラしてるので、コップの水が常に満タン状態です。
なので、まずはコップの水が満タンになってしまう原因を突き止めましょう。
コップの水は「第一次感情」なので、不安やストレス、苦痛、悲しみ、妬み、嫉妬、自己否定、絶望感、悲観など、様々な感情が入り混じっています。
それらを一つずつ文字に書き出してみるのが効果的だと思います。
そうすれば俯瞰的にストレスの原因が見れるので、その中からコントロールできそうな原因だけをピックアップして対処していくのです。
例えば「自分の実家がお金持ちなことを他人に嫉妬されている」などは対処しようがないので、それはコントロールできない原因として割り切りましょう。
次は「強度が強い怒り」についての対処方法を解説します。
この人はコップの水が少ない状態だったとしても、割り箸が入っていないだけですぐにコップの水が溢れてしまうような人を言います。
瞬間湯沸かし器みたいな人ですが、これを治すためにはしっかりと反省する事が大切です。
もし怒りの感情が湧き上がってきた場合は、「果たしてこれは本当に怒ることなのか?」ということを自問自答してみましょう。
瞬間湯沸かし器のように、今だけ怒りの感情が出ている可能性もあるので、とにかく落ち着いて10秒何もせずに待ってみましょう。
それによってほとんどの怒りは解消されるはずです。
次に「持続する怒り」の解決方法についてです。
この怒りの原動力は「復讐心」なので、常に「いつかやり返してやる」という気持ちが心の中にあるのです。
いつも過去に戻っては腹を立てているので、それが第一次感情として積み上がってしまうのです。
しかし、多くのケースでそれは仕事に関することだと思います。
なので転職をしたり、職場を変えるのが一番簡単な対処方法だと思います。
もしそれが難しいのであれば、将来に向けて目標設定するのがおすすめです。
具体的な目標が定まれば、現在は「目標達成するためのステップ」になるので、それに対していちいち腹が立たなくなります。
短い期間で物事を見るのではなく、長い目で物事を見れば、生き方が変わるということです。
そして最後の「攻撃性を伴う怒り」は、最も対処が難しい怒りだと思います。
この怒りの持ち主は集中力がありすぎるので、楽しめる趣味を複数持ったり、自分の個性が発揮できるコミュニティを複数作るようにしましょう。
一つのことに集中しすぎてしまうと、その世界の中で生きることだけを考えてしまいます。
その結果、その世界で勝った負けたとか、優劣ばかりつけてしまうので、もう少し気持ちを分散させる余裕を持った方がいいでしょう。
とは言っても、解決方法は千差万別なので、色々なやり方を試してみてください。
アンガーマネジメント研修をしよう!
先ほども少し触れましたが、企業でパワハラなどが問題になっているため、アンガーマネジメントに関する研修ニーズも増えてきています。
そのような社内研修を提供してくれる会社はたくさんありますが、中小企業にはアウトソーシングする予算など無いかもしれません。
なので、経営者や人事担当者がアンガーマネジメントに対して学び、それを社内共有するという研修方法がとられると思います。
そんな時には、アンガーマネジメントについての知識を共有したり、怒りのメカニズムについて解説したりする座学も必要ですが、オリエンテーションやイベントを開催するのもおすすめです。
怒りをコントロールするテクニックを伝授!
社内研修する場合には、「スケールテクニック」というやり方があります
そもそも怒りの感情は人によって違いがあるので、「自分は今どれぐらい怒っているのか?」ということがあまり理解できていません。
なので、まずは自分自身を客観的に見ながら、「怒りレベル」を仕訳してみるです。
例えば社内研修する場合には、以下のような10個の質問を用意します。
- 道ですれ違ったときに肩がぶつかった
- 指示した通りに部下が仕事をしてくれない
- インターネットで注文した商品と別の商品が届いた etc.
これに対して、参加者ごとに怒りレベルを振り分けてもらいます。
レベル1:一瞬で消える怒り
レベル2:一瞬で消えるが後に引きずる怒り
レベル3:表情が穏やかな怒り
レベル4:ギリギリ我慢できる怒り
レベル5:イライラする怒り
レベル6:ムカッとする怒り
レベル7:表情が強張る怒り
レベル8:声に出る怒り
レベル9:手が出そうになる怒り
レベル10:自分では制御不能な怒り
レベル1~レベル7は心の怒りですが、レベル8以降は表に出ている強烈な怒りだと思います。
例えば「道ですれ違ったときに肩がぶつかった」時には、「レベル1」と答える人もいれば、「レベル8」と答える人もいるでしょう。
このような回答を社員から集めれば、その人のコップの容量が把握できます。
これを一週間に一度、何週間か繰り返していくと、それだけでも社員研修になるのです。
この研修を継続すれば、恐らくほとんどのケースで先週よりも社員の怒りレベルが低下するはずです。
つまり、先週は「道ですれ違ったときに肩がぶつかった」時の怒りを「レベル8」と答えた人でも、今週は「レベル6」、その次の週は「レベル3」という具合になるのです。
これは社員にアンガーマネジメントが浸透してきている証拠です。
それを実現するためのポイントとは、社員がレベル分けをした後に「本当にそのレベル分けが正しかったか再確認してください」と伝えることです。
実はほとんどの怒りの感情は「無駄な怒り」であることが多く、その時に必要のない怒りだったりするのです。
これを判断するポイントというのは「その問題はリカバリーできるか否か?」と「その問題は自分でコントロールできるのか?」ということに集約されていきます。
例えば、コンビニで割り箸を入れ忘れた場合、自分が店頭に戻れば割り箸は貰えますよね。
とすると、それはリカバリーできることなので、本来は怒るべき事象ではないと言えます。
たとえ怒ったとしても、怒りのレベルは低くて済むはずです。
このように怒りをコントロールするためのヒントを与えつつ、毎週訓練していくと、自然とアンガーマネジメントが社員に浸透していくのです。
これには時間が掛かるかもしれませんが、良い職場環境を実現するためには絶対にやるべきトレーニングだと思います。
まとめ
アンガーマネジメントは一見すると難しそうに思えますが、実はそんなに難しい話ではありません。
怒りという感情の仕組みを理解し、それをコントロールするテクニックを身につけるだけなのです。
誰でも実践できるのがアンガーマネージメントの良いところです。
市販されている書籍を購入して学ぶのも良いでしょう。
特に管理職はアンガーマネジメントを身につけて、最大パフォーマンスが追及できるような組織作りを目指しましょう。






























