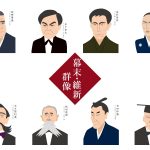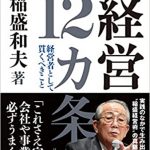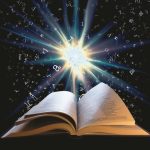出光佐三(いでみつさぞう)と言えば、東京証券取引所のプライム市場に上場する大企業『出光興産株式会社』の創業者ですよね。
「IDEMITSU」の看板が立ったアポロステーション(ガソリンスタンド)は、街中でも良く見かけると思います。
小説家 百田尚樹が書いた「海賊と呼ばれた男」では、荒々しい経営をする破天荒な人物として描かれていましたが、一体どのような人物なのでしょうか?

そこで今回は、伝説の経営者『出光佐三』の名言集をご紹介したいと思います。
出光佐三の名言集を見れば、その人物像が理解できるはずなので、ぜひ最後までご覧ください。
出光佐三の経歴
1885年 福岡県赤間村(現・宗像市)に生まれる
1905年 神戸高等商業学校に入学
1909年 酒井商店に入店
1911年 25歳の時に出光商会を創立し、石油類の販売を開始。
1914年 満州の販路を開拓
1920年 朝鮮の販路を開拓
1922年 台湾の販路を開拓
1935年 華中に販路を拡大
1936年 華北&華南に販路を拡大
1937年 貴族院議員に選任される
1938年 日章丸就航(一隻目)
1939年 中華出光興産設立、満州出光興産設立
1940年 出光興産株式会社設立
1945年 終戦により海外全店閉鎖
1947年 出光商会は営業停止し、出光興産に業務を引き継ぐ
1951年 日章丸就航(二隻目)
1959年 ソ連原油を初めて輸入
1966年 社長を退任し会長に就任
1972年 会長を退任し店主に就任
1981年 出光佐三逝去(95歳)
出光佐三の名言集まとめ
出光は創業以来『人間尊重』を社是として、お互いが切磋琢磨してきた道場であります。
出光の社是は『人間尊重』です。
出光佐三は「人を愛して、人を尊重せよ、そして働け」と語っていました。
まさにそれを言い表したような社是だと思います。
人を育てる根本は愛である。
出光佐三は「愛とはいかなる場合にも、自分を無私にして、相手の立場を考えること」だと語っています。
このような愛情あふれる会社で育った社員は、会社の資本(=財産)になると言ったのです。
家族肉親の愛は最高のものです。
学問や理論や哲学で説明できません。
あらゆるものを超越した人間の基本的あり方です。
そういう愛情を基礎にしたものが家族温情主義です。
出光佐三は、愛情という絆で結ばれた社員が、最大の力を発揮して、会社へ貢献してくれると信じていました。
経営者の都合で整理解雇する現代的な経営について、それは「利己主義」であると釘を刺したのです。
一人や二人出来の悪い人がいたとしても、その人が独り立ちするまでサポートするのが家族温情主義だと語たったのです。
人間尊重主義は、まず尊重すべき人間を養成せねばならぬ。
出光佐三にとって、最も重要な経営資源は「ヒト」でした。
人間こそが全てのビジネスの基礎になると考えていたのです。
働け、そして質素にせよ。
贅沢をするな。
働いて、自分に薄く、その余力をもって人のために尽くせ。
これは出光佐三の父親が、出光佐三に伝えた名言です。
父からの教えを体現したのが出光商会だそうです。
金は儲けなかったが、事業は理想的に伸びた。
これは出光商会のビジネスが飛躍したタイミング(転換期)を回想した時の名言です。
機械油を売っていた出光佐三は、全く売れずに店じまいしようと考えていました。
※実際、出資者にそのような相談をするような状況でした。
そんな折、自動車に乗る機会があったので、出光佐三は自動車や漁船、運搬専用の燃料油に注目したのです。
今後の成長産業であれば、そこで使われる燃料は必ず売れると思ったのです。
そのタイミングで運よく戦争が起こり、燃料油の不足と同時に、漁船の休業が相次ぎました。
そこで出光佐三は薄利でも燃料油を提供し、漁船が休むことなく操業できるように支援したのです。
これこそが、出光佐三の考える「商人としての使命」なのです。
※最後まで読むと↑の意味がわかります。
この結果、漁船関係者から大きな信用を得て、顧客数を激増させたのです。
我々は主義に妥協なしとの建前より、主義主張を曲げざるため、多くの敵を作った。
出光佐三は『信念の人』なので、自分が正しいと考えたことを貫きました。
例えば、漁船が休むことなく操業できるように、薄利で燃料油を提供したこともそうです。
これまで燃料油を売って儲かっていた競合他社からすれば、出光佐三の行為は迷惑極まりなかったのです。
私は真剣勝負だ。
しくじりをやれば命を取られ、店は潰れる。
それだからいつも真剣を抜いてやっておる私と、仕事の立場上真剣の抜けない支店長、支配人あたりが会得するものとの間に、どうしても越すことのできない壁がある。
これはとても心に響く名言ですよね。
竹刀で斬り合うのと、真剣で斬り合うのでは、緊張感が全く違うはずです。
もちろんそこから得られるものも違ってくるでしょう。
仕事も人間が本位である。
資本よりも人間である、組織よりも人間である、規則や法律というものも人間によって生きる。
これは出光佐三の経営理念とも言える名言です。
ビジネスを成功させるためには、資本金よりも優れた組織よりも、その中にいる人間が一番大切なのです。
金持ちの金は借りるな。
人間がしっかりしておれば、金は自然に集まる。
これは借金を批判しているのではなく、そのやり方について語った名言です。
金を借りる側はどうしても弱い立場になるので、足元を見られてしまいます。
しかし、地に足ついたビジネスをしていれば、その噂が色々の所まで届き、自然と金が集まるようになるのです。
学問にとらわれ、理論の奴隷となってはならぬ。
これは頭でっかちになることを揶揄した名言です。
知識が豊富にあるだけでなく、「ちゃんと実行できる人間になれ!」と語ったのです。
仕事の上においても、私のみが独立しておるのではありません。
店員各自がその持ち場、持ち場において独立しておるのであります。
出光佐三は独立自営業ですが、それは自分だけではないと言っています。
社員もそれぞれの立場において責任を持ち、業務遂行するために独立しているそうです。
そのような独立した社員達が一致団結し、総合力を発揮しているのが出光商会だと語っています。
人間しばらく眠る時間も必要である。
チャンスが来るまで、しばらく休憩するのも良いと出光佐三は語っています。
ただし眠る時には「活眼を開いて眠れ!」と言っています。
僕の一生は、知ることを忘れてただ実行してきたということが言えるのじゃないかと思う。
知識や学んだことに捉われてしまうと、周りの意見を聞き入れづらくなります。
それが争いの原因になっていると、出光佐三は語ったのです。
なので、自分は知識というよりも『実行力』を重視していきたいと言いました。
黄金の奴隷になるな。
これは出光商会創業の時に社員へ語った、出光佐三の名言です。
出光佐三の言葉の中でも一番有名かもしれませんが、黄金とは「お金」を意味しています。
つまりビジネスをする上で、お金を第一優先にする「拝金主義」になってはいけないと語ったのです。
しかし、企業経営は売上や利益を追う宿命にあるので、その辺りは矛盾しますよね。
その点について出光佐三は「金の奴隷になることと、金を尊重するということは全く違う」と語っています。
「金を尊重する」というのは、経費を節約して、無駄を省いて、自分を律しながら、合理的に経営することを指します。
金に振り回されてはいけませんが、資本主義においては「金を無視することもできない」と言ったのです。
人間の根本は、平和に仲良く暮らすということだろう。
出光佐三は「大家族主義」を掲げて経営していました。
その考えを広く持てば『世界平和』という考えに行き着くのだと思います。
平和を求めた人物といえばマザー・テレサですよね。
マザー・テレサに言わせれば「世界の貧困国に寄付する日本人は偽善者」だそうです。
その真意が知りたい人はマザー・テレサの名言集をご覧ください。
対立競争は相手を滅ぼす破壊であり、自由競争のみがお互いに助け合って繁栄する進歩の母なんだ。
自由競争とは「資本主義社会」のことを指しています。
資本主義は、お互いに切磋琢磨する仕組みなので、それによって社会は繁栄し、人類は進歩できると考えたのです。
人間は神様ではないよ。
人間は表面上で立派なことを言っても、気分屋なので、裏では嘘をついているかもしれません。
褒められればいい気になって、悪口を言われれば悲観もします。
しかし「このような不安定さが実に人間らしい」と出光佐三は語っています。
つまり「人間らしい矛盾性を持っている」ということです。
そのことを「人間は放っておけば獣だよ」とも表現しています。
人間が物に恵まれることは「必ずしも良いことではない」ということではないか。
物欲に満たされた人間は怠惰になります。
頑張らなくなります。
そのような側面があるので、「あまり恵まれない環境の方が良い」と言ったのです。
金や物を超越するところから、日本人の清廉潔白とか、責任感が強いとかいう独特のあり方が生まれてくる。
その代表的なものが武士道であり、ぼくらの知っている明治時代の官公吏や教育者のあり方だった。
武士道精神は日本人にとっての宗教と同義であり、精神的な支柱になっています。
武士道精神について知りたい人は下の記事をご覧ください。
明治維新前と維新後を区別して考える必要がある。
元々の日本社会は「人の国」でしたが、明治維新後は外国から物質文明を輸入したため「物の国」になったと出光佐三は語っています。
そもそも文化が変わってしまったので、ビジネスをする時には注意しなければいけないと言ったのです。
確かに明治維新は日本の歴史の中でも大きな転換点だと言えます。
維新志士たちの名言集は下の記事をご覧ください。
出光では従業員全部が経営者であると言える。
出光では、自分が担当している仕事の上では、お互いに自主独立の経営者になっているそうです。
これは稲盛和夫の提唱する『アメーバ経営』に似ていますよね。
アメーバ経営について知りたい人は下の記事をご覧ください。
組織は形式的なものであって、心の中に組織を持っておれば、非常に少数な人で少数精鋭主義の力強い形ができるんだが、その呼吸が、今の経営学でやっておる人にはわからないようだね。
出光佐三が目指す理想的な経営は「組織を無とする」ことです。
もちろん実際には会社や部署はあるのですが、それが無くても成立する組織にするということです。
日本人には『和の心』があるため、それが実現できると語っています。
日本人は単一民族なので、多民族国家のように対立することがありません。
なので、お互いに話し合って、心の中でまとまることができると語ったのです。
同じところに達する、最小の労力を持って最大の効果を収める道と、難関を通っても行ける道とがあるならば、僕は自ら選んで難関を通ってきた。
なぜ難関を通るのかといえば、それは『人間として成長できる』からです。
イージー・ゴーイングでお金は儲かるかもしれませんが、人間は養成されないので、人生における本質的な財産が溜まっていかないのです。
愛を持って人を育てて、勤めて自らが率先して難関に向かう、ということが基本だ。
これは「社員全員が経営者として働く組織」を作り上げる基本について語った名言です。
組織のリーダーがこの名言のような行動をとれば、所属するメンバーも主体性を持つと言ったのです。
出光に定年制がないということは、実はやめさせないということなんだ。
出光は『大家族主義』を掲げているので、社員をリストラしたり、定年制を設けることはないそうです。
これは出光佐三が「家族を追い出すことはしない」という精神だったので、会社が定年制を設けるのではなく、辞めるタイミングは自分で決めてもらうというやり方にした為です。
もしフルタイムで働けないのであれば、「働ける時間でこなせる仕事をやってもらえば良い」と出光佐三は語っています。
愛情によって育った人間は非常に純情であるから、お互いが人を疑わず信頼の念が強い。
「愛情」というのは出光佐三の経営スタイルを理解する上で非常に重要なキーワードとなっています。
このような社員達が出光の成長を支えているそうです。
給料というものは生活の保障であるということであって、労働の対価とはみていない。
出光佐三にとっては「社員の生活を保障するために支払うのが給料」という考え方なので、それで贅沢な暮らしをしてはいけないと語っています。
なので、景気のいい時にどんどん給料を上げたり、ボーナスをたくさん支払うこともないそうです。
その一方で、景気の悪い時に給料を下げたりもしません。
出光佐三が考える本当の報酬とは『適材適所によって自由に働くことができ、人生が楽しいと思える仕事を提供する』ことなのです。
変化はいつの時代でも、どういう社会でもある。
これは環境の変化について語った名言です。
環境の変化について、出光佐三は下のような例えを出しました。
春夏秋冬の気温の変化に対して、暑い時はランニングシャツだけで過ごし、肌寒くなれば長袖を着る。
冬になれば毛糸のセーターを着て防寒する。
このように臨機応変に対応すれば良いものを、理屈一辺倒の人は「夏はランニングシャツ」「冬は毛糸のセーター」と決めつけて、それ以外の選択肢を探そうとしない。
出光佐三が言いたいのは、経営環境は常に変化するので、理論ばかり振りかざすのではなく、その時々に人間らしく判断するべきということです。
数や理論の奴隷になるな。
多様性が重視される世の中なので、色んな人の意見に耳を傾けることは必要です。
しかし、そればかりに流されて正しい判断ができなかったり、自分の意見が無くなってしまうのはダメだと言ったのです。
社会は人間が構成しているから人間が中心である。
これは出光佐三の人生哲学であり、経営哲学でもあります。
出光佐三は、この言葉を一生涯のポリシーにしていたそうです。
「愛情」をテーマにしている出光佐三らしい名言ですよね。
資本は人なり、資本は金なり。
この2つは似た言葉なので「企業経営に必要な資源のこと」と捉える人は多いはずです。
しかしその真意は「両方とも(別々に)企業経営に必要な資本」という意味なのです。
出光佐三は「ヒト」を大切にする経営者なので、ヒトとカネは全く別軸で考えて、両者をはっきり区別していたそうです。
単なる「ヒト・モノ・カネ」という話ではないのです。
金儲けに走らずに商人の使命を果たし、それの「報酬」という考え方が、日本人の利益の考え方なんだよ。
企業を存続させるためには利益が必要ですが、利益は企業生存のための前提であって、決して目的とは言えません。
出光佐三の言う『企業の目的』とは、商人としての使命を果たすことだそうです。
それはつまり『顧客への貢献であり、ひいては社会へ貢献すること』になります。
「海賊と呼ばれた男」の経営哲学
ここまで出光興産創業者『出光佐三』の名言集をご紹介してきました。
出光佐三は「海賊と呼ばれた男」を見る限り、かなり強引な人物だと思っていましたが、実際には愛情溢れる経営者みたいですね。
「海賊と呼ばれた男」は出光佐三の半生を描いたベストセラー小説ですが、とても面白いので、まだ読んでない人はぜひ読んでみてください。

出光佐三は「ヒト」を愛する経営者なので、人材育成に力を入れていました。
人間を自由に働かせて、失敗しても怒らず、時間をかけて育てていくと、立派な強い個人が出来上がるそうです。
そのような個人が集まった組織が、少数精鋭の『出光』という企業だと語っています。
ところが今の経営者は「経営学に頼った経営をやっている」と出光佐三は憂いていました。
そのような様子を「経営学の実験室」と揶揄したのです。
「企業の本質は人である」という出光佐三の言葉は、いつの時代でも通用する経営哲学だと思います。
このような経営哲学が知りたい人は、有名CEOの名言集もご覧ください。