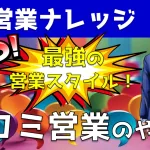いまだかつて一度も敵を作ったことのないような人間は決して友人をもたない。
<アルフレッド・テニスン>
アルフレッド・テニスンはイギリスで活躍した詩人です。
敵を作らないということは、自分の本性をさらけ出せないということなので、必然的に友人もできないのです。
人間をよく理解する方法は、たった一つしかない。
彼らを判断するのに決して急がないことだ。
<サント・ブーヴ>
ブーヴは19世紀に活躍したフランスの文芸評論家です。
近代批評の父とも呼ばれていますが、ブーヴ曰く「人間関係を構築するには時間がかかる」ということです。
人間関係とはそれほど奥深いものなのです。
最も親しき友人というものは、常に兄弟のように退屈である。
<萩原朔太郎>
萩原 朔太郎は、日本の詩人です。
大正時代に近代詩の新しい境地を開拓したので「日本近代詩の父」と称されていますが、残した名言は座右の銘のような重みがある言葉ばかりです。
「退屈な友人」というのは、心穏やかにいられる友人ということなので、お互い気を許せる存在ということです。
強く激しい言葉は、その人の主張の根拠の弱さを示す。
<ヴィクトル・ユーゴー>
ユーゴーは、フランス・ロマン主義の小説家です。
ユーゴーが残した小説「レ・ミゼラブル」はとても有名ですよね。

喧嘩をした時、感情のまま発言するのは決して良くありません。
もっと心穏やかに話し合うことができるはずです。
若い人たちはよく「生き甲斐がない」と言います。
しかしそれは当たり前です。
孤立した人に生き甲斐はないのです。
生き甲斐とは人間関係なのです。
<石川達三>
日本の小説家である石川達三が残した名言です。
とても明快な内容なので、理解しやすい言葉だと思います。
孤独な人は幸せになれず、他人と関わることで幸せになれるのです。
世の人は我を何とも言わば言え。
我が成す事は我のみぞ知る。
<坂本龍馬>
「我が道を行く」を体現した、坂本龍馬が残した言葉です。
批判したい人には言わせておけば良いのです。
結局、自分の目指すべき道は自分にしか理解できないからです。
どんな忠告を与えるにしろ、長々と喋るな。
<ホラチウス>
ホラティウスは、古代ローマ時代の南イタリアの詩人です。
長々と忠告してしまうと、どうしても相手のイライラが積もり積もっていきます。
基本的に人を叱ったりする場合はできるだけ短い時間にして、人を褒め称える場合には長くしましょう。
これは「人の上に立つ人」に覚えておいて欲しい名言です。
怒りを敵と思へ。
<徳川家康>
皆さんご存知の徳川家康が残した名言です。
怒りをコントロールすることが、人間関係をうまく回すためのコツなのかもしれません。
それは「アンガーマネジメント」と呼ばれているので、気になる人は下の記事をご覧ください。
他人を咎めんとする心を咎めよ。
<清沢満之>
明治期に活躍した真宗大谷派の僧侶が残した名言です。
人のことを悪く思ったり、人の悪口を言うことはやめましょう。
それをしたところで何の意味もありません。
そうではなく他人を認めることが大切なのです。
ある人に合う靴も、別の人には窮屈である。
あらゆるケースに適用できる人生の秘訣などない。
<カール・ユング>
ユングは、ジークムント・フロイトと双璧を成す、スイス精神医学の巨匠であり、有名な心理学者です。
人生の格言をわかりやすい言葉に変換してくれてたので、これなら誰でも理解できますよね。
何事もうまくいかなくて当然なのです。
そう思うと少し気が楽になるはずです。
人付き合いがうまいというのは、人を許せるということだ。
<ロバート・フロスト>
ロバート・リー・フロストはアメリカ合衆国の詩人です。
「人付き合いのコツとは?」「どうすれば人間関係は良くなる?」と考えるかもしれませんが、その答えは意外とシンプルなのかもしれません。
人が私のことを知らないということなどは気にかけず、私自身が人のことを知らないということを気にかけよ。
<孔子>
孔子の名言は、論語にたくさん残っていますよね。
人間は社会の中で生きているので、どうしても人目を気にするはずです。
しかし本来は無視して良いことなのです。
重要なことは、人の目を気にしながら生きることではなく、周りの人の個性を認める事なのです。
孔子の名言集を知りたい人は、下の記事もご覧ください。
真の友人は正面から君を刺す。
<オスカー・ワイルド>
オスカー・ワイルドは、アイルランド出身の詩人、劇作家です。
「正面から君を刺す」というのは隠喩で、「正面から意見を言う」とか「真っ正面を向いて反応する」という意味が含まれています。
これができるのは信頼関係があってこそなので、まさに「真の友人」と言えるでしょう。
あなたの周りにいる人、あなたの周りにある物。
すべてがあなたの先生です。
<ケン・ケイエス・ジュニア>
アメリカの自己啓発講演家であるケン・ケイエス・ジュニアの名言です。
これだけ謙虚な姿勢になれれば、きっと周りの人から好かれる人間になれるでしょう。
人と話をする時は、その人自身のことを話題にせよ。
そうすれば、相手は何時間でもこちらの話を聞いてくれる。
<ベンジャミン・ディズレーリ>
イギリス首相経験者のベンジャミン・ディズレーリは、コミュニケーションに長けていたのだと思います。
これはコミュニケーションの基本ですが、自分の話をするよりも、人の話を聞いた方が良いと言われています。
上手な人付き合いがしたい人は「聞く力」を身につけましょう。
自分がわからないものを一生懸命に説いても、わかるはずがない。
<今東光>
今東光(こんとうこう)は、横浜生まれの小説家です。
人に何かを伝える場合、自ら経験したり理解しているモノの方が、具体的に伝えることができます。
なぜかと言うと、生身の感想を伝えることができるからです。
その方が深い話になるので、会話も弾むことでしょう。
逆にインターネットで見ただけの情報は、表面上の話になるので、イマイチ盛り上がりません。
人間としての深みを追求していきましょう。
1年前の悩み事言える人いますか?
いたら手を上げてみて。
いないでしょ?
<斎藤一人>
「銀座まるかん」創業者である斎藤一人の名言です。
斎藤一人は長者番付にもランクインしていたほど、名実ともに「成功者」と言えるような実業家です。
とてもシンプルな言葉ですが、ハッとさせられる言葉ですよね。
日常の悩みなど小さなモノなのです。
人間、馬鹿は構いません。
だが、義理を知らないのはいけません。
<久保田万太郎>
久保田 万太郎は、日本の小説家、劇作家として活躍した人物です。
「義理」というのは日本人特有の感覚かもしれませんが、全ての日本人が大切にしている感情でもあります。
「武士道精神」と言い換えることもできますが、もし理解できていない人は新渡戸稲造の「武士道」をご覧ください。

自分が最低だと思っていればいいよ。
一番劣ると思っていればいいの。
そしたらね、みんなの言ってることがちゃんと頭に入ってくる。
<赤塚不二夫>
赤塚不二夫は「天才バカボン」などを残した、日本の漫画家です。
最後に「それでいいのだ!」と締めくくられそうな名言ですよね。
まとめ
ここまで人付き合いに関する偉人の名言をご紹介してきました。
人間関係を構築することは決して簡単なことではありませんが、時間を要すればきっと素敵な友人に出会えることでしょう。
ここでご紹介した名言にもありましたが、たくさん友人を作る必要はありません。
人生における「本当の友達」というのは2人~3人くらいだと言われています。
むしろそれ以上多い場合には、表面上の付き合いだったり、気心知れない部分があるはずです。
全ての人と分かち合ったり、理解し合うのは無理な話なので、それを前提にした人付き合いをしてみてください。