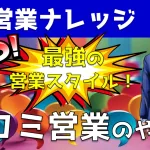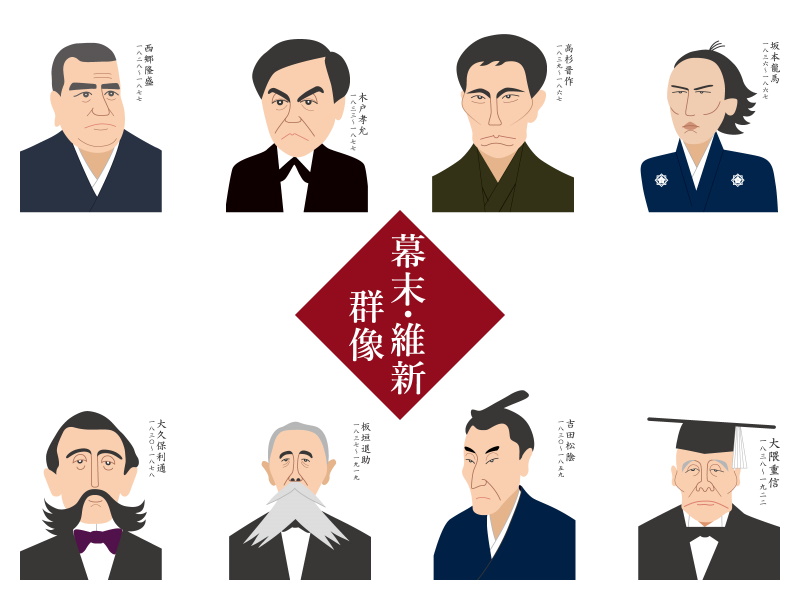
幕末は志の高い維新志士が活躍していた時代なので、とても人気がありますよね。
坂本龍馬や勝海舟、西郷隆盛など魅力的なキャラクターが多く、現代でも多くのファンを惹きつけてやみません。
そこで今回は、幕末(明治維新)の偉人たちが残した名言集をご紹介したいと思います。
目次
坂本龍馬の名言
坂本龍馬(1835~1867)は土佐藩出身の偉人です。
1862年には土佐藩を脱藩して、勝海舟門下に入りました。
翌年に海軍操練所の塾頭になり、薩長同盟の為に尽力します。
その後、日本で初めての株式会社となる亀山社中(海援隊)を設立し、大政奉還へ向けて、働きかけている最中に京都の近江屋で暗殺されました。
世の人はわれになにともゆはゞいへ
わがなすことはわれのみぞしる
この言葉は「世間の人には言わせておけばいい。自分のすることは自分にしかわからない。」という意味です。
これは坂本龍馬が残した歌として有名なので覚えておきましょう。
又あふと思ふ心をしるべにて、道なき世にも出づる旅かな
この言葉は「また会えると信じて、先の見えない世ではあるが旅に出よう」という意味です。
幕末という混乱期に生きた人の言葉だと思います。
天下に事をなすものは、ねぶとくもよくよくはれずては、はりへはうみをつけもふさず候
この言葉は「天下に事を成す者は、腫れ物が腫れ切っていないうちは針を刺さない」という意味です。
これはつまり「状況をよく見て、機が熟した時に行動すべき」ということを伝えているのです。
勝海舟の名言
勝海舟(1823年~1899年)は江戸に生まれました。
私塾を開きオランダ語を教えながら、鉄砲製造の仲介を行います。
そして海軍操練所設立し、坂本龍馬と出会うのです。
戊辰戦争では江戸無血開城を実現し、歴史上の偉業を成し遂げました。
人はよく方針々々といふが、方針を定めてどうするのだ
この言葉は「天下の事は予測しづらいので、状況に応じて判断するしかない」という意味です。
その場その場で適切な判断をしていくことが、幕末という動乱期の生き方なのだと語ったのです。
ナニ、誰を味方にしようなどといふから、間違ふのだ。
みンな敵がいい。
敵が無いと、事が出来ぬ。
この言葉を省略すると「努力するためには敵が必要」という意味ですが、自分にとっての敵(ライバル)は、自分が努力する上で必要不可欠な存在だと語ったのです。
死を恐れる人間は、勿論談すに足らないけれども、死を急ぐ人も、また決して誉められないヨ
「武士道とは死ぬことと見つけたり」という言葉があるように、武士は死に急ぐ傾向がありました。
しかしそれを勝海舟は否定したのです。
この辺りを理解するには「武士道」を学ばなければいけません。
武士道精神を知りたい人は、下の記事をご覧ください。
西郷隆盛の名言
西郷隆盛(1827年~1877年)は薩摩藩下級藩士の長男として生まれました。
その後、薩摩藩主である島津斉彬の側近に抜擢され、薩長同盟の締結に貢献します。
そして王政復古、戊辰戦争を指揮し、江戸城無血開城を実現したのです。
しかし、幼馴染である大久保利通と政治の方向性で対立し、西南戦争で自害することとなりました。
総じて人は己に克つを以て成り、自ら愛するを以て敗るるぞ
この言葉は「総じて人は自分に勝ってこそ成功するのであって、自分を甘やかすとすれば、きっと失敗するものなのだ」という意味です。
西郷隆盛を英雄視する人もいれば、無駄死にした歴史上の犠牲者と揶揄する人もいます。
どのような結果だったとしても、歴史に名を刻んだことは間違いありません。
そのような偉人の言葉は素直に受け入れるべきだと思います。
人を相手にせず、天を相手にせよ
この言葉は「狭い人間世界にこだわるのではなく、広大無限な天を相手にしなさい」という意味です。
ここで言う「天」とは抽象的な概念です。
天地自然のことや宇宙、自然の道理などを「天」と表現しているのです。
つまり人間世界をミクロとした場合、天はマクロになるのです。
命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕末に困るもの也
この言葉は「命を惜しいとは思わない、名誉などもいらない、官位も金もいらないという人物ほど、権力から見て手に負えないものはない」という意味です。
つまりこれは無敵の人を意味しています。
自分の信念だけを貫き通そうとする人は、権力から見て非常に厄介な人物になるのです。
中岡慎太郎の名言
中岡慎太郎(1838年~1867年)は土佐藩出身の人物ですが、江戸に出て久坂玄瑞や佐久間象山などと交流しました。
その後脱藩して長州へ行き、尊王攘夷運動を展開します。
中岡は坂本龍馬とも交流があり、一緒に薩長同盟締結を実現させました。
丈夫立志学を為す、何ぞ一時貴賤を以て心を動かさんや
この言葉は「学問を成し遂げる志を立てたのならば、目先の貴賤で心を動かされてはいけない」という意味です。
貴賤とは、身分の高さや低さ、金額の高さや安さのことを指します。
そのような報酬で信念を曲げてはいけないと語ったのです。
後藤象二郎の名言
後藤象二郎(1838年~1897年)は土佐藩出身ですが、土佐藩藩主であった山内豊信の元で出世した人物です。
その後、坂本龍馬と一緒に「船中八策」を作成し、この構想をもとに大政奉還を実現させました。
事若し行はれずんば余も生還の意思なし
この言葉は「大政奉還が実現されなければ、私も生きて二条城から帰る意思はない」という意味です。
大政奉還という、時代をひっくり返す偉業を成し遂げた人物が後藤象二郎ですが、その信念はどうやら凄まじかったようです。
木戸孝允の名言
木戸孝允(1833年~1877年)は別名「桂小五郎」と呼ばれており、西郷隆盛や大久保利通と薩長同盟を締結した偉人です。
長州藩出身の人物ですが、同じく長州藩出身の吉田松陰から松下村塾で学び、攘夷運動を推進しました。
幕末を語る上で欠かせない人物が吉田松陰なので、ぜひ吉田松陰の名言もご覧ください。
西郷もまた大抵にせんか、予今自ら赴きて之を説諭すべし
この言葉は「西郷隆盛もいい加減にしないか。私は今自ら西郷のもとに赴いて、このことを説得したい」という意味です。
これは西南戦争が起きたことを知った木戸孝允が語った名言ですが、その時木戸孝允は病床にいました。
日本国内で戦争をしている場合ではないと考えた木戸孝允は、西郷隆盛を説得したいと思ったのです。
高杉晋作の名言
高杉晋作(1839年~1867年)も木戸孝允と同じく長州藩出身で、吉田松陰の松下村塾で学びました。
「戦うカリスマ」と呼ばれており、奇兵隊を創設したことでも有名です。
とても頭が良い人物でしたが、頑固な人物として知られていました。
男児事を成す豈時なからんや縦令市井の侠客と呼ばれても一片の素心未だ敢て差わず
この言葉は「男児が事を成すには時がある。たとえ市井の侠客と呼ばれても、胸底にある一片の真心は変わっていない。」という意味です。
高杉晋作は幕府を相手に長州戦争を起こして勝利するという功績を残しました。
たった一つの藩がお上である幕府に勝利した事実は、その後の日本を占う上で非常に重要なターニングポイントになったのです。
弔わる人に入るべき身なりしに、弔う人となるぞはずかし
この言葉は「本当ならば私も弔われる身であったはずなのに、弔う側になるとは何と恥ずかしいことだろう。」という意味です。
これは志半ばで死んだ仲間の墓石の前で語った名言です。
高杉晋作は「国のためならば命を投げ出すことも厭わない」と考えていたので、命をかけて戦ったのに、生き残ってしまったことを恥じたのです。
己惚れて世の済みにけり歳の暮れ
この言葉は「たとえ自惚れと笑われても、吉田松陰先生や死んでいった同志の意思を継ぎ、短い生涯のうちに一つのことを成し遂げたのだ」という意味です。
自分を褒め称えるというよりは、1年に1度ぐらい自分の成したことに自惚れてもいいではないかという意味だと思います。
久坂玄瑞(くさか げんずい)の名言
久坂玄瑞(1840年~1864年)は長州萩藩出身の偉人ですが、吉田松陰の松下村塾で学びました。
藩を超えた尊王攘夷運動の中心人物として、江戸や京都で活動しますが、禁門の変に敗れて自害しました。
諸侯頼むに足らず、公家も頼むに足らず、草もうの糾合の外なし
この言葉は「大名や公家はあてにならない。本当に力を発揮するのは草の根の連中だけだ。」という意味です。
「草の根の連中」は、ちゃんとした地位についてない、いわゆる脱藩者がほとんどだったそうです。
イメージとしては市民運動ですが、そのような草の根が集まれば大きな力になると考えていたようです。
山県有朋(やまがたありとも)の名言
山県有朋(1838年~1922年)は長州萩藩出身の偉人です。
吉田松陰の松下村塾に学び、高杉晋作の奇兵隊軍監として活躍します。
明治政府設立後は「軍人勅諭」を起草し、軍隊の整備や内閣組織などにも携わりました。
ひつじのみ群る世こそうたてけれとらふす野辺に我はゆかまし
この言葉は「世の中では弱い羊ばかりで嫌になる。私は虎が野に寝そべっていても突き進んでいくぞ。」という意味です。
山県有朋の意気込みが感じられる名言だと思います。
島津斉彬(しまづ なりあきら)の名言
島津斉彬(1809年~1858年)は、第11代薩摩藩主です。
明治維新で重要な役割を果たした薩摩藩のトップですが、西洋事情に明るくとても革新的な人物だったと言われています。
西洋人も人なり、佐賀人も人なり、薩摩人も人なり、退屈せず益々研究すべし
この言葉は「西洋人も人であり、佐賀人も薩摩人も人である。諦めることなく益々研究を重ねるべきである」という意味です。
島津斉彬は、集成館を立ち上げて、反射炉を建設し、西洋式の大砲を薩摩藩で作れるようにしたのです。
そのような研究熱心な人物だったからこその名言だと思います。
明治天皇の名言
明治天皇(1852年~1912年)は、明治維新によって倒幕が行われたので、その後の政府を率いた人物です。
けいらは辞表を出せば済むも、朕は辞表は出されず
これは明治天皇が伊藤博文に語った名言です。
この言葉は「みんなは辞表を出せばすむけれど、私は辞表出すわけにいかない。」という意味ですが、明治天皇の覚悟と苦悩が見て取れる名言だと思います。
伊藤博文の名言
伊藤博文(1841年~1909年)は、初代内閣総理大臣となった人物です。
元々は農家出身でしたが、吉田松陰の松下村塾で学び、木戸孝允や高杉晋作とも交流がありました。
維新の三傑(西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允)の死後、明治政府の指導者として活躍します。
現在の日本は地平線から出たばかりの太陽である
まさに日本国旗を表現したような名言ですよね。
新しい時代の幕開けにふさわしい言葉だと思います。
板垣退助の名言
板垣退助(1837年~1919年)は長いヒゲが特徴的なので、社会の教科書で見覚えがありますよね。
明治維新の前は土佐藩士として倒幕運動に従事していましたが、維新後は西郷隆盛の推挙を受けて参与となります。
高知県で立志社を創立するなど自由民権運動に注力し、第1次大隈内閣では内相を務めました。
其楽を共にせざるものは、其憂を共にせざる所以
この言葉は「支配者が領民と楽しみを共有しないことは、苦境に陥った時、領民たちが協力しない原因となりうる」という意味です。
君主論に通じる言葉ですが、政治家らしい名言だと思います。

板垣死すとも自由は死せず
これは自由民権運動の遊説中、刺客に襲われた板垣退助が叫んだとされる言葉です。
とても有名な言葉なので、教科書でも見たことがありますよね。
これで板垣退助が死ぬことはありませんでしたが、自由民権運動がさらなる盛り上がりを見せたそうです。
大久保利通の名言
大久保利通(1830年~1878年)は薩長同盟を実現した「維新の三傑」と呼ばれる薩摩藩出身の政治家です。
西郷隆盛とは幼馴染でしたが、最終的には幼馴染である西郷と西南戦争(大久保利通は新政府側)で戦う悲運を背負っています。
明治維新を語る上で欠かせない人物と言えるでしょう。
孔子は「過ぎたるは及ばざるが如し」と言われたが、私は「過ぎたるは及ばざるに如かず」と言いたい
この言葉は「孔子は「やり過ぎるのは足りないと同じように良くない」と言ったが、私は「やり過ぎるのは足りないよりももっと悪い」と言いたい」という意味です。
大久保利通は政治家だったので、非常に重要な意思決定をしていました。
そのような立場の人にとって、実行したことは取り返しがつかないケースが多いのです。
なので、実行する前は慎重に熟慮するべきだと語っています。
孔子の名言集は下の記事をご覧ください。
聖人の言といえども時勢によっては全部応用することはできない。
時勢に応じて活用しなければならぬ。
これはつまり、状況に応じて動くことを推奨した名言です。
たとえ優れた戦略や考え方だったとしても、市場環境は変化するので、いつでもそれが通用するとは限らないのです。
岩崎弥太郎の名言
岩崎弥太郎(1834年~1885年)は、土佐出身の実業家です。
坂本龍馬とも交流がありましたが、三菱財閥の創業者なので、三菱銀行、三菱商事、三菱重工などの基礎を築いた人物だと言えるでしょう。
商法経営の方策は、現在わが国でわが社の右に出づる者はないようにするべく苦心をしている
岩崎弥太郎は新しい国家を作ろうという意気込みに燃えていた維新志士の一人でしたが、倒幕後は政治でなく、実業界で生きることを決めました。
その結果出来上がったのが三菱財閥です。
当時はまだ混乱期で、実業界が成立していたわけでもなく、そこで商売していくことはとても困難だったことが容易に想像できます。
まとめ
ここまで明治維新の動乱期を生き抜いた志士達の名言をご紹介してきました。
ジャンプコミックスとして有名な「るろうに剣心」というマンガも、明治維新の混乱期を描いた剣客漫画です。
このような大人気コミックスとして描かれたり、新撰組のように語り継がれるケースもあります。
どちらにしても、とても魅力的な時代だったことには間違いありません。
維新志士の言葉はどれも芯が強いので、生きる上でもきっと役立つはずです。
仕事やプライベートにも使える格言ばかりなので、ぜひあなたのビジネスに活かしてください。
ちなみに、今回はご紹介しませんでしたが、幕末に活躍した渋沢栄一という偉人もいます。
「日本経済の父」と言われる人物なので、渋沢栄一の名言を知りたい場合には下の記事をご覧ください。