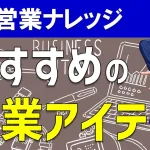成長している企業には「優秀なプレイングマネージャーがいる」と言われています。
しかしその一方で「プレイングマネージャーになってはいけない」とか「プレイングマネージャーはいらない」と言われることもあります。
その理由は何故なのでしょうか?
そこで今回は、プレイングマネージャーという話題にフォーカスしていきたいと思います。
目次
プレイングマネージャーはなぜ大変?
プレイングマネージャーといえば「プレイヤー×マネージャー」の言葉ですよね。
ビジネス界隈では一般的なフレーズだと思いますが、その仕事はとても多忙なので「常人ではこなせない」とも言われています。
例えば、プロ野球界では「選手兼監督」と呼ばれていて、野村克也氏や古田敦也氏などがプレイングマネージャーとして活躍していましたよね。
つまりバッターボックスに入って守備をしながら、選手交代や試合展開まで考えるので、想像しただけでもその大変さがわかると思います。
普通の人ではこなせないような特殊な働き方だと思いますが、一体なぜプレイングマネージャーというポジションが存在しているのでしょうか?
まずはその意味について触れていきたいと思います。
プレイングマネージャーが存在する理由
企業がプレイングマネージャーを置きたがる理由は”コスト削減”につながるからです。
例えば営業活動について考えた場合、決してセールスすることだけが仕事ではありませんよね。
- 新規開拓の戦略立案=営業企画
- 見込み顧客を探す=マーケティング
- 商談機会の創出=アウトバウンド営業
- 商談や打ち合わせ=クロージング
- 契約手続き=営業事務
- 料金回収=経理業務
- 顧客フォロー=カスタマーサクセス
ざっと考えただけでも、これだけたくさんの仕事があると思います。
大手企業の場合には「営業企画部」「マーケティング部」「営業部」「経理部」「カスタマーサクセス」など様々な部署が担っていますが、中小企業の場合には人的リソースが足りません。
予算もヒトないので、それらを営業マンが巻き取らなければいけないのです。
そうなった場合、一人が様々な業務を兼業することになります。
このように仕事の合理化を図った結果、プレイングマネージャーという特殊な存在が出来上がったのです。
その結果一人のプレイングマネージャーに大量のタスクと責任が降りかかってきて、とても辛い状況になっているのです。
プレイングマネージャーの役割とは?
マネージャーの役割は「リーダーシップ」と「マネジメント」の2つに集約されていきます。
リーダーシップとは、簡単に言えば「組織を引っ張る力」のことを言います。
つまり、目標達成に向けてチームの進むべき方向性を示し導いて行くのです。
そしてマネジメントとは、業務オペレーションを作成し、そのシステムを組織に取り入れて、チーム全体の動きをコントロールすることです。
この二つのスキルは、マネージャーとして活躍する上で必要不可欠なスキルだと言えます。
それに加えてプレイヤーとしての役割も期待されています。
積極的に営業現場へ出向き、数多くの商談をこなして、売上を構築するのです。
このようなハードワーカーがプレイングマネージャーなのですが、「プレイヤー」と「マネージャー」は肌感覚としてどれぐらいのバランスで取り組めば良いのでしょうか?
これには様々な意見があると思いますが、個人的には「プレイヤー:マネージャー=6割:4割」くらいの感じが一般的だと思います。
なぜプレイヤーの比重が高いのかと言えば、中小ベンチャー企業には余裕がないので、とにかく目先の売上に追われてしまうからです。
するとマネージャー業の方が少なくなるので、必然的にチームマネジメントが滞るリスクが出てきます。
実は、これがプレイングマネージャー制度における最大の欠点だと言われています。
ボス(=リーダー)のいないチームは決して機能しません。
チームが掲げる目標やノルマを達成することもできないでしょう。
このように、プレイングマネージャー制度を取り入れると「全てが中途半端になる」と言われているのです。
しかし中小ベンチャー企業と違って、大手企業には”専業マネージャー”がいるので、この部分が大きな違いだと言えます。
チームをコントロールしながら売上を追う
プレイングマネージャーに求められているのは、チーム全体をコントロールしながら、売上ノルマを達成することです。
これが具体的な役割と言えますが、それを達成するために必要なのが行動量と管理体制です。
自分の働く量が増えればプレイヤーとしての生産性が上がるので、必然的に売上増加に繋がっていきます。
そして、マネージャーとしての仕事量が増えれば、チーム全体をコントロールできるので組織化に繋がっていきます。
この両輪を常にフル回転するのです。
逆にプレイヤーとしての活動を放置すれば生産性(売上、利益など)が落ちますが、マネージャーとしての活動を放置すると管理コスト(経費、売掛金、在庫など)が増えていくのです。
プレイングマネージャーが機能しなくなる(=両輪が回らなくなる)と、このような逆転現象が起こってしまうのです。
本来企業というのは「売上を最大化」させて「コストを最小化」させることで、利益の最大化を目指します。
なので、プレイングマネージャーという働き方は企業にとってメリットがある一方で、とても大きなリスクを抱えている仕組みなのだと理解しましょう。
役割を全うする方法は?
プレイングマネージャーの役割を全うするのは、とても難しいと思います。
しかしそのやり方は存在しています。
そのセオリーとは「マネージャー業務の比重を増やす」ことです。
例えば「プレイヤー:マネージャー=6割:4割」くらいの比率だった場合、「プレイヤー:マネージャー=2割:8割」を目指すのです。
これが何を意味しているのかと言えば、自分の業務をチームメンバーに移譲することになります。
それはつまり、自分の業務の再現性を追求するということになります。
プレイングマネージャーとして活躍している人は、おそらく優秀なセールスパーソンでもあると思います。
セールスで結果を出すためには、合理的なロジックが必要なので、そのロジックを部下に継承していくのです。
これはつまり”人材育成”を意味しています。
自分が普段やっているセールスは感覚でこなせたとしても、それを言語化してマニュアル化すれば、たとえ自分がプレイヤーとして動かなくても、ある程度の売り上げが確保できるようになるため、その分のリソースをマネジメントに割けるようになります。
これこそがプレイングマネージャーの役割を全うするための成功スパイラルなのです。
「部下に継承⇒マネジメントに専念⇒部下に継承⇒マネジメントに専念⇒部下に継承…」
このようなスパイラルにハマれば、上昇気流に乗るはずなので、いずれ強固な組織が出来上がることでしょう。
目指すべきチームとは?
プレイングマネージャーとして働いている人は、一人で複数の業務ができるので「プレイングマネージャーのように優秀な人が複数人いるチームを作れば良いのでは?」と考える人がいるかもしれません。
しかしそのようなチームを目指すべきではありません。
結論から言ってしまいますが、プレイングマネージャーだけではチームとして成立しないのです。
部長やリーダーと言われる”組織の長”がプレイングマネージャーに該当しますが、そのような人が複数人いると、指揮命令系統が分散します。
すると現場が混乱するので、結局それぞれのプレイングマネージャーが個々人で動くだけの組織となります。
そんなのチームとは呼びませんよね。
またエース級のトップセールスばかりを集めることも控えましょう。
エース級人材は成功体験が多いので、なかなかリーダーの言うことを聞いてくれない可能性があります。
そのような問題児ばかりであれば、組織を統括するだけで一苦労です。
もしリーダーシップに悩みがあれば、下の記事をご覧ください。
そして、いわゆるスーパープレイヤーの人は超多忙なので、マネージャー業務まで兼務させると、自分一人のタスクでパンパンになってしまいます。
そうなるとマネージャー業務がおろそかになるので、部下を育成しなかったり、部下が相談しにくい環境になってしまうのです。
そのような状態が続くと、部下は次第にやる気をなくし、モチベーションが下がっていきます。
それをスーパープレイングマネージャーは把握できないので、ある意味で「裸の王様」になってしまうのです。
このことからも、チーム運営をするポイントは「特定の人だけに頼らない」ということが理解できるはずです。
チームメンバーがお互い補完関係にある組織ほど強いものはありません。
もしこれからチーム作りをする場合、そのような観点のチームビルディングをお勧めします。
プレイングマネージャーが身に付けるべきスキル
プレイングマネージャーとして活躍するためには、プレイヤーとマネージャー両方のスキルが求められます。
なので「全部盛り」のような話になってしまいますが、ここでは月並みな表現ですが「努力し続ける」ことをオススメしたいと思います。
プレイングマネージャーはリーダーとして活躍する人なので、その一挙手一投足を部下はちゃんと見ています。
なので、常に部下のお手本となるような人物でなければいけないのです。
そういった意味では努力することが欠かせません。
プレイングマネージャーとして活躍したいのであれば、もはやプライベートなど無いものと考えましょう。
平日の仕事を終えた後も自己研鑽に励み、土日祝日は外部と交流することに時間を費やします。
そして空いた時間は読書をし、様々なジャンルの知識を蓄積するのです。
特にマネージャー職が身につけておきたい知識は「哲学」と「歴史」です。
哲学は物事の真理を追求する学問なので、善悪の判断がつきやすくなり、合理的な思考回路が手に入ります。
そして歴史は戦略を考えたり戦術を練る時の参考になります。
「歴史は繰り返す」とは良く言ったものです。
さらに行動経済学や地政学、心理学などを学んでおけば、人の動き方が理解できるので、きっと仕事にも役立つでしょう。
つまり博識でなければ、部下から尊敬されることもないのです。
勉強が苦手な人もいると思いますが、このあたりは肝に銘じておきましょう。
プレイングマネージャーには限界がある
プレイングマネージャーは優秀な人なので、なんでもできると勘違いされがちですが、やはり人間なのでそれなりの限界値があります。
その典型的な課題点が「チームメンバーがリーダーに頼りすぎる」ということです。
プレイングマネージャーは優秀が故に、チームメンバーから頼られる存在だと思います。
なので「営業ノルマが未達でもリーダーが何とかしてくれる」とか「顧客から無理な注文を受けても、リーダーが丸く収めてくれる」という勘違いが生まれるのです。
これはチーム運営する上での大きな問題だといえます。
プレイングマネージャーとして組織を動かすためには「指示型組織」にしてはいけません。
リーダーから指示を出すトップダウン式では限界があるのです。
そうではなくチームメンバーとリーダーが横並びになるような組織を作りましょう。
自由に意見が言えて、それぞれに責任のあるフラットな組織であれば、個々人の当事者意識が高まるはずです。
このようにチームとメンバーを”一緒に成長させていく”ことが重要なのです。
なんでもかんでもリーダーがやるのには、どうしても現実的な限界があります。
そんな時にはサブリーダーを設置するのも良いでしょう。
出来る限りタスクを分散させて、チーム全体で達成するようにしましょう。
まとめ
プレイングマネージャーは優秀な人なので、どうしても「自分が動きたい!」という衝動に駆られるはずです。
しかしそれを我慢することが、チーム全体の底上げにつながっていくのです。
そして属人的な組織ではなく、チーム全体を仕組み化しましょう。
そのために必要なのはコミュニケーションだと思います。
部下がたくさんいる場合には大変ですが、自腹を払う飲みニケーションも必要なので「これも必要な投資だ」と割り切る覚悟を持ちましょう。
とにかくプレイングマネージャーに求められていることは結果を出すことです。
その方法論は二の次なので、「どんな方法を用いても必ず目標達成させる!」という強い信念を持って仕事に臨みましょう。