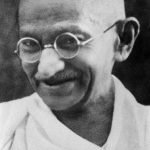客単価は経営者にとって非常に重要な指標だと思います。
この客単価次第で、売上が倍増するなんてことも起こります。
そこで今回は、顧客単価を上げるための方法や、その施策について解説していきたいと思います。
目次
客単価の意味とは?
企業経営者や営業職でなくても、一度くらいは耳にしたことがある言葉が「客単価」だと思います。
客単価の意味は「顧客一人あたりの平均売上高」で、その計算式は「売上=客数×客単価」または「客単価=売上÷客数」で表されます。
英語でも同様に「Average Spend per User」や「Average Revenue per Customer」と言います。
客単価は、飲食店やサービス業、小売業などで非常に重視される項目ですが、BtoCのビジネスだけに限らず、あらゆるビジネスにおいて重要な指標となっています。
一般的に客単価が高いビジネスモデルは、ブランド価値&商品価値が高いと言われています。
客単価の計算事例
客単価の分かりやすい例として飲食店を考えてみましょう。
例えば、あなたがラーメン屋の企業経営者だったとして、1日の売上が10万円、客数が100人だった場合、以下のように計算できます。
売上10万円÷客数100人=客単価1,000円
しかし、同じ売上10万円でも、客単価が全く異なるケースもあります。
例えば、あなたが高級フランス料理店を経営しているとして、1日の売上が同じく10万円だとしても、高級なコース料理を提供している為、1日の客数が10人に限定されてしまいます。
その場合は、以下のような計算式になります。
売上10万円÷客数10人=客単価10,000円
この様に一見同じ売上高でも、ビジネスモデルや業態によって大きく異なるのが客単価なのです。
経営者や営業職の人で、「自社や自分の客単価を計算したことがない」という人は、一度客単価やLTVを計算してみましょう。
LTVという言葉は、Life Time Value(ライフ タイム バリュー)という意味の略語で、「顧客生涯価値」とも言われています。
このような分析をすると、意外な気づきがあるかもしれません。
購入者の客単価を分解しよう!
売上拡大のために重要な指標である客単価ですが、目に見えやすい客数や売上と異なり、計算して分析する必要があるため、意外と細かい対策が講じられにくい指標でもあります。
しかし前述した通り、売上は客数と客単価(売上=客数×客単価)の2要素で構成されている為、たとえ客数が同じでも、客単価を意識して伸ばすことができれば、売上拡大が見込めるということになります。
客単価を伸ばして売上拡大を図る戦略は、主に客数が制限されているビジネスや業態に有効的です。
例えば飲食店や美容室など席数が限られていて、もうこれ以上客数や回転率をあげられない場合は、客単価をアップすることで売上拡大を図ることができます。
法人向けBtoBビジネスでも、1人(あるいは1社)の顧客対応に時間がかかるビジネスモデルだったり、営業人材が限られていて新規開拓が難しい場合は、現状の客数でも客単価を上げることで売上拡大を図ることができます。
- 客数を伸ばすために特別価格やセールを連発してしまった
- キャンペーン中は客数が2倍になったのに、集計してみると客単価が下がってしまった
- 開催したイベントが想定した売上に届かなかった
このような見切り発車な事例をよく見かけますが、客数と同様に客単価も常に意識して考えることが必要なのです。
客単価が下がる原因
客数は定量的に見えてしまうため、意識してリピーターを維持する、または新規開拓が実施されています。
その反面、客単価を細かく集計したりチェックする習慣がないケースが多く、気付かないうちに売上を下げてしまうこともあるので十分注意が必要です。
客単価の構成要素は「客単価=一人当たりの購入点数×一人当たりの商品単価」で表されます。
つまり、値下げをしていないのに客単価が下がる要因は、「一人当たりの購入点数」か「一人当たりの商品単価」が下がったためだと考えられます。
それでは、一人当たりの購入点数の具体例を見てみましょう。
客単価が下がる具体例
あなたはラーメン屋さんを経営しているとします。
今まではラーメン700円にサービス価格の餃子100円を一緒に頼む「客単価800円」のお客様が多かったのに、客単価を上げたいと考えて餃子を300円に値上げしてしまうと、「100円ならよかったけど300円は高いからやめておこう」という顧客が増え、購入点数が一点減った結果、客単価が700円に下がる現象が起こりえます。
同様に「一人当たりの商品単価」の例を挙げると、今まではラーメン700円に生ビール300円を頼んで客単価1,000円の顧客が多かったのに、お客様に良かれと思ってチューハイ250円の品揃えを増やしたところ、生ビールから需要が移行してしまい、客単価950円の顧客が増え、結果として販売単価が50円下がってしまうことになります。
この様に、良かれと思ってやった戦略が客単価を下げる要因になることもあるので、商品価格の設定では細心の注意が必要です。
意外と消費者の財布は固いと心得ておきましょう。
客単価を上げる方法
客単価を上げるためには、客単価が下がる要因の説明とは逆に、「一人当たりの購入点数」か「一人当たりの商品単価」を上げる取り組みが重要になります。
例えば、居酒屋やファミレスなどの飲食店舗で良く見かける「ランチセット」や「晩酌セット」は、価格やメニュー設定によっては客単価を上げることに貢献します。
前述したラーメン屋さんの例では、通常時の商品金額が「ラーメン700円+餃子300円=合計1,000円」となりますが、「ランチセット」としてラーメン餃子セット900円を新しく導入し、お得だからと注文する顧客が増えた場合、昼食帯の客単価を200円上げることができます。
これは「一人当たりの購入点数」を伸ばして客単価を上げる販売事例です。
アップセルやクロスセルでも客単価は上げられる
また美容室でパーマやカラーをしてもらう際、「通常のパーマ液やカラー剤は少し傷みやすいので、お客様の髪質では、こちらの高品質なモノが合っているし長持ちしますよ」と勧められた経験があるかも知れません。
こちらは「パーマをする」「カラーをする」といった購入個数は同じでも、「一人当たりの商品単価」を伸ばすことで客単価を上げる事例です。
つまり、購買する製品・サービスの上位互換を提案する方法になります。
この様なセールス手法はアップセルやクロスセルと言われており、営業現場で良く見かける方法になります。
このように、日常生活の中でも売上を上げる取り組みや販売方法、集客手段などのノウハウはたくさんあるのです。
ブランディングをして価格UPさせる
客単価をアップさせる施策として有効的なのが、ブランディング戦略を検討することです。
この方法は原価が変わらないのに、販売価格だけを上げることができるので、粗利額が大きくなります。
代表的な例が「ルイヴィトン(Louis Vuitton)」などの高級ブランドです。
ルイヴィトンは高級ブランドとして知られており、売られているバックやアクセサリーは1個につき何十万円もします。
全く同じ素材や材質のカバンであれば、ルイヴィトンよりも安く変えることは確実ですが、ルイヴィトンというブランド価値が乗っている為、「50万円払ってでも欲しい!」というような人が店舗には殺到しています。
これは上手く広告宣伝が行き届いている証拠ですが、ルイヴィトンのような小売店だけに適用される話ではなく、法人向け製品(B2B)でもあり得る話しなのです。
クーポンは顧客の集客に効果あり?
「一人当たりの購入点数」を伸ばすための有効な手段として、クーポンが挙げられます。
通常価格よりもお得なクーポンを使うことで、本来購入する予定ではなかった商品を複数購入してもらい、「一人当たりの購入点数」を伸ばして客単価を上げることができます。
実際に、クーポン割引を付加して、成功しているお店やショップの事例はたくさんあります。
「スーツ二着目半額」などは、その典型例だと言えます。
マーケティングノウハウや知識がないと、安易にクーポンを使ってしまいますが、使い方次第では諸刃の剣になり得ますので、活用方法には十分注意する必要があります。
この辺りについて解説しておきたいと思います。
注意すべきポイント①
注意すべき1点目は、クーポン狙いの顧客を予想以上に集めてしまう事です。
ラーメン店の例では、これまで餃子を頼んだ事がなかった顧客に”餃子無料クーポン”を発行する事で味を試してもらい、次回来店時には注文してもらう事を目的としていても、顧客の中には「安いから購入しただけで通常価格で餃子を頼むつもりはない」という人も一定数いるはずです。
この様な既存顧客にクーポンを発行し続けても、客単価向上には繋がらず、販促コスト(販管費)が増すばかりです。
割引クーポン券は使用頻度や回数に注意して、リピート客を作るように工夫しましょう。
注意すべきポイント②
注意すべき2点目は、経営者や営業職自身がクーポン病に取り憑かれてしまう事です。
割引券を発行すると一時的に客数や客単価が上がりますが、止めてしまうと元の水準に戻るか、あるいは元の水準以下に下がってしまう事が良くあります。
そこで慌てて新しいクーポンを発行し、結果的に値引きが常態化するという病に陥るのです。
このような状態になってしまうと、割引すること自体をやめられなくなってしまうので、つまり麻薬のような役割になってしまうのです。
クーポンは客単価向上、あるいは客数向上という目的を明確にして、期間を決めて計画的に導入する必要があります。
また、売上が伸びた事で満足するのではなく、客数と客単価に分解して分析する事で、次の客単価戦略に活かすのが良いでしょう。