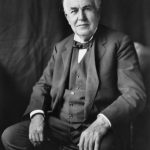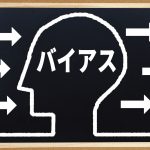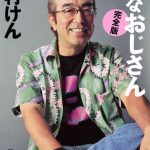福沢諭吉といえば『一万円札の肖像』にも採用されている歴史上の偉人ですよね。
有名な著書には「学問のすすめ」がありますが、慶應義塾大学を創設した人物としても有名なので『福沢諭吉=教育者』として認識している人は多いはずです。
もちろんビジネスパーソンとしても一流だったので、今回は福沢諭吉の名言集をご紹介したいと思います。
福沢諭吉の名言は『社会人の基礎知識』と言えるので、ここから福沢諭吉の考え方&生き方を学びましょう!
福沢諭吉の名言集まとめ
「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」と言われている。
この言葉は「天が人間を生み出した時から、みんな同じ地位・資格を持っていて、生まれながらに平等である」という意味です。
「…と言われている。」とある通り、実はこれ福沢諭吉の言葉ではありません。
しかし世界的に有名な「学問のすゝめ」の書き出しなので、福沢諭吉の中で最も有名な言葉かもしれません。
賢人と愚人の違いは、学ぶか学ばないかによって決まるのである。
人間は平等に作られますが、実社会ではお金持ちの人や貧乏な人、出世する人やしない人など、ある意味優劣がついてきます。
この差がつくのは『学ぶか学ばないか』なのだと福沢諭吉は語っています。
学問とは、ただ難しい文字を知ることではない。
勉強と聞くと、分かりにくい古文や和歌を読んだり、難しい本を読むことのような気がしますよね。
しかしそのような勉強を福沢諭吉は「役立たぬ学問」と一刀両断しています。
そうではなくて、日常業務に必要な『実用学』を勉強するべきだと語っています。
それは具体的に下のような学問です。
※あくまでも一例です。
- そろばんの勉強⇒計算が早くなる
- 帳簿の付け方⇒お金の活かし方がわかる
- 政治の勉強⇒選挙に役立つ
- 地理の勉強⇒旅行に役立つ
- 経済学の勉強⇒仕事に役立つ
これらは日常的に使える学問ばかりです。
このような勉強を福沢諭吉は勧めているのです。
ただ自由自在だとばかり主張して、自分の立場を知らないでいたら、それはわがままになり、身を持ち崩すことになる。
自分の立場とは、天の定めた道理に基づき、人間の情を大事にし、他人を妨げず、一身の自由を守ることです。
つまり「自由とわがままの違いは、他人を妨げるかどうかにある」と福沢諭吉を語っています。
例えば「会社の忘年会には参加したくないから行きません」というのは、福沢諭吉からすると『自由意志ではなく、単なるわがまま』なのです。
忘年会を開催する趣旨の中には、仕事を円滑に回すために社員同士のコミュニケーションを図ったり、自分の仕事を手伝ってくれた人を労う、というのが含まれているはずです。
それなのに忘年会に参加しないというのは、他人の仕事(=円滑に仕事を進める)を邪魔したり、ひいては業務妨害に当たる可能性すらあるのです。
若年層の中には「会社の飲み会に参加したくない」という人が増えていると聞きますが、それは他人の業務を妨害することじゃないのか…
しっかり見極めるようにしましょう。
現在では人民全て平等という基本精神が成立したのだから、我々は安心して自分の力量を発揮できるわけである。
明治維新の前は、幕府という絶対的な存在がありました。
しかし現代社会では、成人に対して参政権が与えられているので、お上を恐れる理由などありません。
もし不満があれば、自分の意思で戦うことだってできるのです。
しかし、そのためには知識という土台がなければいけません。
だから勉強が必要なのです。
世の中で無知蒙昧の民ほど哀れなものはないし、付き合いにくいものはない。
無知蒙昧(むちもうまい)とは、知恵や学問がなく、何も知らず、愚かな様子を指します。
そのような人達には、自分の無知を反省する能力すらないので、金持ちを恨んだり、不平不満ばかりを述べるそうです。
つまり自分の不幸を周りのせいにするのです。
そして自分は国の法律を盾にしながら、不都合な場合には平気で法令違反を犯すのです。
文字は学ぶための道具であり、建築に使うトンカチやノコギリと同じだ。
文字を知っているだけでは意味がありません。
ただ文字を知っているだけの人を、福沢諭吉は「知識の問屋」と揶揄しています。
文字を活用できる人だけが『知恵のある人』なのです。
我が日本国民も、直ちに学問に志し、気力を確かに持って、まず個人としての独立を意図すべきである。
国は国民によって成り立っているので、個人が独立してこそ国も独立するのです。
つまり、国民一人一人が人間でいう『細胞』にあたるので、細胞が強ければ身体も強くなるということです。
独立とは、自分で自分の身の始末をつけ、他人を頼る心がないことをいう。
親に頼っていない人を「独立した成人」と呼びますよね。
ビジネスにおいては、独立することを「個人事業主」と呼んだり「フリーランス」と呼んだりします。
どちらも他人を頼ることがないので、もし他力を当てにしている場合は、まだ独り立ちできてないことになります。
自分自身の独立を保てぬ者は、外に対して独立することなど不可能なのである。
福沢諭吉が生きた時代は、明治維新の真っ只中でした。
なので、日本という国が開かれて、グローバリゼーションに巻き込まれる寸前だったのです。
その事に対して、福沢諭吉は非常に強い危機感を抱いていました。
このままの日本人では外国人に太刀打ちできないと考えた福沢諭吉は、一人一人が猛勉強し、独立するように推奨したのです。
政府は命令を下す権力はあるが、それを説明し実行に移すのは民間の力である。
この名言にあるような『実行力のある国民』を育成するために、慶應義塾大学は作られました。
そこで学ぶ仲間たちを慶応社中(慶応で学ぶ仲間)と呼んだのです。
今日まで国としての独立を失わなかったのは、国民が鎖国の風俗習慣になれ、外国との戦争による国家の危機がなかったためである。
これはつまり『日本はぬるま湯に浸かっている』ことを指摘しているのです。
外部環境は変化しているのに、自分は変わらなければ、それは相対的に衰退を意味します。
十分注意しましょう。
相手に劣等感を持ってしまったら、たとえ自分に多少の知識があっても、それを外に向かって広めることができようか。
これは外国人に対して、弱腰になってしまう日本人に向けたメッセージです。
日本人は『外国至上主義』という考え方に洗脳されているので、どうしても外国人に劣等感を抱いてしまいます。
そのような姿勢は、最初から負けを意味するのでやめましょう。
国民が政府に従うというのは、政府が作った法に従うのではなく、自分が作った法に従うのである。
政治家の仕事は立法です。
しかし、議会制民主主義においては国民から政治家が選出されます。
つまり政治家を選ぶのは国民ということです。
ということは、間接的に国民自らが法律を作ることになるのです。
そう考えた場合、法律を犯した人は『自らが作った法律によって罰せられる』という概念になります。
元禄の世に、浅野家の家来たちが主君の仇とて吉良上野介(きらこうずけのすけ)を殺したことがある。
世にこれを赤穂(あこう)の義士と誉め称えた。
これは大きな間違いではあるまいか。
四十七士の忠臣蔵(赤穂事件)は、有名な逸話として知られていますよね。
しかし福沢諭吉は「この事件は法律違反であり大きな過ちである」と断じています。
赤穂事件はすなわち『私刑』なので、明らかな犯罪行為だと言うのです。
赤穂事件の後に四十七士は切腹しましたが、もしこの事件の後に四十七士が生き残っていた場合、吉良家の一族がまた仇討ちをして、また赤穂一族も仇討ちをし返すという悪循環に陥ります。
これでは無政府&無法律の社会だと、福沢諭吉は語っています。
日本が法治国家である限り、私刑は許されないのです。
この国に住み、国民として政府とどんな約束を結んだのか。
必ず国法は守る。
そしては我が身の保護を受けたいと約束したはずである。
法律を守ることは、自分の身を守ることに繋がります。
つまり、法律は自分自身を守ってくれるということです。
その保護を受ける代償として、自分も法律を守るという約束をするのです。
逆に法律を守らないということは、「いざという時に自分のことを守らなくてOK」と宣言することと同義なのです。
すなわち、法律を守ることと、法律に守られることは、相互契約なのです。
およそ国民には一人の身で二つの務めがある。
- 政府の下に立つ一人民という立場
- 全員の合意を取りつつ日本国の運営に当たる立場
福沢諭吉曰く、国民にはこの2つの役割があります。
これらはそれぞれ『①社員』『➁経営者』に該当します。
それぞれに守るべき義務があり、役割があると福沢諭吉は語っています。
蟻と同じレベルになったくらいで、満足するな!
蟻は自分で巣穴を作ります。
そして、自分で食べ物を探して、それを冬に向けて蓄えていきます。
これと同じように、毎日働いて、お金を稼いで、そのお金を老後のために貯金する…
この程度の日本人が多すぎると、福沢諭吉は警鐘を鳴らします。
夢や目標を持たずに日々過ごしているだけの人は、ただ生まれて死ぬだけです。
人間が人間らしくあるためには、何かしら生きた痕跡を残さなければいけません。
それが結果的に『社会への貢献』となるのです。
人間は一つのものを得ると、すぐに次のものが欲しくなり、満足は不満に変じて、飽きることを知らないものである。
人間の欲望は限りないので、自分で制御することが必要です。
そのやり方というのは『欲しいもの』を求めないことです。
例えば『欲しい洋服』があった場合、「それは本当に必要なのか?」と立ち止まって考えてみるのです。
つまり『必要なもの』だけを求めれば、人間の欲望は制限できるはずです。
チャンスに恵まれなければ、有能な者もその力を発揮できない。
「チャンスがない…」と嘆いている人を見かけますが、本当にそうなのでしょうか?
チャンスを掴むための努力をどれほどしたのでしょうか。
努力している人には必ずチャンスが訪れますが、適切な努力をしていないと『チャンスだと気づかない』こともあるのです。
これはつまり『準備する』ことの大切さを伝えています。
お手軽に得られるものは、お手軽に消える。
世の中はよくできているので、簡単に手に入るものは貴重でなく、得るのが難しいものほど価値が高いという傾向があります。
そう考えた場合、自らの意思で困難に立ち向かった方がいいでしょう。
若いうちは、易きにつくな。
これは「若い時の苦労は買ってでもせよ」と同じ意味の名言です。
若い時に苦労した人と、楽をした人とでは、年をとってから雲泥の差が出てしまいます。
それを巻き返すのは難しいので、若いうちにできるだけたくさん苦労しましょう!
上に立つ者の基本的な考えは、世の民衆はみんな無智で、かつ善良だというところに立っている。
これはとても秀逸な名言だと思います。
この名言の中にある「無智」は「無知」ではありません。
智恵がないことを意味しているのです。
智恵と似た言葉に「知識」がありますが、知識とは「物事を知っている」状態を指します。
知識を持っているだけでは頭でっかちなので、その知識を活用して行動できることを「智恵」と呼んでいます。
よって善良な市民(=向上心があり前向きである)は、それぞれ知識を持っているが、それを行動に移すやり方を知らないという意味の言葉になるのです。
リーダー(上に立つ者)は、そのような前提で人を動かす必要があると思います。
学問は、ただ本を読むだけで事足りるものではない。
学問の本質は、学問を自分がどう活用できるかにかかっている。
学問とは知識をインプットする作業です。
あくまでも作業なのです。
重要なのはその知識をアウトプットすることです。
つまり知識を智恵に変えるということです。
福沢諭吉は、学んだ知識を活用して、積極的に行動することを推奨しています。
誹謗も弁駁も紙一重である。
- 誹謗(ひぼう):他人に嘘の情報を吹き込むこと
- 弁駁(べんぱく):他人の疑惑を解いて、自ら信じた正義を主張すること
SNS全盛期なので、他人への誹謗中傷が社会問題になっていますよね。
受け取った本人は誹謗中傷だと思っても、発信者は弁駁のつもりかもしれません。
世の中に絶対的な正義は存在しないので、この問題を解決するためには『普遍的な真理』について学ばなければいけないと思います。
それはつまり哲学を勉強するということです。
有名な哲学者の名言集は下の記事をご覧ください。
怨望を抱く者どもは、世間の幸福を破壊するだけで、世の中に何の寄与もなし得ない。
怨望(えんぼう)とは、自分の不平不満を満たすため、他人を不幸に陥れようと企てることです。
先ほど「誹謗(ひぼう)も弁駁(べんぱく)も紙一重である。」という名言をご紹介しましたが、ほとんどの感情は表裏一体になっています。
つまり受け取り手によって、プラスになったりマイナスになったりするのです。
しかし「怨望だけは違う」と福沢諭吉は語っています。
怨望だけはプラスになる要素がないので、絶対に持ってはいけない感情なのです。
世の中は生きているし、流動的でその変化は予測できない。
だから賢人でも意外な失敗をするのである。
失敗を恥じる必要はありません。
「失敗は成功のもと」と言われている通り、たくさん失敗した人ほど、成功する確率が高まっていくからです。
このことを、発明王のトーマス・エジソンも名言として残しています。
気になる人は下の記事をご覧ください。
世間で何かの計画を立てた人は「死ぬまでには」とか、「10年以内に成し遂げる」などと言う場合が最も多い。
「3年以内」「1年以内」という者はやや少ない。
「1ヶ月以内」「すぐに今日から実行する」という者は、ほとんど稀である。
この名言が伝えたいことは「思い立ったらすぐに行動しろ!」ということです。
何を信じ、何を疑うか、選択する力が必要なのである。
現代は情報社会なので、様々な情報が溢れかえっていますよね。
中にはフェイクニュースもたくさん存在していますが、福沢諭吉はまるでこのような時代が到来するのを予知していたかのようにも感じます。
正しい情報を取捨選択するために必要なのが『学問』だと結論付けています。
独立には二通りの区別がある。
一つは有形の独立、もう一つは無形のものである。
有形の独立とは、自分で家を用意して、食べ物なども全て自分でまかなうことを言います。
つまり人に頼らず生きていくことを指します。
そして無形の独立とは、精神的な独立のことを言います。
本来目指すべき独立の形は「無形の独立」ですが、一番最悪な状態は『他人に左右されている人生』だそうです。
例えば、他人が持ってるものを欲しがったり、他人に好かれるために自分を変えてしまうことです。
このような人は「独立」から程遠い状態だと福沢諭吉は語っています。
理論と実行とは、寸分も食い違うことなく、一致させねばならない。
人それぞれ、自分の考える正義や、正しいと思う生き方がありますよね。
それと行動が伴っていなければ、人間としては未熟なのです。
身につけた学問を活かしきれない人のことを、福沢諭吉は「気の毒な人」と揶揄しています。
福沢諭吉が学問をすすめる理由
ここまで読み進めた人は、福沢諭吉がなぜ『学ぶこと』を推奨しているのかよく理解できたと思います。
明治維新が起こってから、日本では民主政治が主体となりました。
つまり国民が政治家を選び、その政治家が立法を行い、作られた法律を国民を守るという、双方の契約関係が出来上がったのです。
それ以前の日本は幕府がすべてを決めており、「切捨御免」という文化も根付いていたため、武士の方が位が高いというのが当たり前でした。
切捨御免(きりすてごめん)
江戸時代に武士へ与えられていた特権の一つです。町人、農民などが武士に対し雑言(ぞうごん)など無礼を働いた場合、武士が止むを得ず切り殺しても処罰されませんでした。
そのような旧態依然の仕組みが明治維新によって180度変わったので、日本国民自らが”経営者”として国を運営する必要性が出てきたのです。
そのために必要なのが『学問』です。
知識がなければ知恵もつかないので、福沢諭吉はとにかく日本人に学ぶことを推奨しました。
つまり言われたことだけをやる、いわゆる「サラリーマン根性を捨てろ!」と言ったのです。
現代選挙の投票率は50%前後が一般的ですが、恐らくこのような状況を福沢諭吉は嘆くと思います。
『学問のすゝめ』が書かれたのは100年以上前ですが、それほどの時間が経っても日本人の半分(50%)はまだ学ぶことの重要性を理解してないからです。
自らが政治家を選び、その政治家が立法を行い、作られた法律を国民を守る…
いわゆる民主主義に対して主体的に取り組んでいる人が『2人に1人しかいない』のが日本の現状です。
このような状況は、福沢諭吉の理論を引用すると『2人に1人は法律を守る気がない(=双方の契約関係が出来上がってないから)』と言っても過言ではないはずです。
『学問のすすめ』を読んでいると、福沢諭吉は度々孔子の言葉(論語)を引用しています。
おそらくお気に入りの本なのだと思いますが、福沢諭吉ほどの知識人からしても論語は素晴らしい書物なのでしょう。
そう考えた場合、ビジネスパーソンは論語も読んでおくべきでしょう。
なので、まだ論語を読んだことがない人は、是非一度手に取ってみてください。

もし本を読んでいる時間がない場合には、論語の名言集を見るだけでも良いと思います。
続きは下の記事でご覧ください。