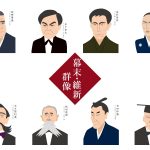吉田松陰といえば明治維新に影響を与えた人物ですよね。
重要な立ち位置にいた長州藩士でもある為、その思想は学問的にも注目されています。
そこで今回は、明治維新の精神的指導者であり理論家でもある吉田松陰の名言をまとめてみたいと思います。
多くの維新志士に影響を与えた思想や、志の持ち方、夢の実現方法など実用的な名言をたくさん残しています。
現代ビジネスにも通じる言葉ばかりなので、「松下村塾(しょうかそんじゅく)」の塾生になった気持ちでご覧ください。
吉田松陰の思想とは?
吉田松陰は「天才思想家」と言われていますが、若い頃はとても大人しい人物だったと言われています。
物腰は柔らかく、非常に謙虚な青年だったのです。
しかしその内側には、燃えるような闘志を秘めた人物だったと言われています。
「読書をせよ。だが学者になってはいけない。勉強は知識を得るためのものであり、人は行動することが第一である。」
これは松下村塾の門下生達に対して、口酸っぱく言っていた言葉ですが、吉田松陰はとにかく行動することを推奨しました。
大事を成し遂げるためには、議論よりも行動することを勧めたのです。
「至誠の精神」こそが本質
吉田松陰を語る上で外せないのは「至誠」に関してでしょう。
至誠は「真心」を指す言葉で、吉田松陰が自らの根幹と位置づけた精神的なよりどころです。
松陰は性善説に基づいて「人間には本来悪い人間などいない」という考え方だったのです。
その上で「誠」を大切にして「人は唯一、誠が大切であり、誠をもって父に仕えれば孝となり、君主に仕えれば忠となり、友と交われば信となる。極まるところは、つまり”至誠”である」と述べています。
誠の精神こそが、吉田松陰の考え方の軸となっているのです。
ちなみに、同じく「誠」を背負った幕末の志士といえば新選組ですよね。
新撰組も「誠」を掲げましたが、それは武士への憧れや、心意気を表しているようです。
例えば「誠」という言葉を解体すると「言」と「成」に分かれますよね。
このことから「言ったことは必ず成し遂げる」という意味合いになり、「武士に二言はない」という精神に通じていったのです。
吉田松陰の名言集
志を立てて以て万事の源と為す。
「維新志士」という言葉があります。
この言葉に出てくる「志士」とは、高い理想を持って、どんな境遇に陥ったとしても節操を変えない人のことを言います。
つまり、志を実現させるためであれば、自分が死ぬことはいとわず、むしろ本望だと感じるのです。
だから武士にとって戦場で討ち死にすることは、元々望んでいることであり、いつ主君から死刑を言い渡されても大丈夫という心構えができていたのです。
このような志さえあれば、それは信念となり、強烈な行動力に結びついていくはずです。
必ず成し遂げるという「誠の志」がなければ、何事も成し遂げられないのです。
学は、人たる所以を学ぶなり。
この名言は「学問とは、人とは何かを学ぶ為のものである」という意味です。
吉田松陰にとって学問とは、自分を見つめてその本質を知り、変化する時代を着実に読み取って、自分が社会に対して何ができるのかを考える道しるべになっていたのです。
そう考えた場合、この名言の意味が良く理解できますよね。
読書は最も能く人を移す。
畏るべきかな書や。
吉田松陰は読書することについて、「およそ読書は物事の要所を掴み取ることが重要である。まとまりがなく、いい加減にすれば、書物の本意を捕らえられない。」と述べています。
さらに、ただ本を読むだけではなく、その内容を頭で咀嚼して、重要なところを書き写しながら読むことを推奨したのです。
読書の効果を「畏(おそ)るべきかな」と表現したのです。
士の道は義より大いなるはなし、義は勇に因りて行はれ、勇は義に因りて長ず。
この名言は、武士道の真髄を明確に言い表した言葉として有名です。
吉田松陰は「武士の道にあって最も大切なのが義である。義は勇によって達成でき、勇は義を知ることで成長し、ますます勇気を出させる。」と述べています。
この思想は、古代中国の偉人 孔子が残した「義を見てせざるは勇なきなり」という言葉に通じるところがあります。
多くの知識を吸収した賢人だからこその結論なのでしょう。
孔子の考え方が理解できる名言集は下の記事をご覧ください。
武道の眼目は大丈夫となることなり。
この言葉は「武道の主眼は立派な男になることだ」という意味です。
武士道と聞くと、なんとなく強くて勇ましい男を目指すイメージがありますよね。
しかし武芸だけでなく、学ぶことも同じくらい重要だと吉田松陰は位置づけたのです。
ただ強いだけでは倫理観が伴わないので、人間としては未完成だと考えたのです。
人賢愚ありといえども、各々一、二の才能なきはなし。
湊合して大成する時は必ず全備する所あらん。
吉田松陰は言います。
「人には賢い者と愚かな者がいるが、誰にでも一つや二つの長所はあるものだ。その長所を伸ばせば、いずれ必ずや立派な人になれる。」
自分の不得意な部分を頑張っても、決してプロフェッショナルにはなれません。
人よりも優れた人間になるためには、自分の得意な部分だけを伸ばせば良いのです。
人の話を徒らに聞かぬ事と、聞いた事見た事、皆書き留め置く事、肝要の心得なり。
見たことや聞いたことの本質を理解するためには、それを自分の中でまとめなければいけません。
つまり自分の頭で考えて咀嚼するのです。
要点を掴んだ文章を書き留めておけば、それを翌年見ることができますよね。
すると前年に書いたものが愚かに見えるはずです。
それはあなたが成長している証なのです。
吉田松陰はこのような行動を推奨していました。
人の精神は目にあり。
故に人を観るは目に於てす。
「死んだ魚のような目」という表現がありますよね。
これも同じく人の精神は目に宿ることを表しているのです。
目を見ればその人がどんな人か大体理解できるのです。
境の順なる者は怠り易く、境の逆なる者は励み易し。
この名言にはほとんどの人が同感すると思います。
これは「順調なときほど怠けやすく、逆境ほど努力しやすい」ことを表現した名言です。
物事が順調にいっている時は、誰でも安心してしまいますよね。
恵まれた境遇にある人は保身ばかりを考えて、努力するのを怠ってしまうのです。
しかし不遇な境遇にある人は、現状を打破しようとして一生懸命に頑張ります。
なので、物事が順調にいっている時こそ、一番危険な状態なのです。
何ぞ深く性善の地に思ひを致さざるや。
「人の本性は善であること」
これは吉田松陰が性善説に基づいていたことを表す名言だと思います。
人間は生まれたばかりの頃、つまり赤ちゃんや未就学児なのに自ら進んで悪事を企てる人はいません。
もし大人になって悪事を働いたとしたら、それは成長する環境に問題があったり、周囲の人間に影響されている可能性が高いのです。
人間は善人にも悪人にもなれるのですが、人間の本性は善であることを理解して欲しいと説いているのです。
大抵小人の恥づる所は外見なり。
君子の恥ずる所は内実なり。
小人とは人格が低くくだらない人のことを言い、君子とは学識・人格に優れた人のことを言います。
その二人を比較してみると、小人は上辺だけを気にして生きていますが、優れた君子は内面を磨くのです。
学者になってはいかぬ、人は実行が第一である。
何よりも行動することを重要視する吉田松陰らしい名言だと思います。
松下村塾の門下生から「実行という言葉は松蔭先生の口癖だった」と言われるほど、日常的に行動することを推奨していたのです。
さらに吉田松陰は次のようにも言っています。
「知を学問で得ても、行いを廃した知は真の知ではない。また行いばかりにとらわれ、知を廃する者も真の行いではない。」
行動することを推奨しているのですが、それと同時に知識を蓄えることも推奨しているのです。
己を以って人を責むることなく、一を以て百を廃することなく、長を取りて短を捨て、心を察して跡を略らば、即ち天下いづくにか住くとして隣なからん。
この言葉は「自分の価値観だけで人を攻撃せず、ひとつの失敗だけで全てを判断せず、相手の長所を取り上げ短所を見ないようにして、相手の心を察して結果が悪くても許せば、世の中どこへ行っても人は慕って集まってくる。」という意味の名言です。
他人を否定するのではなく、認めるようにすれば、自分も相手から認められるのです。
仁義同根にして、遭う所に因りて名を異にするのみ。
父子には仁と云ひ、君臣には義と云ふ。
この言葉は「仁と義は根っこが同じであって、出くわす場所によって呼び名が変わっているだけである。」という意味の名言です。
仁とは「親しみ」を意味していますが、義は君主に対しての「忠義」を意味しています。
両方とも根底には「至誠」があるのです。
兵を学ぶものは経を治めざるべからず。
兵とは「兵法」を意味して、経とは「経学」のことを意味しています。
つまり兵法だけを学んでしまうと、単なる暴れん坊になってしまうので、それと同時に道徳観や倫理観も学ばなければいけないという教えです。
武士には強さだけでなく、高い品格も要求されたのです。
地を離れて人なく、人を離れて事なし、人事を究めんと欲せば先づ地理を見よ。
兵学者にとって、地形を読み解くことは作戦を立てる時の基本だと言われています。
なので、吉田松陰は松下村塾の塾生に対して「大事を成し遂げたいなら、まず地理を見なさい」と教えていたのです。
当時、地理の大切さに気付いていた人はごくわずかだったと言われています。
武士たるものは行住坐臥常に覚悟ありて油断なき如くすべしとなり。
この言葉は「武士は普段から覚悟して、油断してはならぬ」という意味の名言です。
つまり「油断は禁物」ということです。
武士道においては覚悟が重要だと言われていますが、そのような覚悟を持った人は君子に対する忠誠心も強いはずです。
武士は一歩家を出れば、いつでも死ぬ覚悟ができていたのです。
平時直諫なくんば、戦に臨みて先登なし。
諫言(かんげん)とは、主君に対して意見することを言います。
当時それはもの凄く勇気がいることで、相手の気分次第では即死刑を言い渡される可能性すらありました。
なので、諫言できる人はとても勇気のある人だったのです。
この名言で、普段から主君に諫言できない人は、いざ戦になった時、真っ先に敵陣に切り込んで手柄を立てることなどできないと戒めたのです。
体は私なり、心は公なり。
体は自分でコントロールできるので、もちろん自分のものだといえます。
しかし必ず死を迎えてしまいます。
それに対して、心が死ぬことはありません。
吉田松陰が松下村塾で伝えた言葉は、たとえ松陰が死んだとしても塾生に受け継がれていくのです。
そう考えた場合、心は時間軸を超えて存在するので「公」だと言えるのです。
山は樹を以て茂り、国は人を以て盛なりと。
山は樹木が青々と茂ってこそ美しいように、国は優れた人材がたくさんいるほど繁栄していきます。
吉田松陰は、優れた人材登用こそが、国力を上げるための基本であると考えていたのです。
同じような言葉ですが、吉田松陰は以下のようにも言っています。
「水に流れの源があり、木には根っこがある。これがなければ水は涸れ、木は枯れる。国にとって人は水源であり木の根である。」
同じように、戦国武将の武田信玄も下のような名言を残しています。
「人は城、人は石垣、人は堀」
リーダーを目指す人は知っておくべき名言だと思います。
明主に忠有るは珍しからず、暗主に忠なるこそ真忠なれ。
吉田松陰の時代は、生まれた土地が生涯の地であり、藩主を選ぶ権利などありませんでした。
なので、中には暗愚な主君もいたはずです。
しかしそのような逆境に動じず、自分の主君に対して忠義を貫くように諭したのです。
一日に一事を記せば、一年中に三百六十事を得ん。
一夜に一時を怠らば、百歳の間三万六千時を失はん。
この言葉は「1日に何か一つを学べば、一年で360の知識を得ることができる。一夜で1時間サボれば、100歳まで生きたとして3万6千時間も失う」という意味の名言です。
3万6千時間とは「約四年間」なので、塵も積もれば山となるのです。
サボらずおごらず努力し続けましょう!
天下は天朝の天下にして、乃ち天下の天下なり、幕府の私有に非ず。
この言葉は「天下は天皇のもので、幕府のものではない」という意味の名言です。
ペリーの黒船来航に衝撃を受けた吉田松陰は、尊皇倒幕の道を選びます。
これは松陰の立場を明確にする、歴史的にも重要な言葉だと言われています。
征夷は天下の賊なり。
今措きて打たざれば、天下万民其れ吾れを何とか謂はん。
幕府がアメリカと日米修好通商条約を結んだことに対して、吉田松陰は激怒します。
それをきっかけにして「革命家 吉田松陰」となり、過激な道に進んでいったのです。
身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂。
この言葉は吉田松陰が死刑になる前日に書いた一文なので、ある意味では松陰の遺言とも言えます。
この言葉の意味は「私が処刑されて、この体は武蔵の野辺に朽ち果てようとも忘れないで欲しい、僕が抱き続ける日本人としての確固たる精神である”大和魂”を」ということです。
日本の将来を案じ、日本という国に対して至誠を尽くした吉田松陰が残した名言です。
心あれや人の母たる人達よかからん事は武士の常
これは吉田松陰が妹たちに送った言葉です。
自分は死刑になるという状態でしたが、「不幸は突然やってくるので、武士の妻であるなら覚悟しておきなさい」と諭したのです。
身内に対する松陰の優しさが感じられる名言だと思います。
まとめ
吉田松陰は「人を動かす天才」と賞賛されていますが、その生涯はたった30年という短いものでした。
たくさんの名言を残していますが、松下村塾で教えたのもたった2年9ヶ月に過ぎないのです。
短い人生でしたが、それでも幕末を代表する偉人として、長州藩を引っ張った知識人として、吉田松陰が残した名言は今でも語り継がれています。
吉田松陰という人物がいたからこそ、明治維新という大事が成し遂げられたのでしょう。
人生に役立つ言葉ばかりなので、幕末の名言もぜひご覧ください。