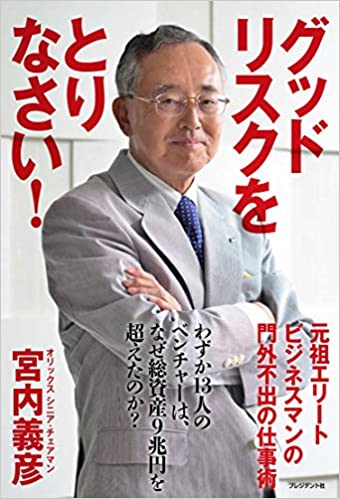
宮内 義彦(みやうち よしひこ)は、オリエント・リース株式会社(現:オリックス株式会社)を大企業に育て上げた立役者です。
オリックスといえば、プロ野球球団「オリックス・バファローズ」を持っていることでも有名ですよね。
そもそもオリックスという会社は、リース事業の成長を見越して、現在のみずほ銀行や三井住友銀行などが共同で設立した事業会社です。
ちなみにオリックスという社名は「オリジナル(original)+エックス(X)」を掛け合わした造語みたいです。
オリックスは創業当時から資本金1億円という企業でしたが、そのメンバーはわずか13人での立ち上げでした。
つまり、ジョイントベンチャーだったのです。
ジョイントベンチャーとは、複数の企業・組織が互いに出資し、新しい会社を立ち上げて事業を行うことです。合弁企業(事業)、共同企業体などということもあります。
資本金1億円でもリース事業ではお金が足りず、金策には相当苦労したそうです。
そのような状況で才覚を現した宮内義彦は、生粋のベンチャー企業の経営者だったと言えるでしょう。
そこで今回は、宮内義彦の名言集をご紹介していきたいと思います。
中小企業の経営者、事業責任者、ベンチャー企業に勤めている方などは是非ご覧ください。
宮内義彦の経歴(略歴)
1935年 兵庫県神戸市に生まれる。
1958年 関西学院大学商学部卒業
1960年 ワシントン大学経営学部大学院で MBA 取得、日綿実業(現双日)へ入社
1963年 オリックス立ち上げのため、アメリカの大手リース会社「USリーシング」で3か月間の研修を受ける
1964年 日綿実業からオリエントリース(現オリックス)へ出向(立ち上げメンバーとして参画)
1970年 オリックス取締役に就任
1980年 オリックス代表取締役社長(グループCEO)に就任
2000年 オリックス代表取締役会長(グループCEO)に就任
2014年 オリックスのシニア・チェアマン就任

宮内義彦の名言集まとめ
企業はトップで決まります。
特に中小企業では、経営者が重要な役割を担っています。
宮内義彦は「一般的にはトップの才覚の範囲でしか企業は大きくなりません」と語っていますが、個人的には「どの分野の事業をやるのか?」の方が重要だと思っています。
もちろん「市場を創造する」というアプローチもありますが、一般論としてはマーケットが小さいビジネスであれば、どんな優秀なトップであってもビッグビジネスにすることはできません。
これから独立起業する人は、「どの分野で戦うのか?」というのを慎重に見極めましょう。
自らを脱皮させる有効な方法の一つは、自分より優秀と思う人物とできるだけ交流することです。
これも多くの偉人が同じような名言を残しています。
自分より優秀な人と付き合えば、視点が高くなってきます。
反省するポイントも多くなってきます。
しかし、自分よりも劣る人物と付き合っても、向上心が保てないので、相対的に退化するしかありません。
旧友は大切ですが、日頃付き合う人は、自分のレベルに応じて変えていくべきだと思います。
学ぶ姿勢の強い経営者の方は、大きな成功を収めています。
宮内義彦は「勉強会に参加すること」を推奨しています。
もし時間がないのであれば「ゴルフの時間を削ること」だと語っています。
経営トップがどのような素晴らしいビジョンを示しても、社員が共感し面白みを感じて働いてくれなければ、成功の確率は高まりません。
これは”人を動かす難しさ”について語った名言です。
中小企業の経営者は社員との距離が近いので、常に見られる存在だと思います。
なので”魅力ある人間性”が必要だと宮内義彦は語っています。
中小ベンチャー企業の経営者は、組織を整える意識よりも、何かにチャレンジする起業家精神を強く保って欲しいと思います。
中小ベンチャー企業は、動き続けなければすぐに死んでしまいます。
最初のうちは綺麗にビジネスできないので、ある程度の泥臭さがあっても良いと思います。
必死でもがいている姿を社員は見ているので、それに奮起されて会社内のモチベーションも上がることでしょう。
中小企業は、大企業の”卒業生”である退職者をもっと活用した方が良いと思います。
大企業に就職する人は、一般的に”優秀な人”が多いので、使い方次第では大活躍してくれるはずです。
なぜ「使い方次第では」と言ったのかといえば、大企業は分業制なので、大企業を退職した人は『ある特定分野に強くても、他の部分には弱い』という傾向があるからです。
しかし地頭が良かったり、専門知識を持っていたりするので、使い方次第では重宝することでしょう。
緊急時にこそ活躍する社員は必ず現れます。
会社経営はいつも順風満帆というわけにはいきません。
必ず緊急時は訪れますが、そのたびに活躍する社員が出てきてくれるそうです。
まさに「ピンチはチャンス」ということでしょう。
「この人はこういう性格で力はこの程度だ」という判断は、思い込みで見間違えていることもあるのです。
思い込みや色眼鏡で社員を見ない方が良いと思います。
なぜかといえば、人間(社員)は常に成長していくからです。
自分の思い込みは変わりませんが、人間の中身は成長していくので、固定観念で見ることはやめましょう。
経営における借り入れは「会社の資産の範囲」あるいは「会社の実力の範囲」を肝に銘じてほしいと思います。
経営者の大事な仕事の一つは”資金調達”ですが、「無理な資金調達は止めるべき」だと宮内義彦は語っています。
自宅を担保にしたり、個人保証をして極限まで借りるようなやり方はおすすめしないそうです。
あくまでも”生きるための手段”としてのビジネスなので、事業のために生きているのではないからです。
このような考え方はとても金融屋っぽいですよね。
経営のプロはあくまで経営者であり、コンサルタントよりも専門家なのです。
経営者が外部のコンサルタントに意見を求めるのは良くある話ですが、コンサルタントの話をすべて鵜呑みにしてはいけません。
悩んだ時に「○○だと考えているが、どう思うか?」とコンサルタントへ質問して、その答えはあくまでもアドバイス程度に受け入れ、最終判断は自分自身が下すのです。
コンサルタントの操り人形になっている”お飾り経営者”なんていりませんよね。
その一方で、コンサルタントの意見を鵜呑みにして事業を成長させたのが、「ホームファニシング」を掲げるニトリです。
創業者の似鳥昭雄は勉強が苦手なので、素直な気持ちでコンサルタントの意見を聞けたそうです。
コンサルタントの言う通りにして成功する例は珍しいですが、ニトリ創業者の名言集は下の記事をご覧ください。
企業のトップには、悪い情報がなかなか入らないものです。
このようになってしまうロジックは以下のような流れで発生します。
- 営業マンが客先でのトラブルを課長に報告
- 課長は評価を下げたくないので、「些細なトラブルがあった」と小さく部長に報告
- 部長は些細なトラブルなので、担当役員には報告せず
- 担当役員は「全て順調です」と社長に報告
このようなリレーでトラブルを放置して、重大事故へとつながってしまうのです。
「私は知らなくてもいい。各々が持ち場でしっかりやってくれているはずだ。」
このくらいの気持ちの余裕が持てると、熟練経営者と言えそうです。
なんでもかんでも現場に首を突っ込んだり、粗探しをするような経営者は、ただ仕事の邪魔をしているだけです。
もっと社員を信頼するべきだと思いますが、それが出来ないということは仕組みが不完全なのでしょう。
社員に頼り切るのは属人的なので、それを仕組みでカバーすることをオススメします。
会社のトップは極めて孤独であると思います。
社員からは常にリーダーシップを求められ、社外の人と交流しても迂闊に悩みを打ち明けることができません。
やはり経営の意思決定は社長自らがしなければいけないのです。
社長のお墨付きが欲しい幹部や社員の場合は要注意です。
部下から「このような案件があるのですが、どうしましょうか?」と聞かれたとします。
それに対してうっかり「それは面白そうだからやってみたら。」と言ってしまうと、会社内では「社長命令の案件」として伝わってしまいます。
もし失敗した場合には、社長の責任にすり替わる可能性もあります。
お墨付きを求める社員には注意しましょう。
攻める場合には社長が「突撃」と号令をかけて、社員を引き連れて攻めていくことが成功への理想型だと思います。
大事な局面では個別具体的な指示を出しましょう。
小さい会社ほどリーダーシップが求められるはずです。
リーダーシップについて学びたい場合には、下の記事を参考にしてください。
トップはつらい時に指揮をとる人、このように表現できるかもしれません。
逆に好景気の場合、リーダーは肝心なところさえ押さえていれば、あとは寝ていても良いと宮内義彦は語っています。
気をつけないといけないことは、ライバルを”仮想敵”にすることです。
「ライバルに勝つこと=事業が成長すること」という方程式は、必ずしも一致しません。
宮内義彦は「仮にリース事業で負けることがあっても、当社は他社がやっていないことで成長している」という自負があったので、特に焦ることはなかったそうです。
ライバルばかりに目がいくと目的がズレてしまうので注意しましょう。
他社をベンチマークにすると、面白い会社が作れなくなる。
競合他社を基準にするのではなく、顧客目線で考えるべきだと思います。
- このサービスがあれば喜ばれる
- このような製品は顧客ニーズがある
自社の製品サービスが社会に貢献して、世の中に受け入れられることが大切なのです。
役職員の結束を精神面で築くことができれば、職場の雰囲気は大きく変化するはずです。
現代は多様性が重要視される時代なので、気軽に飲みニケーションできませんよね。
物理的に集まることが難しいので、そんな時には精神面での結束を重視しましょう。
経営の本質は、人と人とのつながりにある。
これは小手先の「組織論」や「戦略論」に惑わされないことを諭した名言です。
会社を動かしているのは”人”なので、それだけは忘れないようにしましょう。
「できる」と評価されている社員でも、案件や状況によって満点の仕上がりだったり、80点の出来栄えだったりするものです。
仕事を部下へ任せっきりにするのではなく、サポートしたりフォローするのを忘れないようにしましょう。
企業経営についてはつい大企業と中小企業で比べがちですが、肝心なことは規模ではなく、社内のエネルギーがどちらに向いているのかにあると思います。
「大企業だから余裕がある」とか「大企業だからビジネスしやすい」と考える人が多いですが、宮内義彦はそれを否定しています。
結局はがむしゃらに働いて、社員の目指すべき方向が一致していなければ、そのビジネスが成長することなど無いのです。
後継者選びは極めて重要ですから、早くから手を打つことが欠かせません。
後継者選びのポイントを宮内義彦は以下のように語っています。
- 自分と比べて秀でたものを持っている人
- 自分にはないものを備えている人
- 広い経験を持っている人
これらをまとめて「自分よりも上だと思える人」を後継者にするべきだと語っています。
企業が成長とともにパブリックの存在になっていくことは、日本企業の伝統であり、発展を支えた要因の一つでもあります。
「企業は社会の公器である」と語ったのは、パナソニック創業者の松下幸之助です。
松下幸之助の名言集は下の記事をご覧ください。
起業自体に満足しては、会社としての成長はできないということです。
小さな起業はあくまで小さい経営に過ぎず、家業が生まれただけで事業とは異なります。
起業と似た言葉に「独立」や「開業」があります。
小さい起業の場合には「独立」や「開業」と言った方が正しいのでしょう。
ベンチャーは、少なくとも二段階続けて成功させる覚悟で取り掛かってほしいものです。
ベンチャー企業は、ある特定分野での勝負を仕掛けるはずです。
しかしそこで勝つだけでは、まだ市場規模が小さいので、横展開を図らなければいけません。
例えば立ち上げた求人サイトが上手くいった場合、それに付随した採用管理ツールをリリースするイメージです。
小さな成功、小さなセグメントでは大成できないので、すぐにその周辺分野への展開を考えましょう!
ベンチャー経営者は少し背伸びしてでも、色々な所へ出入りして、付き合いを広げていくことが大切です。
これはベンチャー経営者として、とても共感できる名言です。
ビジネスは「人×人」なので、とにかく色々な会食へ顔を出した方がいいと思います。
しかし、夜の会食は時間&予算無制限になりがちなので、できればランチ会食を活用しましょう。
ランチであれば1時間ほどなので、費用対効果が高くなるはずです。
経営について学ぶべき事と言えば、まず経営の概念や組織論から始まって次に財務の知識でしょう。
さらに学ぶべきことはいかに”人を動かす”かです。
企業経営するためには、財務や経理など”資金に関する知識”は必要不可欠だと思います。
これはファイナンシャルリテラシーに関わる話なので、まずは「金持ち父さん貧乏父さん」などライトな本から読んでいきましょう。

そして人の動かし方に関しては、デール・カーネギーの「人を動かす」という名著があります。
まだ読んでない人は一度手に取ってみてください。

自分の目で広い世界の現実を見てください。
世界を見て回ることは、視野を広げることになります。
視野を広げるデメリットはゼロなので、積極的に見識を深めていきましょう。
自分の頭で考えることがベンチャー精神を創り上げる第一歩となるはずです。
日本は横並び精神の強い国です。
なので「出る杭は打たれる」とか「空気を読む」という言葉あるくらいです。
しかし常識を疑わなければ”イノベーション”など起こせないので、事業責任者は注意しましょう。
社長は常に自制して、自重して、なおかつ責任感を持って、思い切り仕事をすることが大切です。
社長という肩書きに奢ってはいけません。
社長は人事権を持っているので”権力者”だと勘違いする人は多いですが、決してそんなことはありません。
仕事上の役職はありますが、それは対外的なものなので、会社内ではフラットな関係であるべきだと思います。
事業は顧客の要望によって変化していきます。
これは「環境の変化に対応する」とも言えるはずです。
顧客ニーズの変化を的確に捉えることが重要なのだと思います。
経営者の方にはぜひ自身の経験や思考から自らの経営哲学や指針を固めてほしいと思います。
企業経営にセオリーはありますが、決して正解はありません。
その場その時の最適解を導き出すだけです。
しかし、その最適解を導き出すためには、筋の通った”経営哲学”と”経験値”がなければいけません。
なので経営者は色々な経験をして、たくさん読書するべきだと思います。
大企業経営者(CEO)の名言集もぜひ参考にしてください。

































