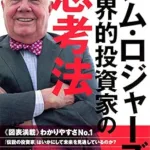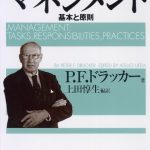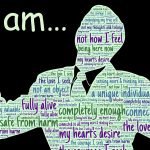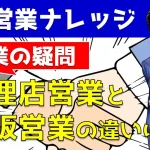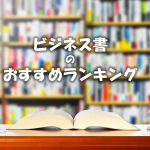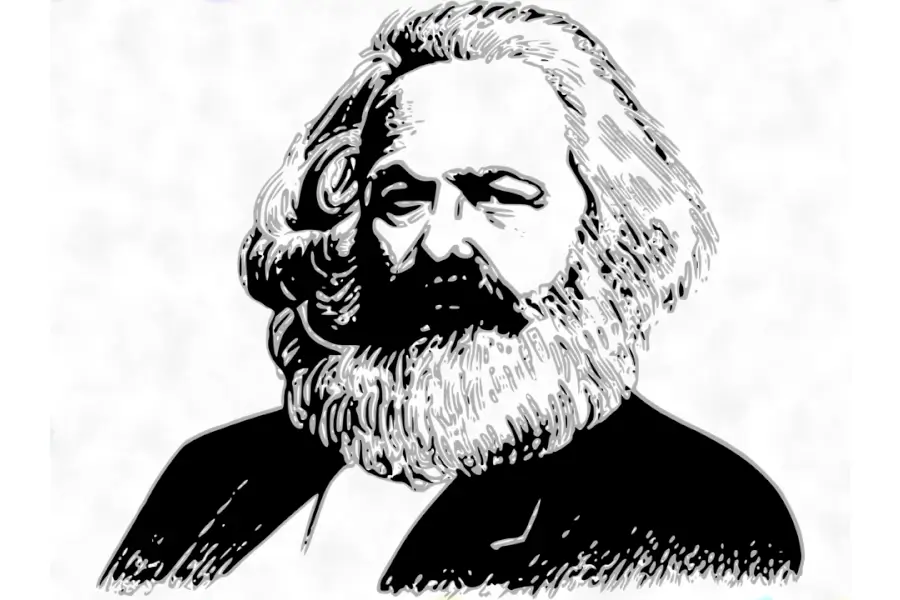
ドイツが生んだ経済学者といえば『カール・マルクス』ですよね。
「資本論」は名著と呼ばれているので、ビジネスパーソンであれば必ず読んでおくべきでしょう。

しかし資本論は「最も難解な書物の一つ」と言われているので、なかなかとっつきにくいですよね…
そこで今回は、カール・マルクスの名言集をご紹介したいと思います。
これを見れば”マルクスの基本思想”が理解できるはずなので、ぜひ最後までご覧ください!
カール・マルクスの名言まとめ
出来高賃金は、一方で資本家と近隣労働者との間に寄生者が入ること、すなわち仕事の請負を容易にする。
<参考書物:資本論>
これはビジネス界隈における「中抜き(ピンハネ)」を批判した言葉です。
中抜きが必要なケースもありますが、基本的には”害悪”でしかないので、マルクスは中抜きする人のことを「寄生者」と批判したのです。
ローマの奴隷は鎖によって、賃金労働者は見えざる糸によってその所有者に繋がれる。
<参考書物:資本論>
マルクスは「資本主義経済における労働者は奴隷と同じだ」と主張しています。
その様子を現代では「社畜」と表現していますよね。
労働者の場合、資本家が儲ける時、必ず儲かるとは言えないが、資本家が損をする時には、必ず損をする。
<参考書物:経済学・哲学草稿>
会社員として働いている人は、この事実に気づいているでしょうか?
実は、賃金労働者のリスク&リターンはバランスが崩れているのです。
労働が分割され始めると、各人はある特定分野にだけ留まるように強いられ、そこから抜け出すことができなくなる。
<参考書物:ドイツ・イデオロギー>
セールスの人はずっと営業畑で働いて、経理に配属された人はずっと経理部で働く…
もちろんOJTする会社もありますが、中小ベンチャー企業ではこれが普通ですよね。
しかしこれは、経営者にとって非常に都合が良い仕組みだと言われています。
分業制にすれば、全ての仕事を一人でできない労働者ばかりになるので、その人が独立したり、競合他社になる可能性も下がるのです。
つまり労働を分割するというのは、『労働者を”見えない糸”で縛り付ける為の仕掛け』ということになります。
機械労働は神経を極度に疲弊させ、筋肉の色々な動きを阻害し、肉体と精神のあらゆる自由な活動を奪う。
<参考書物:資本論>
どうやらマルクスは機械化(オートメーション)に否定的だったようですね。
現代はIT社会なので、たくさん便利なツールが提供されていますが、それで生産性が上がって、果たして従業員の給与は増えたのでしょうか?
逆にリソースが余ったせいで、余計な仕事が増えて、さらに忙しくなりましたよね。
実は『IT化によって恩恵を受けているのは資本家だけ』という事実を忘れてはいけません。
貨幣が資本へ転化するのはなぜかというのは、商品交換に内在する法則の上で議論すべきである。
<参考書物:資本論>
学が無い人は、お金を欲しがりますよね。
しかしお金は”単なるツール”でしかありません。
マルクスは「資本主義においては、全てのものが商品となる」と語りました。
つまり”お金”すら商品となり得るのです。
お金に価値を感じている人は、まず「購買活動とは商品交換である」という概念を理解する必要があるでしょう。
資本はアダム・スミスが言うような労働に対する指揮権にあるのみではない。
むしろ本質は、不払い労働に対する指揮権である。
<参考書物:資本論>
アダム・スミスは「経済学の父」と呼ばれるイギリスの偉人です。
その著書である国富論は、ビジネスパーソンが必ず読むべき経済名著だと言われているので、まだ呼んでいない人は必ず読んでおきましょう。

マルクスの言葉はなかなか難しいので、理解する為に例え話でご説明したいと思います。
例えば、資本家が原価@20円のパンを、労働者に80円支払って製造するとします。
出来上がったパンが110円(110円-100円=10円の利益)で売れれば儲かりますが、もし「100円でしか買わない」と消費者全員が言ったらどうなるでしょうか?
もちろん資本家は儲かりませんよね。
そのような状況になった場合、資本家は労働者にサービス残業を強いるようになります。
つまり労働者を過剰に働かせることによって、支払う給料を相対的に80円⇒70円へと下げて、その分を利益とするのです。
このようなマネジメント方法を教える人のことを、世の中では「コンサルタント」と呼んだりしています。
肩書きは立派ですが、実はコンサルタントは『経済学上では労働者の敵(=経営者の味方)』だと言えるのです。
資本がまるで吸血鬼のように元気になるのは、生きた労働者を吸い取る時だけであり、多く吸えば吸うほどますます元気になる。
<参考書物:資本論>
資本主義社会において、労働者は資本家から”吸血”されている状態なのかもしれません。
このように聞くと、資本主義という仕組みがとても不気味に思えてきます。
一方に労働条件が資本として現れ、他方に自分の労働力以外には売るべきものを持たない人間が現れるだけでは十分ではない。
<参考書物:資本論>
「時給1200円」「月給20万円」というような労働条件が提示され、それに応募するのは『労働者として働くことしかできない人たち』です。
そして労働者は見えない糸で繋がれ、いつまでも死ぬまで吸血される…
まさに資本主義は弱肉強食の世界ですよね。
株式投機ではいつか自分に雷が落ちると分かっていても、自分だけは黄金の雨を受け続け、それを安全な場所へ持って行き、雷が落ちるのは隣人であると期待するのである。
<参考書物:資本論>
誰でも「自分だけは違う」と思いたいですよね。
しかし現実はそんなに甘くありません。
資本主義の申し子と言える、世界的に有名な投資家といえば、ウォーレン・バフェットとジム・ロジャーズですよね。
バフェットは「オマハの賢人」と呼ばれていて、世界有数の資産家になっています。
ジム・ロジャーズはジョージ・ソロスと一緒にファンドを立ち上げ、10年間で4200%という驚異的なリターンを叩き出しました。
株式投資を学びたい人は、2人の名言を参考にしてください。
国家権力は新しい社会をはらむ、古い社会全ての助産婦である。
<参考書物:資本論>
株式相場の格言に「国策に売りなし」というものがあります。
それほど国家の権力は強いものなので、ビジネスパーソンは「国の戦略はどこを向いているのか?」というのを都度確認しましょう!
机はもはや自分の足で床に立つだけではなく、他のすべての商品に対して頭で立っている。
<参考書物:資本論>
机は床に立ちますよね。
その一方で、「この机は○○円だ」「この机はソファーより高い」とか、人間は頭で考えますよね。
資本主義社会においては、このように「どれだけの価値があるのか?」という部分に集約されていくのです。
なんでもお金、お金、お金…
なんか嫌になりますよね。
貨幣は人間の欲求と対象との、人間の生活と生活手段との間の媒介項である。
<参考書物:経済学・哲学草稿>
お金には『価値を保管する』という機能があります。
例えば物々交換の社会では、魚を買う為に肉を差し出したりしますが、ナマモノは腐ってしまうので、それを避けるために”お金”というものに一旦価値を転嫁しておき、いつでも使えるようにしたのです。
どこから来ようと金になればそれでいいことだ。
<参考書物:資本論>
これはつまり「お金には色がついていない」ということです。
資本主義においては”儲けたもの勝ち”なのです。
ブルジョワジーの支配体制にいるものは、頭の中ではいつも自由である。
<参考書物:ドイツ・イデオロギー>
これはとても皮肉がこもった名言ですよね。
ブルジョワジーの支配にいるということは、労働者ということです。
ブルジョワジーとは、生産力の発展を背景として成長した、私有財産を所有する一定程度豊かな都市住民層のこと。
前述した通り、労働者は見えない糸で繋がれているので、本当は自由ではありませんが、頭の中で自由に考えることはできます。
このようなおかしな状態をマルクスは揶揄したのです。
人間は絶えず自然の力を借りている。
だから労働だけが、生産する使用価値の、すなわち素材的な富の、ただ一つの源泉ではない。
<参考書物:資本論>
マルクスは自然の恵みに感謝しているので、このような言葉を度々発しています。
フランスが生んだ有名な哲学者であるジャン=ジャック・ルソーも「自然に帰れ」と言いました。
ルソーが残した『社会契約論』はフランス革命にも影響を及ぼした”人類史における最重要書物の一つ”と言われているので、ビジネスパーソンは必ず読んでおきましょう。

人間が類的存在となるのは人権のおかげではない。
<参考書物:ユダヤ人問題によせて>
類的存在とは”社会に溶け込む”ことを意味しています。
人間には”人権”が与えられているので、一般的な社会生活ができていますよね。
しかし本来人間はわがままな生き物なので、ルールがなければ私利・私欲を追求するはずです。
そう考えた場合、人権という概念は『逆に人間を縛るためのもの』だと考えられます。
つまり人権を保障する代わりに社会生活を強いて、それによって人間本来の欲望を抑えつけるということです。
なんか哲学的ですよね。
欠乏とは、人間にとっての最大の富である他の人間を、欲求として感じさせる受動的環である。
<参考書物:経済学・哲学草稿>
他人に助けを求めたり、人と触れ合いたいと感じるのは、人間という存在が”不完全”だからです。
つまりそのような欲求は自然であり、当たり前のことだとマルクスは語っています。
泥棒、詐欺師、乞食、失業者、飢えた労働者、貧しい犯罪的労働者、こうした連中は国民経済学にとっては存在しない。
<参考書物:経済学・哲学草稿>
経済学において、仕事についていない人は”存在価値”を認められていません。
なぜかといえば、経済的な役割を担っていないからです。
このような人たちのことをマルクスは「亡霊」と表現しています。
ドイツの解放は人間の解放である。
この解放の頭脳は哲学であり、その心臓はプロレタリアートだ。
<参考書物:資本論>
プロレタリアートとは「労働者階級」のことを指します。
つまり労働者階級を解放するためには、哲学を学ぶ必要があるということです。
哲学は小難しいですが、興味がある人は下の名言集をご覧ください。
何をするにも初めが肝心という格言は、どんな学問にも当てはまる。
<参考書物:資本論>
頭の良いマルクスでも、何かを始める時にはやっぱり慎重になるみたいですね。
これまでの全ての社会の歴史は、階級闘争の歴史である。
<参考書物:共産党宣言>
支配階級がいると、いずれそこが腐敗するので、労働者階級が革命を起こします。
それを繰り返してきたのが”歴史”なのですが、そもそも資本家と労働者に分けてしまう資本主義という仕組みは、このような「階級闘争を生み出しやすい仕組みだ」とマルクスは指摘しています。
現代社会は、お金持ちが数兆円という資産を蓄える一方で、貧しい人はその状態から抜け出せなくなっていますよね。
このような状態をマルクスは予言していたのです。
ヨーロッパには亡霊がうろついている。
それは共産主義の亡霊だ。
<参考書物:共産党宣言>
マルクスは共産主義を推奨していました。
マルクスのように「共産主義にしたい!」という人たちがたくさんいることを”亡霊”と表現したのです。
どうやらマルクスは”亡霊”という表現が好きみたいですね。
共産主義と私たちが呼んでいるものは、現在の状態を止揚しようとする運動のことである。
<参考書物:ドイツ・イデオロギー>
これはマルクスが共産主義を定義付けした重要な名言です。
マルクスは「共産主義とは理想状態ではない」と語っています。
つまりマルクスに言わせると、共産主義とは”ある特定の仕組み”などではなく、『現在を変えようとする運動』のことなのです。
これは一般的な解釈と違うので、少し驚きがありますよね。
労働者には祖国はない。
<参考書物:共産党宣言>
労働者は使い捨てなので、資本家のように身を寄せるところ(会社や組織など)がないということです。
資本主義の闇をとらえた、とても恐ろしい名言ですよね。
世界のプロレタリアよ。
団結せよ。
<参考書物:共産党宣言>
現状を変えることができるのは、プロレタリア(労働者階級)しかありません。
だからこそマルクスは”共産主義”を主張していたのです。
これまでの歴史を振り返る限り、労働者階級が革命を起こし、世の中を変えてきました。
この言葉には「決して諦めるな!」というマルクスの強い意思が感じられます。
マルクスは歴史を動かした重要人物
ここまでマルクスの名言集をご紹介してきました。
マルクスの著書といえば「資本論」が有名ですが、友人であるフリードリヒ・エンゲルスと共に書き上げた「共産党宣言」も見逃せません。

共産党宣言は共産主義者同盟の綱領とも言える宣言文をまとめた書物です。
マルクスとエンゲルスが出会ったのは26歳の頃で、ひょんなことから意気投合して共同作業を開始しました。
しかしエンゲルスは資本家(経営者)だったので、いわゆるマルクスが批判する人種でしたが、そのような人物と一生涯付き合っていたというのは、なんか意外な事実ですよね。
マルクスは生涯をかけて「資本論」を書き上げましたが、残念なことに存命中は全く評価されず、暮らしは常に貧乏だったそうです。

しかしマルクス主義に共感したレーニンがソビエト連邦を創り、それを真似した毛沢東が中華人民共和国を設立し、その支援を受けて金日成が朝鮮民主主義人民共和国を設立しました。
よってマルクスは歴史を大きく動かした重要人物であることには間違いありません。
昨今でも、マルクス主義の唱えていたことが資本主義社会で徐々に現実となり、改めてマルクスが再評価される流れもあります。
よってマルクスはビジネスパーソンが必ず押さえるべき経済学上の重要人物だと言えますが、その一方で「経営学の父」と呼ばれるP・F・ドラッカーの理論も学んでおくべきでしょう。
ドラッカーの名言集は下の記事をご覧ください。