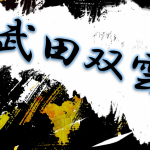鈴木敏文(すずきとしふみ)といえば『小売りのカリスマ』ですよね。
1963年にセブン&アイホールディングスの前身であるイトーヨーカドーへ入社して、そこからNo.2へとのし上がり、イトーヨーカドー創業者であり会社のNo.1だった伊藤雅俊が退任した後は、トップダウン型のリーダーシップを発揮しながら売上規模10兆円を超えるセブン&アイホールディングスを一代で築き上げました。
その経営手腕は世界的にも高く評価されており、鈴木敏文の考え方や実行力は「カリスマ」と呼ばれるのにふさわしいものばかりです。
そこで今回は、鈴木敏文の名言集をご紹介したいと思います。
独立企業を目指す人、ビジネスリーダーを目指している人はぜひご覧ください!
鈴木敏文の名言集まとめ
不仲なんてことは全然ない。
喧嘩も一度もしたことがない。
これはイトーヨーカドーの創業者であり、セブン&アイホールディングス創業者の伊藤雅俊との関係性について語った名言です。
売上10兆円を超えるセブン&アイホールディングスの前身は伊藤雅俊によって創られましたが、総会屋事件で退任した1992年以降は鈴木敏文が経営を任されています。
その頃の会社は少し傾いていた状態だったので、それを立て直し、今のセブン&アイホールディングスを創り上げたのは鈴木敏文だと言っても過言ではないでしょう。
実は両者には度々不仲説が流れていたのですが、「伊藤さんは僕がやることに「いいよ」ということがほとんどなかった」と鈴木敏文は語っているので、恐らくそれが原因なのだと思います。
実際に、鈴木敏文が「コンビニエンスストアをやりたい!」と言ってセブンイレブンの経営権を取得しようとした時、中国へ進出する時、セブン銀行を設立する時にも、伊藤雅俊は大反対したそうです。
しかし実際には強い信頼関係で結ばれていたみたいですね。
発想というものは、他人の意見を聞くことじゃないんだと、自分の人生を振り返ってみて僕は思う。
鈴木敏文は「類まれなるリーダー」だと評されますが、その強烈なリーダーシップはとても有名です。
実際には『かなりのワンマン経営』だったみたいですが、ことごとくビジネスをヒットさせて、周りを黙らせてしまうところは豪腕ですよね。
実績が伴っているので、その経営手腕には疑いの余地がないということです。
1号店を出す前に10人ほどいた幹部を前に、「史上最短で上場会社を作る」と宣言したんです。
鈴木敏文はセブンイレブンを日本へ誘致し、東京都江東区豊洲に1号店をオープンさせました。
「史上最短で上場会社を作る」と聞いた経営幹部たちはみんな笑ったそうですが、鈴木敏文は本当に史上最短(会社設立から6年)での株式上場を実現させたのです。
ヨーカドーは1年10店舗も出店していて、お金がなくて汲々としていたんです。
当時のスーパーマーケットビジネスは、金融機関から資金調達して不動産を購入、その不動産を担保にしてさらに出店するというやり方でした。
このやり方で急拡大したのが当時のダイエーですよね。
しかし結局そのビジネスモデルはバブル崩壊によって崩れ去ってしまいました。
そのようなやり方を選ばなかったイトーヨーカ堂は難を逃れたのですが、その様子を見ていた鈴木敏文は、米国セブンイレブンが基本としていた直営方式ではなく、資金調達のいらないFC(フランチャイズ)という日本独自の仕組みに切り替えたのです。
これがある意味ではヒットするきっかけになったのかもしれません。
江東区から一歩も出るな。
セブンイレブンジャパンの1号店は東京都江東区豊洲でした。
なので最初の頃は、物流効率などを考えて、限られた地域に出店を集中させる「ドミナント戦略」を推進したそうです。
そんなものは日本で根付くはずはないと言っていた。
大学のマーケティング教授なんかも誰一人として賛成しなかった。
コンビニエンスストアという業態について、経営者仲間や大学教授など、全ての人が「そんな事業が上手くいくはずない」と言ったそうです。
なぜかといえば、スーパーマーケットビジネスに劣る店舗規模と商品ラインナップ、しかも定価の商品ばかりが並んでいるお得感ゼロのお店なんか誰も使わないと考えたからです。
確かにそう聞くと、コンビニエンスストアは既存事業の劣後版に見えますよね。
しかし本当に成功するビジネスとは「99%の人が反対するビジネス」だと言われます。
まさにその通りの結果になりましたね。
これまでのPBはアメリカでも ヨーロッパでも安さを実現するためのものだった。
でも、時代は変わっているのに、過去と同じことをやろうとしてはダメだ。
セブン&アイホールディングスには「セブンプレミアム」というPB(プライベートブランド)があります。
これも鈴木敏文が周囲の反対を押し切って始めた事業なのですが、こちらも大成功を収めています。
一般的には”安さ”をウリにするのがPBなのですが、鈴木敏文は最初から”質”にこだわったので、これまでのPBとは全く商品設計が違ったそうです。
店舗が小さく、品揃えに限りがあるから、少しでも消費者の嗜好とずれると、途端に客足が遠のく怖さがあった。
これはコンビニエンスストアという小規模店舗ビジネスの怖さについて語った名言です。
このようなデメリットがある一方で、「店が小さいからこそ機敏に変化できる」というメリットもあるそうです。
まずは食べ物を中心とした商品で、どんどん新しいものを出していかなくちゃいけない。
セブンイレブンといえば、お弁当が美味しいことで有名ですよね。
この商品があるからこそお客様は店舗へやってくるので、食べ物の『フレッシュさ』は非常に重要だと語っています。
日本で成功している小売は、自主マーチャンダイジングしているところでしょう。
セブンプレミアムを開発しているセブン&アイホールディングスだけでなく、ユニクロやニトリ、JINSなど、成功している小売業は商品を自社開発しているところばかりです。
これは実績ありきの成功法則なので、小売業をしている方は成功者から学ぶべきだと思います。
ユニクロ創業者である柳井正の名言集は下の記事をご覧ください。
ニトリ創業者である似鳥昭雄の名言集は下の記事をご覧ください。
JINS創業者である田中仁の名言集は下の記事をご覧ください。
僕は銀行のことなんか何も知らない。
お金をATMでおろしたこともないくらい。
だけど、コンビニにATMを置いて、夜中でもお金の出し入れができたら便利だということはわかる。
これはセブン銀行を設立した理由について語った名言です。
セブンイレブンのキャッチコピーは「近くて便利」というものですが、まさにそれを体現したような発想ですよね。
僕は最近、トラックだってセブンイレブンで売ればいいじゃないかと言っているんです。
コンビニ事業への参入、セブン銀行設立、セブンプレミアムの開発など、周囲が「そんなの無理だ」と言うビジネスを、鈴木敏文はことごとく成功させてきました。
しかし「まだまだコンビニエンスストアは進化できる」と言っているので、経営の第一線から退いてはいますが、これから先のコンビニ事業に期待しましょう。
オムニチャネルの基本は、マーチャンダイジング、要するに商品開発なんです。
セブンイレブンは店舗ビジネスなので、商圏は限られていますが、インターネットであればその商圏が最大化します。
つまりリアルとネットの両方で売るのが正解ということなので、鈴木敏文はオムニチャンネル戦略を提唱していたそうです。
僕はセブンイレブンを作った時に、まず部下に言ったことは、絶対にイトーヨーカ堂の真似をしてはいけないということでした。
イトーヨーカ堂の業績は低迷していますが、そのビジネスモデルには入社当初から懐疑的だったようです。
なぜかといえば、スーパーマーケットに来るお客様は、たくさんある商品の中から『掘り出し物(割引商品)』ばかりを探していたからです。
ちゃんとしたマーケティングもしないのに商品を作っている。
在庫もしっかり見ていない。
企業を成長させるためにはマーチャンダイジングが重要であることはお伝えした通りですが、開発数量を誤ると大量の在庫を抱えるハメになります。
これは自社開発する際の諸刃の剣となりえるので、機会を最大化しつつ、在庫リスクも最小化する生産量を模索しなければいけません。
これが実現できた時、そのビジネスは飛躍的に伸びていくと語っています。
米国のセブンイレブンに学ぶものは何もなかった。
元々セブンイレブンはアメリカ発祥のブランドですが、そのやり方は直営方式でした。
それを日本独自のフランチャイズ方式に変更したのが鈴木敏文なのですが、これはいわゆるチェーンストアを意味しています。
しかしその一方で、ニトリ創業者の似鳥昭雄なども参考にした渥美 俊一が提唱する”チェーンストア理論”すらも「全く参考にならない」と一刀両断しています。
つまり鈴木敏文が創り上げた日本独自の”セブンイレブン”というビジネスは、世の中にない革新的な仕組みだったのです。
渥美 俊一の”チェーンストア理論”は小売業者の名著だと言われているので、まだ読んでいない人は是非ご覧ください。

日本のセブンイレブンが伸び続けているのは、消費者の変化に常に対応しているからだ。
これこそがセブンイレブンが勝ち続けられる秘訣みたいです。
顧客ニーズの変化、環境の変化など、ビジネスは常に変化しています。
そこに適応するだけなので、とてもシンプルですよね。
消費は経済学ではなく心理学の世界になった。
これはなかなか奥深い名言だと思います。
モノ余りの時代なので、消費者の財布の紐はきつくなっており、それを緩めるためには心理学を使わなければいけないということです。
経済学とは合理性を追求する学問ですが、経済学の中には不合理性を追求する「行動経済学」という学問もあります。
それは人間心理を分析した上で、上手に活かすことを目指した学問なので、もちろんビジネスにも応用できます。
例えば300円のメロンと、500円のメロンが並んでいた場合、多くの人は300円のメロンを買いますよね。
しかし500円のメロンにだけ「このメロンの糖度は20度で最高に甘い!」とPOPがあった場合、500円のメロンを買う人は増えるはずです。
人間が経済合理性だけを追求していると仮定した場合、この行動結果には矛盾が生じます。
そのような矛盾を解き明かした行動経済学という学問なので、もし気になる人は下の本を読んでみてください。

在庫を絞れば利益は出る。
鈴木敏文は、とにかく在庫(死に商品)を徹底的に管理して、売れる商品だけに置き換えました。
今では当たり前の発想なのですが、当時の小売業は全く在庫管理をしていなかったそうです。
経営者は60歳を過ぎたら引退すべきだとも思っていた。
鈴木敏文は『60歳で引退する』ことを考えていたそうですが、実際には80歳を過ぎるまで経営に携わっていました。
このことについて「無責任に引いてはいけないという葛藤があった」と語っているのですが、やはり後継者へバトンタッチする難しさがあるのだと思います。
それを綺麗さっぱり捨て去り、潔く実行したのがドン・キホーテ創業者の安田隆夫です。
ドン・キホーテ創業者の考えを知りたい人は下の名言集をご覧ください。
消費者ニーズは多様化していない。
これは目から鱗の名言ですよね。
「消費者ニーズが多様化している」と叫ばれて久しいですが、鈴木敏文に言わせれば「それは表面上だけ」ということです。
本質的な部分(便利なものが好き、美味しいものが食べたい etc.)は、今も昔も一緒だということです。
売上じゃない。
利益を上げるにはどうするかを考えるんだ。
これはP/L(Profit and Loss Statement)についての名言です。
日本語では「損益計算書」とも呼ばれますが、商売ではまず「売上-原価=粗利」を導き出します。
そこから販管費を差し引き、営業利益を導き出すのですが、一般的にはこれが”本業の儲け”となります。
なので「売上よりも利益を見ろ」と語ったのです。
これはつまり売上100億円だったとしても、営業利益がマイナスの場合には事業価値が低くて、それよりも売上100万円で利益10万円の方が「ビジネスとしては優秀」だということです。
過去の成功体験を否定し、改革を続ける。
これは鈴木敏文らしさが凝縮された名言ですよね。
セブンイレブンは常に時代の変化に合わせて、柔軟に変化してきました。
つまり、この言葉を実体化したのが『セブンイレブンというビジネスモデル』なのだと思います。
発表者個人を叱っているんじゃない。
出席者全員に語りかけているんだ。
鈴木敏文といえば「業務改革委員会」が有名ですよね。
これは全国から集められたマネージャー達が「どのように現場を改革していくのか?」を真剣に考える会議のことですが、そこでは毎回のように鈴木敏文のゲキが飛んでいたそうです。
なので、いつも業革委員会は緊張感で一杯だったみたいですが、鈴木敏文としては誰かを吊るし上げる目的で叱ったわけではなく、全員のコンセンサスを一致させるという目的があったみたいですね。
後入れ先出しが徹底されていない。
「後入れ先出し」はセブンイレブンの店舗経営における基本原則です。
一般的な小売業では、賞味期限の近いものから先に出して、最近仕入れたものを奥の方に入れると思いますが、セブンイレブンではその逆を実践していて、常に新しいものを最前面に出すということをしているそうです。
これは小売業界にとっての常識はずれなやり方なのですが、これによって「お客様は常に新鮮な商品を手に取ることができるので、またセブンイレブンに来てくれる」と鈴木敏文は語っています。
先ほど「フレッシュさが大事」という名言もご紹介した通りですが、実はこれがセブンイレブンというビジネスモデルの肝になっているのです。
しかしこのやり方を聞くと「売れ残りが多くなるのでは?」と感じるかもしれませんが、だからこそ鈴木敏文は『徹底的な在庫管理(購買数=仕入れ)』をするように命じたのです。
たとえOFCの陣容が1000人、1万人を超えたとしても、なんとしてでも全体会議を続けていく。
OFCとは「オペレーション・フィールド・カウンセラー」の略称です。
つまり全国の店舗を回るスタッフのことなのですが、OFCのクオリティ担保はとても重要だと感じてたのでしょう。
鈴木敏文は「OFCは店のプロなんだ。店内を10分見れば、問題点を指摘できなくてはならない」と語っています。
交差点を渡る前に考えるな。
渡ってから考えればいいんだ。
これは問題が起こる前から考えてばかりいる馬鹿馬鹿しさを揶揄した言葉です。
鈴木敏文は現実主義者であり合理主義者なので、実際起こった問題だけに対処して、その都度解決策を実行していけば、必ず成果が得られると考えていたようです。
僕がしたいのは、チェーンストア理論の否定なんだ。
時代の変化に対応すべき時に、マニュアルで社員をがんじがらめにするなんてナンセンスじゃないか。
前述した通り、鈴木敏文はチェーンストア理論を否定していました。
それよりも人間味(温かみ)のあるビジネスを求めたのです。
現場に入り込めば業界の常識や売り手の都合が体に染みつく。
そして玄人の常識は必ず、変化に柔軟に対応する妨げとなる。
鈴木敏文は「現場を知らない」ということに価値を見出していました。
だからこそ業界未経験の人間を積極採用していたのですが、素人目線は斬新なので、業務改善するきっかけになると考えていたようです。
消費者に驚きを持ってもらうには、200円くらいの弁当が必要ではないか。
これはデフレまっただ中、セブンイレブンが250円弁当を発売した発端となった名言です。
金額はさておき「消費者に驚きを持ってもらう」という部分は商売において重要なポイントだと思います。
やはり購買行動と「ワクワクする」という気持ちはセットなので、良い意味で『期待を裏切るような驚き』を提供しなければいけないと思います。
変化には時間がかかる。
ゆっくりでもいいので、必ず一歩ずつ前進していけば、きっと結果に結びつくはずです。
焦らずに日々精進しましょう!
鈴木敏文は日本を代表するカリスマ経営者
ここまで実質的なセブンイレブン創業者である鈴木敏文の名言集をご紹介してきました。
鈴木敏文は、控えめに言っても「小売りの天才」だと思いますが、それはイトーヨーカドー創業者の伊藤雅俊も認めていることです。
実質的には伊藤雅俊が上司で、鈴木敏文は部下という構図だったのですが、伊藤雅俊は「鈴木の方が私よりもマネジメントが上手い」「ビジネススキルは鈴木の方が上」と手放しで褒めています。
そのような信頼関係があったからこそ、鈴木敏文は自分の能力を最大限発揮できたのだと思います。
このような日本を代表するカリスマ経営者には学びが多いので、ぜひ下の記事もご覧ください。