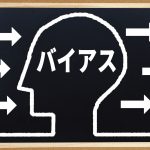中国には”世界四大文明”の一つ『黄河文明』があったので、その歴史はとても古いと言われています。
日本でも三国志が人気になっていたり、「古代中国のファン!」という人はきっと多いはずです。
そこで今回は、中国4000年の歴史が詰まった名言&言葉をご紹介したいと思います。
歴史を感じられる格言ばかりなので、ぜひご覧ください。
中国の偉人達が残した名言まとめ
人生 意気に感ず
功名 誰か復た論ぜん
訳)人生の醍醐味は、自分を”男”と見込んでくれた相手のために粉骨砕身働くことにある。利益や名誉のために計算ずくで働くなど愚の骨頂だ。
<魏徴(ぎちょう)>
魏徴は唐の皇帝だった太宗の参謀です。
とても優秀な人物として有名ですが、このような男らしくて”かっこいい言葉”も残しているみたいですね。
戦に明け暮れていた時代だからこその名言だと思います。
魏徴の名言は貞観政要に記されているので、気になる人は下の記事をご覧ください。
中人以上は、以て上を語ぐ可し。
中人以下は、以て上を語ぐ可からざるなり。
訳)人間としてのレベルが中以上の人には、高度な話をしても良いが、レベルが中以下の人には、高度な話をしてもどうせ理解されないから、話すべきではない。
<論語>
なんとなく冷たい雰囲気のする言葉ですが、とても合理的だと思います。
「理解できない人」以外にも「理解しようとしない人」もいます。
「お互い時間の無駄にならないようにするべきだ」という意味なのでしょう。
老いては当(まさ)に益壮(ますますさか)んなるべし。
寧(なん)ぞ白首(はくしゅ)の心を知らん。
訳) 男たるもの、年老いても志を高く持ち続け、若い頃以上に意気盛んでなければならない。世間の人々には、こんな白髪頭の老人の心などわからないだろうが。
<王勃(おうぼつ)>
これは「老いてますます盛ん」という慣用句の出典となった言葉です。
常に『向上心を持つ』ことを推奨した名言だと思います。
暴虎馮河(ぼうこひゅうが)、死して悔い無き者は、吾れ与にせざるなり。
訳)獰猛な虎を素手で殴り倒したり、黄河のような大河を徒歩で渡ろうとするような、死をも恐れぬ野蛮な勇者と、私は仕事を共にしたくない。
<論語>
「勇気ある行動」と「無謀な行動」は全く違います。
自分では「勇気ある行動」だと思っても、それは単なる”無計画”と見られる可能性もあります。
十分注意しましょう!
徳は孤ならず、必ず隣有り。
訳)知性と品性を兼ね備えた人格者には、必ず良い理解者が現れるので、孤立することがない。
<論語>
孔子は「道」を説いていました。
正しい「道」さえ歩んでいれば、必ず理解者は現れるということです。
孔子の考え方が知りたい人は、下の記事もご覧ください。
手を翻せば雲と作(な)り 手を覆せば雨
紛紛(ふんふん)たる軽薄 何ぞ数うるを須(もち)いん
訳)手のひらを上に向ければ雲となり、下に向ければ雨となるように、軽薄な俗物たちの気持ちはめまぐるしく変わるから、気にするな。
<杜甫>
「紛紛」とは多くのものが入り乱れている様子を指します。
これは現代社会にも通じる名言だと思います。
君子は和して同ぜず。
小人(しょうじん)は同じて和せず。
訳)君子は、嘘偽りのない真の友情を結ぶが、友情を保つために相手に迎合することがない。小人は相手に迎合したり、無理やり同調するため、真の友情を結ぶことができない。
<論語>
「君子」とは、知性や教養がある優れた人格者のことです。
そして「小人」とは、知性や教養にかけて、人格的にも卑しい人物のことです。
この名言は、『成功するためには”君子”になるべきだ』という教訓となります。
論語の名言集は下の記事をご覧ください。
朱門には朱肉臭きに、路には凍死の骨あり
訳)貴族の家の中には、酒や肉が腐るほどあるというのに、道端には凍死した人の骨が転がっている。
<杜甫>
「朱門(しゅもん)」は、赤塗の豪華な門のことなので、貴族の家を指します。
世の中の矛盾を語った名言だと思います。
天 我が材を生ず 必ず用有り 千金散じ尽くすも 還た復た来たらん
訳)天が私を必要としたから、私はこの世に生まれたのだ。だから金など使いたいだけ使ってしまえば良いのだ。どうせいずれは私の元へ戻ってくるのだから。
<李白>
自由闊達に生きた”李白(りはく)”らしい名言ですよね。
李白は「酒飲み詩人」と呼ばれた人物なので、お金についてはあまり深く考えていなかったようです。
何ぞ世を恋いて常に死ぬのを憂うるを須いん
訳)生きることに執着するあまり、死を恐れるなど愚の骨頂だ。
<白居易(はくきょい)>
死ぬのが怖いということは、「人生でやり残したことがある」ということだと思います。
ただ単に”生”に執着したところで、それは無意味ですよね。
「自分は一体何を成し遂げたいのか?」というビジョンを掲げましょう!
蝸牛角上 何事をか争う
石火光中 此の身を寄す
訳)カタツムリの角ほどの小さな世界で、何を争っているのだ。この世の旅人に過ぎない人間は、火打石(ひうちいし)が発する火花ほど短い時間しかこの世にとどまれないというのに。
<白居易>
これは、つまらない争いにこだわって人生を浪費しないように諭した名言です。
「蝸牛角上 何事をか争う」は荘子(そうし)の寓話ですが、荘子の考え方を知りたい人は下の名言集をご覧ください。
春眠(しゅんみん) 暁を覚えず
処処(しょしょ)に啼鳥(ていちょう)を聞く
夜来(やらい) 風雨の声
花落つること知る多少
訳)春の眠りは気持ちが良すぎて、夜が明けたのにも気づかなかった。あっちこっちから小鳥のさえずりが聞こえてくる。昨夜は風雨の音がしていたが、庭の花はどのくらい散っただろう。
<孟浩然(もうこうねん)>
「春眠不覚暁」はとても有名な一句ですよね。
呑気にゴロゴロしているのは”負け組”かもしれませんが、そんな人生でも「自分らしくて良い」と開き直っているのです。
春の気持ち良さも感じられる詩だと思います。
菊を採る東籬(とうり)の下
悠然として南山を見る
訳)東垣根の辺りで菊の花を摘み、ゆったりした気分で南山を眺めた。
<陶潜(とうせん)>
毎日忙しくしていると、身近にある菊の花の美しさにすら気づきません。
目の前にある大きな山にも気づきません。
そのような自然を感じて、共に生きる”余裕”こそが、人間らしさの秘訣なのだと語ったのです。
知者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ。
訳)理性的な人は、滔々と流れる水を好み、情愛の深い人は、どっしりと落ち着いた山を好む。
<論語>
知者と仁者は、両方とも上位の人間ですが、古代中国では『仁愛に溢れて情け深い=仁者』という生き方を理想にしていました。
つまり、変化の激しい水のような生き方をするよりも、悠然と構えている山のように、物静かで落ち着いた生活を推奨したのです。
学びて然る後に足らざるを知り、教えて然る後に困(くる)しむを知る。
訳)勉強してみて、初めて自分の知識不足が分かり、人に教えてみると、初めて自分の力不足が分かる。
<礼記>
これはソクラテスが言う『無知の知』に似ていると思います。
自分自身を知ることが出発点だということでしょう。
ソクラテスなど”世界の偉人”が残した名言集は下の記事をご覧ください。
人の己を知らざるを患(うれ)えず、人を知らざるを患うるなり。
訳)他人が自分の実力を認めてくれるないことを気にするな。自分が他人の実力を十分に理解してないことを気にしなさい。
<論語>
「自分の実力が認められていない」と考えている人は、たくさんいるはずです。
しかし、そんな時にこそ謙虚になって、自分自身を見つめ直すことが必要だと思います。
古(いにしえ)の学者は己の為にし、今の学者は人の為にす。
訳)昔の人は、自分の内面を充実させるために勉強をしたが、今の人は、他人に認められたいがために勉強をしている。
<論語>
これは勉強の本質について語った名言です。
- 自分のために勉強するのか?
- 他人のために勉強するのか?
この二つは全く違うので、勉強するモチベーションにも影響するはずです。
年四十にして悪(にく)まるるは、其れ終わらんのみ。
訳)40歳にもなって、人から憎まれてるような人は、その程度で終わる人だ。
<論語>
孔子は「四十にして惑わず」と言いました。
40歳になると、人生における一通りを経験するので、人間としては大成すると言われています。
そのような年齢なのに、人から憎まれるようなことをする人は、「どうせ大した人間にならない」と苦言を呈しているのです。
孔子の名言集は下の記事をご覧ください。
貌言(ぼうげん)は華なり。
至言は実なり。
苦言は薬なり。
甘言は疾(やまい)なり。
訳)飾り立てた言葉には花があっても実はないが、真実を言い当てた言葉には実がある。耳の痛い忠告は薬になるが、耳に心地良い甘い言葉は病気の元である。
<司馬遷>
「良薬口に苦し」と言いますよね。
人生における教訓がギュッと詰まった名言だと思います。
巧言令色(こうげんれいしょく)、鮮(すく)なし仁。
訳)お世辞を言ったり、媚びたりする人に、誠実な人は少ない。
<論語>
これは人を見極める時に役立つ名言だと思います。
頭の片隅で覚えておきましょう!
豆を煮るに豆がらを焼く
豆は釜の中に在りて泣く
本是れ同根より生ぜしに
相煎ること何ぞ太だ急なる
訳)鍋の下では豆の茎が燃えて、鍋の中では豆が煮られて泣いている。豆も豆の茎も、元は同じ根から生まれた兄弟同士なのに、豆の茎はどうしてこんなにも激しく豆を苦しめるのだろう。
<曹植>
三国志で有名な曹操の息子には、曹丕(そうひ)と曹植(そうち)の二人がいました。
曹操の死後、王座に就いた兄の曹丕でしたが、父から愛されていた弟である曹植のことを恨んでいました。
そんな中、弟の曹植は、兄である曹丕を『豆の茎』に例え、弟である自分のことを『鍋の中の豆』に例えてこの ”詩”を読みました。
実の弟に対して酷い仕打ちをする曹丕に”詩”で抗議した結果、曹丕は大いに反省したそうです。
天地は万物の逆旅(げきりょ)にして、光陰は百代の過客なり。
訳)天と地は万物が一夜を過ごす旅館であり、時間は天地の間を旅する永遠の旅人である。
<李白>
とても美しい表現の詩ですよね。
人間の生命は『永遠の命を持つ時間と比べれば短くて儚い』と語ったのです。
年年歳歳 花相似たり
歳歳年年 人同じからず
訳)花は毎年同じように咲くけれど、花を愛でている人は毎年同じではない。
<劉希夷(りゅうきい)>
花は毎年美しく咲きますが、それを見る人間は入れ替わっています。
つまり生と死があるということです。
美しい対比の影に、人間の生命の儚さが隠れているのです。
歓楽極まりて哀情多し
少壮幾時(しょうそういくとき)ぞ 老いを奈何(いかん)せん
訳)幸せが絶頂に達すると、かえって胸の中に悲しみが湧いてくる。若くて元気でいられる時は、あとどれぐらい残っているのだろう。やがて来る老いをどう受け止めたらよいのだろう。
<漢の武帝>
頂点を極めてしまうと、後は下がるしかありません。
良い事が続くこともなければ、悪いことが続くこともないのです。
刀を抜きて水を断てば水は更に流れ
杯を挙げて愁(うれ)いを消せば愁い更に愁う
訳)流れる水を刀で断ち切ろうとしても、水はサラサラ流れ続けるように、酒で憂さ晴らしをしようとしても、悲しみは次から次へと湧きあがってくる。
<李白>
河島英五の「酒と泪と男と女」が脳内再生されるような名言ですよね。
色褪せない名曲なので、ぜひ聞いてみてください。
前に古人に見ず
後に来者を見ず
訳)自分が生まれる前に亡くなった人に会うことはできない。自分より後に生まれてくる人にも会うことはできない。
<陳子昂(ちんすごう)>
理解者を求める孤独感が漂ってくる言葉ですが、それが逆に腹をくくる要因にもなっています。
つまり『誰にも頼れない』と腹をくくれば、自分一人で成し遂げようと頑張るはずです。
そのような勇気をくれる名言だと思いますが、『勇気をくれる名言』が知りたい人は下の記事もご覧ください。
国破れて山河在り
城春にして草木深し
訳)戦争によって国は破壊されたが、山河は昔のままそこにある。街にはいつもと同じように春がきて、草木を青々と茂らせている。
<杜甫>
これはとても有名な詩ですよね。
たとえ国が朽ち果ててしまっても、そこには自然があり、強い生命力を感じることができるのです。
海内 知己存す
天涯 比隣の若し
訳)この国のどこかに真の友がいると思えば、地の果てに別れていようとも、隣同士みたいなものだ。
<王勃(おうぼつ)>
心の中で繋がっていれば、物理的な距離は関係ないということです。
「天涯(てんがい) 比隣(ひりん)の若(ごと)し」と言えるような友人を作りましょう!
人生 相見ざること
動(やや)もすれば参と商との如し
訳)離れ離れになった友人との再会は、夏の星座と冬の星座が夜空で出会うのと同じくらい難しい。
<杜甫>
参(オリオン座の星)と商(サソリ座の星)が夜空で出会う…
とてもロマンチックな表現ですよね。
昔は携帯電話がなく、インターネットもありませんでした。
手紙を送っても明日到着することはないので、この詩のような現実があったのでしょう。
君に勧む 金屈巵(きんくっし)
満酌(まんしゃく) 辞するを須(もち)いず
花発いて 風雨多し
人生 別離足る
訳)君に黄金の杯を勧めよう。なみなみと注いだ酒をどうか断らないでくれ。花が咲けば風雨に散らされてしまうように、出会いに別れはつきものだから。
<于武陵(うぶりょう)>
友人との出会いを楽しんでいる様子が伝わってきますよね。
昔は、一度離れるとなかなか再開できなかったので、『一緒の時間を大切にする』という気持ちが強かったのでしょう。
まさに”一期一会の精神”ですが、この気持ちを現代人も持つべきだと思います。
言わんと欲して予(われ)に和する無く
杯を揮げて孤影に勧む
訳)誰かに話しかけたいと思ったが、答えてくれる人がいないので、盃を上げて自分の影に酒を勧めた。
<陶潜(とうせん)>
真夜中、月に照らされた自分の影へ酒を勧める…
情緒溢れる酒盛りですよね。
個人的には、とても好きな詩です。
夫れ美は自ら美ならず。
人に因って彰(あらわ)る。
訳)美しいものは、最初から美しいものとして人々に認識されているのではない。誰かが、その美を発見することによって、初めてその美しさが人々に認識されるのだ。
<柳宗元(りゅうそうげん)>
なんとなく哲学的な名言ですよね。
パブロ・ピカソはキュビスム(キュビズム)の創始者として有名ですが、最初に見た時は誰もが「不細工な絵だ!」と思うはずです。
しかしキュビスムの奥深さを知ってしまうと、その美しさに感銘を受けるはずです。
このような事例は多いと思うので、『美』についての感性を磨いていきましょう!
中国には名言が多い
ここまで中国4000年の歴史が作り上げた名言集をご紹介してきました。
他にも有名な言葉や格言はたくさんあるので、もし座右の銘を探しているのであれば、下の記事もご覧ください。