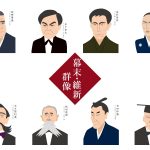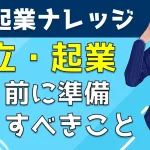夏目漱石(なつめそうせき)と言えば、日本を代表する小説家ですよね。
一昔前の1,000円札に印刷された偉人なので、昭和~平成生まれの人には馴染みがあると思います。
近代日本文学を代表する文豪の一人なので、その代表作には「吾輩は猫である」「坊つちやん」「三四郎」「それから」「こゝろ」「明暗」などがあります。
教科書に載るような名作ばかりですが、そこにはとても奥深い名言がたくさん書き記されているのです。
そこで今回は、ビジネスパーソンが押さえておくべき「夏目漱石の名言集」をご紹介したいと思います。
ぜひ最後までご覧ください。
夏目漱石の名言集まとめ
せんだってはせんだってで今日は今日だ。
自説が変わらないのは発達しない証拠だ。
<小説「吾輩は猫である」>
自分の意見を変えるのは勇気がいりますよね。
「朝令暮改」を良しとしない人を稀に見かけますが、ちゃんとした理由さえあれば、意見は柔軟に変えるべきだと思います。
最初の意見に固執する方がマイナスの影響をもたらす可能性があるので十分注意しましょう。
あなたは思い切って正直にならなければ駄目ですよ。
<随筆「硝子戸の中」>
嘘をつかずに生きていくのは不可能ですが、正直に生きることはできます。
楽しくストレスがない人生を送るためには、自分に正直に生きるべきだと思います。
もっと自分がやりたい事や、好きなことだけに専念しましょう!
財力・脳力・体力・道徳力の非常に懸け隔たった国民が、鼻と鼻とを突き合わせた時、低い方は急に自己の過去を失ってしまう。
<書評「マードック先生の日本歴史」>
30歳半ばを過ぎてくると「人生の成功者」と呼べる人たちが周囲から出てきます。
そのような人たちに嫉妬したり、自分を蔑む必要などないと夏目漱石は言っているのです。
自分の過去を否定する必要などないので、自分なりの努力をしていけば良いのです。
自然は公平で冷酷な敵である。
社会は不正で人情のある敵である。
<随筆「思い出す事など」>
夏の暑さや冬の寒さ、大雨、自然災害などは、まるで人生を邪魔しているように感じますよね。
学校でも競争し、会社でも競争し、周りは敵だらけです。
しかし自然は感動する風景を見せてくれたり、人生を豊かにさせてくれる要素の一つです。
敵だと思っていた人でも、困った時に助けてくれたり、病気の時は親身になってくれたりするのです。
要するに自分の捉え方次第ということです。
世間には大変利口な人物でありながら、全く人間の心を解していない者がだいぶんある。
<小説「抗夫」>
これは「自分の考えは絶対に正しい」と考えている人を批判した言葉です。
そのような傾向は利口な人物(社会的地位のある人)に多いと揶揄したのです。
自分と他人の知識や経験には差があるので、相手のバックボーンを理解した方が良いでしょう。
平生(へいぜい)はみんな善人なんです。
それがいざという間際に、急に悪人に変わるんだから恐ろしいのです。
<小説「心」>
性善説や性悪説のように、人間をどちらか一方だと決めつけることができれば簡単ですよね。
現実世界はそのようにいかないので、相手を見極めることが必要でしょう。
無位無官でも一人前の独立した人間だ。
独立した人間が頭を下げるのは、百万両より尊いを御礼と思わなければならない。
<小説「坊ちゃん」>
この名言が伝えたいことは「人間としての尊厳は地位や肩書に関係しない」ということです。
相手に感謝の気持ちを示して「ありがとう」とお礼するのはもちろんですが、感謝される方も相手に対して感謝するべきなのです。
なぜかといえば、御礼されたということは、自分のことを「立派な人間だ」と認めてくれたことになります。
そのような評価に対して感謝しなければいけないのです。
博士になり、教授になり、空しき名を空しく世間に謳わるるがため、その反響が妻君の胸に轟いて、急に夫の待遇を変えるならば、この妻君は夫の知己とは言えぬ。
<小説「野分」>
これは「夫の肩書きで態度を変えるな」という意味の名言です。
本当の妻ならば世間の評価がどうであろうと、夫の信念を理解するように努めるべきだと、夏目漱石は言っているのです。
所有という事と愛借(あいせき)という事は、大抵の場合において伴うのが原則だから。
<小説「琴のそら音」>
愛惜とは、ある事物や人を大切にして、手放したり傷つけたりするのを惜しむことです。
そう考えた場合、愛惜の感情が湧かなければ、それは本当に必要なものでないのかもしれません。
賢夫人になればなるほど個性はすごいほど発達する。
<小説「吾輩は猫である」>
賢い婦人は夫と衝突するものです。
女性の社会進出が進む一方で、独身者が増え、離婚も増えています。
そこには、女性が一人立ちできる時代という背景があるのでしょう。
僕が思い切った事の出来ずにグズグズしているのは、何より先に結果を考えて取り越し苦労をするからである。
<小説「彼岸過迄」>
失敗を恐れていると行動できなくなります。
怖がらずに前進しましょう!
親よりも勝れて偉い教育者は、詩人文学者である。
<談話「家庭と文学」>
夏目漱石は教師として勤めていた経験があるので、教育熱心で有名でした。
漱石曰く、人の善良さや社会ルールの大切さを教えてくれて、心まで豊かにしてくれるのは文学であると語っているのです。
田舎者の精神に文明の教育を施すと、立派な人間ができるんだがな。
<小説「二百十日」>
「田舎者の精神」とは、純粋さやおおらかさのことなので、誠実な人物のことを言い表しています。
それと対比して「文明の教育」とは、社会生活するためのルールを身につけることです。
この二つが組み合わさった人は立派な人間になると言っているのです。
学校も生徒が騒動をすればこそ、漸々改良するなれ。
<教育論「愚見数則」>
これは教育者らしからぬ言葉ですが、言いたいことは「行動」こそが現状を打破するということだと思います。
何もせず不満ばかり口にしていても、現状は変わらないのです。
教育の精神は単に学問を授けるばかりではない。
高尚な、正直な、武士的な元気を鼓吹すると同時に、野卑な、軽躁な、暴慢な悪風を掃蕩(そうとう)するにあると思います。
<小説「坊ちゃん」>
これは日本的な精神、つまり武士道精神について語った名言です。
武士道精神について知りたい人は下の記事をご覧ください。
勉強をしますか。
何か書きますか。
君らは新時代の作家になるつもりでしょう。
僕もそのつもりであなた方の将来を見ています。
どうぞ偉くなって下さい。
しかしむやみに焦ってはいけません。
ただ牛のように図々しく進んで行くのが大事です。
<芥川龍之介宛の書簡>
芥川龍之介は、夏目漱石晩年の弟子の一人です。
「牛のように図々しく…」という表現は、愉快であり簡潔だと思います。
君は自分だけが独りぼっちだと思うかもしれないが、僕も独りぼっちですよ。
<小説「野分」>
みんな最終的には自分自身の手で人生を切り拓いていくしかないのです。
世の中に偉い人がむやみに多いと思うから、恥ずかしくなったり、極まりが悪くなるので、自分の心が高雅であると、下等なことをする者などは自然と眼下に見えるから、ちっとも臆する必要が起こらないものさ。
<小宮豊隆宛の書簡>
自分を他人と比較してしまうのが人間の性です。
そうすると劣等感を抱いたり、不安になってしまうので、自信を持って生きるようにしましょう。
気に入らないこと、癪に障ること、憤慨すべきことは塵芥の如くたくさんあります。
それを清めることは人間の力で出来ません。
それと戦うよりも、それを許すことが人間として立派なものならば、できるだけそちらの方の修養をお互いにしたいと思いますが、どうでしょう。
私は年に合わせて気の若い方ですが、近代ようやくそっちの方角に足を向け出しました。
<武者小路実篤宛の書簡>
戦うよりも相手を許したほうが人間として立派なことなのです。
人よりも空、語よりも黙。
肩にきて、人懐かしや赤蜻蛉。
<随筆「思い出す事など」>
大自然や自分だけの世界に閉じこもれば、心が穏やかになります。
色々と騒がしい現代社会なので、そのような機会を作ることも大切でしょう。
粥も旨い。
ビスケットも旨い。
人間、食事が旨いのは幸福である。
<日記より>
食事が美味しいということは、健康である証拠だと思います。
当たり前のことに幸福を感じられると、その人は幸せになれると思います。
白髪に強いられて、思い切りよく老いの敷居をまたいでしまおうか。
白髪を隠してなお、若いちまたに徘徊しようか。
<随筆「思い出す事など」>
年を重ねると白髪が生えてくるので、どうしても気になってしまいますよね。
でも白髪が生えることは自然なので、本来は気にする必要などありません。
ありのまま、自然体の自分を愛しましょう。
世の中は煩わしいことばかりである。
ちょっと首を出してもすぐまた首を縮めたくなる。
俺は金がないから病気が治りさえすれば、嫌でも応でも煩わしい中に固執して神経を痛めたり胃を痛めたりしなければならない。
しばらく休息のできるのは病気中である。
<夏目鏡子宛の書簡>
病気の時は「人生の休息時間」だと思えばいいと、夏目漱石を語っています。
やることはたくさんありますが、具合が悪い時はゆっくり休みましょう!
漱石が熊本で死んだら熊本の漱石で、漱石が英国で死んだら英国の漱石である。
漱石が千駄木で死ねば、また千駄木の漱石で終わる。
今日まで生き延びたから色々な漱石を諸君にお目にかけることができた。
これから10年後には、また10年後の漱石ができる。
<寺田寅彦宛の書簡>
人生は死んだらおしまいです。
しかし生きている限りアップデートされていくので、全く新しい自分になれるはずです。
10年後の自分自身が楽しみですね。
所詮我々は、自分で夢の間に製造した爆裂弾を思い思いに抱きながら、一人残らず死という遠い所へ、談笑しつつ歩いていくのではないだろうか。
<随筆「硝子戸の中」>
これは暗さと不安感が入り交じった名言ですよね。
人生は何があるかわかりません。
短い人生なので、精一杯生きましょう!
死んだら皆に棺の前で万歳を唱えてもらいたいと本当に思っている。
<林原耕三宛の書簡>
中国戦国時代の思想家で、道教始祖の一人とされている荘子は下のような名言を残しています。
「時に安んじて順に処(お)る」
これは天から授かった命を全うし、去っていくのは自然の摂理なので、人間が死んだ時には”心から合掌して祝う”ことが正解だという意味です。
夏目漱石は荘子に通じる考え方を持っていたようですね。
荘子の名言集は下の記事をご覧ください。
ことに芸術家で己の無い芸術家は蝉の抜け殻同然で、殆ど役に立たない。
<講演「道楽と職業」>
これはつまり「信念を持つべき」ということです。
仕事でもプライベートでも、自分なりの信念を持つべきだと思います。
それがなければ生き方がブレてしまうので注意しましょう。
美しきものを、いやが上に、美しくせんと焦る時、美しきものはかえってその度を滅ずるが例である。
<小説「草枕」>
この言葉は「美しいものをさらに美しく見せようとすると、逆に醜くくなる」という意味です。
要するに「背伸びするのは良くない」という教訓なので注意しましょう。
昔から大きな芸術は守成者であるよりも多く創業者である。
創業者である以上、その人は玄人でなくって素人でなければならない。
人の立てた門を潜るのではなくって、自分が新しい門を建てる以上、純然たる素人でなければならないのである。
<評論「素人と黒人」>
これはイノベーターについて語ったビジネスパーソン必見の名言です。
固定概念がある人は夏目漱石曰くイノベーションを起こせないそうです。
頭を柔らかくする柔軟性を身につけましょう。
小説なかなか進まず。
しかしこれが本職と思うと、いつまでかかっても構わない気がする。
暑くても何でも、自分は本職に勤めているのだから不愉快の事なし。
<日記より>
夏目漱石は、本を書くことが大好きだったみたいですね。
それほどまで熱中できる仕事に出会える人は幸せだと思います。
古き道徳を破壊するは、新しき道徳を建立する時にのみ許されるべきものなり。
<断片より>
イノベーションとは「破壊と創造」を意味しています。
破壊することは敵を作りますが、それをしなければ人類は進化できません。
そのような覚悟がある人のことを、世間では「起業家」と呼んでいます。
自分で自分の価値は容易にわかるものではない。
全てやり遂げてみないと、自分の頭の中にはどれくらいのものがあるか自分にも分からないのである。
<森田草平宛の書簡>
これは自分の可能性について語った名言です。
絶対に自分の可能性を潰してはいけません。
挑戦する勇気を持ちましょう!
熊本より東京は広い。
東京より日本は広い。
日本より…
<小説「三四郎」>
視野を狭めてしまうと、全てが小さくなっていきます。
「日本より…」の後に続く言葉は「日本より頭の中の方が広いでしょう」です。
人間には無限のイマジネーションがあるので、大いなる可能性が秘められているのです。
まとめ
夏目漱石は明治~大正にかけて活躍した文豪です。
この頃は日本の変革期と呼ばれているので、きっと大きな変化があったのでしょう。
そのような時代は魅力的で、特に明治維新は今でもたくさんのファンがいるほどです。
このような時代背景が好きな人は、ぜひ下の記事もご覧ください。