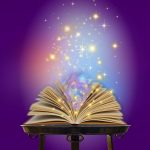営業職の人は、お客様と色々なコミュニケーションをするはずです。
その時に便利なネタが「雑学」ですよね。
お客様との会話が詰まった時や、場の空気を和ませるのに雑談はとても効果的だと思います。
なのでセールスパーソンは”色々な雑学”を知っておいて、きっと損することはないはずです。
そこで今回は、ビジネスに役立つ知識・雑学ネタをご紹介したいと思います。
諸説ある”眉唾話”もありますが、ビジネスパーソンはぜひご覧ください!
目次
- 1 営業職はセールスに雑学を活用しよう!
- 1.1 1:刑事を「デカ」と呼ぶのはなぜ?
- 1.2 2:タンスに足の小指をぶつけるのはなぜ?
- 1.3 3:ドライヤーに冷風があるのはなぜ?
- 1.4 4:唐揚げとフライドチキンの違いは?
- 1.5 5:子供の寝相が悪いのはなぜ?
- 1.6 6:温泉旅館にあるお菓子の意味は?
- 1.7 7:信号の緑はなぜ青信号なの?
- 1.8 8:ペットボトルの凹凸はなぜある?
- 1.9 9:なぜ鳩は地面をつついている?
- 1.10 10:音楽室に肖像画がある理由は?
- 1.11 11:バイキングとビュッフェの違いは?
- 1.12 12:辛い食べ物が人気の理由は?
- 1.13 13:手と足だけがふやけるのはなぜ?
- 1.14 14:年を取ると毛が長くなるのはなぜ?
- 1.15 15:地下鉄の路線図が複雑なのはなぜ?
- 1.16 16:昆布のダシが海の中で出ないのはナゼ?
- 1.17 17:おだいり様とおひな様は誰?
- 1.18 18:なぜ魚には赤身と白身があるの?
- 1.19 19:「差し入れ」と「お土産」の違いは?
- 1.20 20:炭がニオイを消すのはなぜ?
- 1.21 21:なぜハンカチは正方形なの?
- 1.22 22:なぜ接着剤はくっつくの?
- 1.23 23:電話をしながら歩くのはなぜ?
- 1.24 24:祭日っていつ?
- 1.25 25:スーツの襟に穴があるのはなぜ?
- 1.26 26:名刺はなぜ「名を刺す」なの?
- 1.27 27:ネクタイをつけるのはなぜ?
- 1.28 28:カップ麺の待ち時間が3分なのはなぜ?
- 2 まとめ
営業職はセールスに雑学を活用しよう!
ここから様々な雑学をご紹介していきたいと思います。
仕事や営業現場で役立つ知識もあるので、ぜひ最後までご覧ください!
1:刑事を「デカ」と呼ぶのはなぜ?
刑事を「デカ」と呼ぶようになったのは明治の頃だと言われています。
その頃はまだ和服の時代だったので、私服刑事も和服で捜査していました。
その時のポピュラーなファッションに、着物の上に羽織る和装用のコート「角袖(カクソデ)」があったのですが、その言葉を「カクソデ⇒クソデカ」と変化させて、刑事を表す隠語として使っていたのです。
それが省略されて現在のように「デカ」と呼ばれるようになりました。
2:タンスに足の小指をぶつけるのはなぜ?
日常生活では、よく足の小指をぶつけますよね。
しかもなぜか足の小指ばかり…
これはとても不思議なことですが、実は足の小指ばかりぶつけるのにはきちんとした理由があるのです。
その理由は、人間は自分が認識しているよりも「足の位置が1cmほどズレている」からだと言われています。
歩いている時に「足の位置が1cmほどズレている」ので、一番外側にある小指ばかりをぶつけてしまうというわけです。
自分が認識しているよりも足の位置が1cmほどズレてしまう理由までは分かっていませんが、どうやら男女差や年齢差はないようです。
これを理解しておけば、小指をぶつけることはきっと少なくなるでしょう。
3:ドライヤーに冷風があるのはなぜ?
お風呂上がりにドライヤーを使うと思いますが、基本的には温風を使いますよね。
そうすると「なぜ冷風があるのか?」という疑問にたどり着きます。
確かによく考えると冷風があるのは摩訶不思議ですよね。
ここで知っておくべき一般常識は、髪の毛の原理です。
髪の毛にはキューティクルという鱗状の組織があり、それが髪全体を覆っています。
このキューティクルがぴったり張り付いていると髪の毛に艶が出るのですが、お風呂上がりはキューティクルが開いたままになっているので、ボサボサになってしまいます。
そのようなお風呂上がりには髪の毛を温風で乾かすのですが、キューティクルは温度が高すぎても開いてしまうという性質があります。
よって、温風で髪を乾かした後、冷風を当ててキューティクルを閉じれば、髪の毛に艶が出やすくなるのです。
このような理由からドライヤーには冷風が実装されています。
4:唐揚げとフライドチキンの違いは?
みんなが大好きな食べ物といえば、唐揚げやフライドチキンですよね。
しかしその違いを説明できる人は意外と少ないはずです。
実は、唐揚げとフライドチキンは味付けの仕方が異なっています。
唐揚げは鶏肉に醤油などで下味をつけてから揚げますが、フライドチキンはスパイスを加えた衣につけてから揚げます。
つまり、肉に味付けするのが唐揚げで、衣に味付けするのがフライドチキンということになります。
5:子供の寝相が悪いのはなぜ?
小さい子供がいる家では、子供の寝相の悪さにきっと悩んでいるはずです。
しかし子供の寝相が悪いのは当たり前だと思った方が良いです。
そもそも子供の寝相が悪いのは、睡眠時に姿勢を制御する機能がまだ発達していないためです。
さらに、脳の姿勢を制御する機能が発達していないため、一見するととんでもない格好で寝ることになるのです。
しかし子供の寝相を無理に正そうとすると、健全な発育を妨げてしまう可能性があるので逆効果だと言われています。
なので、うつ伏せ寝にならない限りは、基本的には放っておくのが正解ということです。
6:温泉旅館にあるお菓子の意味は?
温泉旅館へ行くと、必ずと言っていいほどテーブルにお菓子が置いてありますよね。
実はあれ「血糖値を上げるため」に置かれているのです。
人間の体は、動くと糖が消費されて血糖値が下がります。
温泉旅館までは長旅なので、その間に血糖値が下がってしまうというわけです。
そのような空腹の状態で温泉に入ると、さらに血糖値が下がってしまい、立ちくらみを起こしたり失神する可能性があるので、そのような事態を防ぐために、温泉旅館の部屋には血糖値を上げるためのお菓子が置いてあるということです。
7:信号の緑はなぜ青信号なの?
「赤・黄・緑」は人間が色を区別する時に、最も感度が良い組み合わせとされています。
なので世界中の信号はこのような組み合わせになっているのですが、緑を「青信号」と呼んでいるのは日本だけなのをご存知でしょうか。
このようになった理由は、当時の新聞が「青信号」と報じたことが原因だと言われています。
それが一般的に広まってしまったため、「緑信号」よりも「青信号」という呼び名が定着してしまい、昭和22年に法律上も「青信号」と修正されました。
ということで、日本では緑の信号を「青信号」と呼ぶのは法律的にも正解ということになります。
8:ペットボトルの凹凸はなぜある?

お茶を飲む時など、ペットボトルの凹凸が気になりますよね。
なんでペットボトルはあんなに凸凹しているのでしょうか?
ペットボトルには色々な凹凸や形状がありますが、あのような形になっている理由は、熱い液体を入れても変形しない為だと言われています。
店頭では冷やして販売されているペットボトルも、工場で中身を入れた時には、中身の液体と容器を殺菌するため、熱々の状態になっています。
この時、凹凸のないペットボトルでは変形してしまうので、あえていびつな形にしているというわけです。
逆に、炭酸飲料のペットボトルには凹凸がありませんが、炭酸ガスには外側に押し広げる圧力があるので、あえて凹凸をつけないデザインにしているそうです。
9:なぜ鳩は地面をつついている?
公園にいる鳩を見ていると、とにかく地面をつついていますよね。
あれは「地面の石ころを食べている」のだと言われています。
鳩はたくさんの石ころを食べるのですが、胃の中には「砂に近い2mmほどのサイズの石」が大量にあるそうです。
そもそも鳩には歯がないので、基本的には食べ物を丸呑みすることになります。
それを胃の中にある石で細かく砕いて、消化しやすくしているのです。
10:音楽室に肖像画がある理由は?
学校の音楽室といえば、バッハやベートーベンなどの肖像画ですよね。
よく考えると美術室などには肖像画がないので、「なぜ音楽室だけ?」と疑問になるはずです。
学校に肖像画が広まった理由は、楽器販売の”おまけ”が原因だと言われています。
販売数量を増やしたい業者が、差別化しにくい楽器の販売だけでなく、おまけとして肖像画もセットにしてセールスしたのです。
その名残が現在も残っていて、音楽室には肖像画が飾られるのが当たり前となりました。
11:バイキングとビュッフェの違いは?
異業種交流会などに行くと「今日はビュッフェ形式です」と言われたりしますよね。
「バイキングじゃないの?」と疑問になるかもしれませんが、この2つには明確な違いがあります。
- バイキング=食べ放題
- ビュッフェ=立食形式
このような違いがあるので、ビジネスパーソンは覚えておきましょう。
12:辛い食べ物が人気の理由は?

「辛い食べ物が大好き!」という人は多いはずです。
人間の舌が感じる味覚は甘味、酸味、塩味、苦味、うま味の5種類だと言われていますが、実はこの中に”辛味”は入っていません。
ということは”辛味”という存在は一体何なのか気になりますよね。
実は「辛い」は味覚でなく「熱い」と感じているそうです。
辛いものを食べると、口の中にある神経細胞にあるTRPV1(トリップ・ブイワン)が反応しますが、これは本来43度以上の熱に反応します。
しかし辛さの原因物質が入ってくると、人間の脳は「43度以上の熱だ!」と勘違いしてしまうので、命の危険に繋がる状態だと勝手に判断してしまいます。
このような強い刺激がきた時、人間の脳ではβエンドルフィンという神経伝達物質が分泌され、それが強い快感を引き起こすのです。
それを繰り返してるうちに、辛さにやみつきになってしまうというわけです。
13:手と足だけがふやけるのはなぜ?
お風呂に入ると、手と足だけふやけますよね。
これは人間の自己防衛反応だと言われています。
人類は陸上で生活していますが、角質で覆われた手と足は水に濡れると滑りやすくなるという欠点(弱点)がありました。
そこで手足の角質が水分を吸って”ふやける”ことで滑りづらくする機能が備わったのです。
14:年を取ると毛が長くなるのはなぜ?
年齢を重ねていくと、おじいちゃんの眉毛のように、体中の毛が長くなりますよね。
長くなる理由は、年齢を重ねて繰り返し毛を作っているうちに、うっかり毛が抜けるのを忘れてしまうからです。
通常であれば1cm程度で自然と抜け落ちるのが普通なのですが、年を取るとその機能が低下して、長いまま残ってしまうというわけです。
15:地下鉄の路線図が複雑なのはなぜ?
これはあくまでも一般論ですが、土地を購入すると地上だけでなく地下もその人の所有物となります。
なので、勝手に家の地下に電車を通すことができなくなるのです。
そのような理由から、国や地方自治体が所有している道路の下に地下鉄を通すことにしました。
その結果、真っ直ぐではなくジグザグな路線図になってしまったのです。
しかしこれだけを続けていくと、地下鉄はどんどん深くなってしまうので、平成13年に大深度法が施行され、公益目的であれば40mより深い地下を鉄道会社が使用できるように変更されました。
16:昆布のダシが海の中で出ないのはナゼ?
これは誰もが抱く疑問ですが、結論から言ってしまうと、昆布は生きているとダシが出ません。
昆布が生きている間はグルタミン酸などが細胞膜によって閉じ込められていますが、昆布が死ぬと細胞膜が壊れて旨味が外へ出るようになります。
これが死んだ昆布から出汁が取れるメカニズムです。
17:おだいり様とおひな様は誰?
ひな壇にはたくさんの人形が飾られていますが、ほとんどの人が「おだいり様」と「おひな様」を間違えて認識しているそうです。
- おだいり様:おびな、めびな両方のこと
- おひな様:ひな壇の人形全体
つまり、おだいり様は男女一対の人形を指しているのです。
おそらく童謡にある「おだいり様とおひな様、二人並んですまし顔」という歌詞のせいで、世間に間違った認識が広がってしまったのだと思います。
18:なぜ魚には赤身と白身があるの?
人間を含めて動物には持久力のある「赤筋」と瞬発力のある「白筋」があります。
赤身の代表的な魚といえばマグロですが、マグロは回遊魚ですよね。
つまり持久力が必要なので赤筋が発達しています。
それと比較してトビウオなどの白身魚は瞬発力が必要なので、白筋が発達しているのです。
19:「差し入れ」と「お土産」の違いは?
差し入れとお土産を同じように使っている人は多いはずですが、その語源は全く違います。
お土産は「土地の産物」という意味なので、旅行などの手土産を意味していますが、差し入れは「隙間に物を入れる」という意味なので、鉄格子の間から入れる食事や日用品を指す言葉として使われていました。
つまり差し入れは、犯罪者に対するお土産という意味を含んでいるのです。
今では同じような意味で使われていますが、その語源は違うのだと理解しておきましょう。
20:炭がニオイを消すのはなぜ?
炭がニオイを吸い取ってくれると勘違いする人は多いですが、決して炭がニオイを消してくれるのではありません。
そもそもニオイとは、空気中のほこりやゴミ、動物、細菌などが混ざり合ってできています。
これが炭にある蜂の巣のようなミクロの穴に引っかかって、ニオイの元となる数が減ることによって、ニオイがなくなるというわけです。
21:なぜハンカチは正方形なの?
中世ヨーロッパでは、ハンカチは装飾品の一つとして捉えられていたので、宝石をあしらったり、レースをつけたり、円形や長方形など様々な形がありました。
しかしフランス王妃のマリー・アントワネットが「全てのハンカチを正方形にしなさい」と命じた為、それが定番となり、現在のハンカチにも適用されています。
22:なぜ接着剤はくっつくの?
接着剤は液体ですが、そのようになっている理由は物と物との隙間を濡らすことで接着できるようにするためです。
例えば、ガラス2枚をくっつけようとした場合、その間に水を垂らせばくっつきますよね。
このように、モノとモノとをくっつけるためには液体が必要なのです。
しかし水では乾いてしまったり、動きが不安定になるので、その液体を固めなければいけません。
それが接着剤ということになります。
23:電話をしながら歩くのはなぜ?
ビジネスパーソンであれば、電話をしながらウロウロした経験がありますよね。
実はこれ、緊張感をほぐすための自然行動なのです。
電話は直接会って話すよりも緊張感が高まるので、そのストレスを緩和させるために、脳から「動きなさい」という指令が出されます。
その結果、ウロウロしながら話すことになるのです。
24:祭日っていつ?
お休みの日を「祝祭日」と表現している人は多いはずです。
祝日は毎月のようにありますが、祭日とは一体いつなのでしょうか?
実は日本に「祭日」という日はありません。
正確に言うと、戦後間もない頃には存在していましたが、法律で「宗教的な要素を含ませてはならない」という取り決めになったため、祭日という表現が使用できなくなったのです。
25:スーツの襟に穴があるのはなぜ?

スーツの襟には穴が開いているので、そこに社章をつけている人は多いですが、そもそもなぜ襟に穴があいているのでしょうか?
実はもともとスーツは軍服として作られたもので、それが形を変えて現代に至っています。
なので最初の頃は一番上までボタンが止められており、襟の穴も使われていたのですが、ビジネスで使われるようになってから襟の穴が無意味になってしまいました。
しかしイギリスの仕立て職人が「軍服であることを忘れないため」という理由で襟の穴を残したので、それが現代まで残り続けているというわけです。
26:名刺はなぜ「名を刺す」なの?

ビジネスパーソンの必需品といえば名刺ですよね。
その歴史は古く、2000年前の古代中国で誕生したと言われています。
その頃の呼び名は「刺(し)」で、紙ではなく木の札に自分の名前や挨拶文などを書いて渡していたそうです。
古代中国では「刺」という漢字には「書く」という意味があるので、その語源が伝わり現代の名刺という名称になっています。
27:ネクタイをつけるのはなぜ?

会社員の人はスーツにネクタイが定番ですよね。
そもそもネクタイとは17世紀頃のフランス貴族の服装が発祥だと言われています。
戦争に出向く兵士が、女性から首元に飾る布(クラヴァット)を渡され、それを首に巻いてお守りにしていたのです。
28:カップ麺の待ち時間が3分なのはなぜ?
カップ麺を開発したのは日清食品創業者の安藤百福ですが、安藤百福が待ち時間を3分と決めました。
実は現代の技術では、待ち時間を1分にしたり2分にすることもできますが、それでもあえて3分を選択する企業が多いのです。
人間は「食べちゃダメ」と言われると食べたくなる習性があるので、短すぎず長すぎない3分という時間が目安にされているそうです。
安藤百福の名言集は下の記事をご覧ください。
まとめ
ここまでビジネスに役立つ雑学をご紹介してきました。
雑学を知っておいて損することはないので、色々な雑学を学んでおきましょう!