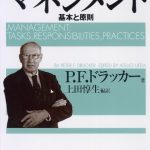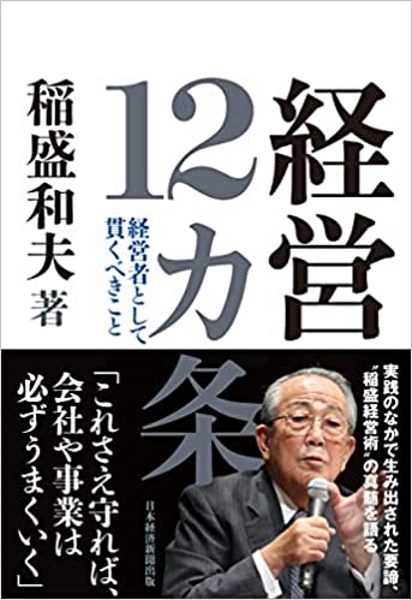
稲盛和夫(いなもりかずお)は京セラ創業者として有名ですよね。
惜しくも2022年8月に亡くなりましたが、「盛和塾」の塾長として国内外問わず多くの経営者たちに、自分が培った経営哲学(フィロソフィー)を伝達してきた偉人です。
京セラだけでなく、第二電電(現・KDDI)の設立やJAL(日本航空)再建も担った人物なので、名経営者であることは疑いの余地がありませんよね。
そのような人物だったので、これまで多くの名言や座右の銘を残しているのです。
そこで今回は、京セラ創業者である稲盛和夫の名言集をご紹介したいと思います。
京セラが成長する土台となった「アメーバ経営システム」に着目し、今回はそれに関連する言葉を集めてみました。
この名言集ではアメーバ経営のやり方、メリット&デメリットをわかりやすく解説しているので、最後まで読めばアメーバ経営の外郭が簡単&短時間に理解できると思います。
ビジネスパーソンはぜひご覧ください!
稲盛和夫の名言集まとめ
アメーバ経営は、小集団独立採算により全員参加経営を行い、全従業員の力を結集していく経営管理システムである。
経営者と従業員という関係性を超越した、仲間意識のある経営システムが「アメーバ経営」です。
アメーバ経営を実践する為には、全従業員が全力で仕事に打ち込める経営理念や経営哲学が必要となります。
中小企業と腫れ物は大きくなると潰れる。
中小企業が”中小企業”のまま大きくなった場合、その会社はいずれ倒産してしまいます。
内面が子供のまま社会に出ると、手痛いしっぺ返しをくらいますよね。
イメージはそれと同じです。
なので、中小企業を脱する革新的な経営システムが求められるのです。
会社をビジネスの単位になりうる最小の単位にまで分割し、その組織にそれぞれリーダーを置いて、まるで小さな町工場のように独立して採算を管理してもらえば良い。
アメーバ経営の根幹にあるのは、このような考え方です。
独立採算制を導入するためには損益計算が必要になりますが、会計知識を持たない人でもわかるように「時間あたり採算制」を導入したそうです。
ちなみに時間あたり採算表とは、「売上を最大にして、経費を最小化すれば、その差である付加価値も最大になる」という経営の原則を採算表の形で表したものです。
この「時間あたり採算制度」については後で解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
アメーバ経営のメリットは、リーダーを育てると同時に、従業員が経営に関心を持ち、経営者マインドを持った従業員が社内に増えることである。
全員参加型の経営システムがアメーバ経営です。
その結果、当事者意識のある社員が増えていくのです。
売上を最大にして、経費を最小化する。
これは稲盛和夫が京セラを経営する上で目指した経営哲学(フィロソフィー)であり、アメーバ経営を実践する上でのポイントになります。
パッと見すると当たり前のことを言っているようですが、これが実践できている企業は少ないようです。
稲盛和夫曰く「売り上げはいくらでも増やすことができるし、経費も最小にすることができる。そう考えた場合、利益はどこまでも増やすことができる。」と語っています。
「なかなか利益が出せない…」という経営者は、「売上を最大にして、経費を最小化する。」というシンプルなことすら実践できていないのです。
経費を最小にすると言っても、組織が大きくなれば、ついどんぶり勘定になってしまい、どこでどんな経費が発生しているのか分からなくなってしまう。
これは経費を最小化する難しさについて語った名言です。
これを解決するアイデアを、稲盛和夫は「ユニットオペレーション」と命名しました。
それは各部門(営業部、購買部、製造部など)を一つのユニットとし、そのユニットがお互いに社内売買するような仕組みのことを言います。
京セラの場合には、原料部門が調達した原料を成形部門に売って、成形部門は原料部門から仕入れるという概念を作り出したのです。
それによって原料部門でも「成形部門への売上50-原価10=粗利40」というような損益計算ができるようになりました。
会社を小さなユニットオペレーションの集合体にすれば、経営者はそれぞれのユニットから上がってくる採算状況を見ながら、どこが儲かっているのか、損をしているのか、という会社の実態をより正確に把握することができる。
これは独立採算制のメリットについて語った名言です。
大きな会社は事業実態が把握しづらくなるので、ユニットオペレーションした方が経営はクリアになるのです。
京セラのユニットオペレーションである「アメーバ」の呼び名は、その小集団組織がまるで細胞分裂を自由自在に繰り返すアメーバのようだと表現した。
アメーバ経営は組織を独立採算制にするだけでなく、ユニット数を自由自在に増やしたり減らしたりする、柔軟性も持ち合わせているのです。
どんな会社でも、経営者とは孤独なものである。
経営トップは自らの意思で判断し、最終的に決断を下さなければいけません。
その決断に対して責任を負う必要もあるので、常に心細いのです。
しかしアメーバ経営であればユニットごとのリーダーがいるので、共同経営者として一緒に考えてくれる仲間が増えることになります。
もし会社が一つの大家族であるかのような運命共同体となり、経営者と従業員が家族のごとくお互いを理解し、励まし合い、助け合うならば、労使一体となった会社経営ができるはずである。
このような考え方を稲盛和夫は「大家族主義」と命名しました。
アメーバ経営の根幹には大家族主義の血脈が流れているのです。
アメーバが一つの独立した事業として成り立つ、最小限の機能を持った単位でなければならない。
これはつまり、一つのアメーバがビジネスとして完結する単位である必要があります。
そうしなければユニットリーダーが創意工夫する余地が無くなるので、現場のやりがいも生まれないのです。
アメーバは、細かくすればするほど良いというものでは決してない。
一見するとアメーバ経営には大きなメリットがあるように感じますが、やはりデメリットもあるようです。
組織というものをあまり細かく分けてしまうと、小さい組織(ユニット)が乱立するようになるので、結果的に無駄が生じてしまうのです。
アメーバリーダーが、小さな組織であっても経営者としてやりがいを感じることが重要である。
ユニットリーダーは、そのユニットの採算が合うように動きますが、自分が創意工夫することによって事業を改善できなければモチベーションが下がってしまいます。
これは非常に重要なポイントなので、ユニット制を取り入れる時には注意するべきでしょう。
たとえアメーバとして収支を明確に計算することができ、事業として完結した単位になっていたとしても、会社の方針が阻害される場合には、その組織をアメーバとして独立させてはならない。
これはアメーバ経営する時の注意点を語った名言です。
アメーバ経営では基本的にユニット制を導入するべきですが、会社の方針とバッティングする部署の場合には、ユニットとして独立させてはいけないのです。
「アメーバ組織をどのように作っていくのか?」ということは、アメーバ経営の始まりであり、終わりである。
アメーバ組織を作るということは、ビジネススキームを構築するのと同じです。
このユニット制が完璧であればあるほど、売上の最大化&コストの最小化に貢献することでしょう。
アメーバ経営の特長は、経済状況、市場、技術動向、競合他社などの急速な変化に対し、アメーバ組織を柔軟に組み換え、即座に対応できるところにある。
アメーバ経営に基づいてユニット制度を導入した場合、それで万事OKというわけにはいきません。
経済状況に応じて、その時々に合ったベストな組織にする必要があるのです。
稲盛和夫曰く、アメーバ組織を常に最適なものにしておくことは一番重要なことであり、これに失敗すればアメーバ経営の意味がなくなってしまうと語っています。
アメーバ間の売買価格を判断する人が常に公正・公平であり、みんなを説得するだけの見識を持ち合わせていなければならないのである。
アメーバ経営では、ユニット間の収支がはっきり数字に表れますが、社内取引なのでフィアな売値(値決め)でなければいけません。
それを第三者的に確認する人が、アメーバ間の売買価格を判断する人(経営者)なのです。
アメーバ経営では自分の組織を守るという思いが人一倍強くなるために、部門間の争いが激しくなり、会社全体の調和が乱れやすいのである。
これはアメーバ経営のデメリットについて語った名言です。
特にユニットリーダーは自分が担当する部門の採算性を高める為、多少無理してでも売値を上げようとします。
それに対して買い手側のユニットは、できるだけ原価を下げたいので、買値を下げようと努力します。
これによって同じ会社内で争いが生じてしまうのです。
これを解決する手段は、経営哲学(フィロソフィー)をユニットリーダーに浸透させる事だと語っています。
その根幹となる考え方は「人として正しい行動をする」ことだと、稲盛和夫は語っています。
「才子、才に溺れる」という言葉があるように、優秀な人材が才覚の使い方を誤ると、とんでもない問題を引き起こす。
商売には才覚が必要ですが、才覚がある人ほどそれにふさわしい人格を持っていなければいけません。
才能がない人は、ずる賢いやり方すら思いつきませんが、頭のいい人は不正なやり方を思いついてしまうので、それを自制する必要があるでしょう。
ユニットリーダーを指名する場合には注意しましょう。
私は常々、リーダーとは、全き人格者でなければならないと言っている。
優秀なリーダーであれば偉業を成し遂げられますが、悪いリーダーが指揮をとると、その会社は海賊船にもなってしまうのです。
金銭により人の心を操るような報酬制度を京セラはとっていない。
アメーバ経営はユニット制なので、自分の所属するユニットが好成績を出した場合、そこにインセンティブを支払う気がしますよね。
しかし京セラでは、いくらアメーバが時間あたりの生産性を高めたとしても、それによって昇給したり、賞与が増えるということはないそうです。
もちろん長期的な処遇には反映されるのですが、大きく貢献したユニットには賞賛と感謝という「精神的な栄誉」が与えられるだけなのです。
この部分について稲盛和夫は「京セラの経営理念は、信じ合える仲間の幸福のために貢献することだから、会社への貢献を皆から賞賛されることが最高の栄誉であると考えている」と語っています。
むしろ成果主義で見られるような実績数に直結した金銭的インセンティブは、非常に危険であると稲盛和夫は警鐘を鳴らしています。
アメーバ経営は、経営者と従業員、従業員同士の間にある信頼関係をベースにした全員参加の経営である。
「どうすれば当事者意識を持ってくれるのか?」と経営者は頭を悩ましていますよね。
アメーバ経営であれば一人一人が「自分も経営者だ」という意識を持つので、自然に当事者意識が身につくのです。
組織運営をしていく上で重要なことは、本当に実力のある人がその組織の長につくことである。
稲盛和夫は年功序列や温情主義について警鐘を鳴らしています。
実力のない人物がリーダーになると、会社経営はすぐに行き詰まり、全従業員が不幸を背負うことになるのです。
よって、京セラでは「実力主義」を原則にしているそうです。
アメーバ経営における組織編成は「まず機能があり、それに応じて組織がある」という原則に基づいて、最低限必要な機能に応じた無駄のない組織を構築することが基本になっている。
会社には経理部、総務部、人事部、企画部、製造部、営業部…などの部署がありますよね。
そのような部署を先に作るのではなく、まずは会社運営に必要な機能を考えるのです。
もし人材採用を積極的にやらないのであれば「人事部は必要ない」ので総務部と一緒にします。
総務関係の仕事がそんなに無ければ、経理部と一緒にして「管理部」と命名しても良いでしょう。
このように会社運営に必要な機能を軸に、組織を構築していくのです。
組織変更においては「朝令暮改も必要である」という前提に立つ、ダイナミックな事業展開を心がけるべきである。
リーダーの中には「指示が二転三転すると現場が混乱する」と慎重に構える人は多いですが、スピード感をもった経営を心がけるのであれば、多少の歪みは仕方ありません。
誤った判断だと気付いた場合、もし最適解が閃いたのであれば、むしろ積極的に朝令暮改した方が良いと思います。
あらゆる創意工夫によって売上を増やす一方で、常に経費を徹底して切り詰めていくことが経営の原則である。
利益を増やすためのアプローチは、究極的に言えば2種類しかありません。
- 売上を増やす
- 経費(コスト)を削減する
どちらのアプローチでも利益を増やせますが、スピード感のある経営をしたいのであれば、まずは経費削減から始めていきましょう!
雑費というのは種々雑多な経費からなり、他の科目に比べて金額が小さいから雑費なのであって、無視できないような大きな金額であればそれを一括りにすべきではない。
これは雑費について語った名言です。
多くの企業では、他の経費科目より雑費の方が大きいという場合があります。
そのようなどんぶり勘定に対して警鐘を鳴らしたのです。
アメーバ経営では「コスト意識」が重要なので、一つの勘定科目についても真剣に捉える必要があります。
アメーバ経営では、営業部門と製造部門がそれぞれ独立採算(プロフィットセンター)であるために、アメーバの全員が少しでも付加価値を高め、採算を向上させるように努力する仕組みとなっている。
経営学の父と言われているピーター・F・ドラッカーは「営業部門以外全てコストセンターだ」と言いました。
経理部門や製造部門は直接的に利益貢献しないので、コストだと言い切ったのです。
しかし、アメーバ経営では全てのユニットがプロフィットセンターだという考え方になります。
ピーター・ドラッカーの考え方と比較したい人は下の記事もご覧ください。
「売上最大、経費最小」という原理原則は、時間あたり採算制度のベースとなるものである。
アメーバ経営を理解する上で「時間当たり採算制度」について、きちんと理解しなければいけません。
時間当たり採算制度は、アメーバ経営を実現するために稲盛和夫が考案した会計制度です。
そんなに難しい話ではありませんが、考え方は以下の通りです。
※あくまでも金額は一例です。
まず売上高100万円(社内販売、社外販売の両方がある)だった場合、その中から購入した金額30万円(社内購買、社外購買の両方がある)を差し引きます。
つまり売上から原価を差し引きます。
するとアメーバの儲けである70万円(粗利)が導き出されますが、そこから今度は諸経費(販管費)を差し引くのです。
もしその金額が20万円だった場合、差し引き50万円のアメーバ利益となりますよね。
そしてアメーバ経営の場合には、その金額の中に人件費が含まれていないことが特徴的です。
一般的な会計制度の場合、販管費の中には人件費を含めますが、人件費はユニットリーダーがコントロールできる部分ではない為、アメーバ経営の時間当たり採算性を測る上で除外すべき項目とされたのです。
あとはアメーバの総労働時間を計算し、その総労働時間とアメーバ利益を割れば時間当たりの採算金額が導き出されます。
「総労働時間=1日8時間×20日=160時間(残業があればその時間も含める)」
「50万円÷160時間=3,125円」
これは1名のアメーバだった場合を想定した計算ですが、もちろんアメーバ内に複数人のメンバーがいれば、その人達の労働時間全てを計算に加味する必要があります。
ここで導き出された3,125円というのが、このアメーバの「時間当たりの採算金額」になる為、時給1,000円で人を雇えば、1時間あたり2,125円の利益が出せるという計算になるのです。
ある部署で時間あたり労務費が平均3,600円かかっているとする。
そうすると1分間あたり60円、さらに言えば1秒間に1円の労務費が発生していることになる。
人件費について1秒単位まで計算する社長は少ないと思います。
稲盛和夫はとてもコスト意識の高い経営者でした。
大企業の経営者としては珍しいですが、たとえ1円だったとしても、決して無駄にしない意識を持っていたのです。
現在の企業経営ではスピードが何よりも重視されており、時間効率をいかに高めていくかが、競争に勝つためのカギとなっている。
アメーバ経営における時間あたり採算制度によって、現場の指標に「時間」という概念を持ち込みました。
それによって一人ひとりが時間の大切さを自覚するようになり、生産性を上げることに成功したのです。

アメーバ経営は革新的システム
ここまで京セラ創業者「稲盛和夫」の名言集をご紹介してきました。
読み終えた人はアメーバ経営というやり方が「いかに革新的な経営手法だったのか」が理解できたはずです。
- 従業員に当事者意識が芽生えない…
- 従業員のモチベーションが上がらない…
- コストを上げずに生産性を高めたい…
- 事業のボトルネックがすぐに見つからない…
- 企業経営を透明化したい…
このような課題を抱えている企業には、アメーバ経営がぴったりかもしれません。
「経営の神様」と呼ばれることも多い稲盛和夫なので、ぜひ残された「有益な知識(ノウハウ)」をあなたのビジネスに活かしてみてください。
稲盛和夫が好きな人は下の記事もぜひご覧ください。