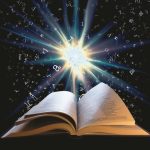ディストリビューターと呼ばれる『ビジネススキーム』があります。
しかしビジネス界隈においてもあまり聞きなれない言葉なので、「詳細がわからない…」というビジネスパーソンも多いと思います。
そこで今回はディストリビューターの意味や役割、ビジネスへの活用方法について解説していきたいと思います。
目次
ディストリビューターの意味とは?
ディストリビューター(distributor)とは、英語由来の和製語になります。
その意味は下記のようなものになります。
- 分配者
- 配給者
- 卸売業者
つまりディストリビューターとは、メーカーなどから商品を仕入れて、その商品を小売店に卸す”中間業者”と解釈するのがわかりやすいと思います。
例えば、海外や国内メーカーから商品を仕入れている”商社”もディストリビューターの1つになります。
ディストリビューターはあくまでも”中間業者”として存在しているので、基本的には直接販売するわけではありません。
また、ディストリビューターが取り扱う商品は複数にまたがることもあれば、限定されていることもあります。
つまり、1つのディストリビューターが衣類と食品など、全く別の商材を扱うこともあるのです。
ディストリビューターの役割とは?
企業単位でメーカーから大量に仕入れて、それを販売店に卸す権利が認められているので、ディストリビューターには”商品を市場に供給する”という役割があります。
しかし海外メーカーと取引する場合、ディストリビューターの営業エリアが限定されていることもしばしばあります。
このようなケースは「エリア代理店」と呼ばれていて、ドミナント戦略をとりたいメーカーにとっては都合が良いと思います。
他にも、例えばイタリアのパスタメーカーが日本で自社製品を販売したいと思ったとき、ディストリビューターとして選ばれるのは『日本の数ある商社の中から1社だけ』というケースがあります。
選ばれたディストリビューターは、その製品をイタリアから輸入して日本の市場に卸す権利を持つことになるのですが、このようなケースは「総代理店」と呼ばれていて、こちらも代表的なディストリビューターの仕組みになります。
もし総代理店について詳しく知りたい方は、下の記事をご覧ください。
ただし、メーカーがディストリビューターを仲介せず、直接エンドユーザーに販売するケースも十分ありえるので、必ずディストリビューターを間に挟まなければいけないという訳ではありません。
ディストリビューターとビジネスの関わり
ディストリビューターは、メーカーが製造したプロダクトを市場へ展開していきます。
特定のメーカー品を仕入れる”独占権”を持っていることが多いので、販売業者はディストリビューターなくしてビジネスが成り立ちません。
流通の変化に伴って販売業者がメーカーから直接仕入れるスタイルが増えつつはありますが、大企業の商品などは販売業者が直接買い付けようとしてもなかなか難しいというのが現実だと思います。
ディストリビューターが取り扱う商品は幅広い分野に渡っているので、日常的に様々な商品を購入することができるのは「ディストリビューターのおかげ」だとも言えるでしょう。
メーカー側にも大きなメリットがある
メーカーにとって、小売り店に商品を直接卸すよりもディストリビューターに卸した方が大量に商品を捌けるというメリットがあります。
ディストリビューターには数多くの販路(販売店)があるため、仕入れた商品を販売店へ効率よく卸すことができ、結果的に多くの商品を市場へ流すことが可能となります。
ディストリビューターと契約しないで販売店に卸したり、個人に販売することもできますが、それでは短期間で売るのが難しい上に、複数の販売店や個人ユーザーの対応するのが手間なので、結果的にコストが嵩んでしまうというデメリットもあります。
こうした背景もあり、大手メーカーであるほどディストリビューターを通じたビジネスを好んでいると言われます。
ディストリビューターを使うメリット
先程解説した通り、ディストリビューターを使うメリットは”メーカー側”にも”販売店側”にもあります。
つまり、両者にとってメリットがあるので成り立つ仕組みだと言えますが、ここでおさらいしておきましょう。
メーカー側のメリットとは?
まずメーカー側にとってのメリットから解説していきたいと思います。
それは、自社製品を「一度に&大量に卸すことができる」という点です。
とりあえず大きめなディストリビューターに商品をまとめて卸してしまえば、「せっかく作ったのに在庫になってしまった…」ということがありません。
とりあえずディストリビューターに卸した分の売上は確保できるので、また製品作りに専念できるのです。
ディストリビューターが間に入れば、大中小様々な規模の販売店に卸す手間もかからないため、コスト削減につながるメリットもあります。
販売店側のメリットとは?
一方、販売店側がディストリビューターから商品を仕入れるメリットは、直接仕入れることが難しいメーカー品でも販売しやすくなるという点です。
1つのディストリビューターが複数のメーカー品を取り扱っていれば、そのディストリビューター企業と取引することで多くのメーカー品を仕入れやすくなりますよね。
つまり、商品ごとに取引契約があるとしても、複数のメーカーと取引するよりは、1社のディストリビューターと取引した方が手続きが簡略化できることになります。
すると、仕入れ値に関しても、交渉しやすくなるメリットが出てきます。
メーカー毎に仕入れをしている場合には、「100万円×10メーカー=1,000万円」のような取引関係になりますが、1社のディストリビューターと取引すれば1,000万円というまとまった取引金額になるので、価格交渉もしやすくなるという訳です。
スーパーやドラッグストアなど大手メーカーの売れ筋商品を幅広く取り揃えておきたい販売店などは、ディストリビューターの存在があってこそ多くのお客様を獲得できるのです。

ディストリビューターが多い業種業界
ディストリビューターが取り扱う商品は幅広い範囲に及びます。
そのため、「業種や業界を問わずに存在する」と言っても過言ではないでしょう。
ただし、様々な業種のメーカー品を仕入れて、小売り店に卸す商社だけがディストリビューターというわけではありません。
元々の意味である”分配者”という役割を果たす職業としては、もっと広義のディストリビューターが存在しています。
例えば、百貨店でバイヤーが仕入れた商品を「いかに効率よく采配するか?」を任されているのも、広義ではディストリビューターと言えるでしょう。
いわば在庫管理の役割をするわけで、個人商店で販売も在庫管理もしている人はディストリビューターと販売担当を兼任していることになります。
アパレル商品を扱うファッション業界でも、ディストリビューターは欠かせない存在です。
ファッション業界は流行の移り変わりが激しく、季節によっても商品の売れ行きに大きな差が出てきます。
在庫管理の仕方にビジネスの成否がかかっているといっても過言ではなく、少しでも多くの売上に貢献し、常にビジネスを先読みするような働きをしなければなりません。
他に、ディストリビューターの活躍が顕著な業種としてはネットワークビジネスがあります。
MLM(multi level marketing)の胴元企業と会員契約を交わして、実際に営業するのがディストリビューターです。
ネットワークビジネスにおいて、ディストリビューターは商品の販売や新たなメンバーの勧誘などを担当しているので、最も重要な存在となります。
ディストリビューターと代理店&卸売問屋
ディストリビューターに関連する仕事の種類には、以下のようなものがあります。
- 商社
- 卸売り
- 問屋
- 代理店
これらはディストリビューターと似た部分が多いのですが、明確な違いがあるので、ここでそれぞれの仕組みを理解しておきましょう。
商社とは?
まず、商社はディストリビューターの役割を持つ企業ですが、ディストリビューターが商社だけを指すわけではありません。
法律上の定義は商行為、その他の営利行為を目的として設立された法人が商社になります。
そして、商社にも特定分野の商品を扱う「専門商社」と幅広い商品を扱う「総合商社」があります。
代表的な企業は「三菱商事」「三井物産」「住友商事」などの元・財閥系商社が挙げられますが、そこに「伊藤忠商事」「丸紅」を加えた5大商社が日本では有名です。
”卸売り”と”問屋”の関係性とは?
卸売りと問屋には似たイメージがあると思います。
実際、商材を仕入れて売るという仕組みなので、商社業務にも共通点があります。
ただし、商社は基本的に物流を行いませんが、問屋は物流も担当するのが大きな違いになります。
卸売りと問屋の違いといえば、「法的に定義があるか否か?」ということでしょう。
問屋は、自社名義で他人のために物品の買い入れ等を行うものという商法上の定義があります。
しかし、卸売りは一般的な商行為なので、この辺りが違いになるはずです。
代理店とは?
代理店は、商品やサービスを代理販売する個人・法人をいいます。
販売や販促などの営業活動から、契約手続き、アフターフォローまでを担当していきます。
契約や販売の手続きを行っても、商品サービスの提供はメーカーが行いますので、あくまでも『販売会社』という立ち位置になります。
つまり、販売代理店は販売した実績分の手数料をメーカーから受け取って利益にするのです。
メーカーと特別な契約を結んでいることになりますが、中でも独占契約を行う販売店、あるいは代理店を「特約店」と呼ぶケースもあります。
他にも、
- 総代理店
- 一次代理店
- 専属代理店
など様々な仕組みが存在しています。
この辺りを詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
まとめ
ここまでディストリビューターについて解説してきました。
ここまで読み進めた人はディストリビューターという言葉の意味や、商社、卸売り、問屋、代理店の違いまで理解できたと思います。
それぞれの仕組みには色々な特徴があるのですが、どれも共通しているのは『業務をアウトソーシングする』ということです。
この部分だけは一緒なので、あとはニーズに応じて使い分けるのが良いと思います。
「少子高齢化で人手不足」と言われているこれからの時代は、いかに上手にアウトソーシングするかで成否が分かれると考えています。
上手にアウトソーシングを活用していきましょう!