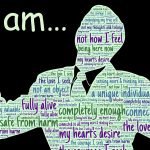「松竹梅の法則」を聞いたことがある人は多いと思います。
実はこの法則は営業活動にも応用することができます。
そこで今回は、「松竹梅の法則」の意味や使い方について詳しく解説していきたいと思います。
目次
「松竹梅の法則」の意味とは?
マーケティング戦略を立てる上で、商品の値段設定は非常に大切な要素だといえます。
値段を安く設定すればするほど販売量が多くなるのは当たり前ですが、そのやり方で儲けが出なければ本末転倒だと思います。
商売をする上では、売上&利益が出ないのであればモノを売るという行為自体が意味ないものになってしまうからです。
もちろん希望通りの価格で商品サービスを売るのが理想的ですが、そうなる為には販売する商材にそれだけの価値があるとお客様に納得してもらう必要があります。
そんな時、顧客の考えを誘導するのに役立つのが「松竹梅の法則」なのです。
「ゴルディロックス効果」とは?
仮に類似品物の価格を、
- 高価格帯(高い)
- 中価格帯(普通)
- 低価格帯(安い)
と設定した場合、人は中価格帯の商品を選びたくなるという法則があります。
このロジックこそが「松竹梅の法則」です。
松竹梅の法則は、心理学の「ゴルディロックス効果」と似ていると言われることがありますが、これは人が大、中、小の3種類の中からひとつを選ぶ際、ついつい真ん中のものを選びたくなるという心理現象のことを言います。
ゴルディロックス効果は、人が安定性を求めることによって発生すると考えられています。
そこに明確な理由が無い場合、人は大や小などの極端(=不安定)な選択をしにくい心理を持っているのです。
松竹梅の法則は、まさにこのゴルディロックス効果を利用したものなのです。
特に狙っていなかったとしても、松竹梅の法則は世の中のあらゆる商売で働いています。
例えば飲食店などでよく見られるS、M、Lなどのメニューサイズは、ほとんどの場合においてM>S>Lの順に売り上げが多く、松竹梅の法則が正しく存在している事が見て取れます。
「松竹梅の法則」の価格設定
マーケティング戦略として「松竹梅の法則」を用いる場合、気を付けておきたい事があります。
それは松竹梅、それぞれの商品が持つ役割と商品価値をよく吟味した上で、バランスの良い価格設定をし、その上で一番「竹」が売れやすくなるよう調整しなければならない事です。
もしそのバランス感覚がよく分からないなら、自分が松竹梅の福袋からひとつ選んで買う時の「期待感」を想像してみると良いかもしれません。
その中でも、真ん中の最も売れやすい「竹」商品は、最も利益率が高くなるような価格付けをすべき商品といえます。
その理由は「一番良く売れる」と想定されるグレードだからです。
この竹の利益率が一番高くなければ、ビジネスモデルの設計自体が間違っていることになります。
とはいえ、商品価値と比べて無闇に安くしたり高くしたりするのは避け、「適正価格」で販売するのがおすすめです。
最も高価な「松」の商品に重要なのは、その高額に見合う商品価値(プレミア感)をきちんと用意する事です。
絶対にNGなのが、価格ほど価値のない商品を松として販売する事で、最悪の場合、顧客の信用喪失に繋がる恐れがあります。
- 梅の福袋は手に取りやすいけど、それなりのものしか入ってなさそう
- 竹の福袋はそこそこの値段だし、変なものは入っていないだろう
- 松の福袋は高いけど、良いものが入っているに違いない
松竹梅からどれを選んだとしても、購入したお客様が「損をした!」と思わないような商品価値、価格設定である事が大切なのです。
付け加えるなら、いざサービスを頼むとき、思ってもみなかった嬉しい驚き(サプライズ感)が演出できると尚良いと思います。
アンカリングを活用する
松竹梅の法則を成立させる為には、「梅」の商品に意味を持たせなければいけません。
それは、松竹梅の商品群全体に対する「アンカリング」の役割になります。
アンカリングのアンカーとは、船が海に落とす錨(イカリ)の事で、マーケティング的には商品に対しての「第一印象」を指します。
梅の商品は価格的に手が出やすいため、
- 一連の商品群がどういうものなのか?
- どれくらいの量が入っているのか?
- いくらが適正価格なのか?
ということを顧客に印象付けることができます。
例えば、全く知らない商品、例えば「レバノンの倒木杉で作った笛」というモノがあったとします。
そのような商品にはこれまで全く触れたことがないので、1個1,000円と言われても、1個10万円と説明されても適正値なのかが判断できません。
このようなケースでアンカリングは効果を発揮します。
例えば、一番安価な梅の価格が1万円だと明示されていれば、竹は3万円、最上位の松は5万円という具合で妥当性が出てきます。
アンカリングを活用することで、顧客の心理には相場観が出来上がるので、購入に結びつきやすくなるのです。
もしアンカリングについて詳しく知りたい場合には下の記事をご覧ください。
「松竹梅の法則」の活用例
「松竹梅の法則」を実際に活用するためには、選択肢を「3つ」にする事、さらには一番売りたい商品を松竹梅の「竹」に設定する事がとても重要です。
松竹梅の法則に則ったマーケティングをしたいなら、あれこれとオプションや価格帯を設定し、選択肢を4つ以上にするのは逆に悪手となります。
何故なら、人には「極端回避性」「選択回避の法則」という心理的作用があり、あまりに際立った選択肢や、数多くの選択肢を提示されると、逆に商品の購入を避けたり見送ってしまう傾向があるからです。
あくまでも松竹梅の法則を活用したマーケティングを行うなら、自由度の高い選択肢を用意するより、厳選した3つの選択肢を用意する方が、効果的だといえます。
「松」と「梅」があるから「竹」が活きる
一番売りたい商品を真ん中の価格帯のものにする事は、松竹梅の法則の基本です。
そしてその際、「竹」にあたる商品を一番儲かりやすい商品にする事も同じくらい重要といえます。
例えば、SaaS(クラウド上で提供されるソフトウェア)のプランを提供する場合などは、
- ライト:3万円
- プロ:8万円
- カスタム:応相談
と料金設定します。
真ん中の「プロ」の利益率が一番高くなるようにサービス内容を設定すれば、松竹梅の法則の恩恵が受けられるはずです。
もちろんそういったケースにおいても、「ライト」や「カスタム」のサービス内容を蔑ろにする様な事があってはなりません。
前段で述べたようにライトは「アンカリング」の役目を十全に果たせるようなサービス内容にして、カスタムはきちんとプレミア感が感じられるようなサービス内容にしておく必要があります。
「松」と「梅」の部分がしっかりしているからこそ、「竹」を売り出す効果もより高くなるのです。
「松竹梅の法則」は営業にも活かせる
「松竹梅の法則」は小売りだけでなく、営業活動においても役立つ法則です。
例えばある商材の営業を行う場合、
- 梅プラン:3万円
- 竹プラン:5万円
- 松プラン:10万円
と3段階のパターンで営業すれば、お客様にサービスの商品価値、販売価格の相場観をざっくり伝える事(アンカリング)ができます。
もし仮にひとつのプラン、一本値の商材だけで営業した場合、顧客はそのサービスの商品価値が価格に見合うものなのか判断する材料がないため、結果的に契約締結まで繋がりにくくなるでしょう。
つまり受注率が落ちることが想定されるのです。
また見込み顧客に3つの選択肢を提示する事で、前述した「ゴルディロックス効果」も期待できます。
提案によって商材の価値が価格に見合うものだと理解してもらえれば、ゴルディロックス効果の心理的作用により、最も利益率の高い「竹」の商品を購入してもらえるハードルがグッと下がります。
特に新規営業において、あまりたくさんの選択肢を提示することは禁物です。
「極端回避性」や「選択回避の法則」などに見られる心理作用によって失敗する可能性が高くなってしまうからです。
松竹梅の法則を営業で活用する時には、選択肢を厳選した3つに絞る事がより重要になってくるのです。
心理学や行動経済学を活用する
「松竹梅の法則」は行動経済学の内容にあたります。
行動経済学とは、「一見すると合理的に思えないような行動を消費者は取る」ことを研究する学問です。
例えば、あなたがスーパーマーケットに行ったとします。
そこの果物売り場に1個398円のメロンと、1個980円のメロンがあったとします。
これだけを見ると1個398円のメロンだけが売れそうな気がしますが、実際には1個980円のメロンも売れるのです。
その理由は付加価値の提供にあります。
1個980円のメロンには、下のようなPRが付け加えられていることでしょう。
高糖度!糖度16度なのでとても甘いです。
テレビで紹介された大人気のメロンです。
このような付加価値をつけることで、人間は合理性に基づかない不合理な行動をとるのです。
ここで紹介した事例だけみても、人間の心理がどれだけマーケティングによって影響を受けるか窺い知れることでしょう。
- 人がしたがる事
- 人がしたがらない事
は誰しも感覚的に理解しています。
しかしそういった人の行動原理を学問として捉え、学ぶ事によって、企業のマーケティングや営業活動に応用する事ができるのです。
行動心理学の第一任者と言われるダン・アリエリー氏の著書もご覧ください。

知識をビジネスに活用する
マーケティングにおいて「商品を買ってもらう事」は簡単ではありませんが、「商品を買ってもらうよう誘導する事」は意外と簡単です。
その理由は、前者が他人に行う提案行為であるのに対して、後者は自らの意思で行う行為だからです。
心理学や行動経済学を学ぶ事は、後者のレパートリーを増やす事に繋がります。
そうして「商品を買ってもらうように誘導する事」を続けていけば、それはいずれ利益(儲け)というカタチになって現れることでしょう。
まとめ
マーケティングの二大巨頭といえば、フィリップ・コトラーとマイケル・ポーターだと思います。
松竹梅の法則をはじめ、マーケティング施策を行うのであれば、この二人の本ぐらいは読むようにしましょう。
フィリップ・コトラーの書籍はこちら↓↓↓

マイケル・ポーターの書籍はこちら↓↓↓

他にも、心理学や行動経済学で有名な理論には、「松竹梅の法則」の他にも「ヒューリスティクス」や「プロスペクト理論」などが挙げられます。
仕事がうまくいかず悩んでいる時は、そういった心理学や行動経済学を軸にする事で、課題や問題を解決できるかもしれません。