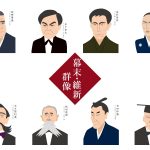ウォルト・ディズニー・カンパニーは、ウォルト・ディズニーが実兄のロイ・ディズニーと一緒に創業したアメリカの映像制作会社ですが、今ではディズニーランドの運営まで行なっているので、総合的なエンタメ企業になっていると思います。
そのブランド価値は凄まじく、常に世界トップレベルのブランドとして認知されています。
今ではアメリカだけでなく、世界を代表する企業に成長したディズニーですが、創業当時には一度倒産するなど、決して順風満帆な道のりではなかったそうです。
特に映像制作会社からエンターテイメント企業へ成長するきっかけとなった「ディズニーワールド」のオープンに際しては、すべての役員から反対されたとウォルト・ディズニーは語っています。
それでも自分が描いた映像作品の世界観を「現実世界に表現したい!」という想いから、ディズニーランドをオープンさせるに至ります。
それだけの大博打をやりながら、大成功を収めたディズニーランドですが、成功の秘密とは一体何だったのでしょうか?
この記事では、ディズニーサービスの真髄や、その中身について触れていきたいと思います。
目次
ディズニーが「凄い」と言われる理由
「ディズニーはとても優秀なビジネスモデルだ」と言えば、ほぼすべての人が同意してくれるはずです。
しかし「具体的にどのような部分が競合他社と違って、どんな風に凄いのか?」と質問すると、おそらくほぼすべての人が答えられないでしょう。
これは非常に残念なことですよね。
身近に素晴らしいビジネスモデルを展開している企業があるのに、それを参考にしないなんて勿体ないと思います。
もしあなたがビジネスパーソンならば、ディズニーサービスの仕組みや、感動を与える仕掛けについて知っておくべきだと思います。
その知識はきっとあなたのビジネスに役立ちますし、もしあなたが営業職なら、お客様に”ディズニーのビジネスノウハウ”を情報提供するだけでも喜ばれるばすです。
もちろんサービス業であればすぐに実践できる内容だと思いますし、それ以外の業種業態だったとしても、何かしらビジネスのヒントが見つかるはずです。
ぜひディズニーのビジネスから成功法を学びましょう!
ディズニーサービスの真髄とは?
東京ディズニーリゾートの入園者数は、東京ディズニーランドと東京ディズニーシー二つのテーマパーク合わせて、年間およそ3,000万人も来園していると言われます。
もちろん同一人物が来園している重複カウントもありますが、それにしても凄い数字ですよね。
これだけの数字を叩き出せるのは、新規来場者数だけでは絶対に無理だと思います。
つまり、ディズニーリゾートの収益はリピート顧客によって成り立っているということです。
その数は年間2,000万人以上とも言われているので、来園者の半数以上がリピート顧客だということに気づきます。
多くの人はディズニーの魅力に惹かれて「夢と魔法の王国」というイメージを持っているかもしれませんが、それはあくまでも表面上の話です。
ビジネス的な観点で言えば、ディズニーリゾートは「ファミリーエンターテイメント」だといえます。
つまりファミリー層をターゲットにしたビジネスモデルだということです。
例えば、あるファミリーが子供を連れてディズニーランドへ行ったとします。
そうすると、そこで楽しい思い出をたくさん作って帰りますよね。
その思い出を持った子供が成人になると、自分を楽しませてくれる場所として、友人と遊びに出かけたり、恋人とのデートに使ったりするのです。
そして結婚して子供ができると、「自分のようにいい思い出を作って欲しい」という気持ちから、子供を連れてディズニーランドへ出かけるのです。
このサイクルが延々と続いていくため、ディズニーリゾートの来園者数は基本的に落ちることがないのです。
秘密のキーワード「SCSE」
ディズニーの理念やテーマを実現するために、あるキーワードが設定されています。
それが「SCSE」です。
S=SAFETY(安全性)
C=COURTESY(礼儀正しさ)
S=SHOW(ショー)
E=EFFICINCY(効率)
この4つの頭文字をとって「SCSE」と呼ばれていますが、安全性とはお客様が安心してアトラクションに乗れたり、安心して食事ができる、安全第一に考えてサービス提供することです。
そして礼儀正しさとは、お客様に対する対応のことを言っています。
3番目のショーは、ディズニーの代名詞とも言えますが、エンターテインメント部分のことを言っています。
そして効率は、できるだけ多くのお客様にパーク内のエンターテイメントを楽しんでいただくことを指します。
この4つは一見すると大雑把なキーワードに思えますが、これがパーク運営において全ての業務と繋がってくるのです。
例えば、下のようなアクシデントが起こったと仮定しましょう。
お客様がパーク内で落とした携帯電話を探している。
このようなアクシデントが起こった場合、企業はマニュアルに沿って対応すると思います。
しかし、現場のアクシデントは多種多様なので、全てマニュアル通りに対応することは不可能でしょう。
そんな時に役に立つのが「SCSE」という考え方なのです。
上記のようなアクシデントだった場合、
- S=お客様の安全は確保できているか?
- C=お客様に対して礼儀正しく対処できているか?
- S=お客様に対してショーの楽しさを壊していることはないか?
- E=お客様に対して効率よく迅速に対処できているか?
というポイントを「SCSE」に基づいてスタッフは確認すれば良いのです。
そしてマネジメントする管理職は、
- S=お客様の安全性は確保できているか?
- S=スタッフの安全性は確保できているか?
- C=お客様に対して礼儀正しく対処できているか?
- C=スタッフの接客を確認
- S=お客様に対してショーの楽しさを壊しているようなことはないか?
- S=スタッフの行動を確認
- E=お客様に対して効率よく迅速に対処できているか?
- E=スタッフは効率よく迅速に対処できたか?
というポイント確認するのです。
この考え方が浸透しているからこそ、サービスクオリティが一定品質に保てて、結果的にリスクマネージメントにも繋がっているのです。
サービスで感動させるディズニーの仕掛け
ディズニービジネスを考察する場合、サービス内容に目を向ける必要があると思います。
ディズニーリゾートはサービス業ですが、そもそもサービスとは一体何なのでしょうか?
それは「付加価値」を意味しています。
例えばディズニーランドの中にはアトラクションやレストランがありますが、それだけを目的に来園している人は少ないですよね。
そこで提供されるサービスも含めて目的となっているため、そもそもディズニーではビジネスモデルにおける付加価値が高いと言えるのです。
例えば、大人気アトラクションであるビッグサンダー・マウンテンは、アメリカのゴールドラッシュをテーマにしたアトラクションです。
ビッグサンダー・マウンテンに行ったことがある人はピンと来るかもしれませんが、実はあそこに飾られている小道具は全てアメリカから直輸入した本物なのです。
そのような小道具を気にするお客様は少ないかもしれませんが、細かい部分への本物志向が、ディズニーの付加価値へとつながっているのです。
サービス業においての付加価値とは「サービスそのもの」ですよね。
つまり目に見えないモノですが、そこで手を抜かないのがディズニーのポリシーなのです。
非日常を演出する
ディズニーでは非日常を作り出すため、沢山の努力が行われています。
それを実現しているのは働いている従業員ですが、その従業員のことをディズニーでは「キャスト」と呼んで、お客様のことを「ゲスト」と呼んでいます。
そもそもディズニーは映像制作会社として始まっていますが、その世界観を現実世界に表現しようと試みたのがディズニーランドです。
そう考えた場合、テーマパークすべてが舞台(ステージ)になるので、そこで働く人は全て映画の出演者(キャスト)という考え方になるのです。
そして、そのステージを見に来ているお客様が「ゲスト」ということになるのです。
ゲストが楽しめるように、キャストは接客しますが、そのためには舞台を整える必要もあります。
例えばディズニーランドでは、テーマパーク内から外の景色が一切見れないようになっています。
また、食べ物や飲み物の搬入作業を見ることもありません。
このような日常風景を一切感じないステージを用意し、テーマ性を損なわない小道具や工夫をたくさん凝らし、ゲストが「夢の国にいる」と錯覚するような演出を施しているのです。
お客様を飽きさせない
ディズニーのアトラクションは待ち時間は長いですよね。
その待ち時間にストレスを感じる人は多いかもしれませんが、実は待つこと自体をアトラクションの一部として設計しているのです。
具体的にディズニーのアトラクションは下の三つに分けられています。
- プレショー(気持ちを盛り上げる効果)
- メインショー(アトラクション本体)
- ポストショー(余韻を楽しむ効果)
これらが一つになったものが「アトラクション」なので、待つこと(プレショー)もアトラクションの一部とされているのです。
例えばビッグサンダーマウンテンでは、アトラクションの搭乗口までかなり距離がありますが、歩いている途中にシャベルやツルハシなどの小道具が置いてあったり、金鉱山のような作りになっているので、事前情報がない人でも「ゴールドラッシュがテーマなのかな…」と感じることができます。
そして、アトラクションのキューライン(待つ列)にも工夫があります。
ディズニーランドのキューラインは横幅1mに設計されていて、大人二人が並ぶとギリギリの幅になっています。
この幅にしておけば、アトラクションの処理(搭乗数)と連動するので、少しずつですが、徐々に徐々に前に進むことができるのです。
確かにディズニーランドで並んでいると、立って待っている時間は少なくて、少しずつですが前進してきますよね。
人間はずっと同じところで待っている事を我慢できない生き物です。
なのでキューラインを工夫することで、少しでも「待つ」という感覚を和らげて、ステージ上の物語を徐々に進行させているのです。
レストランサービスの裏側
ディズニーランドの中には、たくさんのファストフードがありますよね。
しかしそこのメニューが「意外と少ないな…」と感じた経験がある人は多いと思います。
実はココにも「SCSE」の考え方があるのです。
ディズニーのポリシーは「E=お客様に対して効率よく迅速に対処できているか?」という考え方なので、お客様にはできるだけ迅速に料理を提供し、たくさんのアトラクションに乗って欲しい、という結論になるはずです。
この理念を実現するため、あえてメニュー数を削減しているのです。
例えばメニューの数が多いと、
- 注文するお客様がどれにしようか迷う
- 調理マニュアルが複雑なので時間がかかる
- 提供する料理が遅くなる
という悪循環にはまっていきます。
しかしメニューの数が少ないと、
- お客様の注文がすぐ決まる
- 調理マニュアルがシンプルなので作業動線もラク
- 提供するスピードが早くなる
という好循環を実現できます。
バフェテリアの運営ノウハウ
ディズニーランドの中にはレストラン形式のバフェテリアがあります。
バフェテリアサービスとは、お客様がトレーを持ち、カウンターに並んだ料理から各自の好みの料理や飲み物を自由に選んで、テーブルに着く前に会計する形態のことを言います。
この順番がディズニーでは「サラダ⇒デザート⇒スープ⇒メイン料理⇒ドリンク」という順番になっています。
なぜこのような順番になっているのかと言うと、少しでも顧客単価を上げるために工夫されているのです。
具体的に言うと、レストランに来る人はお腹が空いているはずなので、必ずメイン料理を頼みますよね。
なので「メイン料理⇒スープ⇒サラダ⇒デザート⇒ドリンク」という普通の順番で提供してしまうと、メイン料理だけ手に取って、その他の食事は手に取られない可能性が高くなってしまうのです。
しかしまだトレーに何も載ってない状態で、彩の美しいサラダが目に入ってくれば、なんとなく健康を気遣って手に取る人が多くなるのです。
そして普段食べないデザートまで「久しぶりのレジャーだし…」という感覚で手にとって、気が付くとメイン料理以外にもたくさんの料理がトレーに並んでいる、という結果になるのです。
このノウハウは色々な飲食ビジネスに応用することもできます。
例えば、はなまるうどんのようなバフェテリア形式の場合、先に天ぷらが置いてあって、その後にメイン料理であるうどんを注文しますよね。
この順番が逆になっただけで、天ぷらが注文される確率は激減するはずです。
飲食ビジネスに携わっている人は、ディズニーの運営ノウハウを理解しておきましょう。
ディズニーの社員教育&トレーニング
冒頭でも説明した通り、ディズニーのビジネスモデルではリピーター獲得が重要となります。
よって、お客様に対してサービスを提供している社員教育が非常に大切なのです。
ディズニーは良くも悪くもサービス業なので、そのサービスを提供する社員のクオリティ次第でお客様が受ける印象はガラッと変わってしまいます。
なので、しっかりした教育とトレーニングを実施しなければいけません。
ちなみに教育とは「座学」を意味して、トレーニングとは「実践練習」のことを指します。
ディズニーの新人研修では、とにかく次の2点を刷り込むそうです。
- この会社は働く人を大事にしてくれる。
- この会社で働くことは楽しい。
テーマパークという舞台(ステージ)で一緒に働くメンバーなので、一体感を持って仕事に取り組まなければ、ゲストを喜ばすことなどできません。
そのために、まずは会社のことを好きになってもらい、その次に仕事のことを好きになってもらうのです。
アルバイトのトレーニング
ディズニーランドという広大な敷地を運営するためには、どうしてもたくさんの人手が必要となります。
なので、ディズニーランドではたくさんのアルバイトが働いています。
ディズニーにおける人財活用の前提は「長期雇用」です。
これは社員もアルバイトも同じですが、定着率が低いほど生産性も低くなるので、経営効率も悪くなると考えられているようです。
パッケージ商品を販売しているだけの会社であれば、たとえ定着率が低かったとしても、業務内容が簡単なので成り立つかもしれませんが、ディズニーランドは勝手が違います。
ディズニーはサービス業なので、長期間働いた人ほどサービス提供能力が高くなり、ホスピタリティも上がっていく傾向があるのです。
そして基本的にトレーニング中の社員やアルバイトがテーマパーク内に出ることはありません。
ディズニーランドで働いているキャストのネームプレートに「研修中」とか「実習中」と書かれているのを見たことがないはずです。
ディズニーではテーマパーク内をステージ(本番の舞台)と考えているので、そこに研修中の人材を送り込むわけにいかないのです。
なので、アルバイトのトレーニングは裏側(バックヤード)で行われることになります。
ちなみに、ディズニーのキャストにネームプレートが付いている理由をご存知でしょうか?
あれはゲストに対して「私は田中太郎です」とアピールしているものではありません。
働いている従業員の数が多いので、従業員同士のコミュニケーションを円滑にするため、ネームプレートをつけているのです。
例えば従業員同士の会話を想像してみてください。
「パターンA:ちょっと、そこにいる男の子、こっちに来て!」
「パターンA:ちょっと、田中さん、こっちに来て!」
あなたが田中さんだった場合、どちらの方が呼び手に親近感を持つでしょうか?
従業員の数が多く、日々の入れ替わりも激しいため、このようなやり方が採用されています。
ディズニーのようなアルバイトの人数が多い企業の場合、画一的なシステムにしなければ現場が混乱してしまいます。
よって、アルバイトの研修では、各人毎にカルテを作成し、誰が、どの内容を、いつ教えたか?、というのを逐一記録しているそうです。
このようなシステムにすることによって、トレーナーが変わったとしても、また続きから始めることができるのです。
ディズニーが大切にしていること
一番最初にお伝えしましたが、ディズニーのビジネスモデルは「ファミリー層をターゲットにしたエンタメビジネス」です。
なので、安心して子供を連れて行ける安全性や礼儀正しさを兼ね備えた「SCSE」という考え方が重要になります。
この考え方が社員やキャストに根付いているため、お客様はサービスの付加価値を得ることができて、それが感動へと繋がっていきます。
その結果リピーターが増えて、現在のディズニービジネスが完成したのです。
よって、ディズニーではお客様の期待を裏切らないということを、とても大切にしています。
逆にお客様の期待値を上回るようなサービスを提供しているからこそ、現在の地位があるのだと思います。
このような想いを、創業者のウォルト・ディズニーが数多くの名言として残しています。
もし気になる場合には、下の記事をご覧ください。