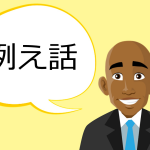どうせビジネスをするなら、1円でも高くモノを売りたいですよね。
しかし現実はそんな甘くなくて、顧客から値下げ交渉をされたり、競合他社との熾烈な競争で安売りせざる負えない場面もあるはずです。
そんな時には、利益が出なくて嫌になっちゃいますよね。
そこで今回は、安売りせずに、モノを高く売るコツについて解説していきたいと思います。
営業パーソンだけでなく、ビジネスに携わる人はぜひご覧ください。
目次
値上げは辛い…
お客様に対して、値上げを打診するのはつらいですよね。
値上げには様々な理由がありますが、適正価格にするためには、時には値上げも致し方ないと思います。
しかし商売人である以上「良いモノを、できるだけ安く提供したい」と思いますよね。
値上げはそれと矛盾する行動なので、ビジネスパーソンとしては心苦しい限りだと思います。
とはいえ、無理をしてまで安売りをしていると、そのぶん品質やサービスが低下し、クレームに繋がりかねません。
そのクレームが頻発して、結局はビジネスが成り立たなくなってしまうのです。
それであれば「適正価格にするんだ!」という強い信念のもと、値上げするのも一つの選択だと思います。
値上げのメリット&デメリット
値上げをすれば粗利率が改善するので、利益額も大きくなります。
そのようなメリットがある反面、さまざまなデメリットをもたらすのが値上げです。
例えば、値上げすることによって、これまで取引していた既存顧客が離れていくことが懸念されます。
資本主義は競争経済なので、同等程度の品質であれば、競合他社との取引に切り替えるケースが一定数あるはずです。
さらに営業現場では、新規開拓営業が難しくなるという問題が発生します。
やはり同等程度のサービスを提供している競合他社がいる場合、そこよりも価格が高いというだけで、選ばれなくなる可能性が出てくるのです。
企業が成長する糧は新規開拓営業なので、これが滞ると成長鈍化どころか、むしろ企業としては衰退していくことになります。
それだけ大きな転換点になり得る値上げなので、経営者としては慎重に判断すべきだと思います。
値上げ交渉は難しい
いざ値上げを行おうとした時、お客様の抵抗は大きいはずです。
特に売上のほとんどを占めるような大口顧客がいる場合、値上げ交渉は困難を極めます。
もしそのような大口顧客との取引がなくなった場合、一瞬で経営悪化するリスクを孕んでいるからです。
これは経営者にとって死活問題だと言えるでしょう。
しかし世の中には、安売りせずに頑張っている企業もたくさんあるのです。
そのような企業は、単純に「原材料が上がったから値上げする」とか「利益率が低いから値上げする」という考え方ではなく、頭を柔らかくしてアイデア勝負しています。
なので、もし値上げを検討する場合には、もう少し工夫した方が良いのかもしれません。
ここからは、難しい値上げ交渉をするのではなく「どうすれば製品サービスの価値を上げられるのか?」という別視点で考えていきたいと思います。
高く売るコツとは?
前述したように値上げ交渉はとても難しいと思いますが、そもそもアプローチ方法が間違っているのかもしれません。
つまり、自分都合でお客様に提案するから難しいのであって、顧客主体で考えた場合、決して値上げすることは難しくないということです。
営業職であれば理解できるかもしれませんが、モノを高く売るコツというのは「商品の価値を伝えて、その価値を高める」ことです。
製品サービスを安売りするだけでは意味がありません。
それだけでは「低価格」しか魅力がないので、値上げすればすぐさま顧客離れが起きてしまいます。
なので、ここでは「どうすれば商品の価値を伝えて、価値を高めることができるか?」ということをお伝えしていきたいと思います。
①特化型の商品にする
ビジネスをする場合、できるだけ幅広いお客様に買ってもらえるような製品を考えますよね。
これは「商機(ビジネスチャンス)を最大化する」という側面では正しいように思いますが、そのような戦い方は資金力がある大手企業のやり方だと思います。
中小ベンチャー企業の場合には、できるだけ幅広い顧客層を取りに行くのではなく、逆にニッチ分野に特化した商品にした方が賢明だと思います。
つまり万人受けするような商品ではなく、ある特定分野に特化した商品にするのです。
例えばラーメンだった場合、
- 醤油
- 塩
- 味噌
- 博多豚骨
- 豚骨醤油
- 担々麺
- 鶏白湯
など、全てのジャンルを網羅しているメニューで戦うのが大手企業のやり方です。
それに対して、「味噌ラーメン専門店」とか「担々麺のお店」という特化型のやり方が、中小ベンチャー企業の戦い方なのです。
大手企業のやり方では競合他社がたくさんいるので、どうしても低価格で勝負しなければいけません。
なぜかと言うと「専門性が低い」という見せ方になるので、付加価値が付けにくくなるからです。
それに比べて、圧倒的な専門性は消費者が選ぶ理由になります。
例えば「味噌ラーメン専門店」だったとしても、「辛味噌」に拘ったラーメン屋であれば、味噌ラーメンというジャンルの中でも差別化できます。
それを追求すればするほどライバルが少なくなるので、結果的に値引きする必要もなくなるのです。
逆にそのジャンルで極端に突き抜ければ、値上げすることもできるはずです。
専門的な商品は消費者が少ない反面、商品自体の価値が高まるので、高くても売れるのです。
➁ネーミング(商品名)を変更する
商品価値を上げるという観点では、そのネーミング(商品名)がとても重要になってきます。
中身が全く同じ商品なのに、改名しただけで売り上げが激増した例は、これまで後を絶ちません。
例えばマンションやオフィスビルでも「麻布」とか「六本木」というネーミングが入っているだけで、その不動産価値は上がりますよね。
「究極の味噌ラーメン」よりも「究極の札幌味噌ラーメン」の方が美味しそうに感じませんか?
このように、ネーミングが消費者に与える影響はとても大きいのです。
有名な例では、アサヒ飲料の「ワンダ モーニングショット」が挙げられます。
これまでの缶コーヒーといえば、「商品名+ブラック」とか「商品名+微糖」みたいな感じでしたが、モーニングショットだけは「朝専用」とシチュエーションを商品名にしたのです。
もちろんこれは「朝一番に缶コーヒーを飲むビジネスパーソンが多い」というマーケティングをした結果ですが、消費者に刷り込まれたイメージが強いため、結果的に大成功を収めることができました。
他にも「かき氷専用の氷」とか「おやつ専用のチーズ」など、中身は一緒だったとしても、アイデア次第で売れる商品は作れるのです。
これらはどれも「商品価値を高めて、実質的な値上げを実現するやり方」だと思います。
➂見た目を工夫する
「人は見た目が9割」という言葉をご存知でしょうか?
これはメラビアンの法則に基づいた格言ですが、消費者は半分以上を視覚情報から得ていると言われています。
もしメラビアンの法則を知らない場合には、下の記事をご覧ください。
つまり、商品の中身は同じなのに、外装パッケージだけを変更しても商品価値は上がるのです。
例えば、中身は同じマンゴーなのに、外装を桐の箱にして高級感を演出するやり方、中身は同じバッグなのに、外装を綺麗な箱に入れてリボンでラッピングするなど、様々なやり方が考えられます。
ルイヴィトンやエルメスなどの高級ブランド店は、まさにこのようなやり方で価値を上げていると考えられます。
もちろん飲食店だって見た目を工夫すれば話題性が出てきます。
有名なところで言えば「二郎インスパイア系ラーメン」があります。

二郎インスパイア系ラーメンは見た目がど迫力なので、強烈なインパクトを消費者に与えます。
すると、どうなるか想像できるでしょうか?
見た目(ビジュアル)にインパクトがあれば、消費者は口コミしやすくなるのです。
例えば、とても美味しい醤油ラーメンを食べたとしても、それを口コミするのはとても難しいですよね。
なぜかと言えば「個人の感覚」を伝えるのは非常に難しいからです。
しかし、二郎インスパイア系ラーメンのようなビジュアルであれば、それを伝えることは簡単なので、口コミがはかどるのです。
その結果、商品ビジュアルを面白がってインスタグラマーが来店したり、YouTuberが取り上げてくれるかも知れません。
このような例からもわかる通り、見た目は工夫するだけでも、商品の価値が上がっていくのです。
④キャッチコピーやPOPを考える
たった1行のキャッチコピーで売上が激増したりもします。
例えばラーメン屋だった場合、普通のラーメンよりも顧客単価がアップするやり方として「味玉ラーメンを売る」というやり方があります。
その時、単純にラーメンよりも100円高い「味玉ラーメン」というメニューを作っただけでは、注文される可能性はそんなに高くならないでしょう。
しかし、味玉について下記のような説明を加えたらどうでしょうか?
この味玉は、高級卵として知られている●●県の××玉子を使用しています。コク深い濃厚な半熟卵をぜひ一度ご賞味ください。
これは味玉のストーリーを語っている一文です。
何事もそうですが、ストーリー(背景)を語ることは、その商品の価値を高めることに繋がってきます。
現代社会はモノ余りの時代なので、消費者は単純に「モノが欲しい!」というよりも、その背景にあるストーリーが知りたいのです。
それに共感した上で、購買行動に移るのです。
つまりモノ余りの時代(=現代)では、いつでも必要なものが手に入る状態なので、ただ商品を売るというだけでは価値を上げづらいのです。
たった一文付け加えただけで値上げができるなら、とても楽ですよね。
➄サイズを変更する
これまでと違ったサイズに変更するのも価値が上がる要素だと思います。
例えば、日清食品がカップヌードルやどん兵衛をおわん型サイズに小さく変更して、ヒットしましたよね。

小さくすることで「寝る前の腹ごしらえにちょっと食べたい」とか、「おやつの時間に食べたい」などのニーズを満たすことができるのです。
これは便利にした反面、単価を上げることにも成功したはずなので、実質的な値上げだといえます。
他にも、水筒の内容量をこれまでよりも小さくした製品がヒットしました。

これまでの常識を打ち破る120ml~150mlというミニ水筒は、ポケットに入る大きさなので、持ち運びにも便利なのです。
この水筒であれば「オフィスに通勤する間」とか「犬の散歩をする間」など、1時間程度の外出時に水筒を持ち歩きたいというニーズを満たすことができます。
水筒を製造するメーカーからすれば、原材料費は下がるのに、価格は上げられる(=原材料に対する利益)ので、これも実質的な値上げにつながる施策だと思います。
アイデア次第で価値は上がる
ここまで読んだ人は、ただ単に商品・サービスを値上げするのではなく、その製品サービスの価値を高めたり、情報を付加価値として加えることで、実質的な値上げが実現できるとわかったはずです。
つまり、ビジネスはアイデア次第で何とでもなるのです。
少し頭を使って工夫するだけで、商品価値はどんどん上がっていきます。
それが結果的に値上げになり、利益率の改善に繋がるのです。
もし「利益を増やすために価格を上げたい」と考えている場合、単純に値上げするのはちょっと待ってみてください。
そうではなくて、まずは「どうすれば価値を上げられるか?」ということを真剣に考えてみましょう。
アプローチ方法を変えるだけで、値上げ交渉せずに、利益率を改善することもできるはずです。
まずは会社内でのアイデア出しから始めてみましょう!