
リアル店舗を開店する場合、どのような売り場にすればいいか悩みますよね。
お店のリニューアルをする時や、集客を強化したい場合でも、それは同じだと思います。
そこで今回は、店舗運営している人(又はこれから店舗経営する人)に向けて、売り場づくりのコツやノウハウを解説していきたいと思います。
目次
売り場作りはセンスじゃない!
- 売上アップする売り場にしたい!
- お洒落な売り場にしたい!
- お客様がまた来たくなる売り場にしたい!
このような売り場を作るためには「センスが必要」だと勘違いしている人は、きっと多いはずです。
しかし実際にはセンスなど関係なくて、きちんとしたロジックやノウハウさえ学べば、誰でも売り上げが伸びる売り場は作れるのです。
つまりロジカルに思考して、マーケティングとセールスを組み合わせるのです。
お客様をお店に呼び込む活動は、全般的に「マーケティング活動」と言えるでしょう。
そして、呼び込んだお客様に商品を買ってもらう活動は、全般的に「セールス活動」と言えはずです。
つまりこの二つは両輪になっているので、どちらか一方が欠けてしまってもダメなのです。
最大効果を発揮する為に、まずは店舗運営というものが「マーケティング×セールス」で成り立っていることを理解しておきましょう。
視覚でアピールする
突然ですが、あなたは「メラビアンの法則」をご存知でしょうか?
これは、1971年にアメリカの心理学者であるアルバート・メラビアン教授が唱えた概念で、話し手が聞き手に及ぼす影響を研究や実験に基づき数値化したものです。
- 言語情報
- 聴覚情報
- 視覚情報
この3要素からアプローチした法則ですが、具体的には以下のようになります。
言語情報:話し手が発している言葉の意味やその話しの内容です。
聴覚情報:話し手の発する声の大きさやトーン、話す時の口調や速さなどです。
視覚情報:話し手の目線や表情、態度、仕草を指しており、身体言語とも言われる事があります。
全体を100%とすると、話し手が聞き手にあたえる影響は、
- 言語情報は7%
- 聴覚情報は38%
- 視覚情報は55%
なので、一番視覚情報の数値が大きいと言われています。
つまり、この数字を見る限り、お客様とのコミュニケーションにおいて、視覚情報が非常に重要だということが理解できるはずです。
お客様に対して視覚情報だけでも伝えようとすれば、その50%以上が届くことになりますが、現代人はとても忙しいので、ゆっくり買い物している暇などありません。
なので、パっと見で50%以上の情報を届けて、すぐさま購入する判断ができるようなレイアウトにすることも大切だと思います。
例えば、誰しも経験があると思いますが、ティッシュボックスを買うときに「どのティッシュが良いのか?」と迷った経験があると思います。
売り場にあるティッシュボックスが、それぞれ何箱入りかを確認して、その中の枚数を確認し、売価で割って、一番お得なティッシュを割り出すのです。
このような作業は時間がかかりますし、正直誰もが面倒に感じているはずです。
なのでティッシュボックスの総額ではなく、ティッシュボックス一箱あたりの@単価を表示したり、ティッシュ一枚あたりの@単価を表示すると、パっと見でどれが良い悪いという判断ができるので、消費者にとってはストレスがありません。
Amazonなどのインターネット通販ではそれが実現できていて、現実のリアル店舗で実現できないわけがありません。
店舗経営者は、もっと消費者に寄り添った目線を持つべきだと思います。
看板にはこだわれ!
店舗経営をする場合、お店の顔ともいわれるのが「看板」です。
一言に「看板」と言っても、その種類は多種多様です。

- 壁面看板:お店にとっての表札の役割
- 屋上看板:遠方からよく見える看板。店名が入ることが多い。
- 突き出し看板:通行人の目に入りやすい看板
- ポール看板:高さがあるのでロードサイド店向けの看板
- 野立て看板:店舗から少し離れた場所でもPRできる
- 置き看板:小型看板なので移動が簡単
- A型看板:入店前情報の提供が目的の看板
- のぼり:動きがあるので目に入りやすい
この中で、最もこだわりたいのは壁面看板です。
壁面看板はお店の表札代わりと言えるので、この看板一つでお店の印象はガラッと変わってしまいます。
なので、高級店であれば黒色背景に重厚な黄金フォント、おしゃれなカフェであればカリグラフィーを活用したり、明るめな色彩を選んだ方が良いと思います。
そして置き看板やA型看板もうまく使いましょう。
この二つは入店前情報を提供できるので、「どんなお店なのか?」を明記したり、メニューや金額を記載しておくと、お客様が安心するので入店しやすくなります。
もし2階にあるお店や、少し奥まったところにあるお店の場合は、置き看板に店舗内の写真を掲載しておいた方が良いと思います。
そのようなお店の場合は、お客様が不安になってしまうので、事前に情報提供しておいた方が入店しやすくなるのです。
店頭にアイキャッチとなるような看板やマスコットキャラクターを置くのも良いと思います。
アイキャッチとは、人の目に付きやすいモノのことを言います。
アイキャッチとして市販されている商品もたくさんあるので、もし良ければ買ってみてください。
看板にはそれぞれメリット&デメリットがあるので、それを理解した上で使い分けていけば、きっと効果を発揮してくれるはずです。
入りやすいお店とは?
店舗運営をする場合、「マーケティング×セールス」を意識するようにお伝えしました。
マーケティングとは、お客様を店舗に招き入れるステップのことを言います。
例えば大きな看板を見やすく掲示したり、警戒されず、誰でも入りやすいお店にする必要があります。
ちなみに、一般的には開放感があって照明の明るいお店が入りやすい店舗だと言われています。
- ガラス越しに店内が確認できる
- 入り口付近に障害物がない
- 照明が明るい
- 店内への出入りがスムーズ
開放的なお店にするには、入り口付近を広くしたり、照明を工夫することが大切です。
具体的には店舗の奥の方を照明で明るくしたり、照明のワット数を上げるだけでも、視覚的な印象はガラッと変わります。
これはそんなに難しい話ではないので、すぐに実践しましょう。
陳列を工夫しよう!
マーケティングが成功して、お店の中にお客様が入ってきた場合、次にやるべきことはセールスになります。
一般的に、販売員が積極的に声掛けして、お客様にセールスすることはやらないので、ここでお伝えしている「セールス」とは、あくまでもお客様が自発的に購買する仕組みのことをいいます。
例えば陳列を工夫するだけでもお客様の購買意欲は高まります。
店内に入ってお目当ての商品を探そうとしても、なかなか見つからないとお客様はお店から出て行ってしまいます。
なので、陳列は「大分類⇒中分類⇒小分類」とカテゴリー分けすることが大切なのです。
例えば「ラーメン」という大分類があった場合、その中には「袋麺」と「カップ麺」という中分類がありますよね。
そして中分類の中には、「カップヌードル」「スーパーカップ」「どん兵衛」などの小分類が出てきます。
このように、パっと見でわかるようにグルーピングしておくと、お客様はストレスを感じません。
他にも様々なグルーピング方法があります。
- サイズごとに分ける
- 色ごとに分ける
- メーカーごとに分ける
- ブランドごとに分ける
- 素材ごとに分ける
- 型番ごとに分ける
- 価格ごとに分ける
- 機能ごとに分ける
商品の分類方法にはある程度のセオリーがありますが、「こうすれば絶対正しい」というものは無いので、色々と変えてみることをお勧めします。
その時の判断材料としては、お客様の声を大切にしましょう。
店舗運営をしていると、必ずと言っていいほどお客様から商品の場所を聞かれるはずです。
それはつまり「顧客の本音=商品の場所が分かりづらい」なので、その声を基にして売り場を改善していきましょう。
顧客の本音は必ず記録する癖をつけて、スタッフ全員で内容を共有することがおすすめです。
商品数は多すぎてもダメ
初めて店舗を運営する人は「商品数が多いほど良い」と思いがちですが、実はそんなことありません。
商品数が多すぎると、お客様は迷ってしまうので、逆に選ぶのが面倒に感じてしまうのです。
例えば、あなたがペットボトルのお茶を買いにコンビニエンスストアに入った時、そのコンビニには20種類のお茶が置いてあったとします。
それを見た時、きっとあなたは「多すぎてよくわかんないな…」という感想を抱くはずです。
この現象には様々な論文が発表されていて、米コロンビア大学のビジネススクールでは「選択肢は5~9が最適」と結論付けています。
これは「7つ」という商品数を軸にして「±2」の範囲内に収めるということです。
人が主体的に選ぶ場合、「7±2」の範囲内でなければ、逆に迷いが生じるので購買に至る確率が減ってしまうのです。
もちろん4つ以下の商品数でも、同じく購買意欲は減ってしまいます。
例えば、お茶を買いに入ったコンビニエンスストアに、ペットボトルのお茶が1種類しか置いてなかった場合、あまりに選択肢が少ないので「ちょっと別のお店に行ってみようかな…」と考える人は多いはずです。
なので、もし商品棚にある程度置けるのであれば、同一カテゴリーの商品を「7±2」の範囲内で置くようにしましょう。
店舗内を回遊させる
これは一般論ですが、店舗の回遊時間が長ければ長いほど、購買に至る確率は高くなっていきます。
店舗の回遊時間が長いということは、レイアウトが見やすくて、購買意欲をそそられることになるからです。
もし店舗内の陳列を考える場合、ゾーニングを前提に考えていきましょう。
ゾーニングとは、ある空間を用途に応じて分けることを言います。
スーパーマーケットをイメージしてもらえると、野菜売り場があったり、お肉売り場、スイーツ売り場、お酒売り場、お菓子売り場など、様々なジャンルごとに分けられていますよね。
このようなやり方をゾーニングと言いますが、これを計画する場合には、お客様の興味関心が途切れずに、最後まで一筆書きで辿っていけるルートをイメージすることが前提になります。
それをやることで、ついで買いが起こったり、無駄な買い物もしてくれるので、購買意欲が最大化されるのです。
ディスプレイやPOPを活用する
お客様の購買意欲を最大化させるためには、ディスプレイやPOP、什器のレイアウトも考えなければいけません。
例えば、入り口すぐの空間は「受け入れ空間」と呼ばれているので、何も置かずに見通しを良くしておかなければいけません。
それをすることによって、お客様は店舗に出入りしやすくなるので、マーケティング(=集客)に役立つのです。
さらに、什器は入り口から奥に向かって段々と高くしていくことがセオリーになります。
そうすると店内の見通しが良いので、お客様は安心して奥の方まで回遊していけるのです。
とはいっても、ドンキホーテやカルディなど、あえて店舗の奥を見せないレイアウトにしているお店も散見されます。
なので、あくまでもセオリー程度に理解しておきましょう。
ディスプレイで誘導する
いきなりですが、「ローボールテクニック」をご存知でしょうか?
ローボールテクニックとは、野球を題材にした言葉なのですが、低い球から徐々に高い球に変化させていくセールステクニックのことを言います。
つまり、最初の条件から少しづつ変化させて、最終的には大きな要求に承諾してもらうセールス手法なのです。
例えばローボールテクニックには以下のような使い方があります。
店頭に「最大70%OFF」という看板を掲げておき、最も売れ筋でデザインの良い服をショーウィンドウに飾っておきます。
その情報を見たお客様は、てっきりショーウィンドウに飾られた服が70%OFFだと思い込み、店舗内に入ってきます。
しかし実際には、ショーウィンドウに飾られた服は定価販売されており、70%OFFの服は店内の一部しかないのです。
このような例は、典型的なローボールテクニックだと言えます。
まずは入店してもらうために「最大70%OFF」というローボールを投げておき、実際に入店したお客様に対しては「定価」というハイボールを提示するのです。
これと同じことがスーパーマーケットでも行われています。
例えばお酒売り場の入り口に「特売品」として1缶88円の缶チューハイを平積みしておき、それに興味を持ったお客様がアルコール売り場に入ってくるという仕掛けも、典型的なローボールテクニックだと言えるでしょう。
人間の心理とは面白いもので、自分にとってのメリットを一つ捉えてしまうと、それを都合よく解釈して「他のお酒も安いのではないか?」と勘違いしてしまうのです。
商売人であれば、このような消費者心理をうまく活用しましょう。
POPの使い方とは?
POPは優秀なセールスマンです。
POPは、24時間365日セールスしてくれるので、絶対に売り場へ設置した方が良いと思います。
しかし「字が下手だからPOPは無理!」と考えている人が多いと聞きますが、実は字が下手でも構わないのです。
誰でもゆっくり丁寧に書けば、クセがなく、それなりに読める字がきっと書けるはずです。
POPを設置する目的とは、お客様の疑問を解決する為です。
つまり、リンゴを買おうとしたお客様に対して、
- このリンゴは糖度16度です!⇒とても甘いリンゴです。
- このリンゴは青森県産です!⇒安心の国産リンゴです。
などの情報を届けるのがPOPの役割なのです。
そのような観点で考えた場合、「字が上手いから商品が売れる」というわけではなく、「届ける情報に価値があるから商品が売れる」のだと理解できます。
なので、見た目ではその商品の価値が伝わりにくいモノほど、POPとの相性が良いということになります。
ほとんどのお客様は、自分自身のニーズ(=潜在ニーズ)に気付いていません。
なので、そのニーズを掘り起こしてあげるようなPOPであれば、セールスが最大化されるはずです。
リピーターを獲得する
マーケティングとセールスが一体化すれば、購買活動が最大化されるはずです。
次に待ち受ける試練は「リピーターの獲得」です。
新規のお客様ばかりを集めるのは自転車操業なので、いつまでたっても事業は軌道に乗って行きません。
なので、一度来たお客様にリピートしてもらって、顧客層を厚くしていかなければいけません。
これはまた別のノウハウが必要になる話なので、詳しくは下の記事をご覧ください。
まとめ
ここまで解説してきたように、店舗運営には「マーケティング×セールス」が求められます。
良い商品サービスを提供すれば、お客様が勝手に来てくれると思うのは間違いなのです。
逆の言い方をしてしまえば、普通の商品サービスであれば、後はマーケティング次第で繁盛店にすることができます。
なので、店舗運営をする場合には絶対にマーケティング知識が欠かせません。
もしマーケティング知識に不安がある人は、自分なりに本を読んだり努力してみましょう。
マーケティングの二大巨頭と言われているのは、フィリップ・コトラーとマイケル・ポーターです。
この二人の書籍は難しいですが、簡単に噛み砕いて解説する本もあるので、まずはその辺りから触れてみてください。



















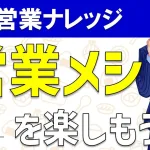

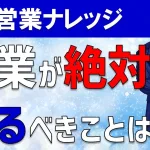
の営業コンサルティングを提案-150x150.webp)











