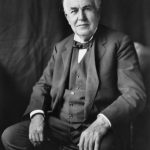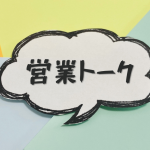※本ページはプロモーションが含まれています。
副業に注目が集まる昨今、副業に挑戦したいと考えている人が増加中です。
でも、いざ副業を始める場合、
- 確定申告はどうすればいいのか?
- 個人事業主になった方が良いのか?
- 開業届を出すべきなのか?
など気になることばかりですよね。
ここでは、副業する時の疑問点について解説していきたいと思います。
目次
個人事業主の定義とは?
働き方改革の一環として副業を解禁する企業が増えた関係で、企業に勤めるサラリーマンでも「個人事業主」とか「確定申告」という言葉が身近なものになってきました。
果たして副業する場合には、「個人事業主」として取り組むべきなのでしょうか?
まずは個人事業主の定義について触れていきたいと思います。
「個人事業主」とは法人を設立せずに事業を行うフリーランサーのことで、個人屋号でビジネスをしている人のことをいいます。
個人とは、法人ではない個々人のことで、法律で人格が与えられた”法人”とは真逆の存在になります。
さらに「事業」という言葉の定義についても触れておきたいと思います。
事業とは、反復・継続・独立している仕事のことを指します。
- その仕事を繰り返し行うことを「反復」といいます。
- その仕事をずっと行うことを「継続」といいます。
- 組織に属さないで働いていることを「独立」といいます。
この3つが揃うビジネスをしている人は、一般的に「個人事業主」と認識されるのです。
例として、フリーマーケットやオークションなどで不定期に収益を得るのは、この反復・継続・独立に属さないので個人事業主が行う事業とは言い切れません。
また、フリーランスの場合には、特定のクライアントから請け負った業務を反復・継続・独立して行うケースが多いため、「個人事業主」に該当することが多いはずです。
個人事業主と法人の違い
法人を設立する場合には、以下のような設定が必要になります。
- 商号
- 会社本拠地となる住所
- 会社定款
- 登記簿謄本に記載する事業内容
- 資本金
- 決算日 etc.
特に重要なのが、会社定款の作成です。
定款とは、事業目的(会社の事業内容)を明確にしたもので、定款に含まれていない事業の場合、定款自体が無効になってしまいます。
なので、法人は定款に記載された事業内容の範囲内でビジネスすることが求められます。
つまり定款に記載されていない業務は、原則的にやってはいけないことになります。
とはいえ、何でもかんでも定款に盛り込んでしまうと、「何が目的の会社かわからない…」という事態になりかねません。
会社は何か明確な目的があるから設立されるのであって、目的が曖昧な会社はなんか怪しいですよね。
それぐらい大事な書類が会社定款なのです。
定款の事業目的に違反した場合の罰則は特に無いですが、事業目的以外の取引を行った場合、取引停止という事態も起こり得ます。
ルール違反するメリットは無いので、将来を想定した事業目的にするのはもちろんですが、定款を常に最新の情報に更新しておきましょう。
個人事業主は法人と比較して簡単
先ほどは法人設立について触れましたが、個人事業主の場合には法人ほど面倒な手続きがありません。
個人事業主は手続きが非常に簡単なのが特徴なのです。
具体的には、個人事業主として登録するには所轄税務署に開業届を提出するだけになります。
しかも、その手続きは無料です。
法人の場合には、会社設立するのにも、解散するにも費用がかるので、これは大きく違いますね。
個人事業主は、会計処理や事業運営も法人に比べてコストや時間がかからないので、費用面で大きなメリットがあります。
法人の決算は複雑なので、税理士に頼むのが一般的ですが、個人事業主は「青色申告ソフト」などを使えば、自分で処理することもできます。
青色申告にすれば、最大65万円まで控除できるので節税効果も高いですね。
副業する時に
- 法人化しようか?
- 個人事業主で開業しようか?
と迷っている場合は、まず個人事業主として開業することをおすすめします。
副業でも開業届けは必要?
副業をしている人の中には、「どのタイミングで開業届を出すのか?」と疑問に思っている人は多いはずです。
開業届けを出さなくても副業できるので、「そもそも開業届って必要なの?」と思ってしまいますよね。
- 開業届けを出すと会社にバレる
- 副業所得が20万円未満だから不要
- 継続的な副業じゃないから手続きしていない
など個々人の知識にもかなり開きがあると思います。
ここでは個人事業主が行う”開業届け”について解説していきたいと思います。
まず結論から申し上げてしまうと、本業でも副業でも継続的な事業を始める場合には「開業届け」が必要となります。
とはいえ、すぐに開業届けを提出しなければいけないわけでなく、収入が安定してから開業書類を提出する人が多いようです。
「年間収入-年間支出=20万円超」の場合に税金が発生するので、そのタイミングでも問題ありません。
開業届を出さなかったからといって罰せられることはなく、提出、未提出によって所得区分が変わるだけです。
結局、開業届を出す意味とは、所轄税務署に「納税義務がある」ことを申告する為なので、正確に納税していれば何の問題もないのです。
逆に確定申告の際、漏れなく納税しないと「脱税行為」と疑われてしまうので注意が必要です。
開業届の提出方法
ここでは開業届を提出するやり方について、詳しく解説していきたいと思います。
開業届は、事業所・居住地など納税をする管轄税務署に提出します。
用紙はwebでダウンロードするか、税務署に置かれているので、直接現地に行ってしまうのも良いでしょう。
書き方が不安な場合は、税務署の窓口を予約しておくことをおすすめします。
また、開業届を提出する際に決めておく必要があるのが、家族を専従者にするかどうかです。
こちらは、開業届を出す際に指定する必要があります。
また、屋号が必要な場合、開業届を提出するまでに決めておきましょう。
詳細は市町村で異なる場合があるので、事前に確認することをおすすめします。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
屋号を持つメリットとは?
個人事業主の場合には「屋号」を決めることができます。
屋号とは会社名のようなものですが、これを設定する最大のメリットは「信頼度がアップすること」です。
ビジネスするにあたって、名刺に屋号が入っているだけでも、相手が受け取る印象は大きく違ってきます。
また、屋号入りの銀行口座を作れることも魅力的です。
屋号を付けることで、仕事への愛着も深まるはずなので、屋号をつける場合は、
- 事業内容が連想できる屋号にする
- 読みやすい&覚えやすい屋号にする
- すでに登録されている屋号は避ける
ということがポイントになります。
個人事業主の屋号は、カタカナ、ひらがな、アルファベットでもOKです。
注意点としては、会社(法人)だと誤解される文字列は使えないことと、商標権で守られた文字列も使用できません。
これらの注意点に気をつけて、お気に入りの屋号を決めてみましょう。
青色申告のメリットとは?
青色申告とは、複式簿記によって正しい記帳を行っている納税者に、所得計算で様々な特典が与えられる制度です。
主に不動産所得、事業所得、山林所得がある人は青色申告することができます。
青色申告のメリット
青色申告をするメリットは、年間最大65万円を所得金額から控除できることです。
また、ある年に生じた赤字額を、3年間に渡って繰り越せて、さらに純損失も1年間繰り越しできます。
昨年が黒字で、今年が赤字になった場合、前年の納税額を上限に所得税の還付が受けられる特典もあります。
さらに、生計を一緒にしている配偶者や親族に支払った給与を全額経費にすることができるのです。(控除対象配偶者や扶養親族はできない)
こんなにメリットが多い青色申告を使わない手はないと思います。
青色申告は専門の会計ソフトを利用すれば簡単に申請できるので、自分で作成することもできます。
もし不安な場合には、税理士に相談してみることをオススメしますが、まずは会計ソフトをチェックすることから始めてみてください。
代表的なクラウド会計ソフトを記載しておきます。
経費(損金)で節税しよう!
個人事業主として活動する上で、経費にできるものは一体どんなものがあるのでしょうか?
経費処理できる原則は、「ビジネスに関係があるのか?」ということになります。
つまり、商売に関係がないものは全てプライベートの購買になるので、経費にすることはできません。
例えば賃貸住宅を自宅兼事務所とする場合、事業用として使用している割合を計算し、その分の家賃などを経費にすることが可能です。
この考え方からすると、もちろん水道光熱費も同じ割合で按分できます。
自己所有の場合は、住宅ローンの一部を経費にすることも可能です。
また自動車を仕事に使う場合にも同じ考え方が適用できますし、自転車の購入についても同じです。
仕事中に飲むコーヒーや、来客用のお茶など、経費にできる備品はとても多いことが理解できるはずです。
なので、まずは経費処理しやすくする為、Amazonビジネスなどに登録しておきましょう。
経費を公私混同しない
前述した以外にも、
- 切手やハガキ
- 電話料金
- インターネット回線使用料
- 社外の人への祝儀
- お見舞金
- チラシ制作費
- 火災保険料
- パソコン
- 携帯電話 etc.
なども事業に利用する場合は経費にできます。
個人事業主の場合、事業経費と生活費の線引きがとても難しいので、何でもかんでも経費処理してしまうケースがありますが、公私混同することは絶対に避けなければいけません。
なお、娯楽や日常生活に使うもの、一人の食事などは経費として認められないので注意が必要です。
副業は個人事業主として始めよう!
サイドビジネスをきっかにして独立開業を目指すなら、個人事業主として始めることをおすすめします。
手続きが簡単でメリットの多い個人事業主は副業向きだと思います。
自宅家賃や光熱費の負担も軽減できて、何よりも所得を増やした場合、それと比例して増加する税金に対する節税効果もあります。
開業届を提出しておけば、税務署が税務に関するフォローアップもしてくれます。
副業で独立起業しようと考えている方は、まず個人事業主からさらなる飛躍を目指していきましょう。