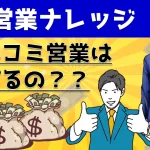※本ページはプロモーションが含まれています。
注目されつつある働き方に「ワークシェアリング」があります。
これからの時代の「新しい働き方」だと言われているので、ビジネスパーソンなら絶対にチェックしておきましょう。
目次
ワークシェアリングとは?
多種多様な働き方が定着するようになった現代において、とりわけ企業から注目されているのが「ワークシェアリング」と呼ばれる働き方です。
これは「workとsharing」から成る造語であり、労働者同士で業務や雇用を分け合うことによって、業務の効率化や労働時間の時短を狙うというアプローチ方法だと定義付けされています。
workの部分をjobに置き換えたジョブシェアリングと呼ばれる呼称も一般的に使われていますが、ワークシェアリングは1970年代に欧米において研究が始まりました。
72年にはアメリカのNew Ways to Work Foundation(新しい働き方財団)に資金が提供され、その動きが加速化したのですが、2000年代に入ると女性の社会進出が専門分野にまで裾野が広がり、その結果として家族と仕事のバランスが取れる「ワークシェアリング」という働き方が国家としても推進されるようになってきました。
ヨーロッパでも75年に設置されたEUの専門機関であるEurofound(生活と労働条件の改善のための欧州財団)で研究が進められ、2015年に新しい働き方として承認されています。
日本でも早くからその考え自体は認知されていましたが、いまいち日本型雇用との相性が良くなかったため、なかなか定着するまでには至りませんでした。
しかしながら、日本の未来を考えた場合に「ワークシェアリングは必要である」と政府も認めており、地方自治体や大企業を中心に、その導入が進められつつあります。
ワークシェアリングが日本で拡大中!
日本においてワークシェアリングが拡大しつつある背景には、大きく分けて2つの理由があります。
1つ目は政府、つまり総務省が推進している”働き方改革”です。
労働時間の減少と離職率の低下が重要視されるこちらの施策は、ワークシェアリングとの相性が良いとされています。
女性の社会進出に伴う就業形態の変化、例えば「働きたいけどフルタイムでは働けない…」という問題や、高齢者問題もクリアできるワークシェアリングは、働き方改革において”渡りに船”と言えるでしょう。
また労働時間が削減できるので、近代日本で社会問題になっている過剰労働やブラック企業問題も改善できると期待されています。
2つ目の理由は、少子高齢化に伴う労働人口の減少に対応できるという点です。
年々出生率が低下している日本において、少子高齢化は避けられない現実となっています。
「1人の現役世代で複数の高齢者を養わなければならない」という構図が確実視されている日本で、ワークシェアリングはとても重要な役割を果たすはずです。
前述した就業形態の変化や高齢者問題もそうですが、労働人口が減る以上は、1人が複数のサービスに従事する必要性もあるでしょう。
そうした時、ワークシェアリングの出番になります。
ワークシェアリングは業務の効率化のみならず、そこから生産性の向上、企業業績の向上へと繋がり、最終的には個人消費の増加や経済効果にまで波及していきます。
日本経済全体の底上げにも寄与する可能性があるワークシェアリングは、これから大注目ですね。
ワークシェアリングの働き方とは?
日本においてワークシェアリングが定着しつつあるのは、主に工場や自治体などでの勤務になります。
まず、工場の場合は基本的に昼夜交代勤務(フレックスタイム制)と呼ばれる労働方法が定着していますが、これは労働者の生活リズムが安定しないというデメリットがあります。
また、企業側からしても夜間は騒音問題になるので、工場全体をフル稼働させることが難しく、どうしても日中に比べて生産性が落ちてしまいます。
そうした問題を改善するのがワークシェアリングという働き方です。
昼夜交代勤務を廃止して、労働者が一つの仕事を複数人で担当すれば、生産性アップが図れますよね。
労働者からすると日中勤務だけ済むというのがメリットですが、企業からしたら生産性の向上のみならず、夜勤時の割り増し賃金を支払わなくて済むので、大きなコストダウンに繋がります。
自治体におけるワークシェアリングでは、労働時間の減少が期待されています。
公務員が働いている地方自治体では、給料における時間外勤務手当の認定や額が厳しい傾向にあります。
そのため、外部から人的リソースを調達できるワークシェアリングであれば、業務の終了を早められるため「相性が良い」と言われているのです。
また、雇用増加に繋げることができるワークシェアリングを自治体が導入すれば、その自治体における失業者の減少も期待できるでしょう。
このように、次世代型の働き方を提唱してくれるワークシェアリングは、様々な業種業界で注目されているのです。
ワークシェアリングの種類とは?
ワークシェアリングは”複数のタイプ”に分類できるので、ここで詳しく解説したいと思います。
実は、日本の監督官庁である厚生労働省が、ワークシェアリングの働き方を”4タイプ”に定めています。
1つ目は、雇用維持型(緊急避難型)と呼ばれるタイプです。
これは企業の経営状態が悪化し、人員削減(リストラ策)などを取らなければならないという時に、「労働組合との協議の上で従業員一人あたりの労働時間を短くする」という緊急対応策として活用されています。
このような施策を行うことで、不景気の時にも多くの雇用を維持するできるというメリットがあります。
2つ目の雇用維持型(中高年対応型)も性質は同じですが、これは対象を主に中高年や定年後の従業員に設定しています。
これはシニアの活用という観点で注目されています。
3つ目の雇用創出型は、失業者などが就業できるようにすることです。
すでに働いている労働者の労働時間を削減して、新しい雇用につなげるというのが特徴的です。
この施策は、企業や既存の労働者にとって経済的不利益が生じるので、このタイプのワークシェアリングが浸透しているヨーロッパでは補助金とセットで実施されることが多いです。
4つ目の多様就業対応型では、在宅ワークやパートタイム労働などの労働形態を導入することによって、それまでの就業形態では就業できなかった人間でも働けるようにすることです。
労働者側のメリットには、育児や介護をしながらでも働けるという恩恵があり、企業には必要な分だけの雇用が創出できる、社会貢献活動のPRができるというメリットがあります。
これは労働者側と企業側の双方にとってメリットがある施策といえるでしょう。
ワークシェアリングのデメリットとは?
ワークシェアリングにはたくさんのメリットがありますが、もちろんデメリットも数多く存在しています。
まず、労働者にとってのデメリットになるのが給与の減少です。
労働時間の削減が主な目的であるワークシェアリングを導入すれば、その分労働者の給料は減少してしまいます。
また、それまで支払われていた手当が削減される可能性があるので、働き手としては注意が必要です。
就業形態も変化するため、場合によってはこれまで正社員だったのに非正規社員(契約社員や派遣社員)になってしまった、というケースも起こり得ます。
こういった労働者にとってのデメリットは、労働組合や労働基準監督署などに相談することで事前に予防できるはずです。
「企業にとってワークシェアリングは悪だ!」と誤解している人を稀に見かけますが、決してそんなことはありません。
しかし、必ずしも生産性の向上や支出の削減に繋がるというわけではないことも事実です。
新しく人材を雇用したり、業務形態を変化させることによって、新たな求人コスト、人件費、教育研修コストが発生します。
また、全体的な従業員数が増加するため、健康保険や経費、トータルでの給与&賞与が膨らむというケースもあります。
こうしたデメリットとなりえる問題は、ワークシェアリングを導入する前にしっかりと投資対効果を見極める必要があるでしょう。
とはいえ、これからの時代の働き方であることに違いはないので、ぜひ前向きに取り組んで欲しいと思います。
ワークシェアリングで副業する方法
ここまでワークシェアリングについて解説してきましたが、このワークシェアリングという制度を副業に活かす人が増えています。
ワークシェアリングでは、相対的に労働時間が少なくなるので、その隙間時間を活用しながらサイドビジネスをしているようです。
副業とはいえ、意外と大きな金額が稼げるので、ある意味ではダブルワークのような感覚になるでしょう。
最近ではワークシェアリングを支援するサイトがたくさん出てきているので、まずはそれらのサイトに無料登録することから始めてみるのも良いと思います。
ワークシェアリングを支援するシェアリングサービスのwebサイトをいくつか記載しておきますので、ぜひ参考にしてみてください。