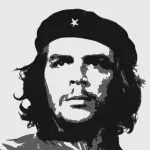副業が解禁されて、サラリーマンなどの会社員が副業や兼業を探し始めています。
しかし、副業禁止は違法行為と言われることもあります。
そこで今回は、副業する上で知っておくべきことや、おすすめの副業情報をご紹介していきたいと思います。
目次
副業禁止は就業規則をチェックする
会社員の副業禁止は何で定められているのでしょうか?
日本国憲法では「職業選択の自由」を謳っているぐらいなので、法律で副業が禁止されている訳ではありません。
つまり、副業禁止は個々の会社が定めている就業規則で決められているのです。
入社したときに就業規則を細かく読む人はそれほど多くないので、就業規則の中身を知らない社会人はたくさんいると思いますが、就業規則とは会社が賃金や労働時間、労働条件などを定めたもので、常時10人以上の従業員が働く会社は作成・届け出が義務づけられているものです。
そして、就業規則にはお手本となる雛形が存在します。
それが厚生労働省の公表しているモデル就業規則です。
多くの会社がこれを参考に就業規則を作成しているのが実態なのです。
モデル就業規則が改正された
2018年まで「モデル就業規則」には副業禁止の項目がありました。
そのため、現在でも多くの会社が就業規則で副業禁止を定めています。
しかし、2018年に政府の働き方改革の一環として「モデル就業規則」の副業禁止規定が削除され、むしろ副業を容認する方向に転換されました。
このため、2018年は「副業解禁元年」と言われ、大手企業でも全面的に副業解禁するなど大きな変化が起こったのです。
しかし、従来の就業規則のまま副業を禁止している企業も多いので、「副業をしてみたい!」という人は、必ず自分の会社の就業規則を確認するようにしましょう。
就業規則は社員に明示することが法律で義務づけられているので、すぐに見ることができるはずです。
企業が副業禁止にする理由
「モデル就業規則」で副業が禁止されたのにかかわらず、副業NGの会社が多いのには理由があります。
ここでは企業が副業を制限する理由について、詳しく触れていきたいと思います。
企業が副業禁止にする3つの理由
1つ目は副業解禁することにより、本業である会社の業務に支障が出る可能性があるからです。
副業は原則的に勤務時間外にするので、本来労働しないで休める時間に働いていることになります。
すると、副業する時間が多いせいで疲労が蓄積し、本業がおろそかになるかもしれません。
また株式投資や不動産投資、FXなどをしている場合、そちらが気になって本業が手につかなくなる可能性もあります。
2つ目は副業の種類によって、会社の信用を落とすことがあるからです。
例えば、副業のアルバイト先が世間体の悪い場所だった場合、それを得意先の人が目撃したとしたらどう思われるでしょうか。
職業に貴賤はないといいますが、「あの会社は社員がこういう所で働くことを認めているのか…」と悪い印象を抱かれる可能性があります。
3つ目は副業で自社の競合企業に勤められると、既存顧客が奪われたり、社内の機密情報などが流出するなどの可能性があることです。
これは企業が直接損害を被るので、できるだけ避けたい事態だと思います。
このように企業が副業を禁じているのには様々な理由があります。
ちなみにこの3つは公務員が副業を禁じられているのとほぼ同じ理由です。
「モデル就業規則」をつくった厚生労働省はこれらの理由で当初は副業禁止を盛り込んだのだと想定できます。
副業禁止は違法!?
原則論で言えば、副業禁止は違法といえます。
つまり、サラリーマンが副業をするのは何ら問題ないということです。
なぜなら副業は勤務時間外に行なうので、会社が干渉することは「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する」という憲法第22条の職業選択の自由を侵すことになるからです。
ただし憲法は国家と国民の権利に関する法律なので、単純に会社と従業員に当てはめることはできません。
そこで労働基準法第34条に目を移してみると、勤務時間外(休憩時間含む)に労働者を不当な理由で拘束することを禁じています。
つまり、勤務時間外に副業することを無条件に就業規則違反として罰するのは法律的に認められていないのです。
確かに、就業時間後の行動を会社に決められる道理はありませんし、文句を言われる筋合いもありません。
会社と契約している雇用契約は、勤務時間中に関するものなので、勤務時間外は何をしても原則自由なはずです。
ただし、副業に関する規定は労働基準法には記述がないので、会社が就業規則で副業を禁止すること自体は法的に問題はありません。
問題になるのは、副業をすることを就業規則違反として罰することです。
しかし、前述したように本業に支障が出るような副業をすると、裁判所も就業規則を根拠に社員を処罰することに合理性を認める判決を出しています。
それ以外の場合は就業規則を根拠に副業をした社員を罰することは許していません。
したがって、本業に支障がなく、会社にいかなる損失も与えていない場合、就業規則の副業禁止規定を根拠に罰することはできないのです。
過去の判例からすれば、裁判で争った場合、高い確率で会社側が不利となります。
おすすめな副業情報
副業としておすすめな仕事を4つほど紹介しますので、ぜひ副業・複業を探す時の参考にしてみてください。
副業その1:アフィリエイト
1つ目はアフィリエイトです。
ブログなどの集客力を持つコンテンツを運用し、そこに広告を載せることで収入を得る仕組みです。
今ご覧になっている「営業シーク」もブログメディアの一種といえますが、このサイト内に貼られた広告をクリックしたり、購入に至ったりすると運営元である弊社(WEBX Inc.)に収益が入る仕組みになっています。
ブログ運営のメリットは非常に低コストで始められることです。
ネットワーク環境とPC1台あればすぐに始めることができ、一旦仕組み化できれば自動的に収入が増えていきます。
もし失敗しても損失はコンテンツを作成した時間と微々たるコストだけです。
デメリットは、最初の6ヶ月ぐらいはほとんど収入が出ないことです。
そして、アクセス数を増やさなければいけませんが、この辺りは個々人のスキルに応じた腕の見せ所だと思います。
おおむね、月2万PVくらいから収益化できるはずなので、まずはそのくらいを目指して、2年以内に10万PVを目指しましょう。
トラフィックが稼げないと広告出稿できないので、最初のうちは無報酬でコンテンツ制作を続けることになると思います。
副業その2:FX(外国為替証拠金取引)
2つ目はFX(外国為替証拠金取引)です。
金融取引の中では初期投資が少なくても始められ、短期間で多くの収入が得られる可能性を秘めています。
AIによる投資も増えてきているので素人でも相場が予想しやすくなりました。
デメリットは、元本が保証されないので、うまくリスク分散しないと思わぬ損失が出るかも知れないことです。
FXでは、レバレッジをかけすぎると自己資金以上の損失が出るので注意が必要です。
投資で自己破産するケースがこれに当たるので十分注意しましょう。
副業その3:アルバイト
3つ目はアルバイトです。
メリットは単純労働が多く、比較的売り手市場のため職を得るのが簡単で、時間の調整も効きやすいことです。
デメリットは単価が安いので収入を多くするためには労働時間を増やすしかないことです。
また、単純労働が多いので、比較的退屈な仕事が多い傾向にあります。
立ち仕事など身体的に負荷が掛かる仕事も多く、本業に影響する可能性があるので注意が必要です。
副業その4:リファラル営業(紹介営業)
4つ目はリファラル営業(紹介営業)です。
簡単に説明すると見込み顧客を探している会社に、自分の顧客や知り合いを紹介する営業のことを言います。
営業職の人などは自分の人脈・販路を活かせるメリットがあります。
また、うまく紹介できれば「企業」と「知人・友人」と「自分」の全員がそれぞれ利益を得られます。
デメリットは、紹介した後トラブルになった場合、紹介した張本人である自分の評判が下がる可能性があることです。
リファラル営業を支援するサイトもあるので、気になる人はチェックしてみてください。
副業がバレたら面倒
就業規則で副業禁止している会社の場合、副業していることがばれると色々と話がややこしくなります。
本業に支障がなければ法的には会社が罰することができないといっても、会社から文句を言われるでしょうし、副業を辞めないと会社の中にいづらくなるでしょう。
そこで、会社に副業をしていることをばれにくくする方法があるので紹介します。
それは年間所得を20万円以内に抑えることです。
会社員が本業の他に副業を持っている場合、その所得が20万円を超えなければ所得税を確定申告する必要がありません。
所得は収入から経費を引いた金額です。
収入の金額ではないので注意しましょう。
副業の確定申告はどうする?
確定申告をしなければ会社が他に収入があることを知ることはないので、副業していることを自分が言わない限り会社には分かりません。
確定申告が必要なだけの所得を得た場合は、確定申告時の「住民税に関する事項」という書類の住民税の徴収方法を「自分で納付」にすることで、地方自治体から会社に住民税について通知されなくなるので、ばれる確率は低くなります。
ただし、外で働く副業(アルバイトなど)で同僚と出くわすことがないとは言い切れませんので、絶対にばれないということはありません。
就業規則に反している以上、罰則はなくても会社での評価が下がる可能性はあるので、最終的には自己責任で副業をするかどうか決めましょう。