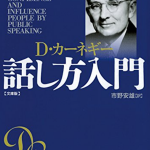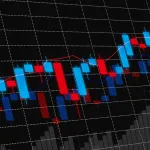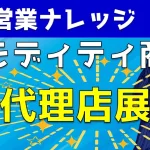ある程度の会社規模になると、営業課長という役職が設けられているはずです。
営業課長の役割は会社によって様々ですが、中間管理職であることは間違いないと思います。
「中間管理職」としてふるまうことは非常に難しいと言われており、高度なサラリーマンスキルが求められます。
そこで今回は、営業課長の仕事内容や求められる能力について解説していきたいと思います。
営業課長の仕事内容
営業課長になるためには、それなりの実績を積まなければいけません。
おそらく新卒入社してから5年ほど経過した段階で営業課長に昇進すると思いますが、この辺りは会社によって様々でしょう。
ただ一般的に言われているのは、同じ職種を3年間務めれば、社会人としては一人前になれるということです。
なので、新人営業マンとしてキャリアをスタートした場合、3年~5年ぐらいで営業課長になるのが普通だと思います。
その仕事内容は大きく二つに分かれます。
- 後輩の教育&育成を行う
- 営業部のノルマ達成に貢献する
①後輩の教育&育成を行う
まず後輩の教育や育成については、営業課長ならずとも先輩社員であれば誰しもが求められる役割だと思います。
後輩営業マンを育成する理由は非常にシンプルです。
それは自分が楽になるためです。
下が育ってくれないと、いつまで経っても自分のノルマは重いままです。
しかし自分の部下の中からトップセールスが出てくれば、そのぶん営業ノルマが分散するので、自分が楽になるだけでなく、所属している営業所や支店の数字も楽になります。
なので、入社してきた営業スタッフはもれなくトップセールスに育成した方が絶対良いのです。
感覚的には「自分の営業成績を追い抜くような人材を育成する」ようなイメージです。
もし自分の部下が優秀な営業パーソンに成長すれば、きっとあなたは営業部長に昇進できますし、その先のキャリアは明るいものになるはずです。
➁営業部のノルマ達成に貢献する
営業課長はいわゆる「中間管理職」なので、プレイングマネージャーとしての役割が求められます。
後輩のノルマを管理しつつ、自分自身の営業ノルマも追わなきゃいけないのです。
そして、もし後輩がノルマ未達成となった場合、その数字は営業課長が負うことになるはずです。
できない後輩営業マンはノルマを消化できませんし、営業部長は色々と忙しいので、営業課長にノルマを押し付けてくるはずです。
これは大きなストレスのある仕事だと思いますが、中間管理職とはこのような役回りなのです。
理不尽だと思いながらも、日々ノルマ達成していけば、いづれその役割から卒業するタイミングが訪れます。
サラリーマン生活を送る以上は、このような期間が一定時期あるものだと理解しておきましょう。
課長職の位置づけ
会社によっては課長職が存在しておらず、「課長代理」という役職になっている会社もあります
いずれにせよ、課長職といえば、営業部の中のリーダー的な存在だと思います。
部長が出張や夏季休暇で不在の時には、部長の代打として営業部の指揮官を任される存在ですし、後輩社員からも頼られますよね。
そして経営者から見た場合、非常に重要なポジションに置かれている存在だと思います。
部長職はある程度キャリアを積んでしまって、モチベーションが下がっている人もいますが、課長職の人は35歳前後なので、まだまだ野心がありますし、モチベーションも高いはずです。
なので、営業部長だけでなく、企画部や人事部に配属したり、バックオフィスのリーダーとして活躍してもらうこともできるはずです。
社長直下の新規事業担当者(=社長室)にするという選択肢もあります。
とにかく、やる気があってモチベーションの高い社員は使いどころが満載です。
このような社員は次期リーダー候補として期待されているはずです。

課長に求められる能力
課長に求められる能力は、「後輩社員の教育&育成スキル」と「営業ノルマの達成スキル」ですが、それだけでは足りません。
もう一つ重要なスキルがあるのです。
それは、社内営業できるスキルです。
社内営業とは、仕事が円滑に進むように社内調整できるスキルのことを言います。
例えば社長や部長に根回しをしておいたり、後輩や同僚を味方につけるようなスキルのことを言います。
これは悪く言えば「ゴマすり」とか「太鼓持ち」、「八方美人」と言われたりもしますが、サラリーマンとして働く以上は必要不可欠なスキルだと思います。
結局、自分が社内営業でうまく立ち回ることによって、周りを動かすことができるので、優秀な営業課長であればあるほど会社内は円滑に回るはずです。
そのような人は上の人(社長や部長など)から重宝されるので、必然的に出世していくことになります。
典型的なダメ課長
「ダメ課長」と言われるような人は、前述したようなスキルを持ち合わせていない人のことです。
つまり、自我が強かったり、変に正義感が強い人のことを言います。
そのような人はプライドが高いので、上司に媚を売るのが下手くそで、それを積極的にしようともしません。
また、「人の仕事は他人事なので、自分の仕事だけをやればいい」という考え方で協調性もありません。
このようなポンコツ課長は、営業部長から見ると頼りがい無く思えて、後輩社員を任せることもできません。
もし後輩社員の教育を任せるとしても、ダメ課長は人から嫌われるのを避けるので、妙に優しかったりするのです。
優しいことは決して悪くないですが、あまりに優しすぎる人は教育担当者としては不向きだと思います。
誰しも新人の頃に言われた先輩社員の忠告は、バイブルのように心の片隅に刻まれているはずです。
教育担当者とは、「その人の役に立つのであれば、自分は嫌われても良い」と思えるような人でなければ務まりません。
周りの目を気にしていて、プライドが高い人は課長職に向かないでしょう。
課長になれる人
営業課長に昇進するためには、それなりの実績を出さなければいけません。
具体的に言ってしまうと、会社内で取り扱っている商材を全て網羅していることが必要不可欠だと思います。
なぜかと言うと、課長職の人は次期部長候補だからです。
つまり、部長の既存顧客を引き継ぐ可能性があるのです。
その中に、もし取り扱ったことがない商材の既存顧客がいた場合、引き継ぐことができませんよね。
それは会社にとっても困ることですし、何よりもお客様に迷惑をかけます。
そうならないために、会社で取り扱っている全ての商材を把握することが最低限必要だと思います。
それに加えて、前述したようなスキルを身につけておく必要があるでしょう。
営業部長とは、限られた一部の人だけに与えられるポジションです。
そこに座るためには、それなりの努力が必要だということです。
まとめ
大手企業に限らず中小企業でも、課長職までなら誰でも昇進できるはずです。
しかし、そこから先のキャリアは人によって差がついてきます。
その差は努力でカバーできる部分もありますが、運の要素もあるでしょう。
しかし、その運を引き付けるのも才能の一つです。
もしこれから営業課長になる人は、日頃から努力を欠かさないようにしましょう。
その努力はいづれきっと花を咲かせるはずです。