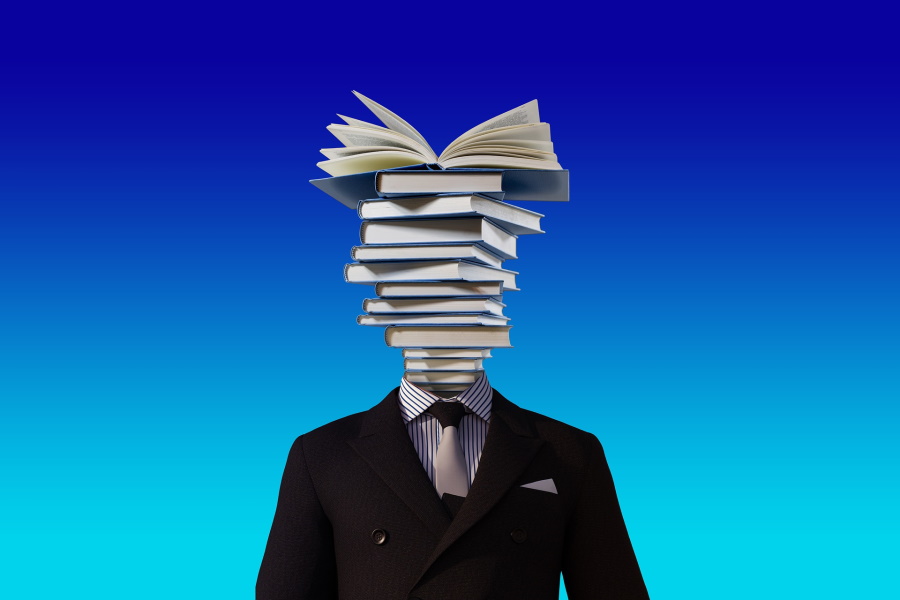
「営業力を強化したい!」
経営者や事業責任者なら誰もがそう思うはずです。
そこで今回は、営業部全体の”営業力”を底上げするやり方について解説していきたいと思います。
営業力強化に課題感がある人、部下の影響力をアップさせたい人はぜひご覧ください。
>>新規開拓の可能性を追求する|side bizz(サイドビズ)
目次
営業がうまくいかない理由
自社の営業活動がうまくいかない原因にはいくつかの理由があると思いますが、代表的なものは「営業の仕組み化が出来ていない」ことでしょう。
1人前になった営業マンは、基本的に1人で取引先と商談させている企業が多いはずですが、この場合、それぞれの営業マンは自己流の営業スキルを駆使しながら商談へ臨むことになります。
すると個々人の営業力に差があるので、もちろん結果はバラつきますし、営業部全体で見た時の成績も伸びにくくなってしまうのです。
それでは「トップセールスの営業ノウハウを共有すれば良いのではないか?」と考えるかもしれませんが、基本的にそれは難しいはずです。
なぜかといえば、自分のセールスノウハウを共有してしまうと、会社内にいるライバルのスキルが上がってしまうので、相対的に自分が苦しくなるだけで、ノウハウを共有したトップセールス自身には何のメリットもないからです。
例えば、営業マンAが画期的な営業テクニックを考え出したとします。
その営業テクニックを社内に共有すると、営業マンB、営業マンCも同じようなセールスを行うので、二人とも営業成績が伸びると思います。
すると、営業マンAは自分が教えた営業テクニックのせいでライバルの成績が伸びてしまうため、相対的に自分の営業成績は落ちていくことになります。
そのうち営業マンBに成績を抜かされてしまうリスクもあるので、「一体何のために共有したのか?」と疑問になることでしょう。
しかも、自分が生み出した営業テクニックを社内共有したところで、何の見返り(インセンティブなど)もありません。
こんなことになるくらいなら、営業マンAは編み出した営業テクニックを共有することはせず、自分だけでそのセールスノウハウを活用していくはずです。
つまり、画期的な営業テクニックや、素晴らしい営業ノウハウを発見したところで、それを社内共有するメリットがないということです。
むしろデメリットの方がたくさんあるので、当たり前の話ですが自ら進んでノウハウ共有する営業マンなどいないのです。
しかし、営業ノウハウを会社のナレッジとして蓄積することは、絶対的な”善”であると言えます。
そこで重要になるのが営業の仕組み化、つまりナレッジを共有したくなるような仕組みの構築なのです。
営業を仕組み化するには、仕事の「再現性」を重視することがポイントになります。
ここがポイントなのでもう一度お伝えしますが、営業には「再現性」が重要となります。
どの営業マンが商談に行ったとしても、ある程度のクオリティが担保出来るように、営業ノウハウが蓄積するような仕組みを作り上げましょう。
ナレッジマネジメントとは?
従業員が持つノウハウを社内で効率的に共有するための取り組みを「ナレッジマネジメント」と呼んでいます。
ここではナレッジマネジメントに関する基礎知識を解説していくので、まずはこれらをしっかりと押さえましょう。
ナレッジマネジメントとは「Knowledge(知識)」を管理するという意味であり、それを経営に活かす事までを含んでいます。
ナレッジマネジメントは日本発祥の考え方で、1990年代に一橋大学大学院の教授である野中郁次郎 氏らによって提唱されました。
それ以前から情報システムを活用した知識の管理というアプローチは欧米を中心に確認されていますが、「言語化・数値化が難しいノウハウ」を管理・活用していくという意味でのナレッジマネジメントは日本で生み出された考え方なのです。
ナレッジマネジメントが注目された背景
ナレッジマネジメントが日本で産声を上げたのには、いくつかの理由があると言われています。
例えば「ワークスタイルの多様化」というのが挙げられます。
日本に古くから根付いていた「終身雇用制度」はもはや形骸化しており、転職やキャリアアップを通じて、どんどん自分のやりたい仕事に進んでいく人も増えてきました。
その結果、人材の流動性が激しくなり、ノウハウを蓄えた従業員が現場で不足するというケースが多発したのです。
他にも、熟練技術者などが退職して、そのノウハウが継承できずに終わってしまうケースも散見されたので、そのような背景があって社内で知識&ノウハウを共有して、財産として継承していく必要性が求められたのです。
また、IT技術の発展によってビジネス界全体の情報化が急速に進んでいるというのも大きなポイントです。
高性能デバイスや多様なアプリケーションによって、ビジネス効率は大幅に向上したと言えます。
それは単に業務スピードが上がったというだけでなく、情報の共有についても同様です。
必要な時に必要な人間が、すぐ情報にアクセスできるようになったので、現代ビジネスでは基本的なIT環境さえ用意出来れば、ナレッジマネジメントを実施するための土壌が整備されていると言っても過言ではないでしょう。
2つの”知識”を考える
ナレッジマネジメントでは、従業員が持っている知識・ノウハウを「暗黙知」と「形式知」の2種類に分けて考えるのが特徴的です。
暗黙知とは個々人が持つ知識やノウハウの事で、言葉や数値に表しにくい状態のモノを言います。
これに対して形式知とは、個々人の知識・ノウハウを文章や数値で表したデータのことです。
ナレッジマネジメントではこの2つの「知識」が密接な関係にあるので、それぞれを適切に扱う事が重要になります。
この2つの知識があるのだと覚えておきましょう!
具体的なプロセス
ナレッジマネジメントを実施するにあたっては、「SECI(セキ)モデル」と呼ばれるプロセスを循環させていく事が推奨されています。
SECIとはこのメソッドにおける、
- 共同化(Socialization)
- 表出化(Externalization)
- 連結化(Combination)
- 内面化(Internalization)
という4プロセスの頭文字を取ったものです。
SECIモデルは先輩社員や教育係が持っている暗黙知を、新入社員に教えて共同化するところから始まります。
共同化した知識・ノウハウはマニュアルや資料に落とし込む事によって表出化されて形式知になります。
その後、ミーティングやプレゼンなどの「現場」を通して積極的に活用されていくのです。
表出化による形式知がある程度蓄積されてきたら、今度はそれらを関連付け・紐付けする事で連結化を図ります。
部署や部門をまたいだ領域横断的なマニュアル構築もできるため、会社全体に影響をもたらすケースも少なくありません。
ここまでのプロセスで全体に行き渡った形式知は、個々人が内面化する事によってまた新たな暗黙知となります。
そしてさらに発展したノウハウが生み出され、共同化・表出化・連結化のサイクルに繋げていくのがナレッジマネジメントの理想的な在り方なのです。
営業ナレッジを共有するメリットとは?
営業ナレッジを共有する事で期待出来るメリットには、主に以下の3点が挙げられます。
そのの恩恵をしっかり把握した上で、ナレッジマネジメントを実践していきましょう。
①人材育成の効率化
人材育成を効率化させる事はナレッジマネジメントの主要な目的であり、期待される大きなメリットです。
前述した通り、営業という個人業務が多いスタイルの関係で、営業ナレッジは個々人が知識などを溜め込んだ状態が続きやすくなります。
これをナレッジマネジメントによって共有・循環させる事が出来れば、新人営業マンを1人前に育てるまでの期間を大幅に短縮させられるでしょう。
②業務プロセスの改善
ナレッジマネジメントではSECIモデルを循環させる過程で成功例・失敗例など様々な事例を共有するので、不要な業務プロセスを特定する事もできます。
また、各営業マンが抱えていた疑問点の答えが共有されているナレッジの中に存在するケースも多く、わざわざ誰かに質問&相談する必要も少なくなるでしょう。
次第に再現性の高い営業手法が確立され、ムダなアクションが抑えられる事によって、業務プロセス全体の合理化と改善が進んでいくのです。
③顧客対応力の向上
営業ナレッジの中には各営業マンが担当している顧客情報も含まれています。
顧客との契約内容や進捗情報を共有しておけば、担当者が不在の場合でもスムーズな対応が可能となるでしょう。
顧客満足度が上がるだけでなく、成約までのスピードも早くなるので営業の回転率が向上すると思います。
ナレッジを共有するやり方
ナレッジマネジメントのスタートポイントは、個々人が持っているノウハウの共有です。
そのため、まずはナレッジを共有するための施策を固めておく事が重要になるでしょう。
この記事の冒頭でもご解説しましたが、基本的に営業マンが自ら進んで自分のナレッジを共有することはありません。
なので、会社としてまずやるべきことは、ナレッジ共有することに対するインセンティブを設定することです。
それはシンプルに「お金」という形で還元しても良いと思いますし、「昇進昇格」というインセンティブにするやり方もあります。
しかし、一番おすすめのやり方はチーム制を導入することです。
営業という仕事は人によって捉え方が違うかもしれませんが、個人的にはとても楽しい職業だと思っています。
なので、もう少しゲーム感覚を取り入れてみるのが良いでしょう。
例えば具体的には、まず営業部をチームA~Cに分けて、そのチームごとにノルマを与え、課長がチーム予算を達成させるためのマネジメントをしていくのです。
各営業マンごとにノルマを与えるのではなく、チームとして目標達成に挑む仕組みにすれば、そのチーム内で営業ノウハウの共有が始まります。
なぜかと言えば、チームが目標達成できなければ、自分の営業成績にマイナス影響を及ぼすからです。
このような仕組みであれば、積極的にチーム内でのノウハウ共有が自然発生するので、会社全体の営業力が底上げできるでしょう。
そして、このチームを定期的に解体してしながらメンバーを移籍させていけば、さらに営業ナレッジの蓄積が早まると思います。
これはあくまでも一つのやり方でしたが、ポイントは「どうすればトップセールスのノウハウを共有してもらえるか?」という仕組み作りにあります。
一般社員のセールスロジックには価値がありませんが、トップセールスのノウハウは非凡なので価値が高いと思っています。
つまり、重要なのはトップセールスのナレッジを会社に蓄積することなのです。
そこだけに焦点を絞って、トップセールス達がノウハウ共有したくなるような仕組みを用意してあげましょう。

営業ノウハウをシステム化する
属人的になりがちな営業ノウハウの共有は、ツールを用いてシステム化するのが理想的だと思います。
例えば一般的にナレッジマネジメントで使用されるツールには、顧客関係管理ツールであるCRMが挙げられます。
「カスタマー・リレーションシップ・マネジメント」の略であるこのツールは、顧客の動向・嗜好を記録する能力に長けており、効果的なアプローチを営業チーム全体で共有する事ができます。
しかし、いきなりこうした専門ツールを導入するのはハードルが高くて難しいと思うでしょう。
その場合にはどのオフィスでも標準とされているMicrosoft ExcelやGoogleドライブのスプレッドシートなどを用いて、知識やノウハウを体系化していくのがおすすめです。
大切なのはノウハウの「再現性」であり、どんな営業パーソンでもその知識を活用して成果が出せるようにしていくことです。
特に新規開拓のアプローチにおけるコツ・ノウハウをルール化しておく事は、事業規模の拡大に大きく貢献してくれるはずです。
営業活動で使えるITツールについては、下の記事にもまとめているのでぜひご覧ください。































