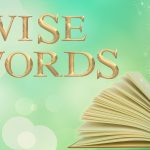※本ページはプロモーションが含まれています。
営業顧問を活用してみたい企業はたくさんあると思いますが、これまで活用したことがなかったり、活用方法がわからない企業も多いはずです。
そこで今回は、営業顧問の活用方法や募集方法などを詳しく解説していきたいと思います。
目次
営業顧問とは何か?
まず始めに、営業顧問とは一体どのような立場の人を指すのかご説明しておきたいと思います。
これはあくまでも一般論ですが、営業顧問とは業務委託契約を取り交わした外部のビジネスパートナーとなります。
つまり正社員や契約社員ではないので、雇用契約を交わすような関係性ではないということです。
「企業の顧問」と聞くと、なんとなく「立派な肩書や凄い経歴のある偉い人」みたいなイメージがあると思いますが、何よりも人脈や知識が豊富であることが特徴的だと思います。
顧問先企業のビジネスに対してのプロフェッショナル人材であったり、豊富な実務経験を持っていることが多く、経営顧問やアドバイザーとして貢献できる場合もあるのです。
顧問の種類
一言に顧問といっても、その種類は様々です。
ざっくり言ってしまうと、顧問の種類には「内部顧問」と「外部顧問」の2種類が存在しています。
内部顧問とは、社内の役員経験者や管理職経験者を「顧問」として選出することを言います。
内部顧問になる人は、これまで所属していた会社に多大なる貢献をしてきた人達ですが、定年退職で引退したタイミングや、役員任期が終わったタイミングで顧問として残留するのです。
内部顧問は自分が経験したノウハウを若手社員などに教えてくれるので、後任者への引き継ぎみたいな役割が大きくて、アドバイスも的確にできることが特徴的です。
現社長の相談役として、前社長が「会長」や「顧問」として留任するケースもあります。
外部顧問の場合は、専門知識や経営実績を持つ「外部のプロフェッショナル人材」を顧問として迎え入れます。
このケースでは、自社にないノウハウや知見を得ることができるので、社内のイノベーションを加速させることにも役立ちます。
外部顧問には専門知識を持った弁護士やコンサルタント、外部企業の元役員などが選出されていますが、そういった肩書きがなくても顧問として就任するケースがあります。
結局、「企業にとってプラスになり得る人材」であれば、実績や経歴を問わずに顧問として迎え入れているというのが実態になります。
顧問と相談役は違うの?
顧問の役職と似たものに”相談役”というのがありますが、それでは一体「顧問と相談役はどう違う」のでしょうか。
相談役とは会社経営で発生する様々な問題に対して、適切なアドバイスをしてくれたり、関係各所と調整をしてくれる役職のことを言います。
勤務形態としては常勤、又は非常勤になりますが、あくまでも困った時の相談役(アドバイザー)というイメージになります。
なので一般的な相談役は、社長や会長が退任した後に指名されるケースが多く、いわば元社内の人間であることが多いのです。
そういった意味では、内部顧問に近い性質があると思います。
もちろん社内に限らず、外部企業で働いていた人が相談役として就任するケースもあります。
それと比較して営業顧問は、自分の人脈を提供することが主な業務となるので、その企業の売上貢献というところに重きを置いているのが特徴的です。
つまり、営業顧問がやっていることは営業支援や販路拡大の支援ということになります。
顧問を”社員”にしない理由
ここまで読み進めた人は顧問がその道の専門家(プロフェッショナル)であり、人脈も豊富な人であることが理解できたはずです。
そうすると、「顧問を社員として雇ってしまった方が良いのでは?」という疑問が湧いてきますよね。
果たして、顧問を正社員にしない方がいい理由などあるのでしょうか?
結論から申し上げると、顧問を社員にすることは現実的ではなく、難しいと言えます。
顧問とはあくまでも外部の人なので、業務委託契約が基本になっていきます。
そもそも営業顧問とは自社を退任した元社員であることが多く、本人の意思はもちろん再雇用を前提としていません。
もちろんやろうと思えば再雇用できますが、顧問になる人物は高齢であるケースが多く、長期雇用に適した年齢ではないという側面もあります。
さらに企業が顧問を頼るケースはスポットでの利用が多く、「この案件だけ相談したい!」「今だけ営業支援して欲しい!」というニーズが多いのです。
よって、継続雇用を前提にした正社員では、お互いのニーズが合致しないということです。
そのような理由から、原則的に顧問とは業務委託契約が交わされているのです。
営業顧問を活用するメリット
いくら社外の人間だとしても、営業顧問は会社のトップが認めた実力のある人物であることに疑いの余地がありません。
会社としては営業顧問に対してコスト(業務委託費)が発生しているので、出来る限り有益に活用したいものですよね。
それでは、営業顧問を有効活用する為には、どうしたら良いのでしょうか。
営業顧問は、そのネーミングの通り営業活動を熟知しているはずです。
なので、以下のようなアドバイスをお願いすることができるはずです。
- 受注率改善について
- 販路拡大のやり方について
- 代理店制度の構築について
製品・サービスやビジネス環境によって、最適な営業スタイルや営業戦略は変わってくると思います。
また、競合他社の動向や、時代の流行などにもよって販売戦略は常に進化させなければいけません。
そのような時の相談役として営業顧問は活用できるはずです。
他にも、営業顧問は数多くの人脈を持っているはずなので、その人脈を活用した「リファラル営業」を依頼することも効果的だと思います。
リファラル営業は「紹介営業」を意味する言葉ですが、人脈が多い営業顧問であればもってこいの役回りだと思います。
リファラル営業については下の記事にまとめているので、是非ご覧ください。
営業顧問の給料
ここまで営業顧問についての解説をしてきましたが、これだけの仕事をしてくれる顧問の給料はいくらほどなのでしょうか?
もちろん業務委託契約なので契約内容によって全く異なりますが、大枠では「固定報酬型」と「成功報酬型(成果報酬型)」の2種類に分かれると思います。
固定報酬型は「月額50万円」というような定額制の報酬になりますが、成功報酬では支援した成果に応じて報酬額が増えるシステムが一般的です。
例えば、自分たちのニーズを伝えた上で、営業顧問が”知り合いの会社”を紹介してくれたとします。
その会社と無事に契約締結となり、売上1,000万円が計上できた場合、固定報酬だけの場合には月50万円を支払って終わりですが、成功報酬がある場合にはちょっと話が違ってきます。
例えば、新規受注したタイミングで、営業顧問に売上の10%(100万円)を成功報酬として支払うようなやり方となるのです。
この成功報酬の割合に目安などはありませんが、一般的な紹介報酬の相場というのは「売上金額の10%~20%」くらいであり、固定報酬よりもリスクがあるので顧問側が儲からなければいけません。
売上金額が大きくなるケースには、あらかじめ「レーマン方式」のようなコミッション形態を採用することもありますが「固定報酬と成果報酬のハイブリッド型」もあるので、様々なパターンが作れると思います。
報酬金額の決め方
顧問の報酬については、お互いにすり合わせて決めればいいと思いますが、「その決め方がわからない…」というケースもあると思います。
なので、ここでは報酬金額の決め方について解説しておきたいと思います。
報酬金額を決める上で重要なことは、以下の通りになります。
- 稼働日数
- 業務内容
- コミットメントの有無
稼働日数に関しては「何日間働いてくれるのか?」ということになります。
例えば、1ヶ月に5日間は会社に常駐してくれるとしましょう。
その時に1日あたり5万円と換算した場合、「5万円×5日間=25万円」という計算になります。
それでは次に、「会社に常駐してる間、どんな仕事をするのか?」ということを決めていきます。
例えば、以下のような業務内容にしたとします。
- 営業戦略の会議に出席
- 新規顧客との商談セッティング
- 営業マンと同行営業
このような仕事内容だった場合、
- 営業会議には何時間出席するのか?
- 同行営業の件数は何件にするのか?
- 商談セッティングの件数は何件にするのか?
というコミットが求められる話になってきます。
この辺りまで落とし込めれば、「報酬金額が妥当か否か?」の判断がついてくると思います。
一応ここでは『おすすめの報酬形態』をご紹介しておきますが、それは【固定報酬(少なめ)+成功報酬のハイブリッド型】となります。
固定報酬だけを払ってしまうと、良くも悪くも報酬がもらえてしまうので「出し惜しみ」されるケースがあります。
つまり、顧問としては出来る限り長期契約にしたほうが儲かるので、たくさんある人脈や取引先を出し渋ってしまうのです。
また成功報酬だけにした場合、どうしても事業に対するコミットメントが弱くなってしまいます。
やっぱり事業はスピード感もって進めたいですし、事業予算の関係もあります。
この両方のデメリットをメリットに変えることができる仕組みが『ハイブリッド型』なのです。
先ほどのように、「固定報酬(少なめ)+成功報酬のハイブリッド型」という形式にすれば、固定報酬によってコミットメントを維持し、成功報酬によってモチベーションアップを図ることができます。
色々と細かく解説しましたが、シンプルに言ってしまうと「費用対効果が合えば何でもOK」だと思うので、最終的には営業顧問を活用すると「いくら儲かるのか?」という粗利金額から逆算するのもいいと思います。
営業顧問の募集方法
実際に営業顧問を使ってみたい場合には、顧問を探すことから始めなければいけません。
内部顧問であれば簡単に見つかると思いますが、外部顧問はそう簡単にいきませんよね。
一般的に、人づてで探すことが多い外部顧問ですが、最近では営業顧問を斡旋する顧問紹介サービスもあります。
そのようなサービスには、顧問として活躍したい人がたくさん登録しているのです。
ここではおすすめの顧問紹介サービスを記載しておきますので、気になるサービスがあれば是非お問い合わせしてみてください。
マイナビ顧問

マイナビ顧問は、皆さんご存知の「マイナビ」が提供している顧問紹介サービスです。
元上場企業の役員や取締役など、高度な経営ノウハウや豊富な人脈を持つ人がたくさん登録されています。
営業だけに限らず、組織運営や事業構築など経営全般について相談することもできます。
様々な課題を解決できるアドバイザー探しに最適だと思います。
i-common(アイコモン)
-i-common.jp_.png)
i-commonは、dodaなどを運営しているパーソルが提供する顧問紹介サービスです。
マイナビと同様、人材事業に強みを持っているため、豊富な顧問人材が強みになっています。
マイナビ顧問と同じく、営業顧問だけでなく総合的な経営支援ができる人材がたくさん登録されているので、きっとニーズに合う人が見つかると思います。
KENJINS(ケンジンズ)

KENJINSは、これまでの顧問紹介サービスと一線を画す内容になっています。
それは、
- 求人掲載料ゼロ円
- 採用成果報酬ゼロ円
- 中間マージンゼロ円
という3つのゼロを実現したことです。
初期費用などが掛かるので”完全無料(0円)”というわけではありませんが、大手の顧問紹介サービスに比べて安価に利用できると思います。
顧問名鑑

顧問名鑑は、老舗の顧問紹介サービスです。
”事業拡大の支援”にコミットメントしているので、企業にマッチした人材を斡旋してくれることでしょう。
これまでの豊富な実績を基にしたマッチングに定評があるので、顧問紹介サービスを検討する際には候補に入ると思います。
顧問バンク

顧問バンクは、約7,000名(※2021年5月現在)のプロフェッショナル人材が登録されている顧問紹介サービスです。
「料金が安い」ことを全面に打ち出しているので、今まで利用していた顧問紹介サービスからの乗り換えするのもおすすめです。
比較的「営業顧問」に強みを持っているので、リファラル営業を強化したい場合にはオススメできます。
side bizz(サイドビズ)
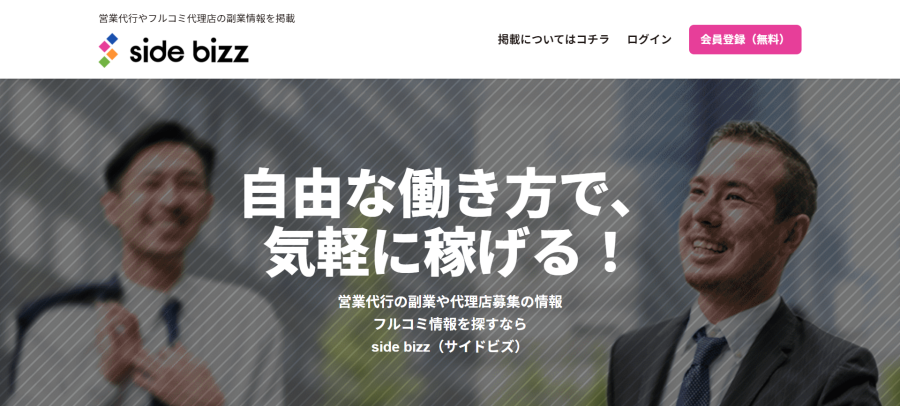
side bizzは、「紹介営業」に特化したリファラル営業プラットフォームです。
顧問紹介サービスとは少しニュアンスは違っていますが、紹介営業をやりたい場合には最適だと思います。
side bizzが実現したことは、全国にいる営業職やフリーランスを一つのサイトに集めて、その人脈や販路をシェアするという考え方です。
これまでの営業顧問といえば、肩書きの偉い人が担っていましたが、それをクラウドソーシングという仕組みで再現したのがside bizzになります。
顧問登録をしてみよう!
ここまで顧問を活用するメリットなどについて解説をしてきましたが、「自分も顧問になれるんじゃないか?」と思った人がいるかもしれません。
実はその通りでして、今の時代は誰でも顧問になることができるのです。
つまり、ある特定分野のプロフェッショナルであれば、その分野についてのノウハウを提供することができるはずです。
それがビジネスの領域であっても、趣味の領域であっても大差ありません。
要するに、ニーズがあって、それに見合う供給があればマッチングするので、重要なことはニーズ(顧客)を探し出すことなのです。
ニーズさえ探し出せれば、あとは顧問として支援するだけです。
その「ニーズを探し出す」という作業を代行してくれるサイトがいくつかあります。
先ほどご紹介したside bizzもその一つになります。
他にも下記のようなサイトがあるので、もし興味があれば登録してみてください。
どのサイトも無料で登録できるはずなので、まずは行動してみることをお勧めします。
まとめ
営業顧問はうまく活用すれば、とんでもない金額の売り上げを叩き出してくれる可能性を秘めた施策だと思っています。
過去にも、営業顧問が裏で動いた結果、大きなアライアンス契約が実現した事例は多いので、活用しないという選択肢はありませんよね。
あなたの事業を飛躍させるきっかけになるかもしれないので、ぜひ営業顧問の活用を検討してみてください。