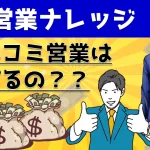営業活動をする以上、必ず起こるのが「クレーム」です。
このクレームをポジティブに捉えるか、ネガティブに捉えるかは会社や上司、あなた次第です。
そこで今回は、営業クレームについての対応方法や、クレームや苦情に対する考え方などを解説していきたいと思います。
目次
営業にクレームはつきもの
営業職として勤めている人で「顧客からのクレームを経験したことがない」という人は皆無でしょう。
逆に、もし「クレームを受けた経験がない」という人がいるなら、それは営業職としての仕事を全うしてない可能性があるので要注意です。
クレームを受けることはストレスが溜まりますが、営業活動をしていればクレームが発生するのは避けられませんし、むしろ一生懸命セールスすればするほど、クレームが発生するはずです。
特に、営業を始めたばかりの新人の頃であれば、分からないことが多いので大失敗することもあるでしょう。
もちろんクレームは発生しない方が良いのですが、クレーム自体をゼロにすることは難しいものです。
なので、問題は発生したクレームの内容だと思います。
クレームが発生する理由は、大きく分けて4つほどあります。
- 商品の不具合
- 社内ルールの強要
- お客様の勘違い
- 営業マンの態度
商品の不具合に関しては、営業マンに責任はありません。
これは製造側の問題なので、マニュアル通りの対応をすれば大丈夫です。
また、社内ルールの強要もクレームに発展する場合があります。
例えば以下のようなイメージです。
- 納品前に入金(前入金)が必要
- 柔軟な対応が一切できない
- 何枚も書類が必要になる
お客様の目線に立っていないやり方やルールなど、会社毎に様々な社内ルールがあります。
その結果起こるクレームに関しては、営業パーソンの問題ではなく社内制度の問題なのです。
なので、社内ルールに関するクレームもネガティブにならなくて良いでしょう。
最後に、お客様の勘違いでクレームが起こるというケースもあります。
これはとても厄介な話ですが、稀に勘違いでキレるお客様がいますが、自分が正しいのであれば毅然とした態度で対応しましょう。
ここまでご紹介したクレームなのであれば、それはあなたのせいではないので、さほど問題ではないはずです。
唯一問題になるクレームとは「営業マンの態度」に関するモノなのです。
クレーム対応は「成長の糧」になる
「営業マンの態度」に対するクレームだけは、自分自身が改善しないと対処できないモノになります。
- 提案する態度が悪かった…
- 接客態度に問題があった…
など態度を起因としてクレームに発展することは稀にあり得ます。
プライドが邪魔するので、これらを素直に認めるのはなかなか難しいことですが、できる限り誠実に聞いて、今一度自分自身を見つめ直した方が賢明だと思います。
なぜかと言えば、それはあなた自身をさらなる高みに連れていってくれるからです。
もし態度を起因としたクレームを受けた場合「これまでと同じような接客をしてきたのに、なぜ今回だけクレームになったのか?」と、冷静になって考えてみてください。
それは、過去に接客してきたお客様も同じように不満に感じていたが、ただクレームを言われなかっただけと考えられます。
これは驚愕の事実だと思いますが、ほとんどのお客様は「何か不満に感じること」があっても、何も言わずスルーします。
普通の感覚からすれば、クレームを言うのは疲れますし、多少なりともストレスが溜まるものです。
それでもクレームを言ってくれるお客様は、比較的良い顧客なのかもしれません。
つまり、「営業マンの態度」に対するクレームが発生したタイミングとは、自分自身の悪い点を改善することができる絶好のチャンスなのです。
わざわざクレームを言ってくれたお客様に感謝して、その点を素直に改善すればいいと思います。
自分一人では、なかなか自分自身の悪い箇所を見つけることはできませんし、人から指摘されて初めて気付くことは多いでしょう。
このようなクレームに対して、誠実&素直に受け入れながら改善していった営業パーソンは、その後にトップセールスと駆け上がっていくことでしょう。
クレームが多い場合の対処法
営業マンは会社の窓口になる存在なので、お客様と接する最前線でクレーム対応する必要があります。
とはいえ、もしクレームの数が多い場合には、業務フローや製品自体に問題があるのかもしれません。
先ほど解説したように、クレームが発生する理由には大きく分けて4種類がありました。
- 商品の不具合
- 社内ルールの強要
- お客様の勘違い
- 営業マンの態度
業務フローや製品に問題があるということは、この中でいうと「商品の不具合」と「社内ルールの強要」に当てはまります。
商品の不具合と社内ルールに問題があるのであれば、それは見直す必要があると思いますが、それ自体は営業社員ではなく社内の問題です。
もし商品の不具合が続くようであればお客様は離れてしまうので、不具合が起こった原因をしっかり分析する必要があります。
なぜかと言うと、クレームが発生した裏側には多くの「ひやり&はっと」するような事例が隠れているからです。
これは「ハインリッヒの法則」と言われており、1つの重大事故は起こった裏側には29の軽微な事故があり、その背景には300の異常があるというものです。
300の異常 ⇒ 29の軽微な事故 ⇒ 1つの重大事故
つまり、クレームを1つの重大事故と考えた場合、その裏側には「300人のクレーム予備軍がいる」と考えることも出来るのです。
このように考えた場合、「1件のクレームだから大丈夫だろう…」という考えが、いかに浅はかなものか理解できるはずです。
もしクレームが1件でも発生した場合、その不具合を防止して、二度と起こさないようにしなくてはいけません。
これは一番現場に近い営業部から経営サイド(社長や事業責任者)に進言するべきでしょう。
また、業務フローの問題でクレームが起こるのであれば、業務フロー自体を改善する必要もあります。
クレームとはアラートのようなものなので「業務フローを改善するチャンス!」と捉えて、前向きに行動するようにしましょう。
クレーム対応の理想形は「クレーム客をファンに変える」ことです。
決して簡単な事ではありませんが、この理想を目指すことが正しいクレーム対処法だと思います。

クレーム対応が「つらい」なら異動する
営業マンは会社の窓口であり、ビジネスの最前線に立っています。
そのため外資系企業では「フロント」と呼ばれていて、クレームを直受けする立場にあるので、その分ストレスが溜まりやすい仕事だと言われています。
営業職と同様に、お客様と対峙するコールセンターも「クレームによるストレスが多い」と言われていて、離職率が高い傾向にあります。
そのような仕事のため、営業職やコールセンターの人がストレスを溜め込まないように、会社はメンタルケアをする必要があるはずです。
商品に大した問題がなかったとしても、「返金しろ!」「上司を出せ!」といった理不尽なクレームも発生するため、気分が落ち込むこともあるでしょう。
中にはモンスタークレーマーと呼ばれる類の人達や「カスハラ(カスタマーハラスメント)」と呼ばれるのも発生します。
このような特殊なクレーマーに対処するには、それなりのノウハウが必要なので、ぜひ下の書籍を参考にしてください。

クレームを受けてから気持ちを切り替えることができず引きずりやすい人は、メンタルケアが難しいので、クレームがあまりにも辛い場合は部署異動について上司と相談してみましょう。
ストレスを溜め込みすぎると精神的におかしくなってしまい、最悪のケースでは”うつ病”などの精神病を発症することもあります。
病気になってまで営業職やコールセンターの仕事を続ける必要は決してありません。
体調を崩してしまうと日常生活にも支障をきたすので、そんな時には異動届を出して、他の仕事に替えてもらいましょう。
クレーム対応のやり方を解説
クレームには様々な種類がありますが、例えば代表的なものは「上司を出せ!」と言われるクレームです。
優しい上司であればすぐに電話を変わってくれるかも知れませんが、上司とお客様の板挟みになって大きなストレスを抱えることもあります。
しかし「上司を出せ!」と言っているクレーマーを、何もせずに黙らせることはできません。
そこで大切なのは、
- どのような不手際があったのか?
- どのようなことに怒っているのか?
などその理由をしっかりとヒアリングすることです。
その過程で、お客様が落ち着いてくる可能性もあります。
というのも、自分が怒っている理由を人に話すと、人間は「自分の不満を聞いてくれた」という満足感が出てくるので、大抵の人は落ち着いてくれるのです。
とはいえ、クレーム対応のやり方に方程式はないので、臨機応変な対応が求められます。
クレーム相手が自分に対して怒っている場合は、まずは謝罪とお詫びを丁寧な言葉でする必要があります。
誠意を示して丁寧に謝ることで、お客様は落ち着いていく傾向があるからです。
ちなみに、謝罪方法について詳しく知りたい場合は下の記事をご覧ください。
不手際があったことを謝罪&お詫びをし、相手の意見に反論せず共感して、事実確認を行います。
そして、ケースバイケースで解決策を提示しましょう。
クレーム度合いにもよりますが、クレーム度合いが強ければ、最終的には担当変更が最も効果的だと思います。
クレームは営業マンの誇り
クレームは受ける側からすると、相当ストレスのかかるものです。
「できる限りクレームが出ないように仕事をしたい…」と誰もが考えているはずですが、営業職である以上はクレームに対する考え方を変えなければいけません。
そもそも、クレームは必ず発生するものですし、完璧に防ぐことはできません。
それであれば、前向きに活用することを考えた方が良いと思います。
トップ営業マンの中には、クレームを「ありがたいもの」として考えている人は大勢います。
なぜなら、クレームは営業熱心に頑張っている証拠ですし、ある意味ではお客様からのフィードバックだと言えるからです。
マインドがあるトップセールスは、クレームを受けることを「営業職としての誇り」だと思っています。
商品自体が悪いものでないという前提であれば、クレームが起こるのは一生懸命売り込んでいる証であり、行動している証拠なのです。
この「行動している証拠」というのが最も重要な部分になります。
つまり、全くセールスしていない営業スタッフにクレームが起こることは絶対にあり得ないのです。
クレームの多い営業マンは、間違いなく努力しています。
ただそのやり方(アプローチ方法など)を間違えた為、クレームに発展したのです。
なので、次からはそのやり方を改善すれば良いだけです。
このような背景が理解できれば、内容にもよりますが「クレームが発生するということは上司としても誇るべき状況」であることがわかります。
顧客との信頼関係が強固になる
クレームが出るのは仕方がないとして、それをうまく乗り越えた時、営業パーソンとお客様の間には強固な信頼関係が出来上がります。
なぜかと言うと、クレームを言ってくるお客様はサービスの改善を求めており、取引を続けたい意思があるからです。
つまり継続意思がないお客様は面倒なクレームなどを言うことなくそのまま去っていくはずですし、クレームを言ってくれるのはあなたや会社に期待をしている証拠だということです。
このように考えると、クレーム対応の重要性がだいぶ違ってくると思います。
良質なお客様を増やすための手段になり得るクレーム対応なので、「どのように対応すべきか?」という知識&やり方を学んでおいて損はないでしょう。
参考になる書籍はたくさん出ているので、接客業をするなら少なくとも3冊ぐらいは読むようにしましょう。
決して驕ることなく毎日自己研鑽をして、クレーム対応のスキルやノウハウを身につけ、これからの営業活動に活かしてみてください。