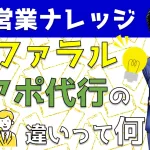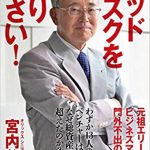どんな職場にも一人ぐらいは「仕事ができない人」が入ると思います。
それは新卒社員を指すこともあれば、窓際族のような人を指す場合もあります。
しかし本当にそのような人材は「仕事ができないダメ人間」なのでしょうか?
この記事では、経営者やマネージャークラスの人に対して「効果的な人材活用術」をお伝えしたいと思います。
仕事ができない人の特徴
どの職場でも一定数「仕事ができない人」が出てきてしまうと言われています。
これはパレートの法則に基づいてる可能性があります。
パレートの法則とは「2:8の法則」とも呼ばれていて、ほぼ全ての事象に当てはめることができる万能法則になります。
つまり組織の中で当てはめた場合、以下のような法則が発動します。
- 全体の2割は優秀な人
- 全体の2割は仕事ができない人
- 売上の8割は上位顧客2割からもたらされている
- 新規営業の受注率は2割
- 代理店の稼働率は2割
これらはどれもパレートの法則に基づいた数字ですが、実際このような状態になっていることが多いと思います。
そう考えた場合、どうしても全体の2割程度は使えない社員が出てきてしまうのです。
一般的に「仕事ができない人」には共通の特徴があると言われています。
まず一番に考えられるのは、思考回路がネガティブなことです。
仕事をすることにやりがいや楽しみを感じることがなく、「生活費を稼ぐために働いている」という思考回路になっているのです。
なのでキャリアアップを目指したり、上昇志向があるような人はほとんどいません。
そして口癖は「疲れた」「めんどくさい」などのネガティブなワードが多く、常に陰気な顔をしています。
このような人がいると職場全体に悪影響を与えてしまうので、経営者にとっては非常に面倒な存在だと思われます。
時には、周囲のやる気がそがれてしまうことを気にせず、「ウチの仕事は面白くないよね」などの同意を求めたりします。
もし相手が否定するようなら、その人を攻撃したり、論破しようとするケースもあります。
たとえ注意しても「自分が正しい」と思っているため、逆に注意してきた人を批判する傾向があります。
そのような人に振り回されてしまうと、周囲の人はヘトヘトになってしまうでしょう。
社会人にとって常識とも言える「報告・連絡・相談」や「挨拶する」などの基本的なルールやマナーすら守れていないことが多いので、もはや組織にとってのがん細胞のような存在になっているのです。
仕事できない自覚がない!?
仕事ができない人は、意外と本人にはその自覚がありません。
そもそも「仕事ができない人」とはどのような定義なのでしょうか?
その定義方法は色々あると思いますが、一般的な回答としては「結果が出せない人」だと思います。
仕事には様々な職種がありますが、どのような仕事でもある程度結果を求められると思います。
その結果を出せない人は、一般的に「ダメな人」とか「できない人」と呼ばれているはずです。
例えば営業職なら「ノルマが達成できない人」は典型的な仕事ができない人だと思います。
しかし、本人は努力しているつもりなので、「結果が出ないのは自分のせいではない」という変な思考回路になっているのです。
仕事では結果を出すことが大切と説いても、「求められるノルマが高すぎるからいけない」とか「ノルマ未達成は自分だけじゃない」と論点をすり替えるような考え方をするのです。
それどころか、「自分は誰よりも仕事しているのに、なぜ周囲の人たちは認めてくれないんだろう?」と思うケースすらあるのです。
このような人が部下にいると、上司も呆れ果ててしまうので、余計放置される傾向があります。
当然周りの社員たちも関わりたくないと思いはじめますが、本人は「自分は悪くない」の一点張りなのでラチがあきません。
そして最終的には、組織の中にいる優秀な人の足を引っ張ろうとし出すのです。
できる人が仕事の評価を褒められると、胸糞悪さを感じて「あいつはきっとズルをしている」とか根も葉もない噂をし始めます。
能力が高い人は人に迷惑をかけないように仕事しますが、能力の低い人は、会社を含めて人に迷惑をかけてばかりいるのです。
ダメな人の改善方法
サラリーマンは会社から給与をもらっているので、仕事をしなければ存在価値がありません。
しかし前述したように「ダメ社員」がいた場合、どうすれば良いのでしょうか?
まず結論から言ってしまうと、本人に改善を求めることはなかなか難しいと思います。
というのも、仕事ができない人はプライドが高い傾向にあるので、改善指示を素直に受け入れることはありません。
先ほども解説したように「悪いのは自分じゃない」という思考回路なので、説得するだけでも骨が折れる作業だと思います。
そのような人材を改善させる為には、仕組みでカバーするしかありません。
例えば全く新規開拓営業ができないダメ営業マンだった場合、その人に対して「早くお客様を開拓してこい!」と叱咤することは逆効果になりかねません。
そうではなくて、むしろ「新規開拓ができない奴」と認めることから始めていくべきだと思います。
これはネガティブな考え方ではなく、個性を認めるということです。
もし新規開拓営業ができないのであれば、アポイント獲得に特化したテレアポ要員にするというやり方もあります。
他にも、既存顧客のフォローアップに専念するカスタマーサクセスに配属するのも良いでしょう。
一言に「営業マン」と言っても様々な個性があるので、どのような長所を持っているか分かりません。
適材適所という考え方で言えば、まずはOJTしてみることをお勧めします。
それをやる中で、飛び抜けた才能が見つかるかも知れません。
もしそのような才能を持っている人材であれば、会社にとってはまさに「人財」へと変化するはずです。
仕組みを提供しよう!
もし会社内に異動できるような部署がなかったり、役割がない場合には仕組みを提供するしかありません。
例えば先ほどの例のように「新規開拓ができないダメ営業マン」がいたとします。
この人を活用できそうな部署がなかった場合、ダメ営業マンでも新規開拓できる仕組みを提供する必要があります。
例えば、反響営業に切り替えるというやり方があります。
反響営業の場合には見込み客からの問い合わせ対応が主になるので、トークスクリプトやFAQさえ用意しておけば、新人営業マンでも受注することができるはずです。
つまり、潜在ニーズを掘り起こすような営業が下手くそな場合、顕在ニーズに対応するような営業スタイルに変化させるということです。
そのような営業スタイルにした場合、もしかしたら新規受注を量産するかもしれません。
もし広告宣伝費が捻出できないのであれば、リファラル営業を活用しても良いでしょう。
リファラル営業を支援するプラットフォームもあるので、反響営業の仕組みはどんな会社でも作れるはずです。
営業部のマネージャーは個人の能力を決めつけずに、改善方法を前向きに検討していきましょう。
仕事を任せてみる
人間にはさまざまな個性があります。
例えば、学校生活で考えるとスポーツができる人、勉強ができる人、コミュニケーションが得意な人など様々な能力が考えられます。
いくら「仕事ができない」といっても、ダメな人にも必ず得意分野があるはずなので、それを探して能力を活かすような戦略を考えましょう。
意外と指示待ち人間になっているだけかもしれないので、まずは仕事を任せてみるのも良いでしょう。
重要な仕事だとトラブルになった時に面倒なので、難易度の低い仕事からお願いしてみましょう。
ある程度の責任感を持てば、本人の心境に変化が起こるかもしれません。
ここで注意すべきことは、一度仕事を任せたら、本人が助けを求めてくるまで一切口出ししないことです。
たとえトラブルが起こっても、とりあえず静観してみます。
人は失敗してこそ成長するものです。
何をやってもダメな人なんていないと信じましょう。
仕事できない人を邪魔者にしない
仕事ができない人を邪魔者にしてはいけません。
「何かやりたい」「助けてあげたい」という感情や意欲を持つのは素晴らしいことだと思います。
彼らも「人のために何かをやってあげたい」という欲求を持っているのに「仕事ができないから」と改善する余地も与えずに邪魔者にしていたら、ストレスがたまって落ち込んでしまうでしょう。
彼らだって自分なりに頑張っているはずです。
ただ、具体的にどのような行動をとれば人に喜んでもらえるかがわからず、空回りしているだけなのです。
その場合はやり方を修正してあげれば良いのです。
実際に仕事をやらせて、失敗させ、反省してこそ人は成長します。
それに対して腹が立ったり目障りに思うかも知れませんが、根気強く接していきましょう。
いらないからと邪魔者扱いしたり、邪険にしていると必ずしわ寄せがきます。
現在は労働者保護の傾向が強いので、「パワハラだ!」と訴えられるかもしれません。
もちろん一定数モンスター社員のような人もいますが、ほとんどはコミュニケーション不足が原因になっています。
「あいつはできない奴だ!」と馬鹿にするようでは、結局自分が損をするのです。
辞めたいなら転職させる
仕事ができないことを理由に転職を希望する場合もあります。
「今の職場では自分の能力を活用できないから、転職して新天地で再出発しよう!」と考えるのです。
もし、仕事ができない人が転職を希望しているなら、そこはすんなりと受け入れて良いと思います。
というのも、仕事ができない人を活かすためには、それ相応の労力が必要になります。
先ほど解説したような仕組みを構築したり、長期間にわたってコミュニケーションを取る必要もあるでしょう。
一般的な中小企業にはそのような余裕がないので、大企業でないなら退職希望者はすんなり受け入れた方が無難だと思います。
無理に引き留めた結果、鬱病になって休職されると最悪のケースにもなりかねません。
そのようになるくらいなら、転職して自分に合った仕事を見つけてもらった方が双方幸せだと思います。
自分の能力を客観的に見極めるのは難しいですが、言い訳ばかりして改善の努力が見受けられなかったり、人のせいにするのはただの甘えです。
人生のどこかで過ちに気がつくかもしれませんが、それが今の職場ではなかっただけです。
もし仕事ができない人が転職を希望しても、決して気を病む必要はないのです。