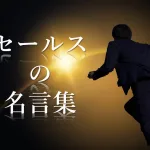ビジネスパーソンであれば、一度くらい「シックスシグマ」という言葉を聞いたことがあると思います。
しかし小難しそうなキーワードなので、なんとなくスルーしてしまいますよね。
そこで今回は、難解な”シックスシグマ”をわかりやすく、且つ簡単に解説したいと思います。
製造業に携わるビジネスパーソン、メーカーへの就職を目指している大学生にとっては有益な情報だと思うので、ぜひご覧ください。
シックスシグマとは?
シックスシグマは取り立てて”新しい手法”というわけではないですが、1995年にGE(ゼネラル・エレクトリック)が導入したことで注目を浴びました。
GEは100年以上の歴史があるアメリカの大企業で、「発明王」のエジソンが創業者の会社です。
その従業員は20万人以上おり、いわゆる「何でも屋」と言えるような規模の会社なのですが、シックスシグマを導入した時の経営者は「20世紀最高のCEO」と呼ばれた、あの有名なジャック・ウェルチです。

それに追随するようにソニーがシックスシグマを導入したり、東芝、日立マクセル、シマノなどの日本企業がこぞってシックスシグマを求め始めました。
その内容を簡単に説明すると、事業経営の中で起こるミスやエラー、欠陥品の発生確率を「100万分の3.4」に抑えることを目標にした経営改革活動ということになります。
「なぜゼロではないのか?」と疑問になるかもしれませんが、製造業であれば必ずと言っていいほど「欠陥品」が出てしまうからです。
しかし、その割合を極めて小さいレベル(=ほぼゼロ)に留めることを目指すので、成功すればかなり大きな業務改善が見込めるはずです。
シックスシグマの誕生経緯
シックスシグマという手法は、1980年頃にモトローラのマイケル・ハリーが確立させました。
モトローラはアメリカの大手通信機器メーカーなのですが、「自社製品の品質が悪い」という問題意識から、業務改善に取り組んだそうです。
昔から「日本製品は品質が良い」と言われていますが、その品質の差に驚いたモトローラは、日本的経営を徹底的に研究し、とにかく高品質の製品を求めました。
その成果がシックスシグマなのですが、そう考えた場合「シックスシグマが誕生したルーツは日本にある」と言っても過言ではないでしょう。
「シグマ(σ)」の意味とは?
「シックスシグマ」という名称の中に入っている「シックス」は「6」だと分かりますよね。
それでは「シグマ」とは、どのような意味なのでしょうか?
そもそもシグマ(σ)とは、統計学用語で「バラツキ」を意味する言葉です。
バラツキと聞くと「???」かもしれませんが、いわゆる”平均みたいなもの”だと思えば分かりやすいはずです。
テストの平均点が60点だった場合、そこを頂点にして左右にバラツキが広がっていきますよね。
そのことを統計学では「標準偏差」と呼んでいます。
そしてこのばらつきの度合いを表す単位がシグマ(σ)なのです。
なぜ「シックス(6)」と呼ばれるの?
シグマは分かったとしても、「シックス(6)」と言われている理由が気になりますよね。
前述した通り「シグマは標準偏差のこと」なので、6は「σが6個分」という部分に由来します。
この辺りはやや難解ですが、6個のσは決められた仕様値と実際の平均値との間に入るので、この「6」という数字がこの時の”Z値”になるということです。
Z値とは、標準偏差の単位で観測統計量とその仮説母集団パラメータの差を測定するZ検定の統計量です。
つまり仕様値と平均値の間の距離を標準偏差σで割った値のことを指しています。
例えば平均値と仕様値が変わらなくて、バラツキ(シグマ)が大きくなれば、当然Z値は小さくなっていきます。
反対に製品やプロセスが安定していて、バラツキも少なければ、Z値は大きくなっていきます。
もしシックスシグマに関わるプロジェクトを立ち上げる場合、まずはこのZ値を定量的に表して、その数字が3未満の場合には現状の不良率を1/10に低減することを目指し、Z値が3以上の場合には不良率を1/2に低減することを目安とします。