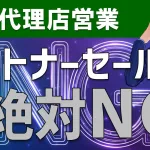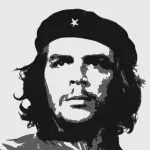孔子(こうし)といえば、中国を代表する思想家ですよね。
紀元前500年頃に活躍した春秋時代の思想家であり、哲学者ですが、その言葉をまとめた書物が『論語』です。
「日本経済の父」と呼ばれている渋沢栄一も論語が愛読書だったようで『論語と算盤』という名著を残しています。

そこで今回は、論語に記されている孔子の名言をご紹介したいと思います。
数多くの経営者に影響を与えてきた『論語の言葉』なので、ビジネスパーソンは是非ご覧ください。
孔子の論語名言集まとめ
学んで思わざれば則ち罔(くら)し。思うて学ばざれば則ち殆(あや)うし。
<訳>外からいくら知識や情報を得ても、自分で考えなければ物事の本質は理解できない。逆に自分で考えるだけで外から学ばなければ独断的になってしまう危険がある。
これは学ぶこと&考えることのバランスについて語った名言です。
読書する優位性についても触れているので、孔子は読書を推奨しているのがわかります。
たくさん本を読みましょう!

これを知るをこれを知ると為し、知らざるを知らざると為せ。是れ知るなり。
<訳>はっきり分かっていることだけを「知っている」とし、よく知らないことは「知らない」という。このように知っていることと知らないことの間に明確な境界線が引けることを、本当に「知っている」という。
この名言は『自分を理解する』ことを解説した名言です。
どうすれば今の自分が理解でき、どうすれば成長できるかも、この名言で明確になります。
知ったかぶりもなくなるので、自分の無知を謙虚に認められるでしょう。
多く聞きて疑わしきをかき、慎みて其の余りを言えば、則ち尤寡(とがめすく)なし。
<訳>たくさんのことを聞いて疑問点を正し、少しでもこれは怪しいと思うことは口にしないようにすれば、人から咎められることは少なくなる。
人から聞いた情報を全て鵜呑みにしてはいけません。
中には嘘も紛れているので、「あいつの言うことは適当すぎる」と言われるかもしれません。
きちんと情報を吟味しましょう。
朝(あした)に道を聞きては、夕べに死すとも可なり。
<訳>朝正しく生きる道がわかったら、その日の晩に死んでもいい。
これは学ぶ覚悟について語った孔子の名言です。
これぐらいの覚悟があれば、学ぶスピードも速くなるでしょう。
これを知る者はこれを好む者に如(し)かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。
<訳>学ぶことにおいて、知っているだけでは好むには及ばない。また、学問を好む者は、学問を楽しむ者に及ばない。
この名言が言いたいのは『「楽しい!」と思えることをやるべきだ』ということです。
例えば、あなたは仕事を楽しいと思っているでしょうか?
もし思っていないのであれば、「仕事が楽しい!」と思っている人には逆立ちしても勝てないのです。
学は及ばざるが如くするも、猶(な)おこれを失わんことを恐る。
<訳>学問を常に追い求めるが、同時に学んだことを忘れていないか恐れなければいけない。
この名言に出てくる「恐れ」とは緊張感のことです。
毎日知識のインプットを行いながら高みを目指しますが、それと同時に知識が失われていないか確認することも必要だと孔子は語っています。
性、相い近し。習えば、相い遠し。
<訳>人は生まれた時、お互い似ていて大きな差はない。しかし、学ぶか学ばないかによって善にも悪にもなり、差が広がってしまう。
人間は学びの差によって大きな差ができてしまいます。
これは人生の真理なので、学びを疎かにしてはいけないと孔子は語っています。
吾れ十有五(じゅうゆうご)にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う。七十にして心の欲する所に従って、矩(のり)を踰えず。
<訳>私は十五歳で学問に志した。三十歳で独り立ちした。四十歳になって迷わなくなり、五十歳で天命を知った。六十歳で人の言葉が素直に聞けるようになり、七十歳でやりたいことを自由にやっても間違うことがなくなった。
これはとても有名な孔子の名言ですよね。
人生を年代別に区切り、その時どのような人間になっているべきかを指標として語ったのです。
人の生くるは直し。これを罔(し)いて生くるは、幸いにして免るるなり。
<訳>人が生きていくには、まっすぐであることが大切だ。この真っ直ぐさがなくても生きているならば、それはたまたま助かっているだけのこと。
人間の真っ直ぐさとは「誠実さ」のことだと思います。
正直で素直な様子を、孔子は「まっすぐ」と表現したのです。
道に志し、徳に拠り、仁に依り、藝(げい)に遊ぶ。
<訳>正しい道を志し、身につけたと徳をよりどころとし、私欲のない仁の心に沿って、教養を楽しみその幅を広げていく。
これは学問を修める意味について孔子が語った言葉です。
学問の楽しみ方や活用方法まで教えてくれる名言だと思います。