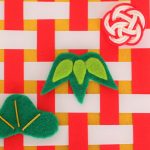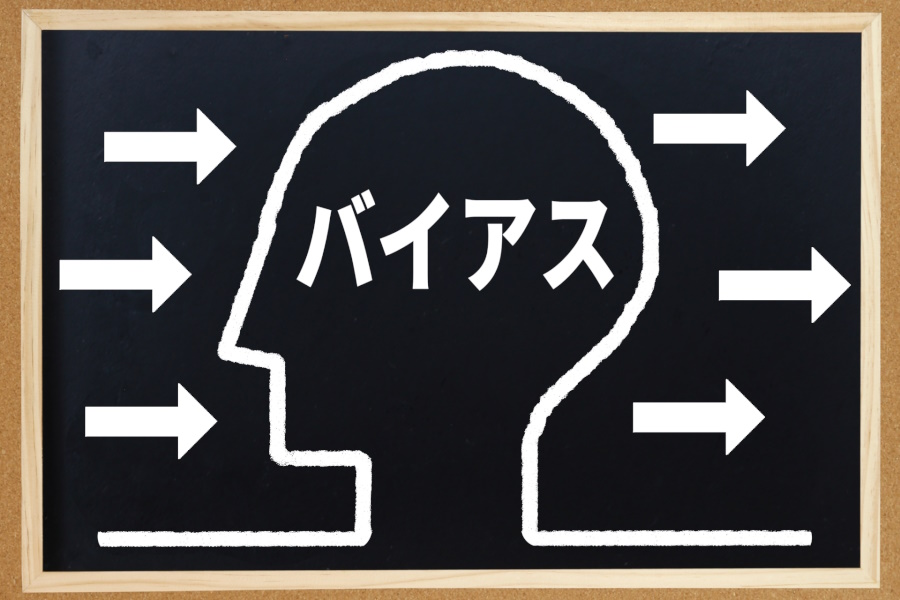
「認知バイアス」という言葉をご存知でしょうか?
これを上手に活用すると「ビジネスが伸びる」と言われているので、ビジネスパーソンであれば知っておくべき基礎知識だと思います。
そこで今回は「認知バイアス」について解説していきたいと思います。
認知バイアスの種類についても触れていくので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
認知バイアスとは?
認知バイアスは「確証バイアス」と呼ばれることもありますが、「人間に本来備わっている機能」と言った方が良いかもしれません。
一般的に「バイアス(bias)」とは、折り目に対して斜めに切った布の切れ端のことなので、そこから派生して「かさ上げする」「偏りがある」「歪んでいる」という状態を指す言葉になりました。
つまり「バイアスがかかっている」という言い方は、「偏った見方をしている」という場面に使われているのです。
なぜそのようになってしまうのかというと、人間には「先入観」があるので、それがバイアスになっていると言われます。
例えば、タトゥーだらけの見た目で、ガラの悪い服装をしている男性がいた場合、初めて見た人は「なんか怖そうな人だな…」という印象を抱きますよね。
これがまさに”先入観”です。
しかし実際に話してみたらとても丁寧な口調で、しっかりしたマナーの人だった場合、逆にその人がとても真面目な人に思えてきます。
しかしよく考えてもらうと「とても丁寧な口調で、しっかりしたマナーで接する」というのは当たり前のことなので、決して特別なことではないのに気づくはずです。
このように認知バイアスを活用することで、自分自身の株(価値)をアップさせることも簡単なのです。

認知バイアスの種類一覧
認知バイアスについて理解できたところで、次は「認知バイアスの種類」をご紹介していきます。
知っておいて損しない知識なので、ここで押さえておきましょう!
1:確実性効果
確実性効果とは、確実な選択、つまりハズレがない選択肢や状況を好むことを指します。
例えば以下のような質問をした場合、どちらが多く選ばれるでしょうか?
- 確実に1万円がもらえる
- 20%の確率で10万円がもらえる(ハズレは0円)
このような質問をした場合、ほとんどの人は「確実に1万円がもらえる」ほうを選びますが、これは「確実性効果」が発揮されているからです。
これだとピンとこないかもしれませんが、もう少し極端な例を出してみたいと思います。
- 確実に1万円がもらえる
- 99%の確率で100万円もらえるが、ハズレた場合は死ぬ
2番目にある「99%の確率」というのは、「ほぼ100%」ですよね。
「100本あるくじ引きの中から、1本のアタリを引く自信がありますか?」
このように聞かれると、ほとんどの人が「No」と答えるはずです。
これと全く同じなので、99%の確率というのは「かなりの高確率」であることが理解できます。
それにも関わらず、ほとんどの人は「確実に1万円がもらえる」ほうを選ぶそうです。
このことから理解できるのは、「100%確実というのは特殊である」ということです。
世の中には「元本保証」という言葉がありますが、それは「100%確実」を保証していることになります。
リスクがあるからリターンを得られるというのは当たり前の話ですよね。
このような特殊な状況(=100%確実)を”当たり前”のように信じている人はまだまだ多いみたいですが、個人的にはそれを信じること自体がナンセンスだと思います。
2:アンカリング効果
アンカリングとは、船の錨(アンカー)が由来となった言葉です。
本質的ではない、もしくは無意味な情報に判断が左右されてしまう心理効果のことを「アンカリング効果」と呼んでいますが、それだけではピンときませんよね。
例えば、身近にある”新聞紙”で例を出したいと思います。
新聞紙1枚の厚みは0.1mmだと言われていますが、この新聞紙を25回折ると富士山と同じ高さ(約3776m)になるのをご存知でしょうか。
実際に計算してみると「0.1×2×2×2×2×2…」と25乗していくと、その数字は3355mになるので、ほぼ富士山と同じ高さになるのが証明できるはずです。
実は新聞紙を42回折ると、その厚さは月まで到達する(38万km)のですが、暑さ0.1mmの新聞紙が月まで到達するなんて、なんだか実感が湧きませんよね。
もちろんこれは理論上の話なので、実際に新聞紙をそれだけ折ることはできないのですが、そもそも「新聞紙は薄い」というバイアスがかかっていると、この話を信じられないはずです。
これはまさに「新聞紙は薄い」というアンカリング効果が発揮されている状態なので、認知バイアスにかかっている状態なのだと思います。
3:サンクコスト効果
これは「サンクコストの誤謬」と呼ばれたり、省略して「サンクコスト」と呼ばれることもあります。
サンクコストは「埋没費用」という意味なのですが、サンクコスト効果とは「一度支払って戻ってこない費用に固執するあまり、合理的な判断ができない」ことを指しています。
例えばプロスポーツ選手を目指して、小学生の頃から毎日誰よりも頑張っていたとします。
そうするとなかなかプロになる夢が諦められず、ズルズルと続けてしまうはずです。
これは「過去に費やした意思決定や時間、費用が全て無駄になってしまう」と考えてしまうので起こる現象だと言われています。
もし合理的な判断ができるのであれば「過去は変えられないが、未来は変えられる」とわかるはずなので、「サンクコストを判断材料に加えるべきではない」というのが正解となります。
それは理解できるのですが、実際にはそのような判断が下せないのが人間の性です。
これを上手にビジネス活用しているのがIT業界だと言われています。
「無料トライアル」という名目でwebツールを提供し、そこに情報蓄積させることで、サンクコスト効果を発生させて解約しづらくしているのです。
もちろん便利だから使っているという側面もありますが、それに加えてサンクコスト効果が働けば、さらに解約率は下がるはずです。
このように考えると、認知バイアスは使い方次第でビジネスに活かせるというのが分かりますよね。

4:ピア効果
ピア効果は「同僚効果」と呼ばれることもあります。
その意味は、仲間や同僚の仕事ぶりやパフォーマンス(成果)が他の人に影響を与えるということです。
例えば進学校に通っている人であれば、周りの友達がみんな勉強しているので、「自分も勉強しなきゃ!」と頑張りますよね。
これは実体験からも言えますが、成績のいい学校や一流企業に就職すると、モチベーションの高い人ばかりが集まっているので、ピア効果が発揮されて自分のポテンシャルも最大化できるのです。
他にも、他人から見られることでピア効果は発揮されます。
社会人であれば誰もが経験するはずですが、上司から注目されていると感じた場合、なんとなくプレッシャーを感じて一生懸命に仕事しますよね。
これは「有能な人に見られている」というプレッシャーが努力水準を引き上げたと考えられるので、ピア効果の一種となります。
会社組織にもピア効果は応用できるので、努力する人が多い組織は伸びて、ダラダラしている人が多い組織は衰退することになります。
採用担当者の人は、自分がピア効果を発揮させるスイッチを握っているのだと自覚しましょう。
5:社会規範
無能なマネジャーは、「インセンティブを設定すれば営業マンはもっと売ってくれる」と考えます。
しかしこれは大きな間違いです。
認知バイアスの観点から言えば、インセンティブを設定したからと言って、営業マンの行動は変わりません。
それよりも大事なのは「周りからの反応」です。
例えば「お客様が喜んでくれる」とか「同僚が頑張っている」といった、周りの行動に影響されてしまうのが人間なのです。
「共感を集める」ことが、人を動かす上で最も重要だと理解しておきましょう!

6:フレーミング効果
フレーミング効果は、トップセールスやマーケターとして活躍するために、「必ず身につけておくべき知識」として知られています。
その内容は「同じ情報や内容であっても、設定次第で意思決定に影響を与えることができる」というものです。
例えばあなたの給料(手取り)が月30万円だった場合、その3割を貯金に回すとしましょう。
給料の3割を貯金するのは大変ですが、どちらの言われ方だったら実現できそうでしょうか?
- 給料の3割を貯金しなさい。
- 給料の7割で生活しなさい。
これは両方とも同じことを意味しているのですが、受け取り手の印象は全く違うと思います。
全く同じ事象であったとしても、伝え方や見せ方で180度逆の印象操作ができるということです。
その他にも、例えば営業する時、どちらの方が好印象に感じるでしょうか?
- 当社のサービスは業界No.1ですが、価格が高いです。
- 当社のサービスは価格が高いですが、業界No.1です。
これも同じことを伝えているのですがメリットとデメリットを「どの順番で伝えるか?」によって、相手の受け取る印象は180度変わってきます。
この知識はセールスやマーケティングに使えるので覚えておきましょう!

7:極端性の回避
突然ですが「松竹梅の理論」をご存知でしょうか?
まさにこれが極端性の回避になります。
うなぎ屋へ行くと「松、竹、梅」というメニューが並んでいますよね。
この3つの選択肢を提示されると、ほとんどの人は真ん中の「竹」を選ぶそうです。
このような行動をとる理由とは、人間には「極端なものを選んで後悔したくない」という気持ちがあるせいです。
とは言っても、何でもかんでも真ん中が選ばれるという話ではありません。
真ん中が選ばれる理由はいくつかありますが、大きく「損失回避」と「相対性」に分けられます。
損失回避は「極端なものを選んで後悔したくない」という心理的な話ですが、相対性というのは価値の話です。
例えば飲み物を買う場合、コーラとオレンジジュースがあったとします。
その値段がコーラS:100円、M:150円、L:200円だったのに対して、オレンジジュースはS:50円、M:80円、L:110円となっていた場合、オレンジジュースが飲みたい人はLを選ぶかもしれません。
なぜかといえば、相対的にコーラより割安感が出ているので、それであれば「Lサイズにしよう!」と考える人が増えるからです。
このようにメニューをコントロールすることで、実は一番売れる(注文されやすい)商品を作為的に作ることもできるのです。
もしその商品が一番粗利率の良い製品・サービスだった場合、企業としてはウハウハですよね。
このように顧客をコントロールしているビジネスモデルが「優秀な仕組み」と呼ばれているのです。
8:選択肢過剰
消費者としては、選択肢が多いことに越したことはないですよね。
しかし実際には「選択肢が多いほど良い」というわけではありません。
人間は選択肢が豊富であればあるほど選ぶことができなくなってしまうので、多すぎる選択肢がネガティブな効果を生み出してしまうのです。
このことを「選択肢過剰」と呼んでいます。
例えばコンビニでお茶を買う時、50種類のお茶が並んでいたら、どう感じるでしょうか?
おそらくほとんどの人が「多すぎる」とか「選ぶのがめんどくさい」と感じることでしょう。
50種類のお茶を目の前にしてワクワクする人はきっと少ないと思います。
他にも、イタリア料理店へ食べに行くとたくさんのワインがメニューに載っていますが、どれを注文しようか迷った経験がある人は多いはずです。
ワインに詳しい人であれば別ですが、ワインに詳しくない人からすると、多すぎる選択肢は逆に混乱を招いてしまうのです。
これはバイアスがかかっている状態なので、顧客満足度が下がるだけでなく、顧客単価まで下げてしまいます。
これはあくまでも個人的な意見ですが、ワイン通の人が通わない一般的なお店なのであれば、ボトルワインは「赤と白」の2種類に絞って、それぞれ松竹梅と3種類を用意して、「2種類×3種類=6種類」のワインメニューにするのがいいと思います。
これ以上多くなってしまうと、逆にワインの注文数は減るはずなので、店舗ビジネスをしている人は注意しましょう。
9:ピークエンドの法則
多くの人にとって、スマートフォンの不具合はストレスですよね。
日常生活に欠かせないスマホが故障した場合、携帯ショップなどに持ち込むかもしれませんが、そこでは長時間待たされたり、やたら難しい説明をされたりすると思います。
手続きもちんぷんかんぷんで、何かよくわからない登録パスワードを要求されたり、身に覚えのないIDを聞かれたりもしますよね。
これらは非常に大きなストレスとなりますが、結果的にスマートフォンの不具合が解消されると、その怒りは全て収まってしまうのです。
このことから理解できることは、「最後をいかに快適に過ごせたか?」が重要なのだと分かります。
このような現象を「ピークエンドの法則」と呼んでいます。
例えば、真冬に寒い廊下を歩いて、快適な温泉に浸かり、また寒い廊下を歩かせるのはピークエンドの法則に従うと顧客満足感を下げる行為です。
東京にある某人気テーマパークでは、入場時に30分~1時間ほど並んで待たされるのでストレス一杯ですが、帰りはスムーズに帰れるので、「また今度来よう!」と思えます。
このようにピークエンドの法則を理解しておけば、正しい接客方法が導き出せるはずです。
ホテルや旅館、観光地、飲食店など、ピークエンドの法則は様々な場面で活かせる為、ここで押さえておきましょう!
10:ハウスマネー効果
ハウスマネー効果とは、不労所得や臨時収入のようなお金を突然手にした場合、人間は大胆な使い方をしてしまうことを指します。
例えば競馬で10万円勝った場合、いつもより高い食事をしたり、ブランド物を買ってしまうことがハウスマネー効果です。
つまりあぶく銭は、自分で稼いだ収入と比べて支出されやすいということになります。
これは遺産相続も同じなので、ハウスマネー効果を知っていれば、大金持ちが子供に遺産を残さない理由もなんとなく理解できるはずです。
そもそもこの心理効果が発揮される原因とは、自分で稼いだお金を失うのは心理的な辛さがありますが、思いがけず手に入れた収入は失う辛さを感じづらいからだと言われています。
この心理効果をうまく活用しているのが、楽天ポイントのような仕組みです。
消費者が購入した分だけポイント還元すれば、それは臨時収入となるので、結果的に消費が活性化するのです。
会員向けビジネスをしている人はハウスマネー効果を覚えておきましょう!

11:デフォルト効果
美容室へ行った時、待合室の中に雑誌が置いてあったとします。
それをなんとなく読む人は多いと思いますが、果たしてその本が置いていなかったら、店員に声をかけて本を持ってきてもらうでしょうか?
おそらくほとんどの人がスマホを見たり、おとなしく待っているなど、別の行動をしているはずです。
このように初期状態によって人の行動が左右されることを「デフォルト効果」と呼んでいます。
これは”現状維持バイアス”がかかっている状態なのですが、最も有名なデフォルト効果だと言われているのは、臓器提供の事例です。
現状維持バイアスとは、現在の状況より好転すると分かっていても、変化を避け現状維持を選ぶことを指します。
ほとんどの人は気づいていないはずですが、日本で発行されている運転免許証の裏側を見ると「臓器提供に関する項目」が並んでいます。
日本の臓器提供意思表示カードは任意になっているので、「臓器提供したい場合にはチェックする」というやり方を取っていますが、ヨーロッパはその逆で「臓器提供したくない場合にはチェックする」というやり方を採用しています。
なのでヨーロッパ各国の臓器提供希望者は90%を超えており、日本と比べて雲泥の差が出ているのです。
同じ施策なのにもかかわらず、デフォルト効果を使うと「結果が真逆になる」というのは面白い現象ですよね。
12:大数の法則&少数の法則
ルーレットを回して黒に入る確率と、赤に入る確率は五分五分ですよね。
しかし10回しかルーレットを回さなければ、「黒7回、赤3回」という偏った結果になるかもしれません。
このような結果から「黒の方が出やすい」と誤った判断をしてしまうのが少数の法則と呼ばれています。
しかし統計的には回数を重ねるごと平均へと近づいていくので、ルーレットを100回、1000回、1万回も回せば、確率は五分五分へと近づいていくはずです。
この法則のことを「大数の法則」と呼んでいます。
これをビジネスに活用しているのが「顧客満足度80%」のような宣伝文句です。
よく見てもらうと、隅の方に小さく「××人にアンケートを実施しました」と書かれているので、もしその数が10人だった場合、そのうち8人が「満足した」と答えれば 顧客満足度は80%になってしまうのです。
これは上手く「少数の法則」を活用した事例ですよね。
消費者を陥れる代表的な認知バイアスなので注意が必要ですが、その反面マーケティング担当者としては便利なバイアスなので覚えておきましょう。
まとめ
ここまで認知バイアスについて解説してきました。
このような心理効果はビジネスパーソンが知っておくべき知識だと思うので、下の記事も併せてご覧ください。