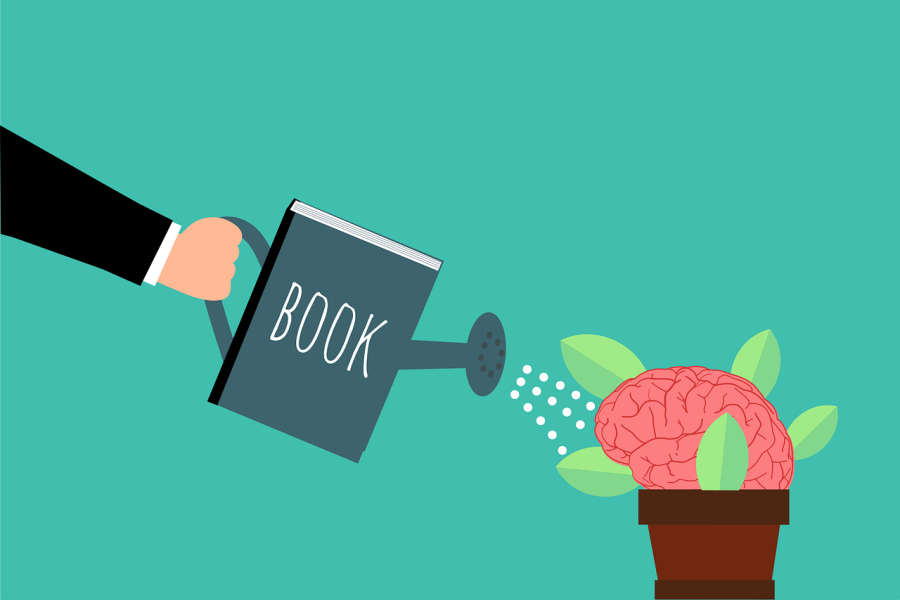
生活していると、地頭のいい人に出くわすことがあります。
地頭がいい人というのは、何が凄いのか説明するのは難しいですが、明らかに人と違うのです。
そこで今回は、地頭の良さというテーマにフォーカスして解説していきたいと思います。
>>新規開拓の可能性を追求する|side bizz(サイドビズ)
「地頭がいい」の意味とは?
世の中には「地頭がいい」と言われる人がいます。
この言葉が使われる場面とは、以下のような人に出くわした時だと思います。
- 難題をすぐに解決する人
- 考え方が柔軟な人
- 頭の回転が速い人
このような人に出くわした時、人々は「あの人は地頭がいい」と評価するのです。
しかし、地頭が良いという評価を与えるためには、もう一つ重要な要素があります。
それは決して学歴が高くないことです。
もちろん学歴が高くて地頭も良い人はたくさんいますが、むしろそれは当たり前のことなので、どちらかと言うと高学歴の人は「頭がいい」とか「賢い」と評価されているはずです。
なので、「地頭がいい」と評価する場合には、ある枕詞がついているのです。
つまりそれは「あの人は学歴がないけど…」という枕詞で、それが付いた上で「地頭がいい」と評価されているのです。
これは一見するとネガティブに聞こえるかもしれませんが、実はそうでもありません。
いい学歴を持っているという人は、お金や運に恵まれてるはずです。
例えば海外留学するのにはたくさんの資金が必要ですし、有名私立大学に通うためには400万円ほどの学費がかかります。
東京大学などの名門校に入るためには、予備校に通ったり、たくさん参考書を購入しなければいけません。
つまりそれだけの資金力がなければ、一般的には高学歴を得ることができないのです。
なので、そのような裕福な家庭に生まれた人はラッキーだと思います。
もしそのような家庭環境に恵まれなかった場合、奨学金を申請すると思いますが、家庭の事情で働かなければいけなかったり、受験勉強する時間がない人も世の中にはいるのです。
つまり、学歴があるということを現代人は当たり前のように感じていますが、決してそんなことはないのです。
世の中にはお金は運に恵まれない人がたくさんいますが、そのような人達でも地頭がいい人はたくさんいます。
このように、人に自慢できるような学歴はなくても、元々賢い人を「地頭がいい」と表現するのです。
「地頭がいい」と「頭がいい」の違い
先ほども少し触れましたが、「地頭がいい」ことと「頭がいい」ことは本質的に意味合いが違います。
地頭がいい人については先ほど解説しましたが、頭がいい人とは、単純に勉強ができる人のことを言います。
つまり、学歴が高い人のことを指すのです。
旧帝国大学を卒業していたり、海外の有名大学を卒業しているような人、大学院に進学して勉強しているような人などを、一般的に「頭がいい」と評価しています。
それでは、「地頭がいい人」と「頭がいい人」の違いとは何なのでしょうか?
先ほども解説しましたが「地頭がいい人」とは、原則的に学歴がない人を指すことが多い言葉です。
そのような前提に立った場合、この両者の違いとは「勉強のやり方を知っている or 勉強のやり方が分からない」ということだと思います。
ご存知の人は多いと思いますが、勉強には効果の出るやり方というのがあります。
つまり、やたらめったら正面突破しようとしても、勉強の場合は決して結果がついてこないのです。
例えば、「鳴くよウグイス平安京」という言葉があります。
これは794年に平安京へ遷都したことを指しますが、「794年に平安京遷都」と覚えるよりも「鳴くよウグイス平安京」と覚えたほうが記憶に定着しやすいですよね。
つまりはこういうことです。
これは社会科に限った例えですが、その他の教科でも全般的に勉強の仕方は存在しますし、記憶への定着のさせ方などにもコツがあります。
このような勉強のやり方を知っている人は、一般的に「頭がいい」と言われますが、勉強のやり方を知らない頭のいい人は「地頭がいい」と評価されることが多いのです。
地頭がいい人の特徴
地頭がいい人は、子供の頃から優秀な傾向があります。
まず特徴的なことは、人よりも想像力が豊かなことです。
物事を三次元で捉えることができ、それを人に説明することもできます。
そうすることで空間認識能力を高めて、脳の柔軟性を強化していくのです。
すると必然的に問題解決能力が高くなり、地頭の良さが発揮されていきます。
逆に「頭がいい」と言われる人の中には、地頭が悪い人が紛れているケースがあります。
このような人は学業に長けているのですが、何かを創造したり、問題解決することを苦手としています。
つまり、ゼロイチが苦手なのです。
このような人が活躍できる場所は、国家公務員や公益法人、大企業のサラリーマンなどでしょう。
既にある仕組みを動かすのを得意としていたり、作業を完璧にこなすことが得意なので、上記のような職業であれば順調に出世できるはずです。
それと比べて、地頭がいい人は起業家に向いていると思います。
独立起業すると、毎日のように問題に直面しますが、それを乗り越えなければ会社が潰れてしまいます。
なので、全ての経営資源を踏まえた上で、常に最適解を導き出すのですが、それが正しいという前例がないので暗中模索する状態になります。
さらに、その問題を解決するためには、相当ハードな行動力を求められるため、人一倍のタフさが求められます。
地頭がいい人は賢い
地頭がいい人の特徴とは、単純に賢いことです。
「賢い」という言葉は抽象的ですが、もう少し具体的に説明すると「理解力が高い」という意味だと思います。
つまり、どんなに難しい話題だったとしても、頭を柔軟にして考えることで、その内容を理解してしまうのです。
その結果、問題点にすぐ気付いたり、それを指摘できるようにもなります。
このような社員はどの企業も欲しがるような優秀な人材だと思います。
なぜかというと、賢い人は新規ビジネスの立ち上げができるからです。
ビジネスモデルを構築するためには、全ての問題点を探り当て、それを一つ一つ潰していかなければいけません。
つまり抜けがないようなビジネスモデルを設計しなければいけないのです。
これは経験や勘によるところが多い作業ですが、実務的には問題点を解決する作業なのです。
勉強すれば地頭は良くなるの?
地頭を良くしたい場合、一体どうすればいいのでしょうか?
地頭は勉強すれば良くなると言われることもありますが、基本的には「天然の頭の良さ」なので、勉学で地頭をよくすることは難しいと思います。
おすすめの鍛え方というのは、ビジネス書をたくさん読むことです。
地頭の良さとは「賢さ」を意味しますが、その賢さを形成する要素は知識と経験です。
つまりたくさんの知識を吸収して、それをアウトプットすることで、多くの失敗も経験するはずです。
そのような失敗(シチュエーション)を経験すればするほど、最適解を導き出す能力が高まっていくのです。
なので、自分自身でそれを一つずつ実践するのも良いですが、それでは時間が掛かりすぎるので、成功者と言われる人たちのノウハウをインプットする作業も同時並行した方が良いと思います。
そして、とにかく多くのシチュエーションを経験して、それに対応できるだけのスキルを身につけましょう。
書籍を出すような人たちは、数多くの失敗を経験しており、その経験をもとに成功法を導き出しています。
それらをまとめたものが書籍なので、それを読むことで時間短縮しながら地頭を鍛えることができるはずです。
つまり「地頭の良さ」とは、決して勉強に限った話ではなくて、状況対応能力も含まれた言葉なのです。
ここではおすすめの本をご紹介しておくので、まずはこのあたりから読んでみてください。




地頭の良さは仕事にも活かせる
地頭がいいことは、きっとあなたの仕事にも役立ちます。
新しいビジネスモデルを上司に提案したり、お客様に対してプレゼンする営業職でも役立つはずです。
もしあなたが「それほど地頭は良くない」と自覚しているのであれば、地頭の良い同期や部下を巻き込んでしまいましょう。
地頭がいい人がまとまると、そのチームは本当に強くなります。
地頭がいい人だって何かしら苦手分野があります。
例えば資料作成が苦手だったり、お客様とのコミュニケーションが苦手だということもあるでしょう。
もしそのようなスキルをあなたが持っているのであれば、お互い補完関係になるので、きっと良いチームになれるはずです。
大きな仕事は一人で成し遂げることができません。
出来る限り地頭のいい人を探して、そのような人と一緒に仕事するようにしましょう。






























