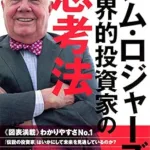海外サッカーには「名監督」と呼ばれる人が大勢います。
やる気を引き出すリーダーの言葉はきっと参考になるはずなので、今回は海外サッカー監督の名言集をご紹介したいと思います。
目次
ジョゼ・モウリーニョ監督の名言
二位という結果は特筆するに値しない。
<ジョゼ・モウリーニョ>
ジョゼ・モウリーニョ監督は世界で最も注目されている名将の一人ですが、なんとなくチェルシーの監督というイメージが強いですよね。
モウリーニョ監督はポルトガル出身のサッカー選手でしたが、15歳の頃には選手としての限界を感じて、首都リスボンの体育大学に進学しました。
そして2002年1月にチャンピオンズリーグでの優勝経験もある名門クラブ「ポルト」の監督に就任したのです。
その就任会見でモウリーニョ監督は「来年は優勝してみせる」と宣言したのです。
その結果、2002~03年シーズンに国内リーグ、国内カップ、UEFAカップの三冠を達成しました。
そして翌年の2003~04年シーズンでは、国内リーグ優勝、チャンピオンズリーグ優勝という栄冠を手にしたのです。
徹底して優勝(1位)にこだわった結果、世界中に「ジョゼ・モウリーニョ」という監督の名前が知れ渡りました。
そして2004年6月に、プレミアリーグのチェルシーへ世界最高クラスの年俸の監督として移籍することになったのです。
戦術自体が問われる時代は終わった。
戦術を実現するためのトレーニングで監督の差がつくんだ。
<ジョゼ・モウリーニョ>
モウリーニョ監督は試合の結果だけで判断するのではなく、とにかく練習を重視します。
その中でも規律を守らない選手を徹底的に排除することは有名で、どんなに優れた一流プレイヤーであっても、練習に遅刻をした時点でチームから追放してしまうのです。
それだけ厳しい要求をするからこそ、選手たちの中に緊張感が生まれるのです。
不安やプレッシャーを口にすべきではないんだ。
絶対にね。
<ジョゼ・モウリーニョ>
プロサッカー選手というのは、結果が全てです。
もちろんそれは監督も同じで、チェルシーのような強豪チームにいれば、必然的に勝つことを求められます。
そのようなプレッシャーは強烈ですが「監督の不安は選手に伝染する」と言って、決して不安を口にしなかったそうです。
単に「試合に勝つ」のではなく「勝つべき試合で必ず勝つ」。
<ジョゼ・モウリーニョ>
ポルト、チェルシー、インテル・ミラノなどで輝かしい実績を出したモウリーニョ監督ですが、それを実現するために勝つことへ執着したそうです。
しかし、長いシーズンを戦い抜くためには、きちんとした戦略が必要です。
モウリーニョ監督は「幸運なことに、監督になってからずっと、私はマッチポイントを落としたことがない」と語っています。
自分で描いた戦略通りに「勝つべき試合で必ず勝つ」を実現していけば、必然的に勝利をたぐり寄せられるそうです。
経験。
これを重ねる以外に、サッカーにおけるインテリジェンスの体得はない。
<ジョゼ・モウリーニョ>
これはインテル・ミラノの監督時代に言った名言です。
リーガエスパニョーラやプレミアリーグでは、強力なチームは2~3しかありませんが、セリエAでは全てのチーム力が拮抗していたのです。
なので、これまでの経験をフル活用して、セリエAで優勝するためのチーム作りをしたと語っています。
その結果リーグ優勝を手にするのですが、それを実現するためには「これまで体験した自分の経験値」が必要不可欠だったと言ったのです。
自分が世界一の監督だとは思わない。
しかし、私以上の監督がいるとも思わない。
<ジョゼ・モウリーニョ>
モウリーニョ監督は強気な発言でも有名です。
その根拠となっているのは、絶対的な自信です。
そのようなリーダーは頼もしいので、選手からも信頼されることでしょう。
選手たちを批判したいなら、まず私を殺してからにしてほしい。
<ジョゼ・モウリーニョ>
モウリーニョ監督は、絶対にメディアを通して選手を批判しません。
試合後のインタビューでも、選手を批判することはありません。
もし何か言いたいことがあれば、マスコミを通してではなく直接伝えるスタンスを貫いているようです。
「選手たちが守られ、落ち着いた気持ちを保てることが一番重要である」という考え方のもと、そのような行動になっているそうです。
我々の仕事は次のために最善の準備をすることだ。
<ジョゼ・モウリーニョ>
サッカーは試合なので、当然負けることもあります。
そこから反省することもありますが、引きずることは一切ないそうです。
モウリーニョ監督は「私は特定の試合を思い出して満足感に浸るような真似はしない。いつも次の勝利、次のトロフィーを取るためだけに働き続けてきた。監督を務める喜びとは、思い出に浸ることではなく、常に勝利を重ねていくことにある。」と語っています。
アレックス・ファーガソン監督の名言
全力を出さずに、控室に戻ってこようなどと思うな。
<アレックス・ファーガソン>
これはチャンピオンズリーグ決勝で、ファーガソン監督が選手に檄を飛ばした時の言葉です。
アレックス・ファーガソンは1986年にプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッド(マンU)の監督に就任しました。
マンチェスター・ユナイテッドは古豪ですが、当時は長い不振に苦しんでいたそうです。
しかしファーガソン監督に代わってから、
- プレミアリーグ優勝
- FAカップ優勝
- UEFAチャンピオンズリーグ優勝
など輝かしい実績を残したのです。
練習は常に完璧なプレイを約束するものではないが、より良いプレーを約束することは間違いない。
<アレックス・ファーガソン>
選手から不満が出たとしても、何度も繰り返し練習をさせるべきだとファーガソン監督は語っています。
マンチェスター・ユナイテッドで活躍したデイヴィッド・ベッカムにはフリーキックの名手ですが、それは一夜にして身に付いたわけではありません。
人一倍フリーキックの練習をしたからこそ、あれほど偉大なサッカー選手になれたのです。
気づかぬフリをするくらいなら、監督などやるべきではない。
<アレックス・ファーガソン>
ファーガソン監督は、人一倍飲酒をする選手が嫌いでした。
プロサッカー選手がシーズン中に飲酒をすることは、パフォーマンスの低下につながると考えていたのです。
なので徹底的に飲酒撲滅施策を実施して、それに従わない選手は無慈悲に放出してチームの強化に努めました。
パっと燃え尽きてしまうような成果では満足できない。
<アレックス・ファーガソン>
アレックス・ファーガソン監督は「名将」と称えられています。
そのように言われる所以は、長い間勝ち続けているからです。
まぐれで優勝することはありますが、そのようなチームをファーガソン監督は目指していません。
いつでも優勝を狙えるチームを作ることが目的なのです。
今日のために戦い、明日のために考える。
<アレックス・ファーガソン>
ファーガソン監督は現実主義者なので、あまり先のことまで考えていません。
地道に着実に一試合ずつ勝利を重ねていくのです。
バスに乗り遅れるな。
<アレックス・ファーガソン>
ファーガソン監督の言う「バス」とはマンチェスター・ユナイテッドのことです。
マンチェスター・ユナイテッドは常に進化しているので、練習を怠ったり、サッカーに集中していない選手は、すぐにチームから外されてしまいます。
ファーガソン監督は「成功したいなら絶対に途中下車してはいけない。脇目も振らずに精進するべきだ。」と語っています。
ジョゼップ・グアルディオラ監督の名言
道は険しいだろう。
でもこの挑戦、僕はクリア出来ると感じている。
そうでなかったら、今ここにはいない。
<ジョゼップ・グアルディオラ>
これはグアルディオラがスペインの名門クラブ「バルセロナの監督」に就任した時の名言です。
ジョゼップ・グアルディオラはバルセロナのカンテラ出身で、現役時代は「バルサの四番」と呼ばれて司令塔で活躍しました。
1992年に開催されたバルセロナオリンピックでは、サッカースペイン代表キャプテンとして金メダルの獲得にも貢献します。
それだけの実績を挙げつつ、古巣であるバルセロナの監督に就任するのは相当プレッシャーだったと思います。
それでも1年目にはリーガエスパニョーラ、チャンピオンズリーグ、国王杯に優勝して3冠を獲得、2年目には前人未到の6冠を達成したのです。
勝利の後にも、変化は必要だ。
<ジョゼップ・グアルディオラ>
一般的な考え方で言えば、結果を残したチームメンバーでその後も続けた方がリスクが少ないと思うでしょう。
しかしグルディオラ監督は、それまで活躍していた主力メンバー(ロナウジーニョ、エトー、デコなど)だったとしても、容赦なく放出したのです。
それには周囲も驚きましたが、自分の考える常勝チームを作るために必要だと考えて、断固実行したのです。
私のサッカー哲学にシークレットはない。
必要なのは、才能ある選手と日々のハードトレーニングだけだ。
<ジョゼップ・グアルディオラ>
バルセロナには一流選手がいますが、それでも練習を怠れば、簡単に負けてしまうと危機感を抱いていました。
グアルディオラに特別なノウハウなどなく、チームの規律を守りながら、ただきちんと毎日練習をすることが勝利の秘訣だと語っています。
我々は、今日よりもずっと良いサッカーができる。
できるというより、しなければならない。
<ジョゼップ・グアルディオラ>
グアルディオラ監督がこのように言うのには理由があります。
それは「どんな選手でもさらに成長できる」という理想を持っているからです。
世界最高プレーヤーと言われていたバルセロナの主力メンバー「リオネル・メッシ」でさえも、更なる高みが目指せると考えていたのです。
お金よりもバルサでプレーすることに価値がある。
<ジョゼップ・グアルディオラ>
グアルディオラはバルセロナのカンテラ(下部組織)出身のプレイヤーです。
なので、バルセロナの良い部分をたくさん知っています。
グアルディオラは「憧れの的であるチームでプレーする喜びと誇りを選手に持ってもらいたい」と語っています。
世界が君たちのサッカーを見ているんだ。
<ジョゼップ・グアルディオラ>
この言葉は、マンチェスター・ユナイテッドと戦ったUEFAチャンピオンズリーグ決勝直前にバルセロナの選手達へ伝えた名言です。
バルセロナ出身の名監督からこんな言葉を言われたら、選手のモチベーションは爆上げですよね。
負けた試合にポジティブなものはない。
<ジョゼップ・グアルディオラ>
プロスポーツ選手なので、絶対に勝つことを求められます。
とにかく勝ちにこだわる必要があるので、それをチーム全体に浸透させたのです。
フース・ヒディンク監督の名言
一旦ボールが転がりだしたら、監督にできることは3度の選手交代しかない。
<フース・ヒディンク>
フース・ヒディンク監督は、オランダ、韓国、オーストリア、ロシア、トルコなどの代表監督を経験しています。
日韓ワールドカップの時には韓国代表の監督をしていたので、フース・ヒディンクという名前は聞いたことがありますよね。
試合中にサッカーの監督ができることは少ないので、試合前の万全の準備が重要だと語っています。
まずやらなければいけないのは、その国がなぜそういうサッカーをするのか、本質的なルーツを知ることだ。
<フース・ヒディンク>
いくつもの国の代表監督を務めたヒディンクらしい名言ですよね。
その国の精神を理解しなければ、勝つための戦略が決まらないと語っています。
お前たちの意思で監督が変わった今、お前たちが何かを見せる時じゃないのか。
<フース・ヒディンク>
これはオランダのクラブチーム「PSVアイントホーフェン」の監督だった頃の名言です。
PSVはオランダの古豪ですが、なかなか成績が上がらず、監督が解任されてしまったのです。
その時、PSVのコーチをしていたヒディンクが、たまたま繰り上げで監督に指名されたのです。
クラブチームとしては一時しのぎの監督指名でしたが、フース・ヒディンクはそれをチャンスと捉えました。
そして選手たちに「前監督はお前達が結果を出さないから解任された。つまりお前達の意思で解任したんだ!監督がダメだから実力が発揮できなかったと言うなら、本当の実力を見せてみろ!」と言ってチームを鼓舞したのです。
その結果低迷していたチームはオランダリーグ3連覇、そしてチャンピオンズカップ優勝まで果たしたのです。
気難しい選手を引き抜かなければ、チームの運営には何ら問題ない。
だが成功もない。
<フース・ヒディンク>
一流選手の中には、なかなか言うことを聞かなかったり、扱いの難しい選手が一定数存在します。
そのような選手を見限ってしまう監督も多いですが、フース・ヒディンクは「気難しい選手を引っ張っていくのが監督である」と言って、うまく扱ったのです。
たった一度の成功のためにどれだけ多くのチャレンジをしているのかが、サッカーでは重要なのである。
<フース・ヒディンク>
サッカーは、大量得点が入るスポーツではありません。
しかし、失敗するのを恐れていては、得点を入れることなどできないのです。
相手に劣等感を感じれば、消極的になる。
消極的になれば、戦術的に失敗してしまうだけだ。
<フース・ヒディンク>
戦う前から負けを意識すると、体が硬くなります。
失敗も多くなります。
昭和の時代に活躍したプロレスラー”アントニオ猪木”は、「出る前に負けることを考えるバカがいるかよ。」という名言を残しています。
このようなポジティブな名言を探している人は下の記事もご覧ください。
楽しむプレイをすればいいサッカーができる。
だから、サッカーを楽しめ。
<フース・ヒディンク>
勝ちにこだわる”サッカー監督”らしくない名言ですよね。
しかし選手のメンタルが沈んでいたり、モチベーションが上がらない場合には、このような言葉を投げかけるのもリーダーの務めだと思います。
アーセン・ベンゲル監督の名言
一度勝利の味を覚えさえすれば、クラブには勝者のメンタリティや哲学が芽生える。
<アーセン・ベンゲル>
アーセン・ヴェンゲル監督は、日本の名古屋グランパスで監督をしていたので、知っている人は多いですよね。
名古屋グランパスエイトでは、監督に就任した1年目に天皇杯を制するという偉業を成し遂げています。
その翌年にはイングランドプレミアリーグの名門クラブ「アーセナル」の監督に就任します。
常勝軍団を作るためには「勝利を味合わせなければいけない」と、ベンゲル監督は語っています。
スーパースターを買うのではなく、育てる。
<アーセン・ベンゲル>
ベンゲル監督のやり方は、若手有望株を安く買って、その選手をじっくり育てるというやり方です。
この方がコストが安いのはもちろんですが、チームに馴染んだ選手が出来上がるのです。
個人が突出し、さらにその選手がカリスマ性を帯びてしまうと、その個人だけが注目されてしまうような状況が生まれるものだ。
<アーセン・ベンゲル>
あるスター選手だけに注目が集まってしまうと、その他の選手は陰(かげ)になってしまいます。
このようなチームは「一人だけに頼ったチーム」なので、非常に脆いとベンゲル監督は語っています。
そうではなく「多様性を持った攻撃力」こそが、アーセナルが目指すサッカーだと言うのです。
明確なビジョンを持った、リーダーらしい名言だと思います。
数値の高い選手はやがて大成していった。
<アーセン・ベンゲル>
ベンゲル監督は「知将」と呼ばれていますよね。
そのように呼ばれる理由は、様々なデータを活用するからです。
旧態依然のやり方にイノベーションを起こし、選手のパフォーマンスを全て数値化し、分析することがベンゲル監督のやり方です。
その結果を分析すると、数値が高い選手ほど、成長率も高かったのです。
この世界では才能さえも落とし穴となり得る。
<アーセン・ベンゲル>
ベンゲル監督は選手を見る場合、短所ではなく長所を見るようにしています。
しかし、周りの選手よりもズバ抜けているプレイヤーは、その長所が落とし穴になり得るのです。
なぜかといえば、自分のスキルやテクニックに溺れて、努力や練習を怠るようになるからです。
監督は常にイノベーター(改革者)でなければならない。
<アーセン・ベンゲル>
ある程度の結果を出すと、今度はその地位を守りたくなります。
しかしそれは「衰退」を意味するので、絶対に避けるべきだとベンゲル監督は語っています。
カルロ・アンチェロッティ監督の名言
極上のチーズを作るためには最低でも1年はかかる。
<カルロ・アンチェロッティ>
サッカーチームをチーズに例えるあたりは、イタリア人らしいですよね。
アンチェロッティ監督はパロマやローマ、ACミランで活躍したプロサッカー選手です。
イタリア代表としても選出されていたので、一流プレイヤーだったことには疑いありません。
長いサッカー人生において、「良いチームを作るためには時間がかかる」ということを理解しているのだと思います。
要求しても遂行できないとすれば、監督に残された選択肢は、「諦める」か「別の選手を起用する」かのどちらかだ。
<カルロ・アンチェロッティ>
素晴らしい理想を掲げたとしても、それを実行できる選手がいなければ絵に描いた餅です。
アンチェロッティ監督はチーム戦術の決め方について以下のように語っています。
「どんな戦術を選ぶか決める最大のファクターは、チームにどんな選手がいるかである」
レギュラーメンバーはもちろんですが、控え選手の能力や特徴、性格まで細かく理解しておく必要があるのです。
我々にとって何よりも重要なのは「負けない」ということなのだ。
<カルロ・アンチェロッティ>
監督の仕事は「勝つか、負けるか」だけで判断されるとアンチェロッティは語っています。
特にイタリアサッカー界はチーム戦力が拮抗しているので、勝つことに大きな意義があるのです。
極限的なプレッシャーにさらされる試合でゴールを決めるために必要なのは、フィジカルコンディションではない。
<カルロ・アンチェロッティ>
フィジカル(身体)とメンタル(精神)という言葉があります。
サッカー選手はスポーツ選手なので、フィジカルが重視されると思われがちですが、大事な試合であればあるほどメンタルが重視されるそうです。
「メンタルが強いのはどの選手なのか?」というのは、監督の目利きになります。
日頃から選手とコミュニケーションを取り、相手のことを理解した監督だけが大きな大会で勝利を掴みとれるのです。
監督に迷いがあれば、選手は敏感にそれを察知する。
<カルロ・アンチェロッティ>
人間は迷う生き物ですが、リーダーと呼ばれる人たちが迷ってしまうと、チームメンバー全員に影響してきます。
リーダーの地位にいる人は、明確なビジョンを持って、強いリーダーシップを発揮しなければいけないのです。
選手にとっては、徐々に試合が単なるルーティーンにしか感じられなくなる。
<カルロ・アンチェロッティ>
これは「慣れ」に警鐘を鳴らす名言です。
アンチェロッティ監督はトッププレイヤーでもあったので、3日おきに90分の試合を戦い抜く難しさを知っています。
緊張感がなくなると「この試合を落としても後で取り返せる」という間違った認識になって、徐々に勝ちから遠ざかっていくのです。
そうならないように「選手のマインドをコントロールする」ことが監督には求められています。
ヨハン・クライフ監督の名言
ボールを持とうとしないのであれば、サッカー選手ではなく陸上選手になればいい。
<ヨハン・クライフ>
ヨハン・クライフは20世紀を代表するサッカー選手の一人ですよね。
レジェンド選手なので、クライフの名前は知っている人も多いはずです。
ヨハン・クライフはオランダ出身のFWなので、攻撃的なサッカーを好みます。
1対0で守り抜くイタリア的サッカーに対して、上記のような名言を放ったのです。
フィールドを支配するナンバーワンのチームを作りたい。
<ヨハン・クライフ>
ヨハン・クライフが目指すサッカーは「攻撃的なサッカー」です。
観客を魅了する、圧倒的な攻撃力を持ったサッカーチームを目指したのです。
能力のないプレイヤーほど他人のミスを責めたがる。
<ヨハン・クライフ>
クライフは「試合で勝つためにはゲームの流れを先読みする必要がある」と語っています。
それができるプレイヤーは能力が高く、先が読めないプレイヤーは能力が低いとしました。
そのような能力が低いプレイヤーほど、負けた責任を他人に押し付けるのです。
才能ある若手にこそ、挫折を経験させなければならない。
挫折はその選手を成長させる最大の良薬だ。
<ヨハン・クライフ>
「失敗は成功のもと」と言いますよね。
挫折することで「どうすれば勝てるのか?」を真剣に考えるので、自分の長所を発見するきっかけにもなるそうです。
才能も必要だ。
しかし、それを最大限に生かしてこそ素晴らしいプレイヤーになれる。
<ヨハン・クライフ>
「宝の持ち腐れ」ということわざもありますが、たとえ素晴らしい才能を持っていたとしても、それを使わなければ意味がありません。
ヨハン・クライフは、選手たちに「常に110%の力を出すように」と命じていたのです。
あらゆる可能性があるのは間違いないんだ。
むしろ怖いのは選手の可能性を指導者がつんでしまうことだ。
<ヨハン・クライフ>
これは企業経営にも共通する名言だと思います。
大手企業には高学歴の優秀な人材が集まってきますが、そこの経営幹部は「ウチにはいい人材がいない…」とぼやくそうです。
これこそまさに「人材の可能性をつんでいる」状態だと思います。
才能のある選手は多いが、炎のようになれる選手は少ないんだ。
<ヨハン・クライフ>
これは情熱について語った名言です。
たとえ一流のスキルを持っていたとしても、熱心に練習へ取り組まなければ、いづれ普通の選手になってしまいます。
まとめ
ここまで海外サッカーにおける名監督たちの名言集をご紹介してきました。
サッカーはスポーツなので、他のスポーツでも参考になるような言葉ばかりだったと思います。
監督の言葉は「リーダーの格言」なので、ビジネスにも使える考え方が多いでしょう。
ここでご紹介した名言を、ぜひ仕事やプライベートに取り入れてみてください。
もしアスリートの言葉が好きな場合には、ぜひ下の記事もご覧ください。