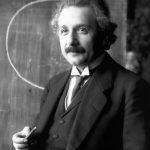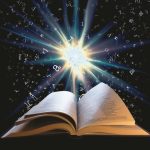ビジネスパーソンであれば、一度くらい「マーチャンダイジング」という言葉を聞いたことがありますよね。
このキーワードは卸売&小売業で良く使われているので、スーパーマーケットに勤めている人や、アパレル販売している人には馴染み深いかも知れません。
しかし「マーチャンダイジングは難しい…」とも言われるので、多くのビジネスパーソンが苦手に感じていることでしょう。
そこで今回は、マーチャンダイジングについてわかりやすく簡単に解説していきたいと思います。
マーチャンダイジングは、モノを販売するセールスパーソンが知っておくべき知識なので、卸売&小売業者以外も幅広くご覧ください。
目次
マーチャンダイジングとは?
マーチャンダイジング(Merchandising)は、「MD」と略されることもありますが、その意味は『適正な商品を適正な数量・価格で、適正な場所に提供する活動』ことになります。
つまりマーチャンダイジングとは、”商品計画”や”品揃え計画”を考えることなのです。
この言葉は主に流通業で使われているので、卸売業や小売業の人には馴染みあると思いますが、それ以外の業種・業態の人はあまり聞いたことがないかもしれません。
卸売業や小売業に多い
これはビジネスモデルの話になりますが、一般的なメーカーは自社製造した商品を、卸売業や小売業へ販売して儲けます。
そして卸売業や小売業は、メーカーから仕入れた分を販売するので、仕入れた量に応じて売上&利益が増大する期待値も上がっていくことになります。
従って、卸売業や小売業にとっては、どんな商品を、いつ、何個仕入れて、いくらで、どのように販売するのかが重要となってくるのです。
それは当たり前の話なので、言葉にするとなんか簡単そうですが、実行するのは「非常に難易度が高い」と言われています。
このような商品の仕入れ、在庫管理、販売に関わる業務全般を「マーチャンダイジング」と呼んでいるのです。
マーチャンダイズとは違うの?
マーチャンダイズは、マーチャンダイジングの略語ではありません。
マーチャンダイズとは、マーチャンダイジングにより生み出された製品、商品、在庫品のことを指す言葉です。
先ほどマーチャンダイジングは”商品計画”や”品揃え計画”のことだとご説明しました。
なので、その計画内で発生したものがマーチャンダイズということになります。
他にも「マーチャント(商人)」という似た言葉があります。
これはビジネス界隈で使われている言葉なので、もしかしたら聞いたことがあるかも知れません。
以上を図で例えると下のようになります。

一番外郭にマーチャンダイジングという概念があって、その中にマーチャンダイズとマーチャントが内在しているのです。
マーチャンダイジングの目的とは?
卸売業や小売業がマーチャンダイジングする目的は下の2つに集約されていきます。
- 商品販売を通じてエンドユーザーの価値を最大化する
- 商品販売を通じて売上高や利益を最大化する
この二つは相互関係にあるので、どちらか一方を求めれば、もう片方も達成されることが一般的です。
なぜマーチャンダイジングが求められているのかといえば、大量購入&大量消費の時代が終わってしまったからです。
これまでの時代は「大量に仕入れて、余った分は廃棄すれば良い」という発想でしたが、2015年の国連サミットで採択されたSDGs(持続可能な開発目標)の高まりから、「適切な量を仕入れ、ロスを最小化して販売する」という方向に社会全体が舵を切り始めたのです。
よって、流通事業者は「儲かれば何でもOK!」という旧態依然の発想を捨てて、顧客志向や社会動向、消費者志向などに合わせなければいけない状態となったのです。
マーチャンダイジングを実施するコツ
マーチャンダイジングで管理すべき”5つの適正ポイント”は以下の通りです。
- 商品
- 場所
- 時期
- 価格
- 数量
これらを一つずつ解説していきたいと思います。
①適切な「商品」を管理する
まず「商品」というのは、顧客ニーズに合った商品サービスを揃える全ての手段を指しています。
卸売業で言えば、小売業が求める商品を揃えておくことであり、小売業で言えば、エンドユーザーが求める商品・サービスを用意しておくことを指します。
➁適正な「場所」を用意する
そして「場所」というのは、顧客ニーズに合った場所のことを意味しています。
小売業で言えば、店舗の立地、店内のレイアウト、ゾーニング(空間を用途に応じて分けること)やフェイシング(商品陳列の最前面数(フェイス)を決定すること)などが適切な場所にあたります。
どんなに素晴らしい商品であっても、お客様の目に留まらなければ売れませんし、逆に店内のレイアウトが秀逸なだけでモノの売れ行きは良くなります。
③適正な「時期」に販売する
「時期」とは、顧客ニーズに合ったタイミングで商品提供することを指します。
虫除けスプレーや日焼け止めなど、季節性の高い商品は、そのタイミングにしか売れないので分かりやすいですよね。
それ以外にも、ランチタイムに売れやすい商品を用意したり、休日に売れやすい商品を用意することもマーチャンダイジングの一部です。
そして天気に注目したマーチャンダイジングを「ウェザー・マーチャンダイジング」と呼んでいます。
これは有名な話ですが、アイスクリームは真夏よりも「夏になる直前が一番売れる」と言われています。
具体的には、気温が25度を超えるとアイスクリームが売れ出すので、そのタイミングでアイスクリームを大量に仕入れるというのがウェザー・マーチャンダイジングの好例となります。
④適切な「価格」を設定する
プライシングは非常に難しいですが、売り手は顧客ニーズに合った適切な価格を設定しなければいけません。
高すぎれば商品が売れず在庫を抱える羽目になりますが、その一方で、安すぎれば想定よりも売れてしまうため、在庫が足りないという状況になりえます。
マーチャンダイジングを前提とした場合、営業時間ギリギリにちょうど売り切れるのが理想的なので、それをコントロールする為に適切な価格設定が求められるのです。
⑤最適な「数量」を仕入れる
顧客ニーズにあった最適な数量を仕入れなければ、過剰在庫となってしまいます。
過剰在庫はビジネスを潰してしまう原因になりえるので、十分注意するべきでしょう。
そういった意味では、在庫管理がマーチャンダイジングの中で最も重要なポイントなのかもしれません。
例えば下のようなケースは、果たしてマーチャンダイジングできているのでしょうか?
100個の商品を仕入れて、100個の商品が完売した。
一見すると理想的な状態に見えますが、実はまだ不完全なのです。
マーチャンダイジングにおいて重要なのは『発注精度を向上させる』ことです。
100個の商品が完売したということは、品切れを起こしたということですよね。
もし売り切れた後に、その商品が欲しいお客様が来店してきた場合、そのお客様には販売できないので機会損失が生まれてしまいます。
なので、品切れ時刻を想定し、そこから売れたであろう数量を計算する必要があるのです。
これが機会損失金額の算出へと繋がっていきます。
このような販売データをPOSシステムから導き出し、PDCAサイクルを回し、最適な在庫数を手探りで見つけるのです。
過剰在庫にならず、品切れも起こさない在庫数のことを「適正在庫」と呼んでいますが、適正在庫にコントロールするのは至難の技だと言われています。
しかし適正在庫が見つからなければ、マーチャンダイジングは不完全だと言わざるを得ないでしょう。
クロス・マーチャンダイジングで販売する
商品・サービスを販売する場合、一つずつ提案すると費用対効果が悪くなってしまいます。
なので、ある程度のロット提案で、顧客単価アップを狙うのです。
そのための手法が「クロス・マーチャンダイジング」と呼ばれています。
これはつまり「クロスセールス」のことなので、そのように言えば営業職はピンとくるはずです。
例えばスーパーマーケットのお肉売り場で、”焼肉のタレ”を売ることがクロス・マーチャンダイジングに該当します。
このように、一顧客あたりの買上点数を増やす試みが「クロス・マーチャンダイジング」と呼ばれているのです。
一見するとメリットしかないようなクロスマーチャンダイジングですが、同一商品が異なる売り場に並ぶというデメリットもあります。
それによって商品陳列が複雑になり、在庫管理も難しくなるという欠点があるのです。
なので、なんでもかんでもクロスセルすれば良いという話ではなく、ある程度の目星をつけながらクロス・マーチャンダイジングするべきだと思います。
マーチャンダイジングは難しい
ここまでマーチャンダイジングの概要をご説明してきましたが、そのやり方を語り尽くすにはまだまだボリュームが足りません。
おそらくこの10倍ぐらいのボリュームを書かなければ、マーチャンダイジングのノウハウをすべてお伝えすることはできないでしょう。
マーチャンダイジングにおけるPDCAサイクルを回すためには、以下のようなポイントを改善していかなければいけません。
- ”売れ筋商品”を見つけて、”死に筋商品”を撤去する
- ロングセラー商品とファッド商品(すぐ消える商品)の見極めをつける
- 商品のプライスゾーンを設定し、プライスラインを決め、プライスポイントを導き出す
- 廃棄ロス、品切れロス、棚卸ロス、値下げロスを見極める
- グルーピング、ゾーニング、フェイシングで売り場を演出する
- 縦割り陳列と横割陳列によって見やすくする
この他にも様々な手法を用いながら、売上&利益の最大化を目指していきます。
販売方法一つをとっても、前述したクロス・マーチャンダイジング以外に、特売セール、デモ販売(デモンストレーション)、EDLP(Every Day Low Price)販売、サンプリングセールスなどがあります。
飲み物や冷凍食品などを販売するリーチインケースにも、良く売れる”ゴールデンゾーン”というのがあります。
そのゴールデンゾーンで”売れ筋商品”をプッシュすることになりますが、それ以外の商品は「本当に死に筋商品なのか?」、それとも「意図的に作り上げた死に筋商品だったのか?」を分析する必要もあるでしょう。
このようにマーチャンダイジングはとても奥深いので、自分なりに色々と勉強してみましょう。
世界で最も有名な小売業といえばウォルマートだと思いますが、その創業者サム・ウォルトンはEDLP(Every Day Low Price)販売の先駆者と言われています。
きっとEDLP商法にウォルマートが勝てた要因が隠れているのだと思います。
「小売王」と呼ばれたサム・ウォルトンの自伝本も発売されているので、もし良ければ読んでみてください。