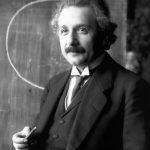営業キャッシュフローとは「企業の生命力」と言われたりもするほど重要な指標です。
そこで今回は、営業キャッシュフローが重要と言われる理由や、その意味について詳しく解説していきたいと思います。
ビジネスパーソンが知っておくべき知識だと思うので、ぜひご覧ください。
目次
営業キャッシュフローの意味とは?
「営業キャッシュフローがマイナスになった!」と聞いて、その意味がすぐに理解できる人はそんなに多くないと思います。
ただ、「営業キャッシュフローがマイナスに転じた」ということは、株式投資情報でもニュースになったりすので、なんとなく「大切なことなのだろう…」ということくらいは理解できるはずです。
営業キャッシュフローの意味を一言で伝えてしまうと、「その企業が一年間の本業によって得たキャッシュ(現金)がどれくらいなのか?」ということを意味しています。
ただ、キャッシュフロー(CF)と一口に言っても、企業には3つの種類があるので注意が必要です。
- 営業キャッシュフロー
- 財務キャッシュフロー
- 投資キャッシュフロー
その中でも、企業のフリーキャッシュフローを増やす為に、最も重要だと言われているのが、今回のテーマでもある営業キャッシュフローなのです。
営業CFは企業の生命力である
営業キャッシュフローが持つ意味とは、「その企業が販売している商品サービスが、どれくらいのキャッシュを生み出せるのか?」という企業パワーです。
そういった観点では、「営業キャッシュフローがプラスである」ということが、事業価値の高い会社である証拠とも言えるでしょう。
そして、営業キャッシュフローのプラスが大きければ大きいほど優良企業だとも言えます。
それはつまり「キャッシュインが多い」ということを意味するので、それだけ企業経営が安定していることにも繋がっていきます。
その為、営業キャッシュフローは企業の生命力を表すと言っても決して過言ではありません。
営業キャッシュフローの計算方法
フリーキャッシュフローを増やすために重要なものが、「本業で稼いだキャッシュ量を示す営業キャッシュフロー」ですが、その計算方法を知っておくことはビジネスパーソンにとって大切なことだと思います。
この計算方法を知っていれば、「どうすれば営業キャッシュフローを増やせるのか?」ということが理解できるからです。
営業キャッシュフローの求め方
営業キャッシュフローの計算方法には2種類のやり方が存在しています。
- 直接法
- 間接法
ただし、直接法は手数が多くなってしまうため、一般的には間接法が用いられるケースが多くなっています。
間接法による営業キャッシュフローの求め方ですが、損益計算書の税金等調整前当期純利益を基にして計算していきます。
まず、税金等調整前当期純利益から損益計算書上の項目を加減していきます。
それらの項目の中には、
- 有価証券評価損
- 減価償却費
など、実際キャッシュアウトしない項目があるので、これらは差し戻していきます。
そして、売掛金や棚卸資産、買掛金などを加減し、小計まで求めていきましょう。
最後に法人税を差し引いて、営業活動によるキャッシュフローが導き出されます。
営業キャッシュフローは実際にキャッシュの動きがあるものを計算するため、キャッシュの動きがないものを除きながら加減していくのです。
営業キャッシュフローと営業利益の違い
営業キャッシュフローと似た言葉に「営業利益」があります。
この両者は似ている言葉なので、同じものだと勘違いしている人は多いのですが、実際は全く別モノになります。
例えば、端的に表現すると以下の通りになります。
- 営業キャッシュフロー:企業が本業で得たキャッシュの量を示しているもの
- 営業利益:企業が本業で稼いだ利益
つまり、営業キャッシュフローは「現金」のことであり、営業利益は「会計上の利益」であるということです。
これでも両者の違いを明確に理解するのはちょっと難しいかもしれませんが、そのような複雑な仕組みになってしまう理由は、ビジネスの現場では”掛け取引”が多くなっている為です。
掛け取引とは?
掛け取引とは、商品を納品したと同時に商品代金を受け取る”現金商売”ではなく、納品後に請求書を発行して、その請求書に基づいて支払いをしてもらう方法をいいます。
ちなみに、一般的な会計仕訳としては「売掛金」や「買掛金」と言われています。
コンビニエンスストアやラーメン屋さんのような個人消費者向けに生活消費財を売っているのであれば、その場で現金が支払われるかもしれませんが、法人取引になると現金取引はかなり珍しくなります。
たとえ後日だったとしても、「結局支払ってもらうなら一緒じゃないの?」と思う人がいるかもしれませんが、制度会計上ではその性質が全く違ってきます。
なぜかというと、制度会計は”発生主義”になっているからです。
つまり、会計上では納品した時点で売上高や営業利益は計上されてしまうのです。
しかし、会計上は売上が計上されていたとしても、実際に売上金(=現金)を回収することができるのは、請求書を出した30日後や45日後、遅いと60日後や90日後なんてケースもあり得ます。
したがって、会計上の売上高と実際の支払いにはどうしてもタイムラグが生じてしまうのです。
このようなタイムラグがあるため、営業利益と営業キャッシュフローの数字が違ってくることになります。
営業キャッシュフローがマイナスになる意味
営業キャッシュフローがマイナスになるというのは、企業にとって大変危険な状態を意味しています。
危険な状況というのは、企業倒産に向けて一直線に前進している状態を言います。
それでは、果たして営業キャッシュフローがマイナスになるというのは、一体どういう意味なのでしょうか?
営業キャッシュフローがマイナスということは、本業によって得たキャッシュ(現金)が少ないことを意味しています。
このような状態で想定される危機的ケースとは、キャッシュインよりもキャッシュアウトの方が多くなっているというケースです。
つまり、事業活動をすればするほど、手元の資金が流出してしまうことになります。
こうなってしまうと事業を継続するために銀行などから借り入れを行わなければなりませんし、そうすると有利子負債だけがドンドン増えてしまうので、最終的には債務超過に陥ります。
一時的に営業CFがマイナスになったのであればまだ良いですが、長期的に営業キャッシュフローがマイナスのままだと、将来の事業投資もできませんし、ビジネスモデルにも疑義が生じてきます。
そのような負債ばかり増えてしまう会社には、銀行も融資をしてくれなくなるので、どんどん悪循環に陥っていくでしょう。
このような悪循環に陥ってしまうと、余程のことがない限り抜け出すことは難しいと思います。
営業キャッシュフローがマイナスになって、事業改善も難しいという状況になってしまうと、経営者としては会社をたたむという最悪の事態も視野に入れなければいけません。
営業キャッシュフローは最も重要な指標
キャッシュフローは、
- 営業キャッシュフロー
- 投資キャッシュフロー
- 財務キャッシュフロー
の3つに分けることができますが、健全な企業経営において最も重要な指標と言えるのが「営業キャッシュフロー」であるということはこれまで解説してきた通りです。
営業キャッシュフローがプラス圏内であれば、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローがマイナスであっても、さほど問題ではありません。
というのも、投資キャッシュフローは将来の設備投資のためにマイナスになることがありますし、財務キャッシュフローも借入が多くなればマイナスになるからです。
むしろ見方によっては「攻めの経営」をしているほど、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローはマイナスになりがちという側面を持っています。
しかし、営業キャッシュフローは本業におけるキャッシュフローなので、これがプラスになっていないと「そもそも本業が利益を生み出していない状態」なので、商売(=ビジネス)として成立していないことを意味しています。
独立起業したばっかりの時や、新規事業を立ち上げたばかりの局面であれば、営業キャッシュフローがマイナスになることも十分ありえます。
当然多少の増減は出てしまうものですが、速やかに原因を究明して対策を取らなければ最悪の結果になってしまうかもしれません。
特に体力のない中小企業はキャッシュフロー経営を心掛けるようにしないと、帳簿上は利益が出ているのにも関わらず倒産してしまう「黒字倒産」というケースも十分あり得るのです。
黒字倒産は景気後退局面で出てきやすいケースです。
もし会計に関して苦手意識があるのであれば、わかりやすい解説本がたくさん出ているので、一度それらを読んでみてください。
「現金こそが企業の生命力」なのだと理解して、経営者やマネージャーは企業経営していきましょう。